残っていた秋田大学通信教育の「一般科学技術コース」のうち「機械工学概論」の学習単位認定試験問題を近くのポストに投函してきた。これでこのコースに関しては当面やることがなくなったので(再提出がなければ出すものはこれで全部終わり。なお同コースの終了要件は既に満たしている。)、「地球科学コース」の方を始めたいと思う。在籍期間は3年なので、制度上は、2023年の8月まで在籍できるが、今回は計画的に勉強して早めに終了したいと思う。「一般科学技術コース」のように、在籍期間が残り少なくなって、慌てるようなことはしたくないな。
アクティブラーニングとは何か。本書にはこう書かれている。
ひと言でまとめると、プレゼンテーションやディスカッションのような様々なアクティビティ(学習技法)を介して、学習者が能動的に学びに取り組んでいくことを指す言葉である。(pi)
一時流行ったディベートなどもその一つであり、企業の研修にはつきもののグループワークもそうだと言えるだろう。
アクティブラーニングの事例として、アテネのアメリカ系インターナショナルスクール(国際学校)での取り組み例が紹介されている。もちろんプラスの評価事例としてだ。(pp27-30) しかし、本当にそうだろうか。インターナショナルスクールといっても、本書を読む限り、通っていたのはギリシア人が多いように取れる。もしアクティブラーニングが優れているのなら、ギリシアは人材を輩出しているはずだ。しかし実際は、ギリシアから人材が多く出ているという話は聞かない。経済はご存じの通りだし、ノーベル賞受賞者も文学賞以外は出していないし、フィールズ賞受賞者も出していない。ギリシアの人口が日本の10分の1以下ということを考慮しても、少し寂しい数字だ。
教育が有用なのは、おそらく普通の人々なんだろう。普通の人々を平均レベルに引き上げるのは教育が有効だと思う。ただしその手法に優劣があるという根拠はないことを指摘したい。一方、天才クラスになるとどんな教育を受けても、たとえ自学自習でも頭角を現すのではないだろうか。教師側に天才を教えられる人がそれほど多くいるとは思えない。実際天才と呼ばれた人の伝記を読むと、教師から何かを教わったというのは少ない。それどころか、学校時代の評価は決して高くはない。学校から教育を受けたというよりは、自分で才能を切り開いたのだろう。
教育の有効性を測るには、例えば、能力が同じような人を別々の教育法で教育し、ある期間の後に成果を比べるというようなことが考えられるが、実際には色々な問題があり、やることはできない。だから教育の世界では、フィーリングで「これ良さそう」だと思われれば、他に何の根拠もなく取り入れられる。ゆとり教育しかり、総合的学習の時間しかりである。それに付き合わされる子供たちにとっては、教育内容がころころ変わり、大迷惑なのだ。アクティブラーニングもこの流れの上にないことを願いたい。
☆☆☆
※初出は、「風竜胆の書評」です。
今日から放送大学の2020年度2学期の科目登録申請だ。忘れないうちにシステムWAKABAから登録した。登録したのは「データベース」1科目のみ。
ツイッター情報によれば、今年は1学期の科目の単位が取れているかどうかを確認する裏技が使えないらしいが、もし落ちていても郵便事故で3科目共ダメでない限りは全部落ちたというのは考えられないので、2学期に試験を受ければいいと考えている。
2学期もコロナの影響で在宅試験になるようだ。それもあり、面接授業の方もどうなるかわからないので、今回は申請しなかった。
相沢沙呼さんは、私が好きな作家の一人だ。本書は短編集で、6篇の短編を収めている。最初の「ねぇ、卵の殻がついている」と最後の表題作、「雨が降る日は学校に行かない」は後者が前者の前日譚になっている。保健室登校をするナツとサエの物語である。
本書には、この他に、「好きな人のいない教室」、「死にたいノート」、「プリーツ・カースト」「放課後のピント合わせ」の4編が収録されている。登場人物はどれも女子中学生。女子はそれでなくとも同調圧力が強い傾向があるのに、この年代は特にそうなのだろうか。そして描かれるのはこの同調圧力になじめない女の子たち。
保健室の長谷川先生がサエに言った言葉が胸を打つ。
「小町さんは、学校に行けないんじゃないよ。学校に行かないだけ。先生は、そんな生き方があってもいいと思う。本当は勉強するのに、教室に閉じこもる必要なんてないはずなんだ。学校が世界のすべてじゃあないんだよ。(以下略)」(雨が降る日は学校に行かない p248)
解説で声優・タレントの春名風香さんは長谷川先生にも否定的だが、こういう先生が一人でもいればだいぶ雰囲気は変わると思う。
それにひきかえこいつはだめだね。担任の教師・川島だ。
「小町はさ、そんなふうに自分の主張を通さないでいるから、男子にちょっかいかけられるんだよ。もっと飯島みたいに明るい子を見習ってさ、教室の雰囲気を盛り上げて、みんなと仲良くなれるようにしようよ。なあ?」(雨が降る日は学校に行かない p230)
ちなみに飯島というのは、サエをいじめていた女子である。最悪なのはこんな教師ばかりいるとき。解説で春名さんが「ぶんなぐりたい」(p267)と書いていたが、その気持ちはよく分かる。
ところで、相沢さんは男性である。それも1983年の生まれというから、もうアラフォーのおじさんだ。それなのに、どうして多感な時期の女子中学生の心理をこのように鮮やかに描けるのだろう。
☆☆☆☆☆
※初出は、「風竜胆の書評」です。
鬼娘といってもラ〇ちゃんではない。そして、タネも仕掛けもある話だ。確かに犯人は娘だったのだが、服装も白地の浴衣に跣足(はだし)で、決して、トラ模様のビキニなんて来ていない。なにしろ江戸時代の話だ。あの時代にはビキニがあったとは考えられない。ましてや宇宙人などではない。
と前置きはさておき、本作も岡本綺堂の「半七捕物帳」の中の1作だ。江戸で3件の連続殺人事件が起きた。被害者は若い娘で、いずれも喉笛をかみ切られていた。鬼なら、ムシャムシャと被害者を食べそうなものだが、みな喉笛をかみ切られただけ。
この作品、ミステリーとしての出来はどうだろう。正直に言うとあまり良いとは言えない。読んでいると、なんとなくネタが想像できるのだ。
半七は袂をさぐって、鼻紙にひねったものを出すと、庄太は大事そうにそれを開けて見た。
「こんなものをどこで見つけたんですえ」
「それは露路の奥の垣根に引っかかっていたのよ。勿論、あすこらのことだから何がくぐるめえものでもねえが、なにしろそれは獣物の毛に相違ねえ」
想像通りの結末になるのは、予定調和というところだろうか。この半七捕物帳には、最初ホラー風味の味付けがされ、結局タネも仕掛けもありましたというものが多い。この話もその芸風を継いだ作品と言えるかもしれない。
☆☆☆
※初出は、「風竜胆の書評」です。
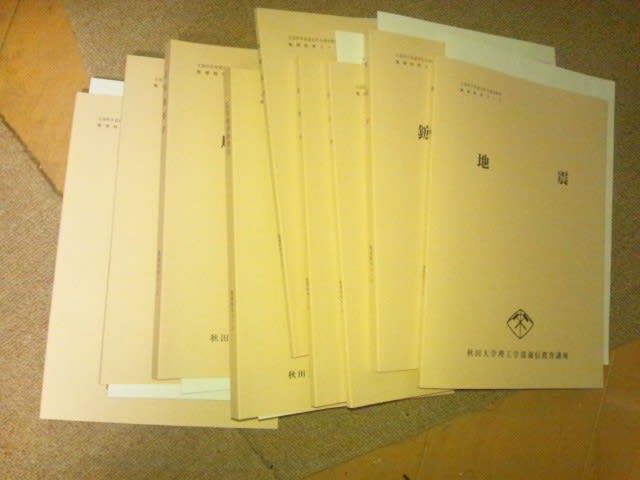
先般学費を振り込んだ秋田大学通信教育「地球科学コース」のテキストが届いた。今度は1単位科目が多くその分テキストも多いためか、2箱に分けて送られてきた。
今度は一般科学技術コースのように最終在籍年年になって慌てないようにしよう。以前のコースで共通科目を3単位分とっているので、7単位取得が終了要件となる。こんどはしっかり計画的に取り組むことにしよう。
この作品は、昨年、出版社3社を横断する形で刊行されたもののうち、2番目に当たる。話の中心となるのは、前巻と同じく京極堂の妹で科学雑誌稀譚月報の記者である中禅寺敦子と「絡新婦の理(じょろうぐものことわり)」に出てきた女子高生の呉美由紀。
物語は、美由紀とその友人たちが、河童談義、尻談義を行っている場面から始まる。尻談義は、河童が尻子玉を抜くという話から来ている。女三人寄ると姦しいというが、彼女たちの話がなんともいえず面白いのだ。それにしても、河童に対していろいろな呼び方があるものだ。
この作品でも、ヘンな人が出てくる。ヘンな人と言うと、榎木津や、敦子の兄の京極堂などがその最たるものだ。関口もかなりヘンな人に分類されるだろう。この作品に出てくるのは、多々良勝五郎という在野の妖怪研究家。この先生、主役を務める「今昔続百鬼」という作品があるので、こちらでもレギュラーになるのかと思いきや、次の巻の天狗には名前しか出てこなかった。
夷隅川水系で相次いで死体が見つかる。その共通項は、尻が丸出しになっていたということ。果たして河童の仕業なのか?
この作品で扱われているのは、戦後の物資横流しや迷信に基づいた差別など。しかしやっぱり、京極堂の付き物落としや榎木津のハチャメチャぶりが懐かしい。
☆☆☆
※初出は、「風竜胆の書評」です。
主人公の秋場慎一は高校2年生。銀行員の父親の転勤に伴い、東京から月見ヶ丘市に引っ越してきた。転校した月見ヶ丘学園は、元伝統ある女子高で、前年度から共学になっている。ただし、この2年はテストケースで男子は1割しかいない。だから生徒はあまり男子に慣れていないようだ。
慎一君、さっそく3年生の女子にいたずらされる。そういえば共学になったのが2年前なので3年生には男子がいない。だから女子は男子に興味深々。慎一君、ちょうどよいターゲットになったみたいだ。それを助けてくれたのが音楽教師の藤木小夜子先生。美人でスタイルの良い小夜子先生に年上趣味の慎一君の欲望がムクムクっと・・・。ブツを引き出して先生に出血しているといけないと、先生に見せたり、触ってみてといったり、最後はもちろんドッキング。ちなみにタイトルは、小夜子先生のお尻の形がとても綺麗なことから。綺麗なお尻に萌える人をビジリアンというそうな。
これを皮切りに慎一君のモテモテ人生が始まる。学園長の豪徳寺友里恵。3年生のいたずら女子のリーダー美貴子。小夜子先生の姉でバツイチの美佐子など。もう次から次に慎一君は頑張る(何を?)。特に小夜子先生にはものすごく頑張る。
これ確か、雑誌に連載されていたような記憶があるんだが、調べてみても分からなかった。昔の記憶は当てにならないことは、時々実感するので、もしかすると気のせいだろうか。誰ですか、慎一くんのような高校生活を送りたかったという人は。そりゃ男子の夢だけど。まあ、夢は夢で終わるよ(笑)。
☆☆☆
※初出は、「風竜胆の書評」です。
著者はミドルネームを名乗っているが、別に外国の出身という訳ではない。純粋の日本人だ。これは、著者がサバクトビバッタの研究で滞在したモーリタニアの国立サバクトビバッタ研究所のババ所長が、著者を称えて与えたものだ。但し、どこかが公式に認めた名称という訳ではなく、本書を読む限りは、あくまで研究所の所長が言っただけのようだ。
「ウルド」の意味は「~の子孫」という意味で、例えばババ所長の正式な名前は、モハメッド・アブダライ・ウルド・ババと言って、つまりはババの子孫だという。著者は、ババ所長に誠意を示すために改名した。
ここで、ツッコミをひとつ、その使い方なら、ウルド浩太郎とつけると浩太郎の子孫ということになり、著者の次の世代以降のことになる。「ウルド」を使いたければ、浩太郎ウルド前野とする必要があると思う。実際にババ所長から言われたのは、「コータロー・ウルド・マエノ」というものらしい。
ただし、この「ウルド」というのはモーリタニアでは法律が改正され廃止されたという。理由はみな誰かの子孫であるということらしい。だから、前述のババ所長は、「モハメッド・アブダライ・エッペ」に改名したという。「エッペ」はどこから来たんだと思うのだが、ババが無くなったので、かなり混乱を招いたようだ。
本書には、バッタとイナゴの違いが書いてある。群生相のような相変異を示すものがバッタで、示さないものがイナゴだという。だからオンブバッタやショウリョウバッタなどは、名前にバッタとついているが、厳密にはイナゴの仲間だという。
面白いのが、著者が京大の白眉プロジェクトに応募した際のエピソード。なんと、面接のときに、本当に眉を白く塗ったらしい。これが果たして、合格に役立ったかどうかは分からない。しかし、あの大学は、こういった茶目っ気は好きな人が結構いる(全員という訳ではないが)。
もう一つ面白かったのが、著者がサソリに刺されたときのエピソード。なんとババ所長も、著者のドライバーも、お祈りを唱えて、「これで大丈夫」。結局日本大使館で軟膏と鎮痛剤を処方してもらって、大事にはならなかったようだが。
本書は、ユーモラスな書きぶりで書かれており、著者のバッタ愛が至るところからあふれ出してくるようだ。どのくらいバッタ好きかというと、夢はバッタに食べられること。バッタを触りすぎて、バッタアレルギーになってしまったくらいである。また、ユーモアあふれる文章の中にも職業として研究者を続けることの厳しさが伺え、研究者を目指す人には一読することを勧めたい。
ちなみに、表紙のいかにも怪しげな写真が著者で、本書中にも、全身緑タイツでバッタの大群に向かっているというヘンなおじさん丸出しの写真がある。
☆☆☆☆
※初出は、「風竜胆の書評」です。
主人公は三並英太という私立央生高校の生徒。この作品は「東雲侑子シリーズ」三部作の最初の巻となる。巻が進むにつれ、学年が一つづつ進むというのがこのシリーズの特徴だろう。
英太の入った高校では、全員が部活に入らなければならないというおかしな校則がある。しかし、図書委員になれば、部活に入っているとみなされ、拘束時間も短い。
という訳で、帰宅部希望の英太は図書委員になったのだが、彼と同じ日にカウンターに座っているのが同級生の東雲侑子。
彼女は、いつも無表情で、不愛想で、いつも何かを読んでいる。何を読んでいるのかと聞きだすと、読んでいるのは、短編小説らしい。
ところが、ひょんなことから、彼女が西園幽子と言う名前で作家活動をしていることを知る。彼女は短編しか書かない。
「人間ってとてもちっぽけで、小説にしてみればせいぜい原稿用紙50枚とか60枚とかの短編小説みたいな人生しか送れないんじゃないかって」(p78)
担当編集者からも長編を書いてみたらと勧められていたこともあり、長編小説を書いてみようとした東雲に、英太は、長編を書くために彼氏役をして欲しいと頼まれる。東雲は恋をしたことがないというのだ。これをきっかけに、二人の距離は次第に近づいていくという1種の恋愛小説というところか。
つまりは、男女が恋人同士になるきっかけは、ひょんなことからだということか。
「俺、彼女できたかも」(p302)
さて、二人の関係はどう進展するのか。
☆☆☆☆
※初出は、「風竜胆の書評」です。























