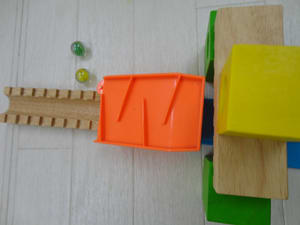■ちゃんと◎ちゃんの説明はこうでした。
最初に○ちゃんと◎ちゃんがベッドの上段に上がって勝手に自分の場所と決めていたようなのです。
そこに■ちゃんが現れて、◎ちゃんのベッドに登って行ってベッドを取り合ってじゃんけんをしたそうです。
すると◎ちゃんが勝ちました。
負けた■ちゃんに、気のいい○ちゃんが、「私のところにおいでよ~いっしょに寝ようよ~」と誘いかけたそうです。
そこで■ちゃんと○ちゃんがいっしょに寝る算段で、二段ベッドの上でふざけていたところ、
親御さんたちから「危ないから、上でふたりで寝てはダメ!」と注意を受けたようです。
■ちゃんと○ちゃんがじゃんけんをしたところ、先にベッドを陣取っていた○ちゃんが負けて、
泣いて抗議するものの、「じゃんけんで負けたのだから仕方ないでしょ」「最初に勝手に場所を取ってたからって自分のものにはならないでしょ」と親御さんたちからも子どもたちからも理路整然と説明され、
本人としては納得できずにしつこく抗議して愚図っていたので、
しまいに○ちゃんのお母さんのカミナリが落ちたようなのです。
○ちゃんのお母さんというのは私の数倍は寛容で気の長い方です。
その○ちゃんのお母さんがきつい言葉で叱ったとあれば、おそらく私がそこに来るまでに
○ちゃんは、カミナリでも落とされないと収拾がつかないほどのごね方をしていたのでしょう。
「家に帰るわよ」という脅し文句は、
こうした楽しいイベント事が何より好きな○ちゃんにかなりこたえたらしく、
私が着いた時には、しくしくと静かに泣き続けているだけでした。
出来事を説明する■ちゃんと◎ちゃんの興奮した口調のなかには、
自分だけが上の段を取っていることへの罪悪感や、
じゃんけんの結果を素直に受け入れることができない○ちゃんを罰する気持ちや、
自分たちは悪くないもんと主張したい気持ちや、上の段が取れて有頂天になって自慢したいような気持ちなどが
入り混じっているようでした。
そのテンション高くまくしたてる様子は、じゃんけんに負けて泣いている○ちゃんからすると、
「イケズ」として映っていたかもしれません。
そこで私は、「○ちゃん、こっちにおいで」と呼んで
「上の段で○ちゃんも寝たかったんだね。それに、■ちゃんに親切にしようと思って
自分のところに呼んであげたのに、こんなことになって悲しいのよね」とだけ言いました。
○ちゃんは素直にコックリすると、私にもたれかかって涙を拭いながら
黙っていました。
私はあれこれ言うのはやめて、ただ泣かせておいてあげました。
○ちゃんは怒っているわけではなく、自分が遭遇した現状を受け入れるために
もう少し泣く必要があるだけでしたから。
私はベッドの上から何か言いたげに顔を出しているふたりに向かって、
いたずらっぽく、
「じゃんけんで勝った人は、カーテンを閉めて静かにしていてちょうだい。
自慢たらしく騒がれたら、負けて悲しい気持ちの人が、悲しいけどしかたがないか、我慢しようか……って
気持ちになれないでしょ。さぁさぁ、上の段の人はベッドの横から足を出したり、
はしごのところから顔を出したりしないで、ひっこんでてちょうだい。
ベッドから足を出したりして寝ぞうが悪くてもいいのは、下の人たちだけよ。
上の段はそんなことしたら危ないんだから。きっちりカーテン閉めてお行儀よく寝てちょうだい。
下で寝る人は、落ちてもけがしないでしょうから、暑い時にはベッドから足を半分くらい出してたり、
ごろごろ寝返りうっても構わないわよ。」
上の段の■ちゃんと◎ちゃんが苦笑いをしながらも黙ってひっこむと、
○ちゃんは次第に機嫌をなおしていきました。
しまいに1段目のベッドに寝てみて、上の人たちに自慢するように
わざと足をベッドから落ちそうなほど外に出して、「こっちで寝る方がいいわ」と言って、
ごろごろ寝返りを打つと、にっこり笑顔を見せました。
その様子を、最初から下の段に寝ることにしていた☆ちゃんは
黙って見ていました。
☆ちゃんは聞き分けがいいおりこうさんタイプの子です。
子どもたちが2段ベッドの取り合いを始めた時点で、☆ちゃんのお母さんが、
「☆は弟がいるんだし、下で寝なさい」と言った一言で
すぐにそれに従っていたのです。
争いごとが嫌いな☆ちゃんは、揉め事が激しくなるのを見て、
1段目を取っていてよかったと思っていたようです。
でも夜の大人だけの勉強会では、☆ちゃんのお母さんは
☆ちゃんが何を選ぶのかをお母さんが決めてしまったことに対して
反省していました。
最終的には揉め事がきらいな☆ちゃんは自分で下を選んだ可能性が高いけれど
最初から☆ちゃんを揉め事の外に出してしまったことを反省していました。
いい子タイプの☆ちゃんは、聞き分けが良すぎる半面、
「自分からこんなことをしたい」「勝ちたい」「できるようになりたい」という意欲が弱いときが
あります。
見たところ意欲的でしっかりした子なのに、
自分が遭遇している現実に対して、どこか他人事のように振舞うときが
多々あるのです。
がまん強いけれど、どこかでしらけた態度をとることがあるのです。
ユースホステルでの☆ちゃんはおそらく本来の性質である
芯が強くて情緒が豊かで他の子らを惹きつける魅力的な一面をたくさん発揮していました。
大人の顔色をうかがって緊張しているときではなく、
子ども同士で自由に自発的に振舞っていた時です。
☆ちゃんは、さまざまな場面で本人の判断に任せても大丈夫な
利発で責任感のある子なのです。
こうして他の親御さんや子どもといっしょに過ごすなかで、わが子に対する認識を改めながら、
☆ちゃんとお母さんとの関係も、少しずつ微調節していくと、さらにいいものになっていくように思いました。






















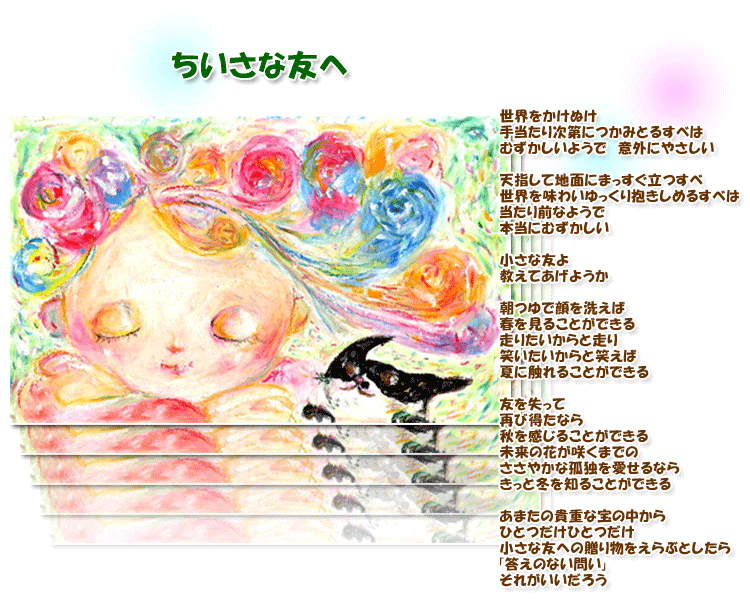

 見ているものを言葉で表現する
見ているものを言葉で表現する