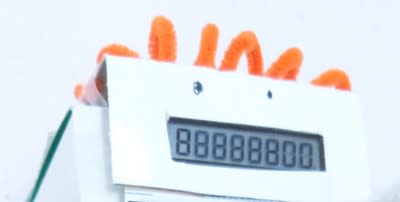ひと月ほど前に書いた
子どもとの間で生じる『力のゲームから抜けるには』 1
子どもとの間で生じる『力のゲームから抜けるには』 2
子どもとの間で生じる『力のゲームから抜けるには』 3
子どもとの間で生じる『力のゲームから抜けるには』 4
子どもとの間で生じる『力のゲームから抜けるには』 5
の記事に、こんなコメントをいただいていました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「正解がないことから逃げない」ということばが心にしみました。
>子育てにしても、鷲田先生の言葉を借りると、
>「あいまいなものにあいまいなまま正確に対応する」べきもの
>「正解などそもそも存在しないところで最善の方法で対処する、
>という思考法や洞察力」が求められる
これも、いままでの子育て経験を振り返ると本当にそうだなあと思います。
上の子が3才くらいまではかなり「嵐」な子育てだったのですが、
いろいろな情報や他の子育て経験者のアドバイスなどが一応頭にありつつも、
ひとりとして同じ子どもがいない中で目の前にいるこどもはどういうタイプで
いまなにを求めているのか、そしてわたしはいまどう感じているのか、
そしていまこの瞬間なにをするべきなのか、正解はないままにその場
その場をなんとか乗り切ることの積み重ねでいまがある気がしています。
いまたまたまこどもが小康状態というか落ち着いているからって、
簡単に「こういう場合はこうしたらいいのよ」なんて
他の人にアドバイスできないし、これからどうなっていくかもさっぱりわかりません。
わかったつもりが危険なんですね。いままでの経験や本で得た知識にあてはめて
「これはこういうことか」と決めて安心してしまえば、
その途端にいま目の前にいるこども、いまこの瞬間の自分の状態からは離れてしまう。
常に敏感にこどもや自分についてアンテナを働かせる、
ということが大事だなとおもいました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「興味を広げる環境を整えてきたのに知的好奇心が薄い気がします」4
の記事には別の方からこんなコメントをいただいていました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
週末この記事が頭の中を回っていました。
以前からこの通りだとは思っていましたが、どうしても面倒になるのが嫌だと感じると
先回りして問題を解決したい衝動に駆られていました。
また子どもたちに問題がおこると、どうやって乗り越えたら良いのだろうと
試行錯誤すると同時に、困り果てたり、悲観したりすることもありました。
(もちろんそのポジにふれるかネガにふれるかは、私の精神状態に左右されるのですが。)
でもこの記事と、様変わりする算数セットの記事、
また子どもたちとの週末を通して、なんともスマートに過ごせない日々の生活に対して
ポジティブに受け止めるための心構えみたいなものを体感的に再確認できました。
こどもたちのジレンマを歓迎する気持ちも、とても客観的なところからですが、
でてきました。
また子ども発の言葉や気持ちの裏にあるものの奥の深さを感じ、
しっかり受けとめ保障したいと感じました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
先日、『ひきこもる小さな哲学者たちへ』という本を読んでいて、
ふと先のふたつのコメントを思い出し、お返事がてらに記事を書くことにしました。
『ひきこもる小さな哲学者たちへ』は臨床心理士の小柳晴生先生が、
20年余りにわたる学生相談の仕事の現場をもとにして書かれた本ですが、
学生の親だけでなく、子どものいない方もまだ就学していない子を育てている方にも
読んでいただきたい今を生きる指針となるような本です。
この本を読んでいてどうして先のコメントを思い出したのかといえば、
どちらのコメント主さんの声も、小柳先生が現代の豊かな世界を生きる知恵や力として
挙げておられる4つの力を使って書いておられるな、と感じたからです。
小柳先生によると、今の時代の豊かさは、欠乏が生み出す苦しさは減じてくれたけれど、
新たに「生きる難しさ」をもたらしたそうです。
豊かさは、欲しい物がすぐに手に入るという安逸さをイメージしがちですが、
実際は「物と情報があふれるジャングル」であり、
いつ対処できないほどの物や情報の濁流に襲われ、多様な選択肢に絡みとられて
身動きできなくなるかわからない過酷な世界。
大人も子どももめまいを起こすほど早い変化に、やけを起こさずにつきあう方法を
みつけるという課題に直面しているそうです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
欠乏の時代の生き方が皆でそろっての電車やバスでの団体旅行だったとすれば、
豊かな時代の生き方は、個人や少人数での車での旅行といえます。
団体旅行は、自由に行動できない不便さはありますが、(略)
旅行仲間とは、目標を共有し「同じ釜の飯を食う」一体感があります。(略)
一方、個人旅行では、どの道を行くか、どこに泊るか、いつ食べるか、
旅行のすべてを自分で決めなければならないのです。
自分の裁量による部分が大きくなり、どう判断するかで結果が大きく
異なるのです。選択肢が多くなった分だけあいまいさが増え、その中を手探りで
進まざるえなくなったのです。判断という作業は孤独を感じさせるものです。(略)
このような豊かな時代を生きるには、
これまでとは違った知恵や力が必要になるのです。
その第一の力は「あいまいな状況を探索的に生きる力」です。
ある学生が、「ひたすら打ち込めることがない。それさえ見つかれば、
そして成功する約束があれば取り組めるし、生活が充実するのに」と
語ったことがあります。
この生き方は、決められた一本のレールをひた走る受験のような生活には
有利かもしれませんが
豊かな時代にはレールそのものがないのです。困難や苦しみに耐えて進めば目標に
到達するという、成功が約束された道がなくなったのです。
うまくいくかどうかわからないリスクを自分で背負い、道を作りながら進しかないし、
そうした生き方を良しとする価値観を身につけることが
求められるようになったのです。(略)
第二の力は「自分とつきあう力」です。
あいまいな状況を生きるには、「自分が何を望んでいるのか、どう感じているのか」が
羅針盤やナビゲーターの働きをするのです。自分で楽しみを味わい、
結果を自分で評価する力もいります。
このためには自分の心の声をうまく聴けることが必要になるのです。(略)
豊かな時代では、自分の声が聴こえないとどう進んでいいかわからず
途方に暮れて立ちすくみ、時には遭難さえしかねないのです。
第三の力は、「自分と折りあう力」です。
豊かさは、たくさんの可能性を提示するので、
何でもできるかのように思わされがちです。
しかし、人は体が一つしかなく、時間は一日二十四時間しかないために、
現実に選びうるのはごく限られています。
苦労して選んだとしても必ずしもうまくいくともかぎりません。
苦労して選んだことがうまくいかないときに、
やけを起こさないで対処する力が必要になるのです。(略)
不完全さに折りあいをつけて楽しみを味わう力がないと、
「豊かさ」はあくまで欲望の充全な充足を求める無間地獄のような世界になるのです。
第四の力は、「内的な倫理観や価値観、センスに裏付けられた節制力」です。
豊かな時代は、子どもでも消費社会という「巨大なテレビショッピングの世界」に
放り出されるのです。
そこはあらゆるものが魅力的にすり寄ってくる誘惑の地雷原です。
一瞬にして金を失わせる投機的な誘惑や健康を損ねる薬など、
危険と隣り合わせの世界なのです。(略)
自分にとって何が大切かをはっきりさせ、それ以外はなるべくこだわらない、
関わらないという生き方を確立していないと、
誘惑に振り回され地雷を踏みかねないのです。(略)
(豊かな時代の知恵は)まだ誰も知らないために外から学べるものではなく、
自分の声を聴き自分の内側を見つけ培っていくしかありません。
そのために、大人も子どもも「ゆっくり自分と向き合う時間」を確保することが
求められているのです。
『ひきこもる小さな哲学者たちへ』 小柳晴生 生活人新書 P31 より
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
今の時代は大人も子どもも生きるのが難しい? 1
の記事が中途半端なままになっていることを気にかけながら、
ずいぶん日が経ってしまいました。前回の記事を読んで、
「ん?」と腑に落ちない気持ちを抱いた方がいらっしゃるんじゃないかと思います。
誰もが経済的な面で何らかの不安感を抱え、
ニュースでは貧困とか生活苦という言葉がクローズアップされることも多い昨今、
「豊かな世界を生きる知恵」とか「豊かさが生きる難しさを生み出している」なんて、
バブル崩壊前の勘違いを引きずっているのでは……という印象を
与えかねない地雷付きの話題なのかもしれません。
でも、今の時代、子どもを育てていくには、この話題から決して目を背けるわけには
いかない、というのがわたしの実感です。
臨床心理士の小柳晴生先生は、著書の中で、「歴史上はじめて、物と情報のあふれる
『豊かな世界』に足を踏み入れた」わたしたちが、
どのような生きづらさを抱えるようになったのか、書いておられます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「生きるために食べ、食べるために稼ぎ、稼ぐために働く」という疑いようもなく
信じられた価値観が力を失い、
「空腹に腹いっぱい食べた満足感」や「経済的にしばらくしのげる安心感」や
「長年欲しかったものを手に入れた喜び」といった生きる実感が味わいにくくなりました。
着るものがないから服を買うのではなく、タンスいっぱいにあるけれど流行や買い物を
楽しむことが目的となり、飢えを満たすために食べるのではなく、
おいしさや人と楽しい時間を過ごすために食べるようになったのです。
※『大人が立ち止まらなければ』小柳晴生著/生活新書
の一部を少し短くまとめて紹介しています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
生きる実感が味わいにくくなると、
何が確かなものかわからないことからくる漠とした不安や
絶え間ない物足りなさをもたらします。
そうした生きる実感が味わいにくい世界で
生まれ、育っていく子どもたちは、どうなるのでしょう?
豊かな世界というのは、たとえ経済的に自分が豊かでなかったとしても、
絶え間ない誘惑や欲望を刺激する情報にさらされ続ける世界です。
つまり何かを手にしても、すぐに新たな欲望にかきたてられて不足感しか残らないし、
何をしようと思っても、すでに誰かがやった後なのを思い知らされて、
気持ちが萎えてしまうのです。
そこで、大人たちが、とにかく他の子より先に学習を進めておいて、
他の子より上手にできることを増やしておきさえすれば、
「明るい未来を手にすることができる」「幸せに生きていける」と思って子育てしても、
実際に努力の末、子どもが手にできるのは、
不足感や自分に対する不満足感だけなのかもしれません。
生きる実感が希薄なまま、
「この大学に入れさえすれば幸せに生きることができる」
「この職に就くことさえできれば安穏と暮らしていける」と信じて目標に邁進しても、
得た結果に満足し続けることができるのでしょうか。
それならどうすれば子どもに生きる実感が味あわせてあげることができるのかというと、
まず、溢れる情報やハイスピードに変化していく世の中に、
大人の心がいっぱいいっぱいになっていることに気づくこと、
現在の世界で、生きる実感を味わうことは本当に難しいんだと
実感することじゃないかと思っています。
立ち止まること、ペースを落とすこと、自分の不安をごまかすために掲げた競争心や
見栄を満たすための目標を手放してみないことには、始まらないのかもしれません。

話は変わって、
上の写真は、大阪城の巨石をどうやって船に積み込んだのか実験するための模型です。
この実験をする際、引き潮から満ち潮に変化していくところを再現するために、
子どもたちが総出で、ペットボトルに水を溜めては注ぐを繰り返しています。
この実験を、さまざまな年齢の子らのグループでやりました。
2歳くらいの子(さすがにこの年齢の子は、グループの子ではなく妹、弟さんですが)
から中学生になる子まで、
どんなにやる気なさげにぐだぐだ言ってた子も、何をするのもめんどくさがるような子も、
本当にいきいきと大はしゃぎで水を汲みに行っては注ぐ作業に興じるものですから、
わたしを含め見ている大人はみな、子どものパワーに圧倒されてしまいました。
水の重さ、汲みにいく手間、注ぐ時の水の迫力、みんながわいのわいのと夢中になって
やっている感じ、めちゃくちゃややんちゃがしたい気持ち、
「どうなるんだろう」という疑問、「もっともっと」と身体を使いきりたい感じ……と、
どれも生きている実感を感じさせてくれるものなのでしょうか。
生きている実感は、こんなにも子どもをパワフルにするものなんだろうか、
と、子どもの頃、団地の自転車置き場の屋根に上ったり、
近くの池にザリガニ釣りに行ったりして、
自分の心や身体が望むことを思いっきりやりきった時の充足感が蘇ってきました。