多元的知能に関するご質問をいただきましたので、過去記事を紹介させていただきます♪
このブログでも何度か取り上げさせていただいたMI理論…
「多元的世界の世界」の著書のエピソードのタイトルは「2013年のMI理論」
その中に、





2013年までに知能が多元化に値するという考えがより幅広く
受け入れられているなら、私は本当に満足するだろう





と著者の痛切な願いが書かれていました。
私もMI理論が教育の世界に浸透していくことを、切に願うもののひとりです。
2013年に近づきつつある今、多元的知能という考えは
多くの方に受け入れられてきたのでしょうか?
最近はかつてのような成績至上主義は影をひそめていますね。
私は、脳科学の進歩などのおかげで、
年々、そうした多角的な視野に立った教育法が
理解されているように感じています。





『子どもの脳が学ぶとき』の著者の戸塚 滝登先生が教育現場で実践されていた
教育も、このMI理論を素晴らしい形で教育現場に生かしたものであると思います。
親子レッスンでお会いする親御さんたちも、大きな視野で子どもの教育を捉えている方が多いです。




やっぱり2013年に向かって、一歩一歩、教育は進化しているのでしょうね。
数年すると、人の育ちを多元的に見て、
教育の世界に役立てていくことが当たり前のこととなっていることを
願っています。
多元的知能の関する過去記事です。
☆ 多元的知能を評価するテスト!? 1 IQを超える試み
☆多元的知能を評価するテスト!? 2 エジソンくんは救えるのか?
☆多元的知能を評価するテスト!? 3 科学編
☆多元的知能を評価するテスト!? 4 学業成績とは何でしょう?
☆ 多元的知能を評価するテスト!?5 得意分野と不得意分野
写真はお手をするワンコロボットです♪

web拍手を送る
このブログでも何度か取り上げさせていただいたMI理論…
「多元的世界の世界」の著書のエピソードのタイトルは「2013年のMI理論」
その中に、





2013年までに知能が多元化に値するという考えがより幅広く
受け入れられているなら、私は本当に満足するだろう





と著者の痛切な願いが書かれていました。
私もMI理論が教育の世界に浸透していくことを、切に願うもののひとりです。
2013年に近づきつつある今、多元的知能という考えは
多くの方に受け入れられてきたのでしょうか?

最近はかつてのような成績至上主義は影をひそめていますね。
私は、脳科学の進歩などのおかげで、
年々、そうした多角的な視野に立った教育法が
理解されているように感じています。





『子どもの脳が学ぶとき』の著者の戸塚 滝登先生が教育現場で実践されていた
教育も、このMI理論を素晴らしい形で教育現場に生かしたものであると思います。
親子レッスンでお会いする親御さんたちも、大きな視野で子どもの教育を捉えている方が多いです。




やっぱり2013年に向かって、一歩一歩、教育は進化しているのでしょうね。
数年すると、人の育ちを多元的に見て、
教育の世界に役立てていくことが当たり前のこととなっていることを
願っています。

多元的知能の関する過去記事です。
☆ 多元的知能を評価するテスト!? 1 IQを超える試み
☆多元的知能を評価するテスト!? 2 エジソンくんは救えるのか?
☆多元的知能を評価するテスト!? 3 科学編
☆多元的知能を評価するテスト!? 4 学業成績とは何でしょう?
☆ 多元的知能を評価するテスト!?5 得意分野と不得意分野
写真はお手をするワンコロボットです♪
web拍手を送る











 お勉強ぽいものは面白くない、
お勉強ぽいものは面白くない、
 web拍手を送る
web拍手を送る


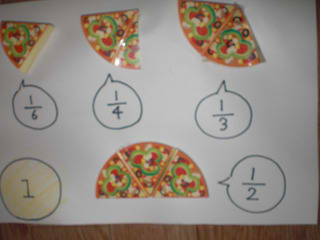




 )
)