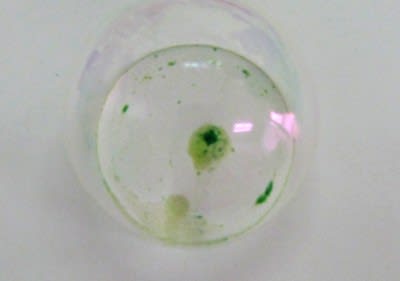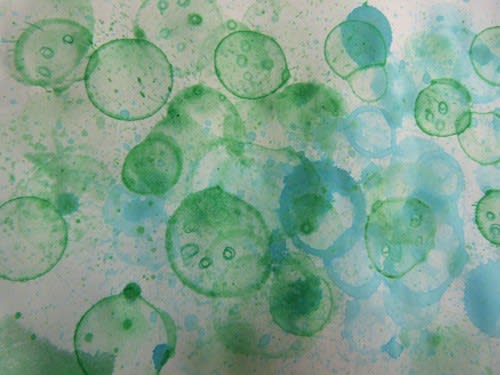(わたしの子どもの頃の話です。)
小学校低学年頃だったと思います。
わたしは妹と近所の年下の子らを連れて、坂を5分ほど上って行って給水塔のそばの広場で遊んでいました。
そこは駐車場でもあるのですが、昼間の車の出入りはなく、四葉のクローバー探しの穴場でした。
小さな子たちを連れて、大人の目のないこんな場所まで遊びに行っていたのも、団地の前の庭には、じめじめした雑草が生い茂っていて、やぶ蚊やムカデや蛇がいるので、遊びといっても、探検ごっこか落とし穴作りしかしようがなかったからなのです。
ひとしきり遊んで、みんなでぞろぞろ来た道をくだりはじめた時、郵便配達人の格好をした20~30歳くらいの男性がこちらに近づいてきました。
優しい口調で話しかけてきましたが、その雰囲気や表情からは、気味が悪いような恐ろしいような得体の知れないものが感じられました。
当時、その地区では幼い子どもをターゲットにする変質者が出没するという噂が繰り返しささやかれていました。
また、そうした事件で、カッターで切りつけられたり、首を絞められたりして死んだ子がいるとニュースでやっていた、というこそこそ話が、子どもたちの間をまわってもいました。
わたしは見知らぬ人が近づいてきて、何かすごく楽しいことがあるような口調で団地の裏の人気のない場所に誘おうとしているのを聞くと、ゾクッと背筋が凍るような思いがして、警戒心をあらわにして、年下の子たちを催促するように押しながら帰りを急ごうとしました。
すると、その男性は、わたしの緊張した疑り深そうな目つきを避けるように無視したまま、少し離れたところにいた妹と妹の友だちの前にかがみこんで、朗らかで親切なお兄さんという様子で声をかけていました。
そして何気なくふたりの手を取ると、どこかへ連れて行こうとしました。
妹は快活で怖いもの知らずなところのある気の強い子でした。それと同時に、母との関係がうまくいっていなかったからか、(そうした事情については、「親のコンプレックスと子どもの困った行動 」という記事の中で書いています)自分に構ってくれる甘えられそうな相手に、強く惹きつけられるところがありました。
他の子らも、その男性と妹たちの後ろをぞろぞろと付いて行こうとしていました。
誰といっしょだったのかはっきり覚えていないのですが、おそらく妹たちよりももっと幼い子らだったのだと思います。
わたしは後ろずさりをしながら、近くの団地の階段をかけのぼってドアを叩いて大人の助けを得ようか、母のところまで知らせに戻ろうかと思いをめぐらせていました。
でも、周囲はひっそりと静まり返っていて他の大人の気配がありませんでした。
母を呼びに行って戻ってくるまでは途方もないほど時間がかかるようにも思えました。
そんなことを迷っている間にも、妹たちは団地の裏に消えようとしていました。
あの人はカッターを持っているのかもしれないし、いきなり両手で首を絞めようとするのかもしれない……。
恐怖心で声も出せずにガタガタ震えていたわたしは、ふいに覚悟を決めて、その人に向かって突進していきました。
それから妹たちの手を握るとグイグイと引っぱりました。
その剣幕に驚いて、その男性はふいに妹たちの手を放すと近くにとめていた自転車で走り去っていきました。
それからどうなったのか、記憶はそこで途切れています。
ですが、自分が自分でないような不思議な感じがした覚えがあります。
というのも、その頃のわたしは、内気過ぎるほど内気で、弱々しい子どもだったのです。
鼻が悪かったり、喉や胸がぜいぜいして息をするのも苦しかったりして、疲れると身体を引きずるようにとぼとぼ歩く癖を、近所の人に笑われたこともあります。
人と関わる時に強く出れなくて、隣の席の子に下敷きで繰り返し頭を叩かれても言い返すことも逃げることもできなくて、その場にフリーズしていたり、近所の年上のいじめっ子に繰り返しだまされて、留守宅に閉じ込められたりしていました。
そんな風に自分で自分を守る力すらないのに、妹のこととなると、カミナリが怖くて震えあがっているのに、激しくカミナリが鳴るどしゃぶりの中を駆け抜けて迎えに行った記憶もあります。
わたしと妹は特に仲のいい姉妹というわけではなく、性格も遊びの好みも違う上、「妹は困った子、悪い子」という母のまなざしに同調しなくてはならない雰囲気の中で、親戚の子たちや友だちよりも遠い存在でした。
親戚の子たちや友だちよりも遠い存在であった妹のことで、どうして自分はいつも躍起になるのか、我を忘れて、恐怖の中に飛び込んでいったりするのか、ずっと自分でも不思議でした。
このブログの記事(ワガママな振舞いが目立つ子にどのように接したら良いでしょう? )を書く中で、「そうした激しい気性や気難しさや過敏さを持っている子たちを、特別にかわいく思い……」と書いてから、「これだと、育てやすい子は、特別には、かわいく思っていないようでよくないな」と躊躇しつつも、なぜだか削りたくありませんでした。
迷った挙句、言葉をそのまま残した瞬間、どうして自分が妹に関することでは、強い衝動に駆り立てられることが多かったのか、理由がわかったような気がしました。
妹は要求が多くて妥協を知らない育てにくさのある子で、どんなささいな衝突もとことんエスカレートさせて、長丁場の戦いに持ち込まずにはおれない性格でした。
わたしは、赤ちゃん時代に始まって、何年経っても母が妹とぶつかり続けたことや、結局、妹が大人になるまで互いに歩み寄らなかったことに腹を立てる一方で、それがどうしようもなかったことも承知していました。
母はその時代の子ども観やしつけ観の中で精いっぱい誠実に子どもを育てようとしていただけで、妹に対する愛情も優しさも本物でした。
わたしは母と揉めてばかりいる妹に、「どうして1つもらったら10欲しがるのか」
「どうして今、この状況では我慢すべきだと納得できないのか」とやきもきしていました。
昼寝の時に、母の両隣にわたしと妹が寝ることを、妹は絶対に許しませんでした。
毎回、母の全てを独占したがって、わたしに噛みついたり、髪の毛を引っぱったりしていました。
次回に続きます。