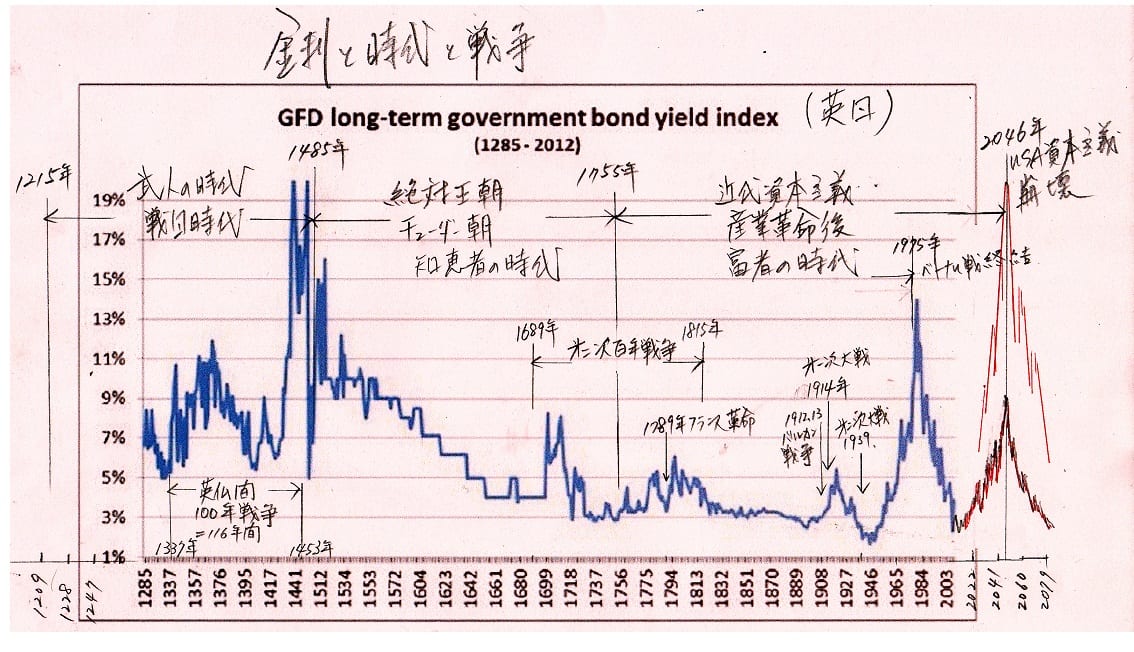前回の水野和夫さんの、金利低下と資本主義の危機”に対する批判です。
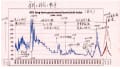
● 図からわかるように戦争と金利は略、どの時代でも連動しています。
お金の借り手で、最大のお得意さんは、国家なのです。
● 従って、戦争すれば、国家は民間の銀行から大量のお金を調達します。
これが国債金利の上昇となって現れるのです。
● 図から、英国の戦国時代=武人の時代はその前半の金利は分かりませんが、
仏との100年戦争を開始した、1337年前後から急激に金利が上がって います。
いったん下がりますが、100年戦争の終わりころにも、急激な上昇がみられます。
● 100年間毎年戦争をしているわけではありませんから、変動は当然です。
終わりころの急激な上昇から、絶対王朝への移行期は、再び急激な
低下を見ます。
● 同様の時代の移行期、絶対王朝と近代資本主義への移行期も、金利は
低下しています。その移行期の前後は、第二次100年戦争が起こり、
両端で金利が増えているのが分かります。後者の金利の上昇期は
その間にフランスの革命があり、また革命後はナポレオンが
大陸を侵略した時代でもあるのです。
● バルカン戦争とそれに続く、第一次大戦は、小さな山を造っています。
第二次大戦とそれに続く朝鮮戦争、ベトナム戦争とUSAは膨大な
お金を費やして疲弊してゆく過程でもあります。
● 1966年から~1982年までの不景気は、金利が上がって行く過程でもあり、
不景気なのに金利が高くなる、スタグフレーションと呼ばれる現象を
起こしています。
● むしろ高金利が、経済の疲弊を齎し、その後の没落に関わっていると
見るほうがよいでしょう。特に武人の100年戦争の時の金利からは
そのような傾向がみられます。
● 貸し倒れのリスクなどを勘案して金利は決めますから、むしろ高いのが
困るのです。これは日常の高いサラ金を借りている人を見れば
分かります。リスクが高いので、銀行では貸してくれない人に
高利で貸すのがサラ金です。
● 当然貸し倒れがあるので、金利は高くなるのです。直近の例では、
ギリシアがその信用を無くし、一時30%前後の金利を呈して
いたと記憶しています。
● 従って金利が低いのは、むしろ貸し倒れの心配が少なくから、つまり
信用度が高いから起こるというのが正解でしょう。勿論お金が
有り余ってかつ借り手がない状態ともいえます。
● もちろんお金に対する需要がない=不景気ということもありますが、
金利はそのサイクルを造っているので、低金利=資本主義の
崩壊とは単純には結び付かないものです。
● 図から、19世紀、英国の絶頂期は、むしろ低金利が100年近くも
続いているのが見えます。日本の低金利も、お金が有り余って
供給能力も十分ですが、不景気で借り手がない状態の為に
金利が上がらないとも言えます。
● もちろん不景気になれば、企業や金融機関を助ける為にも金利を
下げます。いずれにしても、お金に対する需要が高まれば、金利は
上がるものです。その一番大きな原因が、戦争なのです。
● 図の予想のように、2046年は英米型の先進資本主義が崩壊するときです。
金利のサイクルから、図のように崩壊直前は高金利が予想できます。
そして、崩壊と同時に、つまり次の武人の国家になる前後は、
急激な金利の低下がみられるでしょう。
● 1485年の戦国時代から、絶対王朝の時代に移行するときの様相に
似ています。大小二つの金利の山を書いていますが、これは
世界的に大混乱すると思われる、2029年から2046年までの
間の混乱期=第二次大戦期≒内戦型世界大戦と予想できる
時代に、USAがどの程度関与するかによって
変わるとみていることです。
● つまり、資本主義が崩壊して、お金が無くなったUSAは、その関心が
薄れて、再びモンロー主義に走る可能性があるからです。
それが、低い金利と表現しています。
● 高い金利は、腐ってもタイのUSAは、やはり世界の混乱や戦争に
巻き込まれて、戦費を費やすとみた場合です。
● いずれにしろコンドラチェフサイクルから見えることは、金利の上昇です。
今回の世界の金融緩和の結果、多大なお金が世界にあふれ、やがて
景気の回復とともに、インフレが起こり、それを抑えるためにも
高金利になることが予想できます。
● ハイパーインフレを心配する人もいますが、少なくとも世界一の
貯金大国、供給能力のある日本では起こらないでしょう。
● 既に、今まで年間換算で90兆円近い余分なお金の垂れ流しをしても
殆どビクともしない日本経済です。
● 図からも、一つの時代は略270年で転換しているのが見えます。
つまり、270年の寿命が来たから崩壊するのです。
● それにまつわる諸々の現象は、その発展・成熟・老化に合わせた、
病態にしか過ぎないのです。原因ではありません。
● Life Span Theory of Era=時代の270年寿命説とでも表現しましょう。
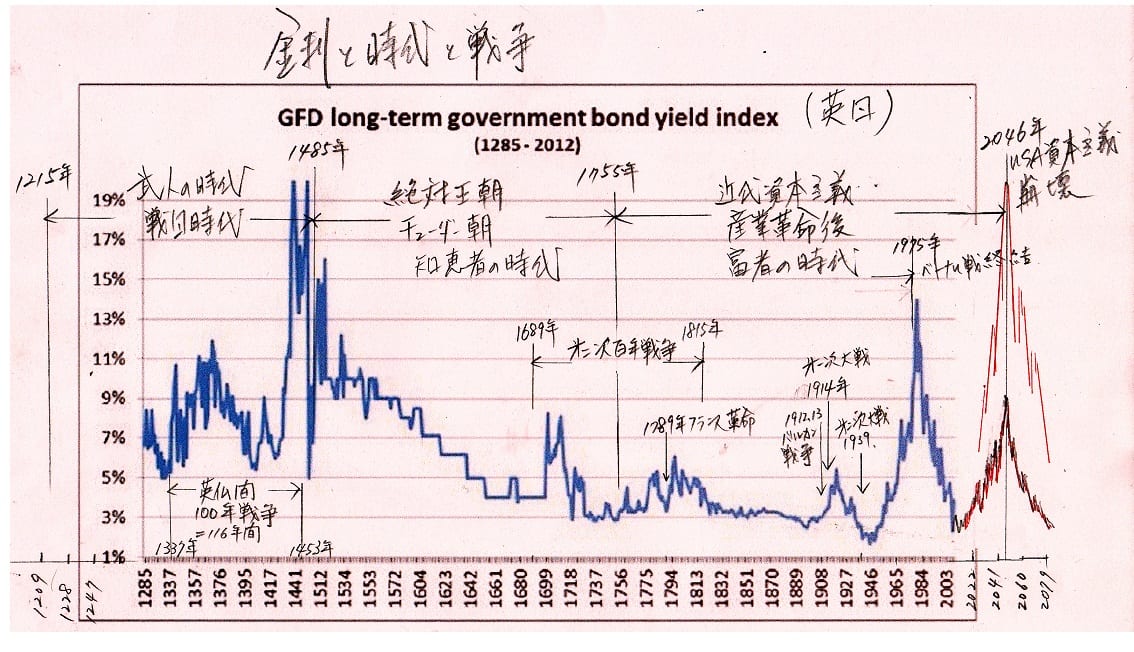
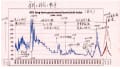
● 図からわかるように戦争と金利は略、どの時代でも連動しています。
お金の借り手で、最大のお得意さんは、国家なのです。
● 従って、戦争すれば、国家は民間の銀行から大量のお金を調達します。
これが国債金利の上昇となって現れるのです。
● 図から、英国の戦国時代=武人の時代はその前半の金利は分かりませんが、
仏との100年戦争を開始した、1337年前後から急激に金利が上がって います。
いったん下がりますが、100年戦争の終わりころにも、急激な上昇がみられます。
● 100年間毎年戦争をしているわけではありませんから、変動は当然です。
終わりころの急激な上昇から、絶対王朝への移行期は、再び急激な
低下を見ます。
● 同様の時代の移行期、絶対王朝と近代資本主義への移行期も、金利は
低下しています。その移行期の前後は、第二次100年戦争が起こり、
両端で金利が増えているのが分かります。後者の金利の上昇期は
その間にフランスの革命があり、また革命後はナポレオンが
大陸を侵略した時代でもあるのです。
● バルカン戦争とそれに続く、第一次大戦は、小さな山を造っています。
第二次大戦とそれに続く朝鮮戦争、ベトナム戦争とUSAは膨大な
お金を費やして疲弊してゆく過程でもあります。
● 1966年から~1982年までの不景気は、金利が上がって行く過程でもあり、
不景気なのに金利が高くなる、スタグフレーションと呼ばれる現象を
起こしています。
● むしろ高金利が、経済の疲弊を齎し、その後の没落に関わっていると
見るほうがよいでしょう。特に武人の100年戦争の時の金利からは
そのような傾向がみられます。
● 貸し倒れのリスクなどを勘案して金利は決めますから、むしろ高いのが
困るのです。これは日常の高いサラ金を借りている人を見れば
分かります。リスクが高いので、銀行では貸してくれない人に
高利で貸すのがサラ金です。
● 当然貸し倒れがあるので、金利は高くなるのです。直近の例では、
ギリシアがその信用を無くし、一時30%前後の金利を呈して
いたと記憶しています。
● 従って金利が低いのは、むしろ貸し倒れの心配が少なくから、つまり
信用度が高いから起こるというのが正解でしょう。勿論お金が
有り余ってかつ借り手がない状態ともいえます。
● もちろんお金に対する需要がない=不景気ということもありますが、
金利はそのサイクルを造っているので、低金利=資本主義の
崩壊とは単純には結び付かないものです。
● 図から、19世紀、英国の絶頂期は、むしろ低金利が100年近くも
続いているのが見えます。日本の低金利も、お金が有り余って
供給能力も十分ですが、不景気で借り手がない状態の為に
金利が上がらないとも言えます。
● もちろん不景気になれば、企業や金融機関を助ける為にも金利を
下げます。いずれにしても、お金に対する需要が高まれば、金利は
上がるものです。その一番大きな原因が、戦争なのです。
● 図の予想のように、2046年は英米型の先進資本主義が崩壊するときです。
金利のサイクルから、図のように崩壊直前は高金利が予想できます。
そして、崩壊と同時に、つまり次の武人の国家になる前後は、
急激な金利の低下がみられるでしょう。
● 1485年の戦国時代から、絶対王朝の時代に移行するときの様相に
似ています。大小二つの金利の山を書いていますが、これは
世界的に大混乱すると思われる、2029年から2046年までの
間の混乱期=第二次大戦期≒内戦型世界大戦と予想できる
時代に、USAがどの程度関与するかによって
変わるとみていることです。
● つまり、資本主義が崩壊して、お金が無くなったUSAは、その関心が
薄れて、再びモンロー主義に走る可能性があるからです。
それが、低い金利と表現しています。
● 高い金利は、腐ってもタイのUSAは、やはり世界の混乱や戦争に
巻き込まれて、戦費を費やすとみた場合です。
● いずれにしろコンドラチェフサイクルから見えることは、金利の上昇です。
今回の世界の金融緩和の結果、多大なお金が世界にあふれ、やがて
景気の回復とともに、インフレが起こり、それを抑えるためにも
高金利になることが予想できます。
● ハイパーインフレを心配する人もいますが、少なくとも世界一の
貯金大国、供給能力のある日本では起こらないでしょう。
● 既に、今まで年間換算で90兆円近い余分なお金の垂れ流しをしても
殆どビクともしない日本経済です。
● 図からも、一つの時代は略270年で転換しているのが見えます。
つまり、270年の寿命が来たから崩壊するのです。
● それにまつわる諸々の現象は、その発展・成熟・老化に合わせた、
病態にしか過ぎないのです。原因ではありません。
● Life Span Theory of Era=時代の270年寿命説とでも表現しましょう。