元日は昼も夜も飲んでしまったので、新聞以外の活字は読まなかった。そこで2日から読書開き。
年末から読み始めていた2冊を読み上げる。ちなみに私は、一冊に集中し、それを終えてから次にかかるということはあまりしない。しばしば、並行して複数の書を読み進めたりする。だいたいはジャンルの異なったもので、哲学や思想関係と小説やエッセイなどを同時進行的に読んだりする。
なぜそんなことをするかというと、理由はいたって簡単で、飽きっぽい性格だからである。ある程度集中して読んでいると、疲れて注意力が散漫になり、いつの間にかただただ視線が活字の上を滑っているだけになる。こうなると理論書などはその論理の筋道がまったく追えなくなる。
そんな時は、さっとジャンルを替えてまったく別のものを読み始める。すると、不意を突かれてリフレッシュされた頭脳の別の箇所が回転し始めるという仕掛けだ。ときには2冊以上でそれをするから、まるで学校の時間割に沿ったようになる。もちろん、読み終えるのは同時とはならない。

ところが2日は珍しく、ともに2冊の書を読み終えた。
一冊は、同郷岐阜の芥川賞作家、堀江敏幸の『雪沼とその周辺』という連作オムニバス風の短編小説集で、7篇の短編が「雪沼」という架空の街を舞台に、緩やかな結びつきをもって展開されている。ひとつひとつは独立した短編だが、よく読むと、それぞれの話の節々に、ほかの短編で展開されている状況や風景とオーバーラップする部分があって、これらがまとまって「雪沼」であり、「その周辺」の話であることがわかる。
そして読了すると、ひとつひとつの短編の味わいがひとつに凝縮されて、いっそうそれらを引き立たせるというとても良くできた短編集である。
全体を貫くトーンはノスタルジーといえるかもしれない。しかし、ここにあるノスタルジーは失われゆくものへの惜別や哀愁という後ろ向きなものではなく、そのノスタルジックなものをポジティヴに引き受けて生きてゆくような人たちの生きざまそのものといえる。だからこの短編集は、近代が押しつぶすものへのレクイエムというより、むしろ、にもかかわらずマニアックな生を全うしようとする人々へのオマージュといえるだろう。
その意味でも、この「雪沼」にまとめられた各短編は、その舞台としての地理的同一性のみではなく、その内容やテーマ性においても確固とした芯のようなものを共有している。
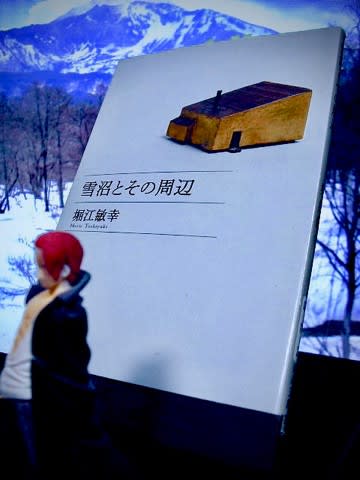
しかし、読み終えて思うのだ。思えば、この短編集の舞台、「雪沼」こそ現代の桃源郷ではないのかと。スーパーもコンビニもない商店街を中心とした街、その孤立と孤高こそがここに紡ぎ出された物語を可能にしている地平ではないのかと。
なお、この小説集は、川端賞、谷崎賞、木山捷平賞などを受賞している。
もう一冊は『ローティ論集』。アメリカの哲学者、リチャード・ローティのやはり7篇の短い論文やエッセイ風のものに、編訳者である冨田恭彦が、それぞれの文頭に「解題」を置き、その後にローティの本文が始まるという読みやすい構成で、ローティの入門にも、そのおさらいにもなる書といえるだろう。
哲学という世界には、それを二分する不思議な壁のようなものがある。それが、いわゆる大陸系の哲学と、分析哲学などの英米系のそれであって、この二派は相互に、まるで相手がなきかのように振る舞っていて、その間の架橋も越境もほとんどないぐらいである。

そんななか、このローティはその両者に精通した稀有な存在である。スターリズムが猛威を奮った1930年代、それに断固として抵抗したトロッキストの両親に育てられたという珍しい経歴のローティは、アメリカという土地で育ち、学びながら、どこかトランスナショナルな気風をもつに至ったのかもしれない。
彼の関心は、哲学を「役に立つ」思考にすることである。役に立つといっても杉田水脈ばりに「生産性」に役立つという卑近でいじましいものとはまったく違う。
ローティは、世界と自分とを位置づけ、人間の共同体を維持してゆくための「有効な」思考を目指している。
そのために彼が拒否するのは、世界を一者から説明し尽くすとし、世界には唯一の真理や正義が存在しそれに帰依せよと説くような哲学、すなわち、形而上学である。それに基づく偏狭な世界観が世界を分断し、人々の共存を危うくしているというわけだ。

彼は、哲学というのは、「より適切な説明の更新」だという。哲学者は、一つの世界解釈を提示する。それらは私たちの世界観をより広げることになるかもしれない。しかし、賞味期限が終わるとそれ自体が桎梏になる。そんなとき、それを凌駕するより適切な説明が登場する。彼のいう哲学史は、その歴史にほかならない。
そんな立場から彼が共感するのは(もちろん差異は差異として保留しながらだが)、分析哲学系では「言語ゲーム」の後期ウィトゲンシュタイン、大陸系では、ニーチェ、ハイデガー(ただし前期)それにデリダなどである。
彼の論法は明確である。私的信念としての哲学をその「使用」と厳密に区別する。そこにこそ、たんなる信念の吐露ではなく、使ってなんぼ、役に立ってなんぼというプラグマティストの面目躍如たるものがある。
役に立てば何でもありかという相対主義への彼の歯止めは、「人類の苦痛や悲惨の減少」という極めて具体的な点にあることをいい添えておこう。
これらをも含めて、プラグマティズム特有の論法ではある。
これを書きながら、この国のプラグマティストとして、上のローティに似た信念を生き抜いた鶴見俊輔を思い出した。
*『雪沼とその周辺』 堀江敏幸 新潮文庫 400円+税
*『ローティ論集』 冨田恭彦 編訳 筑摩書房 4,200円+税
年末から読み始めていた2冊を読み上げる。ちなみに私は、一冊に集中し、それを終えてから次にかかるということはあまりしない。しばしば、並行して複数の書を読み進めたりする。だいたいはジャンルの異なったもので、哲学や思想関係と小説やエッセイなどを同時進行的に読んだりする。
なぜそんなことをするかというと、理由はいたって簡単で、飽きっぽい性格だからである。ある程度集中して読んでいると、疲れて注意力が散漫になり、いつの間にかただただ視線が活字の上を滑っているだけになる。こうなると理論書などはその論理の筋道がまったく追えなくなる。
そんな時は、さっとジャンルを替えてまったく別のものを読み始める。すると、不意を突かれてリフレッシュされた頭脳の別の箇所が回転し始めるという仕掛けだ。ときには2冊以上でそれをするから、まるで学校の時間割に沿ったようになる。もちろん、読み終えるのは同時とはならない。

ところが2日は珍しく、ともに2冊の書を読み終えた。
一冊は、同郷岐阜の芥川賞作家、堀江敏幸の『雪沼とその周辺』という連作オムニバス風の短編小説集で、7篇の短編が「雪沼」という架空の街を舞台に、緩やかな結びつきをもって展開されている。ひとつひとつは独立した短編だが、よく読むと、それぞれの話の節々に、ほかの短編で展開されている状況や風景とオーバーラップする部分があって、これらがまとまって「雪沼」であり、「その周辺」の話であることがわかる。
そして読了すると、ひとつひとつの短編の味わいがひとつに凝縮されて、いっそうそれらを引き立たせるというとても良くできた短編集である。
全体を貫くトーンはノスタルジーといえるかもしれない。しかし、ここにあるノスタルジーは失われゆくものへの惜別や哀愁という後ろ向きなものではなく、そのノスタルジックなものをポジティヴに引き受けて生きてゆくような人たちの生きざまそのものといえる。だからこの短編集は、近代が押しつぶすものへのレクイエムというより、むしろ、にもかかわらずマニアックな生を全うしようとする人々へのオマージュといえるだろう。
その意味でも、この「雪沼」にまとめられた各短編は、その舞台としての地理的同一性のみではなく、その内容やテーマ性においても確固とした芯のようなものを共有している。
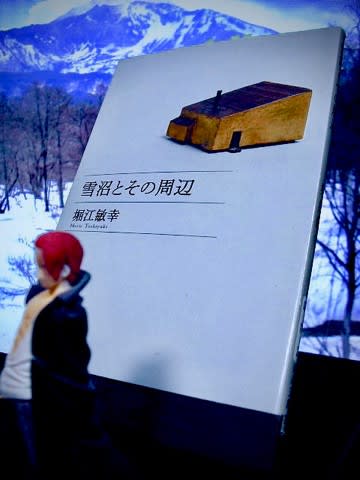
しかし、読み終えて思うのだ。思えば、この短編集の舞台、「雪沼」こそ現代の桃源郷ではないのかと。スーパーもコンビニもない商店街を中心とした街、その孤立と孤高こそがここに紡ぎ出された物語を可能にしている地平ではないのかと。
なお、この小説集は、川端賞、谷崎賞、木山捷平賞などを受賞している。
もう一冊は『ローティ論集』。アメリカの哲学者、リチャード・ローティのやはり7篇の短い論文やエッセイ風のものに、編訳者である冨田恭彦が、それぞれの文頭に「解題」を置き、その後にローティの本文が始まるという読みやすい構成で、ローティの入門にも、そのおさらいにもなる書といえるだろう。
哲学という世界には、それを二分する不思議な壁のようなものがある。それが、いわゆる大陸系の哲学と、分析哲学などの英米系のそれであって、この二派は相互に、まるで相手がなきかのように振る舞っていて、その間の架橋も越境もほとんどないぐらいである。

そんななか、このローティはその両者に精通した稀有な存在である。スターリズムが猛威を奮った1930年代、それに断固として抵抗したトロッキストの両親に育てられたという珍しい経歴のローティは、アメリカという土地で育ち、学びながら、どこかトランスナショナルな気風をもつに至ったのかもしれない。
彼の関心は、哲学を「役に立つ」思考にすることである。役に立つといっても杉田水脈ばりに「生産性」に役立つという卑近でいじましいものとはまったく違う。
ローティは、世界と自分とを位置づけ、人間の共同体を維持してゆくための「有効な」思考を目指している。
そのために彼が拒否するのは、世界を一者から説明し尽くすとし、世界には唯一の真理や正義が存在しそれに帰依せよと説くような哲学、すなわち、形而上学である。それに基づく偏狭な世界観が世界を分断し、人々の共存を危うくしているというわけだ。

彼は、哲学というのは、「より適切な説明の更新」だという。哲学者は、一つの世界解釈を提示する。それらは私たちの世界観をより広げることになるかもしれない。しかし、賞味期限が終わるとそれ自体が桎梏になる。そんなとき、それを凌駕するより適切な説明が登場する。彼のいう哲学史は、その歴史にほかならない。
そんな立場から彼が共感するのは(もちろん差異は差異として保留しながらだが)、分析哲学系では「言語ゲーム」の後期ウィトゲンシュタイン、大陸系では、ニーチェ、ハイデガー(ただし前期)それにデリダなどである。
彼の論法は明確である。私的信念としての哲学をその「使用」と厳密に区別する。そこにこそ、たんなる信念の吐露ではなく、使ってなんぼ、役に立ってなんぼというプラグマティストの面目躍如たるものがある。
役に立てば何でもありかという相対主義への彼の歯止めは、「人類の苦痛や悲惨の減少」という極めて具体的な点にあることをいい添えておこう。
これらをも含めて、プラグマティズム特有の論法ではある。
これを書きながら、この国のプラグマティストとして、上のローティに似た信念を生き抜いた鶴見俊輔を思い出した。
*『雪沼とその周辺』 堀江敏幸 新潮文庫 400円+税
*『ローティ論集』 冨田恭彦 編訳 筑摩書房 4,200円+税

















