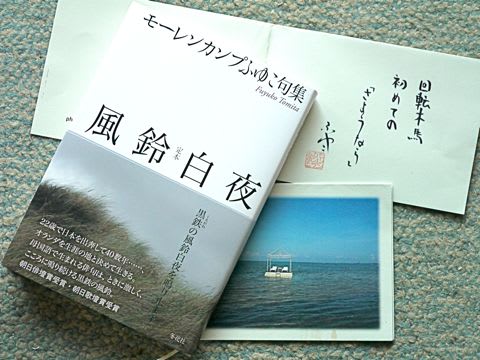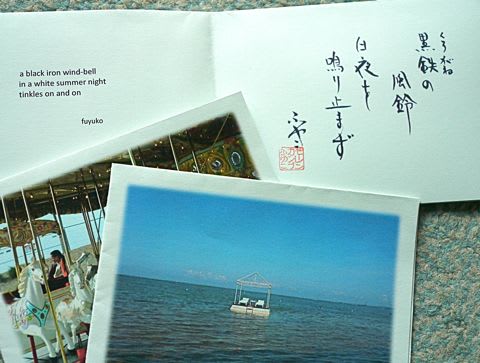写真は私が作った門松です。片田舎に住んでいるおかげで何とか素材は揃います。わかりにくいでしょうが、一応、松竹梅が揃っています。それだけでは締りがないので我が家の紅葉したナンテンを添えたらなんとか格好がつきました。
高さは70センチほどで片側だけです。

==================================
石原千秋の『国語教科書の思想』の続編ともいうべき、『国語教科書の中の「日本」』を読了しました。
正直いって、前著のリフレインも多く、この人の語り口もだいたいわかってきたので、それほど驚くような刺激はなかったのですが、それでもいろいろ考えさせられたり勉強になるところもありました。
この書は題名に見るように、小中の国語の教科書がどのように日本を描写し、もってどんな日本像を子どもたちに内面化させようとしているかにあります。
2008年、教育基本法が改正となり、そのひとつのキーワードは「伝統の重視」でした。
これらがどのように教科書に反映しているかについて著者は、その教材においての「昔話」と「思い出」の多さ、しかも相変わらず「田園風景の挿絵」が多いことを見出し、そうしたノスタルジーは、もはやその7割が都会生活を送っている子どもたちとの間に著しい齟齬をきたしていると指摘します。
総じていって、それらは「古き良き日本が肥大化され独り歩きする仕掛け」だというのです。
またそうした伝統重視はともすればテクノロジーそのものへの情緒的な否定に陥りがちで、高度成長期のテクノロジー礼賛と表裏をなすことが指摘されています。
さらに日本語(国語)については、他言語との比較立証を欠いたままでその「豊かさ」を強調し、根拠なき「豊かな日本語」の称揚に満ちているとします。
子どもたちは、氾濫するITテクノロジーのまっただ中にあり、効率本位の都会ぐらしやそれに準ずる生活を送りながら、一方では道徳的説教を伴った「古き良き日本」という価値基準を与えられ、その間で引き裂かれているというわけです。
これらの裏付けとしての実際の教科書からの引用は、なるほどという説得力のあるものが多いのですが、反面、著者のないものねだりではという箇所が数多く見受けられます。
例えば、小1の『じゃんけん』という教材からの連想で、「グー・チョキ・パー」が否定的差異の記号でしかないところからソシュール以降の言語論的転回との関連を指摘したりするところです。
言語論的転回とは世界がまずあって、それを言語が描写するのではなく、言語が(物自体的な)世界を分節化することによって初めて世界が立ち現れるということなのですが、それをこの段階で云々することはさして意味があるようには思えません。
さらに小2の教材『お手紙』からは、ジャック・ラカンの「手紙は届く」から、ジャック・デリダの「手紙は必ず正しい宛先に届く」という精神分析と哲学の融合のような話が展開されるのですがこれも同様です。
また、「他人の痛みをどうして知ることが出来るか」というヴィトゲンシュタイン的な設問についても触れられたり、同じくヴィトゲンシュタインの「家族的類似性」という概念への言及に及び、別の箇所では、フロイトのいう「不気味なもの」についても触れられます。
いってみれば一昔前の現代思想ブームのような観を呈するのですが、これらはそれ自身、著者である石原氏の「読み」であって、現実にそれを教えることは(氏もほのめかすように)無理というものです。小中の教室で、そうした哲学的テーマを咀嚼して子どもたちに教えることは不可能なのです。
おそらくそれらを教材として採用した側も、そこまでの深読みはしていないはずです。
話が逸れました。
著者の主張は、前著同様に「国語教育はどんな教材を選び、どんな教え方をしても思想教育たることを免れ難い」というところにあります。しかし著者は、だからといって国語教育そのものを否定するのではなく、むしろ、だからこそその内容を考えなければならないのだといいます。
そのとおりだと思うのですが、そしてまた、現在の国語教科書が(古き良き日本という)内面の共同体を作る装置に化しているという主張には十分同意できるのですが、ではどうすべきなのかはとても難しい問題だと思います。
確かに平和教育も環境教育も、ひとりひとりの内面の問題に還元されて歴史的社会的広がりから閉ざされたお説教に終わっているのは著者の引く例証から明らかなのですが、そこからの脱却は容易ではありません。
著者も指摘するように、ものごとを自由に見ることができる子がいて、そうした教科書の欺瞞とは違う見解を持ったとしても、その子にはさらなる難関が待っています。
それは上級学校への入試という関門です。
それら入試は、教科書の示す「思想」をどれだけ内面化しているかをテストします。したがってそのパラダイムから外れた子は、その関門の前で拒否されてしまうのです。
こんな風にしてまとめてしまうとミもフタもないのですが、国語は決して日本語を習得させるにとどまらず、それ自身がある種の思想やイデオロギーからなっていて、それらの内面化と日本語(国語)への招請が同時的な事象であることを気づかせてくれる点でこの書は一読の価値があると思います。
*この一年、いろいろ右往左往しながらの文章を綴ってきましたが、今年はこれで幕を閉じます。
それでもお読みいただいた皆さん、ありがとうございました。
暮れの選挙による政変は、既にじわじわっとした変化をもたらしつつありますが、来年はもっとドラスティックな変化があるやもしれません。
そんな中ですが、皆さんがいいお年をお迎えになることを祈ります。
来年もよろしくお願いいいたします。