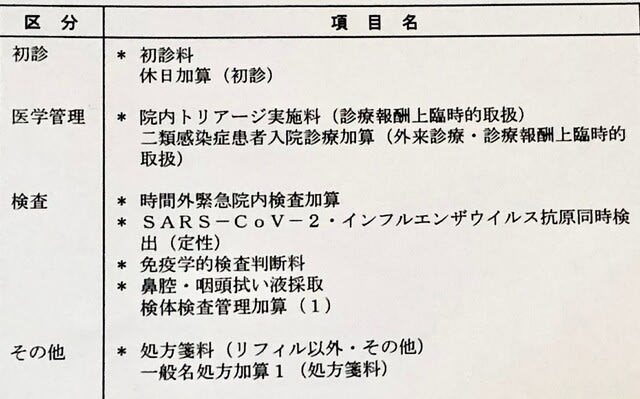先般、1・2とある小説本を、てっきり上・下と勘違いし図書館から借りてきて読んだところ、実は3巻があって、その3巻は著者デパントの母語=フランス語では出版されてはいるものの、まだ邦訳はされていないとあって、生きてるうちはその結末を見届けられないかも・・・・というミスを犯してしまったと書いた。もっとも、結末はともかく、その過程自身がけっこう面白かったからさほど後悔はしていないが。
で、今回はまたまた失敗をやらかしてしまったのだ。
舞台はやはり岐阜県図書館の新刊コーナー。ふと目をやると、ベルンハルトの『推敲』という書が並んでいるではないか。すわ、「あの」ベルンハルトの新作と迷わずに借りてきた。
この作者については、最初手にとった『朗読者』が面白かったので、その後、邦訳されているもの7、8冊を読み漁ったことがある。この『朗読者』は国際的に評価され、2008年には映画化もされている。ただし、映画の邦題は『愛を読むひと』(監督:スティーブン・ダルドリー)だった。

帰宅して早速読みはじめてみると、なんか違和感があるのだ。文体や叙述のスタイルがまったく違うし、どこか実験的な書に思える。著者の名前を確認する。トーマス・ベルンハルトとある。ん?ちょっと違うような・・・・ということで『朗読者』で検索してみると著者名はベルンハルト・シュリンンク。同じベルンハルトでも、一方は姓の方であり、もう一方は名の方なのだ。ついでに『朗読者』のベルンハルトはドイツ人で今も健在だが、『推敲』のトーマスの方はオーストリア人で、しかも1989年に既に故人となっている。
つまり、ベルンハルトという字面のみでまったく別人の書に接することになったわけだ。
でも面白ければいいじゃないかと読み始めたのだが、はじめっからまず視覚的に違和感があった。見開きでスキャンして載せた写真を見ていただきたい。2ページ分をびっしりと文字で埋め尽くされているのがおわかりだろう。これは、たまたまこのページでのことではなく、どのページもそうなのだ。
どういうことかというと、300ページほどの小説なのだが、前半に「ヘラー家の屋根裏部屋」という小見出しがあり、中間に「目を通し、整理する」という小見出しがあり、それぞれの始まりに段落の始まりを示す「一字下げ」があるほか、全てのページがびっしり文字で埋め尽くされているのだ。ようするに、300ページから成るこの小説は、たった2つの段落からなっているのだ。そうそう、小説によくある「 」付きの会話体がまったくないのも各ページが文字で埋められる原因をなしている。

余すところなくページ全体を文字が。どのページも・・・・。
ようするにこの小説の前半は、隠れた主人公ロイトハイマーの友人である「私」が、ヘラー家の屋根裏部屋に逗留し、自死したロイトハイマーの遺構に「目を通し、整理する」に至った経緯と、ヘラー家の描写なのだが、その描写は150ページ近くの一つの段落で語られる。
後半は具体的にロイトハイマーの書き残したものの紹介だが、ロイトハイマーによって延々と語られるその家族関係が何やら凄惨である。どうやら彼の家族は父母と自身を含む三人兄弟、それに姉との六人家族なのだが、それを彼は、父と姉、そして自分の陣営と、母と兄弟の陣営とに分断する。その分断は、前者を「聖」、後者を「俗」とするほどである。
彼=ロイトハイマーにとって、母はもはや母とも呼ばれず、その出身地からなるエファーデング人でしかない。これら家族のうち、彼が最も侮蔑的に描写するのはその母=エファーデング人である。そして、彼が最も敬愛するのがその姉である。
この小説のもうひとつの主人公は、その姉のためロイトハイマーが設計し建てたコーベルンアウサ―の森の中心の円錐形の家である。彼は、イギリスのケンブリッジでの研究生活の傍ら、故郷オーストリアでのこの円錐の建設の没頭するのだが、後半はこの円錐の虜となったかのようである。
この円錐の家は完成し、それを敬愛する姉に披露するのだが、その直後、姉は急死する。その後を追うようにロイトハイマーは自死する。
ここまで読んで、私にはひらめくものがあった。それはこの小説の主人公に模されているロイトハイマーの正体についてである。オーストリア出身でケンブリッジで学究生活を送り、自分の姉のために住宅を設計したのは、まさに今世紀初頭の哲学者、ヴィトゲンシュタインにほかならないのだ。ヴィトゲンシュタインが姉のために設計したのは森の中の円錐形のものではなく、ウィーン市街の方形のものだが、彼はそのディティールにまでとことんこだわり尽くしたことが伝えられている。
この私の推理は、訳者あとがきで正解であること知った。

ヴィトゲンシュタインがその姉のためウィーンに建てた住宅
その他の人物は、父、母、兄弟、姉、友人などなど、その関係性でしか語られない。
それと、母の俗物性(ほんとにそうであったかも疑問)についての記述はミソジニー風である。「 女性である限り精神に反対し感情に味方する。自然とはそういうものですでに証明されている」という叙述があるかと思うと、その姉に対しては「誰よりも親しい愛する人」などと今度は近親相姦的な記述が続く。まさに主観的な好悪が露骨に表出されている。
既に白状したように、早とちりで間違えて借りてきて読まざるを得なかった小説ではある。しかし、面白くもなかったかというとそうばかりではない。この 実験的スタイルは細かいフレーズにも施されていて、それはそれで結構面白かった。ただしそれにしても、全ページをびっしりと文字で埋め尽くされている文章を読むというのは、なんとなく重圧に抑え込まれている感じがするものだ。
表現における差異化の追求、それは広義の芸術界を貫いてあるものだろう。
長生きすれば(といっても百歳社会ではまだ八十路前半はその端っくれだが)いろんなものに出逢えるものだ。
*来月早々に両眼の白内障の手術を行うこととなった。そのせいで、この所を今月中に返済すべく、慌てて読んだため、どうしても冗漫な箇所はななめ読みになるなどし、ディティールで見逃しがあるかもしれないことをお断りしておく。


































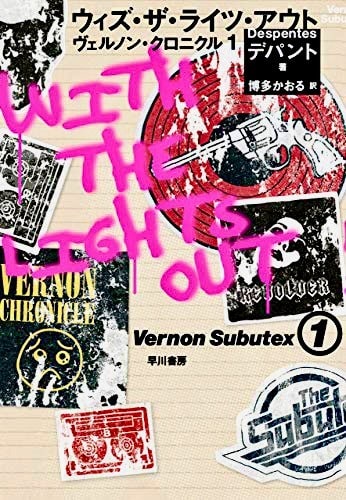


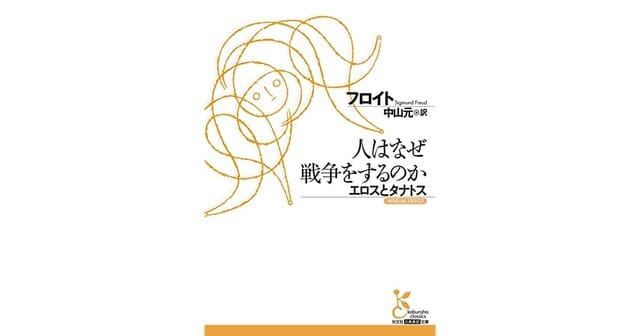







 そこで、今年こそはリベンジを誓い、また植えた。しかし、何を勘違いしたのかまたしても遅かったのだ。農家の知り合いから、「何を今頃。もうとっくに収穫の時期じゃない」と笑われてしまった。そして、「まだ冬のうちに準備しなきゃだめだよ」とのアドヴァイス。 しかし、想像力に疎い私、まだ寒い時期にキヌサヤエンドウをイメージすることなど出来はしない。でも来年も生きていたらチャレンジしてみたい。
そこで、今年こそはリベンジを誓い、また植えた。しかし、何を勘違いしたのかまたしても遅かったのだ。農家の知り合いから、「何を今頃。もうとっくに収穫の時期じゃない」と笑われてしまった。そして、「まだ冬のうちに準備しなきゃだめだよ」とのアドヴァイス。 しかし、想像力に疎い私、まだ寒い時期にキヌサヤエンドウをイメージすることなど出来はしない。でも来年も生きていたらチャレンジしてみたい。