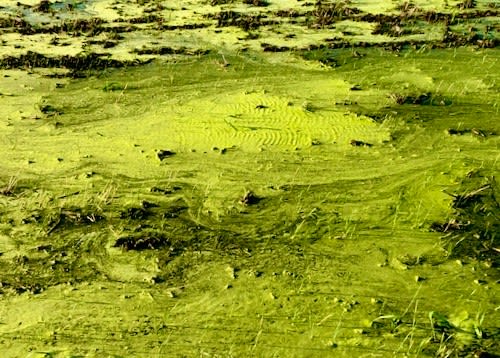しかし、2025年には75歳以上が人口の五分の一以上を占めることが確実で、しかもその75歳を上回ること10年近い私の世代には極めてリアルな問題なのだ。なぜリアルかというと、もし、この制度が今日実現したとしたら、それに呼応するかもしれない何人かの人たちを知っているし、かくいう私だって、然るべき条件下では応募する可能性はゼロとはいえないからだ。
私自身の経験からしても、受け取る年金額は十数年前から一万円近くダウンし、月80,000円ほどだ。しかし一方、物価はどんどん上がり続けている。もちろんこれは私のみの例ではなく、年金生活者の一般的な情況である。

この映画においても、「PLAN 75」登録者になる前の老人たちは、そしてそれを取り巻く現実は至って厳しい。倍賞千恵子が演じる角谷ミチ(78歳。賠償さん自身は81歳)は夫に先立たれながらも、ホテルの清掃従業員として働いている。しかし、映像で示唆される同僚の老女の仕事中の事故をもって、その職を追われる。作業中に従業員が死亡するなどという話題が拡散することをホテルが嫌ったのだろう。

ミチは、収入源に見合ったアパートへの転居を決意するが、アパートの家主や不動産業者は高齢者の入居を忌避する。入りたければ、何年か分の家賃を前払いせよなどと迫る。高齢者の孤独死の舞台となることを嫌うからだ。
ハローワークでの職探しの過程を含めて、自助のための努力は八方塞がりで、しかも、本人の尊厳をも傷つけられることが多い。ようするに老人が、いまここでこうしていることすらが困難な状況がある。
こうした出口のない現実がミチをも登録者へと誘うことになる。

この制度では、至れり尽くせりのフォローがなされる。もちろん、一度登録したからといっても、いつでも引き返すことが保証されているし、登録者たちには若いフォロアーが時折の話題の相手になってもくれる。ここには「福祉の極地」があるかのようだ。
登場する若い世代も、無批判にこの制度の進行役を演じているばかりではない。
この制度の勧誘や登録を業務としているヒロミ(磯村勇斗)は、長年行方不明になってた自分の叔父がこの制度に応募してきたのを知り、その最後まで付き合うこととなる。

「その日」が来るまで、志願老人の相手をするコールセンターの瑤子(河合優美)もその名前の通り、まさに揺れている。フィリッピンから出稼ぎに来た子持ちのマリアは、子供の病の支払いにとより高額の収入が得られる「政府関係」の仕事に就く。それは安楽死させたひとの遺品をまるでごみの分別のように整理する仕事であった。
これら登場人物がラストでさまざまに絡む。
それは書くまい。実際の映画で確認されたい。

繰り返すが、この『PLAN 75』で示される国家の対応は至れり尽くせりであり、福祉国家の極限でもあるかのようだ。
しかし、私の想念にはある事件の記憶が蘇る。入居者の19人が刺殺された、津久井やまゆり園の襲撃事件だ。その事件で逮捕された植松死刑囚は曰く、「重度の障害者は生きてる価値はない。むしろ健常者にとって負担であるに過ぎない」。その「弊害」を取り除くべく、彼の手によって大量の殺害は実施された。
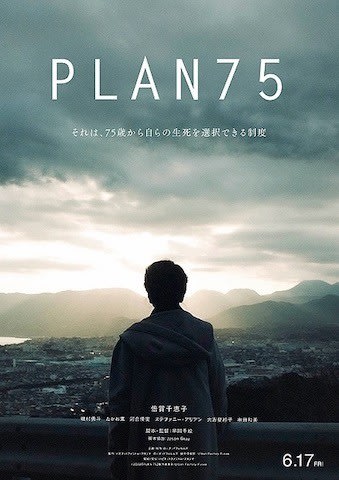
一見この事件と、映画『PLAN 75』が描く高齢者への「手厚い」処遇は対極にあるかのようだ。しかしだ、障害者や老齢者の生存理由は次第に希薄になるのであり、つまるところ、商品価値を産み出すことへの寄与こそが人のあるべき姿、労働力商品こそが人間の存在理由だという論理は、そうではなくなったひとたちを公の措置として「丁重に」安楽死させようが、植松被告のように「荒々しい」の暴力で刺殺しようが、まったく変わらない論理ではないだろうか。
この映画が、「仮の」姿としてえぐり出す国家の「不要者抹殺」の姿は、決してありえないものではないし、むしろ、しっかり目を見開いて観るならば、あらゆる国家はそうした論理をその度合いはともかく、隠然、公然と背景に持っているのだ。「福祉」という名の管理において。
実年齢をメイクなどで隠すことなく、その老いを演じきった倍賞千恵子さんと、初長編という脚本・監督の早川千絵さんに、さらなる表現の可能性を期待したい。
私に関するならば、安楽死よりも野垂れ死にこそがふさわしいと思っている。エロスという生の衝動を道連れに、「ここにいる老人」として、くたばるまであがき続けるという意味においてだ。