今季最寒、細やかな雪が舞い散る岐阜から名古屋へ。
これが降り積もったら、夜の帰途、バスはちゃんと運行しているだろうか。
木曽川を渡って愛知県へ。台風時に流されてきた樹木が流れの中程にずーっと留まったままだ。
寒さのせいか、いつもみられる水鳥の姿もない。

雪は降っていないが名古屋も寒い。
スマホを頼りに行ったことのない読書会の会場へ歩を進める。
ここだという箇所にたどり着いたがそれが確認できる名称の表示はない。
駐車場に車を止め、降りてきた若い女性に、「〇〇というこの辺の場所をご存知ありませんか」と尋ねる。
「さ~、そんな建物は知りません」との返事。
さらに2,30歩ほど歩を進めると、あったっ、私が探していたのは彼女が入っていったビルの隣だった。
3時間の読書会、著者は優れた理論家だが、20代前半の若書きのせいか、晦渋な表現がめだち、咀嚼し難いところもある。
その後の飲み会兼フリートーク。
途中からの参加者もあり話は尽きないようだったが、帰りの足も心配だったので8時半ぐらいで中座させてもらう。
岐阜についたが幸い積雪はなかったようで、しばらく待って最終のひとつ前のバスに乗って帰宅。

バス待ちの間に、JR岐阜北広場の金の信長像を中心にしたライトアップを撮る。
スマホの電池残量は10%。
読書会会場への途次、つけっぱなしにして道案内にしたのが負担だったのか、それとも、バッテリーがもうへたってきたのか、もう少し様子を見よう。

そのなかで、私がある意味、衝撃的に受け止めたのは人類そのものが終焉を迎えているのではないかということだった。
それらのうちには、BT=バイオテクノロジーによる生物としての「人」そのものの変革管理があったが、同時に、デジタル技術の最先端としての人工頭脳=AI の進化による人智そのものの凌駕とそれによる人間への支配の可能性であった。
こうしたAI による人類の追い越しと人類への管理はシンギュラリティ(=特異点)といわれ、早ければ2045年には起きるとされている。
その折、人間はAI の目指すところ(それ自身が何かはわからない)に有用な部分と、無用な部分(無用者階級)とに分断されるとする。

このSFのような推測はまんざら根拠がないわけではない。私たちはすでにして意識するとしないとに関わらず、デジタル監視社会に属しているのであって、これは視られるのみではなく、その監視の結果、それによりセレクトされた情報が与えられ、私たちの欲望そのものがコントロールされるに至っている。
たとえば、何かを検索すると、それに即した情報や商品などがどんどん紹介される仕組みはすでにして日常のものである。
私が今回読んだのは、彼の次なる書、『哲学と人類』なのだが、この書が、『哲学と人間』ではなく「人類」であるところにこの書のコンセプトがある。
というのは、この書が、人間が哲学をはじめた文字言語以降の、いわゆる「哲学史」を問題にしているのではなく、人類発生以来の「メディア」の変遷に注目しながら「人類」の行方を考察しているからである。

メディアというのはいわゆる「媒体」であり、「伝達手段」である。したがって、かつては、そうした手段はともかく、それによって伝えられるものこそが重要だと考えられていた。
それを覆したのがハーバート・マーシャル・マクルーハンであった。彼の思想を簡潔に表す言葉、それは「メディアはメッセージである」である。
彼は、メディア=媒体は、手段にとどまらず、それ自体が人間にとって有意味な何者かであると主張したのであった。
音声言語の時代、文字の時代、印刷技術によるその大衆化の時代、写真、録音、その集大成の映画などによる感覚的対象の再現の時代(ベンヤミンの『複製技術時代の芸術』。ベンヤミンは実はマクルーハンに先立ってメディアのもつ「手段」にとどまらない役割を論じていた)、そして、テレビによる映像氾濫の時代、これが二〇世紀前半までのメディアの歴史であった。

それぞれのメディアは、単に伝達手段の進化にとどまらず、それ固有の歴史的現象を生み出した。
文字は思想や芸術作品、歴史的事実の後世への伝達を可能にし、印刷術は情報の大衆化、とりわけ西欧では聖書の普及による宗教革命の推進を実現した。
その他のメディアの出現もそれ固有の状況を生み出してきた。例えば写真や録音、ラジオといったメディアは、文字に還元されていた情報をダイレクトに感覚に訴えて伝えることになったし、映画やテレビの動画は、状況の映像と同時に時間的経由をも共有させることとなった。
これにより促進されたのは、大衆社会そのものである。

それにも増して革命的なのは、20世紀後半に端を発するデジタル技術であった。あらゆる情報の0・1という数字への還元は、途方も無い情報の量とあらゆる分野を埋め尽くし、計算は愚か、それ自体の自己言及化的進化により、いまや人工頭脳=AI を産み出すに至った。
これが、2045年頃に想定されるシンギュラリティにより、人智を上回り、人類を支配下に置くか、あるいは人のありようを劇的に変えるであろうと考えられていることは初めの方で観たとおりだ。

この書は、それらが具体的に述べられているのだが、その時代、時代のメディアのあり方と、哲学そのものの相互関係が主要な哲学的動向、キーとなる哲学者やその思想とともに述べられている。
そこには、とても面白い考察もある。
周知のように、ソクラテスは自分の書というものは残さなかった。文字として固定化されることによる知の形骸化、それによって失われるものを恐れたからだといわれている。だから、ソクラテスの思想というものは、今日、その弟子のプラトンの書によって間接的に知られるのみである。
要するに、文字による知を否定したソクラテスの知を、プラトンは文字で表すのだからそれ自身が矛盾を孕んでいるが、ダイレクトな音声メディアが文字メディアへと変遷するその時点の推移をも反映している。
加えて面白いのは、そうした時期にあって、ソクラテスは「書かなかった」のではなく「書けなかった」、すなわち文字を使えなかったのではないかという推察も成り立つということだ。
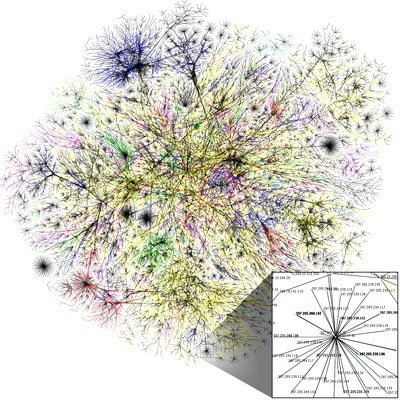
その他、主要な哲学者をメディアとの関連で論じていて面白い。
この書が、「哲学」と「人間」ではなく、『哲学と人類』であることがおわかりいただけたであろうか。
そして、そこには、「人類の終焉」というか、少なくとも人類はここ数千年の歴史とは異なる段階を迎えようとしている近未来が見通せるのである。
若い人たちはその辺のところを真剣に考えなければならないだろうと思うのだが、一方、80歳過ぎた私は、その頃にはとっくにオサラバしているのだが、生来のおせっかい癖で、「さあ、若い人たちよ、いったいどうするんだい?」と尋ねてみたいのだ。
この書は、あまり哲学の素養がなくとも読めるのではないだろうか。
以下は、岩波新書『リベラル・デモクラシーの現在 「ネオリベラル」と「イリベラル」のはざまで』(樋口陽一)に触発された感想。
この書によれば、リベラル・デモクラシーがネオリベラル(現今の新自由主義)とイリベラル(反知性的で偏狭ないわばトランプ的あるいはネット右翼的連中)の挟撃に逢っているという図式だが、実態はネオリベラルとイリベラルが相互に関連し、浸透し合っているということではないだろうか。

ネオリベラルとイリベラルはさほど矛盾した存在ではない。ネオリベラルの自己責任論による格差の拡大、セーフティネット崩しなどによる貧困層の創出があるところに、それら排除された部分のルサンチマンを組織するイリベラルが跋扈する。トランプ支持者たちがそれに相当する。
もちろん、わが国のネット右翼といわれる連中も例外ではない。
翻って、現在進行形の米大統領戦をみるに、世論調査等の数字がそのまま実現するとすればバイデンが勝利するだろう。しかし、表層的にはトランプより紳士・淑女的であれ、その政策が基本的にネオリベラルの域を出ないとしたら、イリベラル生産の環境や過程は変わることなく継続されるだろう。

なお、このイリベラルは、『全体主義の起源』で、ハンナ・アーレントがいうところの「モッブ」に相当する。そしてこのモッブは、いわばゴロツキなのだが、しばしば全体主義の露払いをするばかりか、場合によっては、ポピュリストとしてその全体主義の担い手そのものに成り上がったりもする。ヒトラーがそうだったように。
また、このイリベラルを背景にしたポピュリストとしてはトランプがそうだし、身近なところでは名古屋市長の河村がいる。彼はレイシストで歴史修正主義者で、低俗極まりないデマゴーグである。
ここから見えてくる課題は、ネオリベ支配の現実による犠牲者たちを、その支配の構造のなかに放置したり、あるいはイリベラルの疑似変革の罠に取り込まれないようにすることなのだが、現今の野党といわれている勢力がどこまでそれを自覚的に追求しているのだろうか。
たんに、ネオリベやイリベラルに対しリベラルを対置するのみでは無力であろう。先に見たように、いわゆるリベラルを呼称しながら、その実、ネオリベと大して変わりない連中もいるからだ。
マルクス・ガブリエル『新実存主義』(広瀬 覚:訳 岩波新書)を読了した。
この著者のものは、前に『なぜ世界は存在しないのか』(清水一浩:訳 講談社選書メチエ)を読んでいる。率直にいって、彼のその「新実在論」と称するものが、哲学史上で、ないしはポスト「ポストモダン」といわれる現在において、どう位置づけられるべきものなのかに戸惑いを覚えながら読んだ。
今回の挑戦は、そうした戸惑いをどこまで払拭できるかへの試みでもあった。
ところでこの書名は「新しい」実存主義を意味している。古い方の実存主義はというと、第二次大戦後の一大思潮として、私の少し上から私たちの年代まで、サルトルなどのその哲学上の展開に触れてはいなくとも、その文学作品(サルトル、カミュ、ボーボワールをはじめ、多くの作家をその系列に数えることができるかもしれない。いってみれば、文学的な生の一回性のようなものに馴染みやすい思潮だったから)や映画などで、意識するとしないに関わらずそれらに触れてきた。

こと人間に関しては、まずその本質があって、それに従い私たちがたち現れるのではなく、私たちがどうあるか(どう実存しているか)によって私たちの本質が決められてゆくという「実存が本質に先立つ」というこの主張は、私たちが何にどう関わるか(投企)が私たちを決定するとし、その投企の対象はこれと限定されてはいないという意味で、「自由への恐怖」などともいわれた。その意味で、この思想はある種の決断主義ともいいうる。
この実存主義は、私たちがいまここにあるということ自体が、単に投げ出されてある(被投)ということではなく、すでにして何ごとかの規定を受けているものであり、したがってその決断の内容も、仕方も、それらとは無縁のところで行われるわけでもなく、「自由の恐怖」というのも観念的な幻想に過ぎないとして次第に後退してゆく。
しかし、芸術の分野では、その一回性、既存の制約を打ち破る偶然性の発露として、実存的な衝動は生き延びているのではなかろうか。
それはともかく、それではそうした古い実存主義に対してガブリエルのそれはどう新しいのであろうか。
先に第二次大戦後の実存主義ブームの中心にいたサルトルについて触れたが、一般的にそれに先行し実存哲学の系譜に属する思想家には、キルケゴール、ニーチェ、ハイデガーなどの名が挙げられる。しかし、新実存主義においては、カント、ヘーゲル、マルクス、キルケゴール、ニーチェ、ハイデガー、サルトルの名が挙げられている。これは妙なことなのだ。カントの「普遍的理性」、ヘーゲルの「絶対精神」、マルクスの「自覚したプロレタリアート」などは、強固な本質規定として、「実存が先行すべき」実存主義とは対峙してきたものにほかならない。

しかし実は、ここに新実在論に基づくガブリエルの「新しい」実存主義を解く鍵があるともいえる。
ガブリエルは、自分がサルトルから継承したものを次のようにまとめている。
1)人間は本質なき存在であるという主張
2)人間とは、自己理解に照らしてみずからのあり方を変えることで、自己を決定するものであるという思想
この2)のまとめ、「自己理解に照らしてみずからのあり方を変える」という僅かな拡大解釈の中に、カントやヘーゲル、そしてマルクスが登場する余地があるのである。彼らは、大きな意味では、対象を受動的に解釈する、あるいは対象からの一方的な侵食に身を任せることなく、まさに「自己理解に照らしてみずからのあり方を変える」試みをなしたと評価するわけである。
もう一つ指摘すべきは、彼はここで、人間の「心」に関する問題を、自然科学的な理解へと還元する自然主義と闘っているということである。この自然主義とは、ようするに人間の心や意識のありようを、脳内のニューロンの働きとして説明しうる…今はできなくとの将来はできる…とするもので、人間を自然の延長(のみ)として考えようとするものである。
この悪しき自然主義の極論は、他者も自身も、所詮は物質の運動にすぎないというニヒリズムへと誘う。
だから彼のこの第一章「新実存主義」には「自然主義の失敗の後で人間の心をどう考えるか」というサブタイトルが付けられている。
思えば、ガブリエルの「新実在論」は、この現実、事実自体などは存在せず、言語を中心とした私たちの営為によって構築されたものに過ぎないというポストモダンに帰結するような「構築主義」に対抗するために構想される一方、自然主義による人間そのものとあらゆる意味の場である世界(地理的な意味ではない。むしろハイデガーの世界内存在に近い意味での世界)の抹殺に対抗するものであった。
その意味では、彼の「新実存主義」は、その「新実在論」の人間における展開を示すものといえる。
いずれにしても、マルクス・ガブリエルの展開にはまだまだ良くわからないところがあり、上の整理も的を射ているかどうかわからない。ましてや、この哲学のもつ意味合いのようなもの、実践的な指針としてのそれなどの検証はこれからだろうと思う。
ただし、一部の社会学などでは、すでにそれを方法に取り入れているようにも見受けられる。
それは、ウソには言葉や記号が必要だからです。
動物も嘘をつくという見方もあります。例えば昆虫などの擬態を指してのことです。
しかし、これは人間があとからとってつけた目的論的な考え方のたまものでしかありません。つまり、擬態は天敵をだます目的をもって仕組まれたものではなく、たまたまそのような姿態を持っていたがゆえに生き延びてこられたということにすぎないのです。
しかもこれにはもうひとつ突っ込んだ話があって、そうした擬態は、人間の視覚にとっては、「木の葉そっくり」や「木の枝そっくり」なのかもしれませんが、それらを捕食する天敵にとってどれほどの効果があるかは疑問だというのです。
ある調査によれば、昆虫を食べる動物の胃袋を調べたところ、擬態をしているといわれる昆虫も、そうでない昆虫と同様に食べられていたのだそうです。
したがって、「食べられないように」という目的説もむろん、「擬態」という事態そのものも、人間が自分の狭隘な五感や経験でもって断定したものにすぎないという疑いがあります。
擬態に何がしかの効果があるとしても、それはすでにみたように、「そのために」そうなったのではなくて、「そうであったから」生き延びてきたということが本当のところなのでしょう。

その点、言葉は容易に嘘を可能にします。白を黒にし、大を小にするぐらいのことは朝飯前で、時にはあったことをなかったことに、なかったことをあったことにしたりもします。
ではなぜ言葉を使う人間においてのみ嘘が可能なのでしょうか。
その答えは上に述べたことの中にすでに出てしまっています。
ようするに、ないものをあるかのように表現できるのが言葉の力なのです。
これを哲学の世界では「不在の現前」などというようですが、例えば私が「犬」といったとき、ここには犬などいないのにあなたは犬のイメージを思い浮かべることができるということです。これは名詞ばかりではなく動詞においてもそうです。
ですから私が、「犬が来た」というと、あなたは犬がやってくることを想起します。ところが、犬が来た様子も来そうな様子もないとき、あなたは私が嘘をいったことに気づくわけです。
ところで、こうして嘘をつくことができるという言葉の性質が、皮肉なことにも同時に、本当のことをいうことをも困難にしています。
私がある経験をして、それをあなたに伝える場面を考えてみましょう。
私はある経験をします。そしてそれを記憶にしまい込みます。この場合にもやはり言葉を介しています。私たちの意識や記憶というものは言葉と切り離しては考えられないのです。
実は、この経験を受容すること、それを記憶にとどめることの中にさまざまな心理的要因があり、それらによって私の記憶は支配され加工されるのですが、この際、煩雑になりますからそれらは除外して考えてみましょう。
私は誠実にありのままに私の経験をあなたに伝えようとします。そのために、あなたと私の関係にふさわしい言葉を選び、その経験を再現しようとします。あなたもまた、私が再現した経験を素直に文字通り受け止めようとします。
さて、私の経験は本当にあなたに伝わったのでしょうか。

これがすこぶる難しいのです。
私の経験はひとまず言葉に翻訳されました。しかし、ここにおいてすでにズレがあります。私の経験は言葉と同じではないのです。私はそれをあなたに話します。ここにもズレが生じます。あなたは私の話を受け入れ、私の経験を自分の中で再構成します。ここにもまたズレが生じるのです。
それに加えて、先ほど棚上げにしておいた私の側の心理的要因、そしてあなたの側の心理的要因、加えて、あなたとわたしとの関係そのものの要因も実は情報の伝達には不可欠なものであり、それらの作用のもとで、やっと私の経験はあなたに伝えられるのです。
さて、あなたも私も誠実に私の経験を授受しようとしたのですが、その間のズレは不可避ではないでしょうか。これは例えば、私が自分がかつて飼っていた雑種を思い起こしながら「犬」といったとき、あなたが血統書付きのゴールデン・レトリバーを思い起こすようなズレの重なりといっていいでしょう。
むろんこれらは嘘ではありません。むしろ、伝え、伝わるということが避けがたく含むズレの問題だといっていいでしょう。
ようするに言葉は、透明で無機質な道具ではなく、それ自身ある重みをもったものだということです。
にも関わらず、私たちはそうした負荷を背負いながらも伝え合わねばならないのです。それは私たちが、この世界の中で共存しているという事実に根ざすものであり、また、共存するとはそうしたコミュニケーションを諦めないということなのです。
もっとも一方、こうした言葉の作用を巧みに利用して、あからさまに虚偽を述べ立てる言説もあります。これは、いわゆる詐欺やデマゴギーといわれるもので、相手の言葉への信頼を利用して、相手を欺いたり架空の事実に誘導したりするものです。
私たちは最近、TVのニュースなどでふたつのあからさまなそれに出会っています。
ひとつは、猪瀬知事の弁明というにはあまりにも貧しい言葉の羅列です。そしてもうひとつは、衆参両院での強行採決の連続を指揮してきた当事者である首相の、
「まず、厳しい世論については、国民の皆様の叱正であると、謙虚に、真摯に受けとめなければならないと思います。私自身がもっともっと丁寧に時間をとって説明すべきだったと、反省もいたしております。」
という極めて明るいトーン「反省」の言葉です。
しかし、ここで首相が本当に反省していると受け止めたひとは多分、病的にナイーヴな人だと思います。
こうした言説は、本来のコミュニケーションを目指すというより、言葉の壁でもってディスコミュニケーションを形成するものだと思います。
したがってこれらは、先程述べた共存のためのコミュニケーションとは全く相容れないものだといえます。
しかし、生死とともにその中間で生きている過程に関しても、全面的な管理や監視が試みられます。それらを総称して「生権力」とか「生政治」とかいったりする向きがありますが、そうした小難しいことはおいといて、近未来に実現されそうなことを述べてみましょう。

産み落とされた以降の話なのですが、例えば、ナノ・テクノロジーを利用した超小型の検出器を諸個人に装着させたり、あるいは体内に埋め込んだりし、中央監視局でキャッチしたそのデータをもとに、医療措置や投薬の指示なども行おうという未来像があります。
ただしこれらは、あなた任せでなんとかしてくれることを意味はしません。
逆に、これだけしてやっているのだから、自己の健康管理はそれぞれの責任において行うべしという自己責任論がついて回ります。

ではこうした管理体制の増進によって人の病は減るのでしょうか。
近年、医療は格段の進歩を遂げ、それに依って治療可能な分野が開けていることは事実です。しかしながら、人の疾患は減ってはいません。治療技術が進み、その分野が細分化されたり、あるいは新薬の開発により治療可能な症状が明らかになるにつれ、それに対応した疾患=病気そのものが増えているのです。
例えば、かつては神経症と分裂症ぐらいの大雑把な区分けであった精神性の疾患は、今では〇〇症候群といったかたちで無数に分類され、それぞれ異なる治療と薬品が対応するのです。
これらとはまた別の要因ですが、新しいウィルスがこれでもかこれでもかと次々に登場しています。

薬の細分化について述べましたが、最近取り締まられるようになったいわゆるデザイナー・ドラッグは、もともとは従来の違法薬品の分子構造を少し変えてその規制を逃れようとするものでした。もう、「麻薬取締法」と「大麻取締法」では対応できない段階ともいえます。
そうそう、前回述べた胎児の管理と関連するのですが、受精卵の段階で遺伝子操作を行なうことによって、親が望む外見や体力・知力等を持たせた子供のことをデザイナー・ベビーというのだそうです。親がその子供の特徴をまるでデザインするかのようだからですね。

人間が人間という種を管理しデザインする段階にいたっているのがお分かりいただけると思いますが、これってやはり優生学の実践であることは間違いありません。
これがいいことなのかどうかについてはあえてニュートラルに述べて来ましたが、これらが究極の生命管理、「誰が(どのように)生きていいのか悪いのか」に関することはいうまでもありません。

これまで述べてきたことから、いわゆる「管理社会」の一段の発展をイメージされるかもしれませんが、実はそれとは次元の違う問題なのです。
これまで語られてきた管理社会は、人の生活態度や習慣、思想や行動などを一定の規範で統制しようとしたもので、そこでの対象は人間の社会的な生き方であるビオスに結びつくものでした。
しかし、ここ三回にわたってみてきた人間の生への管理は、社会的な人間のありようについてではなく(それはそれとして別途あるのですが)、それ以前の生物としての人間、いわば「剥き出しの生」としてのゾーエーに関するものなのです。
普通は、もっと遅く生まれればよかったと思うものなのですが、こうした予測を考慮に入れると、早く生まれてよかったというべきかもしれません。
もっと後ですと、私のような悲しい遺伝子の持ち主は、「不適格」と判定されたり、もしそれをかいくぐることができたとしても、在特会のデモ隊に試験官ごと踏み潰される可能性があるからです。
もちろん動植物たちも食ったり食われたり、あるいは昆虫と植物の花のようにその食性を介して繁殖の手助けをしたり、寄生などというかたちで共生したりするという意味で干渉し合っているともいえます。
しかし、そのことによってお互いの品種を変えてしまうまでには至りません。

もう散り始めた
それに対して人間は、人間が人間になったのとほとんど同時に他の品種に干渉し始めます。
具体的には家畜の改良、栽培植物の品種改良などで、それぞれの動植物を人間の都合の良いように変えて来ました。
結果として、今日私たちに馴染みの深い野菜などについて、これが本来の野生の原種だといって示されても、その差異のあまりの大きさにすぐにはそれと同定できないほどなのです。

コデマリ
最近知ったのですが、ブルドックという犬も人間が闘犬用に鼻の短い犬をということで作り出した品種だそうです。そればかりか、この犬は自然の中では生きて行けないらしいのです。なぜなら、そうした不自然な交配のなかで作られたこの品種は、その出産時に帝王切開をしなければ子犬を産むことができないからです。
人間が絶滅して彼らが生き残ったとしても、彼らはその次の代を産むことができないのです。
ですから人類は、ブルドックを生み出した責任上、ちゃんと生き延びねばなりません。
さて、人間の生物種の改良(?)は、これまでの突然変異を利用したりする自然交配とは違って全く新しい段階に入りつつあります。遺伝子工学の進化や生化学の分野における発展は、これまでとは全く違った生物を設計図に基づいて生み出したり、コピーをとるように複写したりすることを可能にしつつあります。

すっかり夏の気配が 30℃
これをもって人間が神の分野を侵しつつあるなどといわれますが、神は「なぜナシに」創造したのに反し、人間のそれは自己の欲望に基づくという大きな違いがあります。神の創造が無政府的であるとしたら、人間による創造は極めて恣意的であり政治的であるといえます。
その是非についてはとりあえずいわないでおこうと思います。
問題はそうしたテクノロジーが、人間以外の生物を対象とするのみならず、人間自身にも向けられ始めたということです。
かつて人間の死は確たる判定基準を持たなかったにもかかわらず、それはほぼ自明のことでした。ところがここに来て俄然、揺らぎが生じています。
それは人間の死が、延命措置の技術の発展によってかえって曖昧になったり、あるいはそれと裏腹のことですが、臓器摘出と移植などの必要から「資源」として見られるようになったからです。

どうしてうちの八手は七手なのだろう
私は母が意識をほぼ失い、生ける屍のようになってから一年半、付き合って来ましたが、その間、医療機関から提案される選択肢に何度も苦渋の選択を迫られました。
その際、基準にしたのは、健康な折に母がいっていた「ぽっくり逝きたい」という意志であり、たとえ意識はなくともその苦痛を軽減することでした。はっきり言って、医師が回復の見通しがないといっている段階で、不必要で母に苦痛を強いるような延命措置(胃瘻など)は一切拒否し、いつ逝ってもいいと覚悟を決めていました。
母が逝ったとき、その死を悲しむと同時に、やっと苦痛から解放されてよかったねという思いが相半ばしました。

これが松の花(だと思う)
なにが言いたいかというと、現代では人間の死もテクノロジーの基準に即したものになっていて、それ自身は、人間がほかの生物の生そのものに干渉してきた結果が折り返されて人間の生そのものに及んできているということです。
人間の生に関する干渉についてはさらにいいたいことがあるのですが、もう十分長くなりました。
次回に譲りたいと思います。
この言葉には、はじめてではなく前に何処かでお目にかかっているのですが、浅学と老害の悲しさ、どこだったかはわかりません。
そこで調べたところ、敗戦から一年しない1946(昭和21)年5月『思想の科学』という雑誌が創刊され、その中に載せられた論文のタイトルであることが分かりました。

ただし、私がお目にかかったのはそこでではありません。そりゃぁそうでしょう、その折私はおん歳7歳、国民学校の2年生だったからです。
ちなみに、国民学校令が廃止され、現行の6・3・3・4制が施行されるのは翌47(昭和22)年からです。
ですから、「言葉のお守り」という言葉に出会ったのはどこか他の所で、それはどこだったのかは特定できないままです。
雑誌『思想の科学』の創刊メンバーは、鶴見和子、鶴見俊輔、丸山眞男、都留重人、武谷三男、武田清子、渡辺慧の7人でしたが、この内ご存命なのは武田清子さんと鶴見俊輔さんです。
武田さんは95歳、鶴見さんは92歳です。

鶴見さんなどと馴れ馴れしく呼ぶのは大それたことかもしれませんが、4年ほど前、私が小冊子に書いた文章についての感想のはがきを、直接私にではなく、その小冊子の編集者宛に頂いたことがあるからです。
これは内緒ですが、その文字の解読は困難を極め、その編集者と私とで、ロゼッタ・ストーンの解読もかくやとばかりの論議を重ねたのでした。
それは私のつたない文章への好意ある評価でしたから、とても嬉しく思いました。
さて、その「お守り言葉」ですが、鶴見さんは戦前の有無を言わさぬ権威を持った言葉と、それを所有し振りかざした態度をそう批判するのです。
例えば「八紘一宇」「大東亜共栄圏」「聖戦」「皇国日本」などなどがそれですが、戦前戦中、この言葉はその他の言説に対しては絶大な力を発揮しました。

それらの言葉は、水戸黄門の葵の御紋入り印籠同様、「この紋所が目に入らぬか」とかざすだけでも絶大な力を持ったのです。しかし、この事実は、それらの言葉の使い手がそれをお守りとして振りかざすという側面と、その言葉のもとに身を寄せてそれによって守ってもらうという側面があったのではないかと私は考えています。
何れにしても、それらの言葉が厳密に何を意味するのかはどうでも良かったのです。それらの言葉の権威が独り歩きをし、人々に力を及ぼしたのです。ようするにそれらのことば自身が物神化されることによってその権威を保っていたのでした。
これが戦前でした。
幼年の私も、それらの言葉をなんの意味かも理解しないまま口の端にのせていただろうと思います。
鶴見さんはその「言葉のお守り的使用法」を糾弾します。

しかし、鶴見さんの射程はそれにとどまっていませんでした。当時、雨後の竹の子のように這い出た戦前の左翼や、この間まで神国日本を説いていたにも関わらずマルクス主義として立ち現れた右翼から左翼への転向組に対しても「言葉のお守り」を使用するものとして批判を加えたのです。
戦後のお守り言葉は曰く、「民主」「自由」「平和」「人権」などです。
内容や実質を伴わないままにその「言葉のお守り」を振りかざし、あるいはその言葉に庇護を求めて身を寄せることによって世の中の主流を占めている、そうした意識に対しても厳しい批判を加えたのでした。

こうした「言葉のお守り」が、その意味では戦前の「言葉のお守りの使用法」を反省することなく、振りかざす看板を変えたままで安易に使われる場合、それらは膠着化し、決してその内容が含意するものを実現することはないだろうというのがその批判の要旨でした。
今日の状況は、そうした「言葉のお守り」の誤った使用法の結果というか、「言葉のお守り」に依拠して現実をネグレクトしてきた過程がもたらしたものともいえます。私達はそれらの言葉をお守りのように、あるいは葵の印籠のように振りかざしたり、あるいはその言葉の傘のもとに身を寄せるのみで、ほんとうにその言葉の内実を実現してきたでしょうか。
鶴見さんは続けます。
「お守り言葉をめぐって日本の政治が再開されるなら、国民はいつまた知らぬ間に不本意の所に連れ込まれるかわからない」
1946年の、今から67年前のこの予言が的中しつつあるのではないかと危惧するのは私だけでしょうか。
その二冊とは、以下です。
『国語教科書の思想』『国語教科書の中の「日本」』
石原千秋(ちくま新書)
これがなかなか面白いのです。
正直にいってまだ前者しか読んでいないのですが、面白くて一気に読み上げたものですから、まあ、中間報告のようなものを書きます。
著者は、国語教育は本来、リテラシー(広い意味での読解力にくわえて記述能力)と文学の享受で成り立っているはずなのに、近年、後者の文学の側面が次第に希薄になり、前者の情報リテラシーの側面のみが強化されてきたことを指摘しています。
そして、そのリテラシー自身が、道徳的説教やある種のイデオロギーをも含んだものになっているというのです。ようするに、「こう読むのが正しい」という結論の中に凡庸で陳腐な道徳への誘導が巧妙に織りこまれているというのです。彼はそれらを、現在使われている教科書の内容を具体的に検証しながら見てゆきます。

とはいえこれは、いわゆる「偏向教育」とは少しくレベルを異にする問題なのです(そこへ結びつく要因ももちろんあるのですが)。いってみれば、いわゆる「左翼」「右翼」にかかわらず、あるいはむしろ進歩的と自称する向きほど、陥りやすいトラップのようなもので、それが「国語」の名で子どもたちに押し付けられているといいます。
たとえば、小学校の教科書に見られるそれらのメッセージを大別すると、以下のようにまとめられるといいます。
1)自然に帰ろう 2)他者と出会おう
これだけですと、それぞれもっとも至極で、それのどこが悪いのといえそうです。しかし、それらを詳しく見ると、やはりいろいろと問題があるようです。
たとえば、この自然回帰については、教材に頻出する動物の話が象徴的です。動物の純粋さを賞賛するそれらの記述を、筆者は、まるで「進化論に逆行」しているかのようだといいます。
「動物化するポストモダン」という言葉がひと頃流行ったのですが、筆者同様、私もそれを想起しました。ようするに、動物は自然で(素直で)いいのだという繰り返しは、「動物化」することで与えられた環境に従順な受動的人格へと誘導することにほかならないと筆者はいうのです。
環境保護への呼びかけが繰り返しでてきますが、それらも過去への回帰が主として語られているようです。それらのほとんどが、大部分の子どもたちの住む都市部とはもはやかけ離れた昔ながらの山村や田園風景をモデルとして語られるのです。
「昔はよかった」「自然に帰ろう」「動物に戻ろう」というメーセージのリフレインは、大部分の子どもたちが住む都市部、そのうちのかなりの部分の子は鉄筋コンクリートの団地やアパートという箱のなかに住んでいるのですが、そうした子たちのリアリティがすっぽり抜け落ちたところで、いわば「田舎はいいが都会は悪い」かのように語られているのです。
「鉄筋コンクリートの校舎のなかでカラー印刷の教科書」を使い、やはり鉄筋コンクリートの箱の家でゲームにいそしむ子らに、そうした後ろ向きの自然回帰を教えることにどんな意味があるのかを著者は問います。
それれは、「自分の顔を見ないで他人の顔を批判する」ような欺瞞ではないかというわけです。
もう一つのテーマ、「他者と出会おう」にも似たような問題があります。
サバンナで、ライオンの赤ちゃんが生まれ育ち、またシマウマの赤ちゃんも生まれ育つことが「共生」の名で語られますが、それらが、喰うか喰われるかの「共生」であることは語られません。
また、ほとんどの「共生」が、「みんな違っていいだね」のレベルにとどまっていて、その違いを前提にした「共生」を具体的にどう実現するのか(現実の社会ではそれが求められるのですが)には踏み込まれません。また、自然との共生もよく読んでみると、人間による自然の一方的な利用に帰するのみで、人間のエゴの肯定ともいえるようです。
これらの問題点のひとつは、それらのフィクションに気づいた子が、「先生、私たちのところにはもう、兎を追うような山もないし、小鮒を釣るような川もありません。大切にしようという自然がもうないのです。それに、ゲームを持っている子とそうでない子とは一緒に遊ぶことは難しいのです」といったとすると、その子は確実に読解力がない子とみなされてしまうのです。
逆に、それらのフィクションの欺瞞性をどこかで感じながらも、「環境を大切にしましょう。自分とは違うものとも仲良くしましょう」と答えた子は良い評価をもらえ、内申書も良くなるのです。
これはやはり、一種の強制を背後に伴った刷り込みといえるようです。
もちろん、自然を大切にしたり、異なるものとの共生をはかることが必要ななことには違いないのですが、それをどのように進めるのかというところで、これら教科書の最大の道徳的欺瞞が露呈します。
教科書はそれを、「私たち一人ひとり」の課題だというのです。
「私たち一人ひとり」でなしうることはあるし、またそのための努力を否定するものではありません。しかし、環境にしろ人々の共生にしろ、「私たち一人ひとり」の努力で決して解決しない歴史的社会的な広がりをもった問題であることは改めていうまでもなく明らかなのです。
ましてや、ここまで広がった環境破壊や、共生が困難なほどの格差の拡大は、子どもたち「一人ひとり」の責任ではまったくありません。
にもかかわらず、教科書はそれについては全く触れません。それどころか、それらを「私たち一人ひとり」の問題に内面化させる道徳的なお説教によって、それらを真に解決するための社会的な眼差しそのものを閉ざす役割を果たしているのです。
これがこの本の趣旨です。そして、こうした教科書の読みが、それ自身筆者によるひとつのリテラシーをなしていることはいうまでもありません。そしてこれはまた、それに対する私の読みでもあります。
*なお、「国語」というのはほとんど日本のみで通じる言葉で、たとえばイギリスでは、英語のことを National language などということはないようです。これは、国家と民族と言語がそれぞれ単一で対応している、ないしはすべきだという日本特有な偏狭な意識のなせるところで、それ自身が問題含みであることはいうまでもありません。
「日本人の大半は、《日本語》を用いている」というのが現実であって、それ自身もグローバル化のなかで変わりつつあります。たとえば、リービ英雄が日本語で小説や評論をかくのを、彼は「国語」で書いているとは決していわないのです。
*もうひとつ、著者の重要な問題提起に、現行の「国語教育」を広い意味での読解と記述表現にかんする「リテラシー」教育と、文学の享受とに分離すべきだというのがあるのですが、また、稿を改めます。

タイトルの書の読後感です。
本書の概要は既にいろいろな人が要約しているので割愛。
問題点のみ記述。
1)ルソー的な一般意志をバージョンアップした「一般意志2.0」は、ネットの、たとえば東が例に出している「ニコニコ動画」で拾えるのか。
その包接範囲なども含めてそれを彼のいう数学的意味でのモノとしての一般意志となしうるのかどうか。
2)ハーバーマスとハンナ・アーレントをともに「熟慮民主主義」としてくくっているが、これはいささか荒っぽい括りではないか。
ハーバーマスはともかく、アーレントは「熟議」や「コミュニケーション」に力点を置くのではなく、そこへと参加できる人間の可能性の条件についてつねに語っている。
それはゾーエーとしての生命活動(=労働)からの解放としての「活動」だが、それらが常にうまくゆくとはいっていない。ようするに、公共の場へと参加しうることに意義を見出しているのである。
この書の場合、そうした公共の場への参加は「ツイート」に還元されてしまうのだが、果たしてそれでいいのか。
3)集合的無意識の集積された一般意志2.0として可視化された「データベース」と、意識としての「熟議」が相補的に働いた政治のイメージが語られるが、その「相補」の具体的なイメージが見えてこない。
ニコニコ動画によるフィードバックとそれへの呼応として一応は語られているが、その双方向的なチェック機能はどのように働くのだろうか。
4)モノとしての一般意志2.0に従った政治は小さな政治を理想とするとあるが、それのみではローティのいうところの「悲惨の減少」は実現しないのではないか。述べられている「治安警察国家」の他に、たとえば、ベーシック・インカムのような政策が実施されないところでは、アーレントのいうところの「経済」や「労働」に足を取られざるを得ず、したがって常にバイアスのかかった「一般意志(?)」しか形成されないのではないだろうか。
それらの疑問を禁じ得ないのであるが、20世紀の政治を止揚した形態を、アーレントやローティに沿いながら考えてきた私にとっては、この二人に言及しながら、こうした政治のイメージが出来上がるということに、大いに刺激を受けた次第である。
著者は、これはエッセイであり論証という点に重きは置いていないという。しかし、明らかにこれまでの著者の延長上に位置づけられる論考であり、したがって、上の私の疑問などもふっきる形で、さらに論証を深められることを切望する。

















