亡父譲りの紅梅の鉢植えは、ほぼ満開に近づいた。


追いかけるように、桜桃のなる桜は蕾が膨らみ、その蕾の紅色が見え始めた。例年、開花は3月10日ぐらいだが、今年はやや早いかも・・・・。


で、何の関係もなく、今日の昼食はラーメン。動物性タンパク質は何もなかったので、ウインナーソーセージを使った、ウィンナーラーメン。
ちなみに、ウィーンへ行って、ウィンナーコーヒーを下さいといっても、ないそうだ。
もちろん、このウィンナーラーメンもない・・・・と思う。

ある日の昼餉。適当に残り物を放り込んだら、なんか春めいたパスタになった。

山かけ蕎麦。いろんなものを乗せるのが好きだ。これはねぎ、大葉、柚子のみじん切り、切り海苔をのせているが、ゴマを振るのを忘れた。それを含めれば、五目山かけ蕎麦になったのに。

うどん。具は、水菜、鶏肉、舞茸、揚げ。残り物のオンパレード。

これは夕餉。左の生姜の漬物は既製品。上の黒っぽいのはもずく。生姜の千切りが入っているのだが、写真を取る前に撹拌してしまった。
メインディッシュはブリの煮付け。右側は、ごちゃまぜサラダ。

どういうわけか味噌ラーメンが食べたくなったので作る。キャベツとモヤシはあったが他に具になりそうなものはない。そこで余り物のがんもどきが登場することに。がんも味噌ラーメン。これって、「元祖味噌ラーメン」のモジリだが、わかんねぇだろうなぁ。

トロロ飯。ねぎ、大葉、切り海苔、ゴマを乗せている。左の高菜の切り漬けは既製品。

【おまけ】
24日放映のNHKの「ドキュメント72時間」で、名古屋大須の屋台のラーメン屋をやっていた。
いろいろな人たちがやってくる。リーマンショックで云々という人が2人もいたのにはいささか驚いた。
離婚し、5人の子どもを抱えたシングルマザーが、子どもたちの食はこの屋台の店主が支えてくれたというのに接し、つい涙腺が緩みそうになった。
いささか手垢のついた「人情屋台」という台詞が、ここでは生きているように思った。ラーメンが500円、酒一杯が300円。800円を握りしめてそこへ行きたくなった。
この書を手にした動機は、普通、「超人たれ!」と説く「強いニーチェ」を連想しがちなのだが、そのタイトルに「弱い」という形容を冠しているからだ。
一つ考えられるのは、唯一無二と決めつけた真理や正義の側(形而上学的立場)に自分を置き、その世界観で自分を律する「強い」人、あるいはそうした真理や正義の体系から自分は疎外され逸脱しているとするいわゆる「強さ」への憧憬を抱くルサンチマンの人、これらを「強い人」ないしは「強い人の陣営」と形容するならば、それを嫌悪し、自分の「生」をあるがままに「諾=ヤー」といって引き受ける二ーチェは「弱い人」になるかもしれない。

しかし、いってみればこれは反語的な表現で、やはり自分の思考を放棄し、既存の体系に依存するしかない人たちは「弱い」のであり、自分の「生」をそうした既存の価値観から解き放つニーチェのような人は「強い」のである。
というようにまとめてしまえば、この書はこれまでのニーチェの解説書と変わるところはない。ああ、やっぱり二ーチェは強い人であり、形而上学的価値観に屈する「強さを装う」人たちがそれらを大上段に振りかざして人々を抑圧したのが、20世紀のナチズムやスターリニズムの歴史であったのだということで終了してしまう。
しかしこの書が、それにとどまらない点があるとしたら、次の二点であろう。
その一つが、ニーチェの妹(エリザベート)が編纂し、『力への意志』または『権力への意志』として、ナチズムに利用されるような民族主義、国家主義、全体主義を導きかねない(実際のところ、エリザベートはナチスの支持者であった)書に仕立てたその遺稿『Wille zur Macht 』を、もう一度解体的に読み直し、そこでのニーチェの思想を別様のものとして掬い上げたことである。
もうひとつは、そこにたち現れたニーチェ像を、東洋哲学の道元などと対比させながら読み込んでゆくところである。私は、東洋哲学に関してはほとんど無知だが、道元の「尽」という概念との突き合わせはわかる気がする。

ようするに、ここに述べた遺稿『Wille zur Macht 』の2つの方面からの読解こそが、著者が従来のニーチェ解釈、人間の解釈に加えた新しいものといえる。そしてそれが、この書のサブタイトル「ニヒリズムからアニマシーへ」が意味するところといえる。
この「アニマシー」というのは聞き慣れない言葉であるが著者の造語だという。その造語はこうだ。普通、アミニズムというのはすべてのものに生命が宿るとし、またアニマシズムは生命があるかどうかは定義できず、偶発的に感じとられることする。そこからアニマシーは偶発的な〈あいだの命〉を感受することだとする。
二ーチェは生命を次のように考える。
*第一の生命 一つ一つの命、このものの命、それ自体の命 生物学的命
*第二の生命 すべての命、乗り越える命、あまねく行き渡る命 超越的生命
*第三の生命 あわいの命、立ち現れる命 リアルな生命
第一のそれはまさに自然の生命である。しかし、その有限でやがて終焉するであろう生命を恐れる人間は、第二のそれ、超越的で永遠の生につながるものとして考える。これは「強い」人間であるとともに、自分はそれから疎外され、本来性を失っているというルサンチマンを抱いた「弱い」人間としても現れる。これはまたニーチェが退けた人間像である。
そこで改めて登場する生が、第三の生命ということになる。「あわいの命」、「立ち現れる命」とあるが、この生は一人の個人のなかには他者と同じ知覚像が多数多様に入り込んでいて、それ故に人は他者に感情移入したり、共感、共苦することが可能になる。いわば私の主体というのはハイブリットで多重的なのである。
それのみか、わたしたちは、動物、モノが持つ他への働きの運動に対応することもできる。それが、先に見た「ニヒリズムからアニマシーへ」のアニマシーに相当する部分である。

ようするに人間は形而上学的超越性(第二の生命)にすがりがちだが、実際には多重的複合的主体であることによって、ヒト、コト、モノの諸関連によって生じるあらゆる生成、生起に立ち会うことが出来るのである。ここにあるのは力をもち、「力への意志」を振りかざす強い人間ではないが、あらゆる力の発現に立ち会うことが出来る人間像である。
しかし、その人間は多重的、複合的、総合的にして混沌である。そして、出来事はそうしたなかで生じる。
結局のところ二ーチェは強いを弱い、弱いを強いと言い換えた哲学者だったといえるようだ。
最後に、『Wille zur Macht 』のなかからというニーチェの言葉を引いておこう。
ひとつのものを設定して生を生きようとする者どもよ その人間的な強い生によって、お前たちはどれほど数多くの人間を殺し、自然を破壊してきたのか すべてはヴィレ(意志)の闘争なのである この闘争の動態を見ることなくして、いたずらに一とか超越とか平和とか理性とか同情とか尊厳などといった虚構を捏造し、そのことによってすべてを破壊しようとしてきた人間どもよ、君たちは自分たちの弱さを知らないのか 君たちが自分たちこそ強いと自認する時、私は逆に弱さを選ぶことにしよう そしてその弱さを、私自身の言葉で「強さ」と呼ぶのだ
*『弱いニーチェ ニヒリズムからアニマシーへ』 小倉紀蔵 筑摩選書
もう何度もあちこちに書いたが、1991年8月、私は初めての海外旅行の途上にあった。行く先はモーツァルト没後200年に際しての記念すべき音楽祭に湧くザルツブルグであった。三つのオケと二つのオペラを含むこの夢のような旅は、ボーナスもなにもない自営業の私に、私自身が与えた開業20年ぶりのボーナスであった。
この旅で、私が最初にその足を下ろす異国の地は、当時のソ連、モスクワ空港であった。モスクワに滞在する予定はなかったが、そこで給油のため一時間半か二時間の滞在があるので、空港内へ降り立っての行動は予定されていた。
ノーテンキな私は、その空港内で、上質のウオッカでも入手せんものと手ぐすね引いていた。機は、大小の湖と白樺林が点在するモスクワ郊外の空港へと滑り込んだ。

その時であった。スワと席を立とうとした私に無慈悲な宣告が下された。機内アナウンス曰く、「ソ連当局のお達しにより、乗客の空港内立ち入りは禁止されました。そのまま、お席にて出発をお待ち下さい」
ガ~ン、ソ連の、モスクワの地をこの足下で感じとりたいという私の望みはかくして断たれることとなった。1991年8月22日(日本時間)のことだった。
その要因もほぼ推測できた。いくら世間に疎い私でも、ゴルバチョフのペレストロイカやそれに同調するエリツィンに対し、それに抵抗する旧共産党系の反動派がクーデターを図ったが既に鎮圧されたというニュースは出発前日にキャッチし、それじゃ、モスクワ空港内の散策も・・・・と安心しきっていたのだ。

しかし、結局はソ連が崩壊し、その傘下の国々の独立と同時にその中心であったロシアは新生ロシアとして再出発するという歴史的大事件が、この現地においては、日本の地で新聞やTVで見ていたように、「ハイ終わりです」というわけにはゆかないことは当然だったのだ。
しかも、私がモスクワ空港へ着いたその日、クーデター派によってクリミアに幽閉されていたゴルバチョフが、開放され、まさにモスクワ空港経由で帰ってくるその日だったのだ。
航空機の窓から見る空港は、まさに厳戒態勢だった。機関銃を積んだ装甲車が走り回り、完全な戦闘ムードの兵士たちが、あちこちで警備の体制をとっていた。銃を携帯した兵士の一隊が、機体の周りをパトロールする。窓越しにではあるが、下手に目を合わせると狙撃されそうな気分にすらなる。

前置きが長くなった。私が観た映画は、ちょうどその頃、当時のレニングラード(いまのサンクトペテルグルクで何が起こっていたことを映像にしたものである。
日にちや時間などの字幕が入る以外、ほとんどノーナレのモノクロ映像は、この都市の各地での凄まじい数の人々の不安や怒りや訴えを映し出す。それらは、やっと73年にわたるスターリニズムの抑圧体制からテイクオフしようとしているとき、そのネジを逆転させようとしている反動派のクーデターに反対するものだ。
実は私は、コロナ禍が始まる寸前の2019年夏、このサンクトペテルブルクを訪れている。その折は、主として1917年のロシア革命の痕跡を追いかけたのだが、その折見た多くの風景が、この映画では、その17年の革命を否定する場として登場するのは感慨深かった。
ここに載せたモノクロの写真は映画からのものだが、カラーは2019年に私が撮ってきたものだ。

映画は、サンクトペテルブルクの各地で人々が集まり、集会やデモを行うシーンが出てくる。とりわけ、私が何度も行ったエルミタージュ美術館(1917年のロシア革命では、ボルシェビキがケレンスキー一派を最終的に追い出し、政権を樹立した当時の冬宮)前の宮殿広場には、八万人の大観衆が集結する大集会がおこなわれ、人々は口々に要求のスローガンを叫び続けた。
この映像を見て、これだけの人々が集まりながらも、ほとんど流血をみなかったのは、素晴らしいと思う。

その結果が、ソ連の解体となり、連邦内の国々は独立し、新生ロシアが誕生したことは誰もが知っている。そして映画は、そこで終わっている。
この映画には、若き日のプーチンもチラッとだが出てくる。反動派のクーデターに反対する立場からのものである。

私たちにとっての興味は、その後のロシアがどうして今日見られるようなプーチンの専制政治体制になり、ウクライナへ侵攻するなど大ロシア主義の道をたどることになったかである。
あの、サンクトペテルブルクの街を埋め尽くした「自由」への叫びは、どこへ行ってしまったのだろうか、ということでもある。

その解明に役立つのは、ハンナ・アーレントの『革命について』ではないかと思う。これを論じだすと長くなるので端折るが、彼女は、革命の成否はその革命が要求する内容の方向性によるとする。
搾取や強権、抑圧からの解放は革命の要因になりやすい。ただ、その「~からの自由」のみの革命は挫折しやすいという。むしろ、問題は獲得すべきものを明確にすること、つまり、「~からの自由」にとどまらず、「~への自由」が明確にされねばならないとする。

それを適用するならば、1991年のロシアの「革命」は、73年続いたスターリニスト支配「からの自由」を実現したものの、自らの体制をいかなるものとして形成するかの、新しい体制「への自由」という展望を欠いていたがゆえに、新自由主義とのグローバルな世界的競争に投げ出されるなか、今日のような奇怪な体制を余儀なくされているのではないか。

世界には、いま開催されているG7のような一時的安定の中で静態的に不動であるかのような「優等生国家」がある。しかし、それらの国々がいつ炸裂するかわからないマグマを抱え込んでいるのは、アメリカやこの国をみるだけでじゅうぶんわかる。
世界の歴史は、そうした潜勢態にあるものが、ちょっとした変化で、現勢態に転ずることから生じる。

1991年までの20世紀の大半は、米ソの不動の体制下にあり、左翼も右翼も、リベラルも、全てその舞台で踊っていたのだから。
亡父譲りの紅梅の鉢が、次第に花をつけ始めました。

私が譲り受けてから、もう30年は経つので、おそらく樹齢は数十年でしょう。
今年はなんだか、花の数が少ないように思えます。樹齢のせいか、私のものぐさのせいか気になるところです。

この写真を撮った日、たまたま昼食にカレーピラフを食べました。

そこでこんな文章を書きました。「亡父譲りの紅梅の鉢にどんどん花がついてきたので、昼食はカレーピラフにしました。」

なぜこんな変な文章を書いたかというと、今話題のAI と会話(chat)ができるという、「chatGTP」をテストするためです。
これをそのまま送ったところ、AI は以下のように答えてきました。
「この二つの要素は、本来ならば何の関係もないように思われますが、プロキシによってはやがて可能性があります。
仮に、この場合であれば、『亡父譲りの紅梅の鉢にどんどん花がついてきた』という状況が作者にとって喜ばしいものであったことがお願いします。そして、その喜びを表現するために、作者が昼食にカレーピラフを選んだことを示唆していると考えることができます。 つまり、作者が心地よい状況にあるために、カレーピラフを食べることができたのだということです。
規則、このような文章はアルゴリズムによって異なる解釈ができるため、正確な解決には解決を適応する必要があります。」
まだまだ日本語がこなれていない感じがしますが、いってることはそんなに外れてはいません。
このchatGTPはいま急速に世界中に広がりつつあります。アメリカの大学生にとっては必需品扱いだそうです。
折しも、AI が人間の知能を超えるというシンギュラリティ(技術的特異点)は2045年だといわれています。
さてその折、現実にはどうなっているでしょうか。私はもう生きてはいませんが、人間が現状のように愚かでいるとしたら、AI が世界を支配し、人間はその下僕となっているかもしれませんね。
それが、戦争や格差のない社会だとしたら、それでいいのじゃないかと思っています。
AI とのチャット、面白いですよ。今日私は、カントとニーチェの哲学について問答をしました。知識はAI 、その解釈などは私のほうが・・・・といえそうですが、AI は日々学習しますから、その逆転も近いのかも知れません。
私が常備している食材にわかめがある。わが家の味噌汁は、豆腐、わかめに小口切りのネギを散らすというシンプルなものが多いため、乾燥したカットわかめは必需品で、業務店用のかなり容量の多いものを在庫している。
その他に、いわゆる生わかめが出回った際にはそれを購入する。細かくカットした乾燥わかめは、味噌汁以外の用途には小さすぎるからだ。
酢の物やヌタ、麺類などその他の料理の添え物としては生わかめがうってつけだ。
まあ、ざっくりいえばわかめ好きなのだろうが、中でもとりわけこの時期のわかめは絶対に外せない。なぜなら、「ほんとうの生わかめ」が出る時期だからだ。
年中、生わかめは出回るが、それらは貯蔵したものを加工(たとえば、葉の部分と茎の部分を別の商品としたり)したものである。そしてその色合いはというと、乾燥したものは黒く、その他のものは緑色である。なかには若葉のように明るい緑もあり、これぞ「生」わかめと思わせたりする。
それらに対して、この時期は「ほんとうの生わかめ」が出回る。「ほんとうの」というのは上記のように貯蔵されていたものを加工したりしたものではなく、まさに海から穫ったそのままがでてくるのだ。というのは、この時期がまさにわかめの旬であることを示している。
そしてその色彩はというと、黒くもなく、緑でもない。最初の写真のように褐色をしている(この写真のみ図鑑から拝借)。

スーパーなどではそれを折りたたんで二枚目の写真のようにして売っている。ちなみに、これは160円で手に入れたが、普通200円前後で手に入る。
すぐ隣にある緑色の従来の生わかめは、この分量だと数百円はする。
これの処理はかんたんである。ややたっぷりめの湯を沸かし、沸騰したなかにそれを入れる。その途端に、鮮やかな緑に変わるのは楽しい。
しかし、あまりグラグラ煮るのはよくない。わかめの旨味が出汁になって出てしまう。

全体に色が変わり、次に沸騰しそうになったら(多少は加熱しないと日持ちの問題がある)さっと冷水にとる。それを食べやすい大きさにカットし、タッパーなどに入れて冷蔵庫で保管する。
先にも述べたが、他の時期の生わかめは葉の部分のみで、茎の部分は茎わかめとして別に売っているが、この時期、自分で湯がいたものは茎も一緒だ。
調理をする折、茎だけでなにかをつくってもよいし、一緒に調理しても構わない。

こうして保存しておくと、いろいろなものに使える。
酢の物はもちろんだし、イカやわけぎ、ホタルイカなどとヌタにするのも良い。
刺身類の付け合せにもなるし、サラダにも使える。
私がけっこう多用するのは、麺類の具としてだ。うどん、ソバ、ラーメンとなんにでも使える。

この間、こうした「ほんとうの」生わかめを見かけ次第、買うようにしている。
ちなみにここでうんちくを一つ。
わかめは実に見慣れた食材であるが、これが穫れるのは、日本の近海と朝鮮半島の南の方に限られるというからわかめ好きの私にはありがたい話だ。

若布は昆布と並んで普遍的な海藻なので、昔から詩歌に詠まれてきた。
そのうち、万葉集に東海地方に関連したものがあるというので載せておく。
打ち麻を麻続の王海人なれや伊良虞の島の玉藻刈ります
うつせみの命を惜しみ波に濡れ伊良虞の島の玉藻刈り食む
この玉藻はわかめのことで、この二首ともに、麻続の王(おみのおおきみ)が流刑先の伊良虞=伊良湖でわかめを穫って食しているのを哀れんだ歌だという。
一種目は、「麻続の王は海人なのだろうか 伊良湖の島で若布を穫ってる」で二首目はその続き。
麻続の王は生没年不詳、七世紀末の皇族。675年、天武天皇によって流刑にされたというがなんの咎かはよくわからない。
また流刑地も諸説あるが、万葉集は伊良湖をとっているようだ。

なお、俳句にも多くの作品があるが
若布刈るやかなしきまでに汐碧く 鈴木真砂女
が目についた。
この鈴木真砂女(1906~2003)は、波乱の生涯を歩んだ人のようで、丹羽文雄や瀬戸内寂聴の小説のモデルになっているという。
例によって、蛇足が長くなった。
私は、フェミニズムやジェンダー、セクシュアリティについてきちんと学んだことがない。小説やドラマ、映画などを通じて感覚的に身につけてきた不確かなものしかもちあわせていない。
ただし、1960年前後、シモーヌ・ド・ボーヴォワールの「人は女に生まれるのではなく、女になるのだ」を読んで、その逆、「人は男に生まれるのではなく、男になるのだ」もまた真かなと思ったことはある。
だいたい、私は男らしさに欠けていると思っていたし、それを希求したこともない。ただし、性意識としては自分を男性だと思ってきたし、性的志向も異性愛的である。
家父長制意識は希薄だと思ってきたが、希薄であろうが濃厚であろうが、部分的な逸脱はあれ、家族制度のうちで暮らしてきたことは間違いない。

この書を手にしたのは、図書館の新着コーナーでけっこう特異な表紙を見かけたのと、「カウンターセックス宣言」に署名したというジャック・ハルバースタムの「前書き」冒頭に、
「 ポール・プレシアドのカウンターセックス契約に署名するとき、あなたは自然な男/女としての地位を放棄することに同意し、〈自然化された異性愛大勢の枠内で〉あなたに与えられるかもしれないすべての特権を放棄する」
とあり、また著者自身の序論では、
「異性愛ー資本主義ー植民地主義という三つの近代的物語、すなわち、マルクス主義、精神分析、ダーウィン主義」を崩壊させるという精神のマニフェスト」
と、刺激的な文章が並んでいたからである。
またこの著者が、デリダ、フーコー、ドゥルースなどのいわゆる現代思想(前世紀後半のであるが)を経由しての論客であることから、それをどう適応しているかの興味、さらには、セックスにおいての補綴、義体であるディルド(いわゆる「大人のおもちゃ」として扱われてきたモノたち)に特権的な位置づけをしていることにも興味をそそられた。
著者自身の経歴も気にかかる。1970年、スペインでベアトリスという女性として誕生するも性的違和を覚えるトランスとして育ち、2015年にはベアトリスからポールに名前を変え、16年には戸籍上の性も男性に変更したという。ラディカル・フェミニストからノンバイナリー(アンチ二項対立)なトランスジェンダーへという経歴らしい。
このトランスジェンダーは、 単なる性同一「障害?」を超えて、中性、無性などなどあらゆるセクシュアリティやその自意識を含んだ多様なものを指し示し、 しかもそれらを、男性/女性という二項対立の間にあるマイノリティとするのではなく、全く同等なそれ自体の存在とすることにより、これまでの性的マイノリティの運動自体に内在していた男/女の性的二項対立そのものを止揚しようとする。
要するに、ゲイやレズというマイノリティとされる内にもあった、男性/女性の役割分担などに残る二項対立(それらは結局の所、男根中心主義的家父長制支配に還元される)を拒否することによるセクシュアリティにおけるコミュニズムを目指す。
これはまた、男性器、女性器による、ないしはそれに限定される快感の生産に対し、それらの補綴、義体とされたディルドの普及を推奨する。それは、男女の二元化されたセクシャリティを超えたあらゆる性的身体に共用されるものであり、その観点からすれば、むしろ男根自体が社会的通念によって工作されたディルド機能の代補であるに過ぎない。
この論理は、性的営みを男/女の結合にある生殖行為を本来とし、それを自然なものとして特権化することに反対する。むしろ、この生殖のための性的行為の特権化こそ、多様であるべきセクシアリティを奇形であるとして抑圧し、排除する男根中心主義的家父長制、それに依拠した国家の実体だとする。

ここに至ってプレシアドの理論は、性的マイノリティの権利の主張という消極的なものから、広く普遍的なセクシャリティのありようを媒介とした、コンミューン的展望という積極的な地平を見渡すこととなる。
そのとき、ディルドは男/女の二元論に依拠した「自然的性行為」という正当化工作を乗り越え、性的権力を自分たちの手に取り戻すために連帯する新たな性のためのプロレタリアートを目指す特権的な用具として機能する。
プレシアドは性におけるトランス化を目指すと同時に、世界のトランス化を目指す性的プロレタリアートを登場させる。彼ら/彼女らが世界を変え、世界をトランス化させるのに、巨大な権力闘争や革命的転覆は必要ない。必要なのは、今ここにある小さなディルドの潜在力をラディカルに肯定し、拡大することだとする。
以上がすごく大雑把だが、私が読み取った限りでのこの書の概要である。
残念ながら、それについての評価を記すことは出来ない。冒頭に述べたように、フェミニズムやジェンダー論、セクシュアリティに関する問題にもともと暗いからである。
しかし、プレシアドの理論はじゅうぶん刺激的であった。彼女が集中的に攻撃する男/女二元論、それに依拠した現今の異性愛的男根中心主義的家父長制的ありようが性的マイノリティは無論、あらゆるセクシュアリティに及ぼしている抑圧的体制をなしていることは確かだろうと思う。
問題はそれへの闘いの武器としてディルドを特権化することであるが、それへの判断は保留するしかない。この立場は、かつて精神分析を勉強した際、その異端とされたヴィルヘルム・ライヒ*を思わせるのだが、はからずも訳者あとがきにその名が出てきたのには驚いた。
なお、岸田は国会答弁のなかで、「同性婚を認めると社会が変わる」と答弁したが、これは正しい。まさにいま、社会は変わろうとしているだ。
その変化の一つの最先端が、この書で提示されている。
*ヴィルヘルム・ライヒは、晩年、生命体(organism)とオーガズム(orgasm)を組み合わせた効能を持つという「オルゴンボックス」なるものを普及させようとした。
『カウンターセックス宣言』
ポール・B・プレシアド 藤本一勇:訳 法政大学出版
目醒める
一日が始まる 始めなければならない
だが待てと 安逸の岸辺に押し寄せる反省の波・波・波
知っていたこと 知らなかったこと
知らないふりをしてきたこと 知ったかぶったこと

母の乳房を知らないし 父の抱擁を知らない
丘には蜜柑の花が咲いていたし 柱の傷はおととしからあった
戦争があって 竹林の下には防空壕
その闇を抜けると戦争はもはや痕跡となっていた
群れなす屍体と傷病 瓦礫の街と血染めの運河
やってくる進駐軍 その防波堤として動員された娼婦たち
注入される平和と民主主義のワクチン
効いたふりをして 経済の海へ漕ぎ出す人たち
それを鼓舞するいまや人間となったオオミカミ

快楽 快感 快挙 壮快
失楽 失意 失敗 失禁
適度に名付けられ それをなぞるように走る
なんとかなるさ 行く先? そのうちに見えてくるはず
畜群・・・・誰が?
群れている他に安全などないだろう
群れに背くは危険分子
離れすぎたやつは抹殺すればいい

大丈夫 自分は外れてはいない
自分は 自分は 自分は と繰り返すたびに希薄になる
もはや影もできない あちこちから陽が射しすぎるから
振り返る? そんな無理なことは言いっこなし
どっちが前で どっちが後ろかわからないのに
隣であえいでいるのは 周回遅れの自分
置き去りにするしかない
邪魔な自分は どんどん脱ぎ捨てアップデイトだ

突然 別の群れに分類される
老齢 前期 後期 要介護 寝たっきり
明日の自分 いや 今日の午後からかも
かくて 起床前のルーティン 形だけの反省は終わった
こうして始める一日 始める? どこから?
しまった 昨日の終りに栞を挟んでおくのを忘れた
TVの画面越しでの映画は観ていたが、映画館のスクリーンでは今年初めて。しかも、二本続けて、さらにどちらもドキュメンタリー。

一本は、かつて私が観て感動した、帰国事業で北へ渡った兄が一時帰国でやってくるということを巡っての劇映画『かぞくのくに』(安藤サクラ、井浦新など)を撮ったヤン・ヨンヒ監督(在日二世のコリアン女性)が自分の母を対象にしたドキュメンタリーで『スープとイデオロギー』と題されている。

この母も、そして既に亡くなっている父も、朝鮮総連(北側の在日コリアンの組織)の活動家であった。そのせいで、ヤン・ヨンヒ監督の三人の兄はすべて、いわゆる帰国事業で北へ「帰って」いる。その兄の一人が一時帰国した折の状況を踏まえた劇映画が私の感動を呼んだ『かぞくのくに』だったわけだ。
このドキュメンタリーは、監督の一家がなぜ「北」を選んだのかを1948年の済州島事件に遡って明らかにする。

済州島事件というのは、第二次大戦後(日本敗戦後)、38度線で分断された南側の権力者たちが、南側だけの選挙を行い、分断されたままの国家を立ち上げようとしたのに対し、それに反対する済州島の住民に対し加えられた大弾圧である。
1954年まで続いたというその弾圧の凄惨さは、「政府軍・警察及びその支援を受けた反共団体による大弾圧をおこない、少なくとも約1万4200人、武装蜂起と関係のない市民も多く巻き込まれ、2万5千人から3万人超、定義を広くとれば8万人が虐殺されたともいわれる。また、済州島の村々の70%(山の麓の村々に限れば95%とも)が焼き尽くされたという」(Wikiによる)。

このドキュメンタリーの主人公=監督の母は、その折、18歳であり、後に監督の父(朝鮮総連幹部)となる男性とは別に、若き医師と婚約関係にあったが、この男性はその父とともに済州島事件で殺害されてしまった。
済州島事件で、活動家でもない住民をも対象とした殺戮撃は凄まじく、母の証言によれば、かたわらの小川は赤く染まって流れていたという。
この済州島事件を始めとする南での惨事の連続は、日本の敗戦で一度は帰国した在日コリアンを、さらには新しいコリアンをも亡命同然に日本へ向かわせた。
監督の母も、幼いきょうだいを伴い、済州島で30キロを歩き、手配した船で日本へ入国したのであった。

ここに、彼女と、後に連れ添った夫とが、南側ではなく、北側の朝鮮総連の活動家になった経緯がある。そして同時に、戦後の在日コリアンの90%以上が南の出身でありながら、なぜ北側の「朝鮮総連」に圧倒的に多くの人々が所属していた時期があったのかを解く鍵がある。

さらにはそれが、のちの北への帰国事業に発展し、息子たち三人の北への「帰国」となり、そしてこのドキュメンタリーの主人公の連れ合いにして監督の父は、亡くなったあと平壌郊外の墓地に眠っているという。
要するに、済州島事件は朝鮮半島分断とその双方におけるその後のいきさつを決定づけた事件だったのであり、ヤン・ヨンヒ監督一家はそうした歴史的経由をまるまる抱え込んだいっかだともいえる。

映画のクライマックスは、認知症に侵された母が、2018年、済州島で行われた4・3弾圧70周年記念大会に参加するところである。記念式場では、沖縄の平和祈念公園同様、済州島事件で亡くなった犠牲者を彫り込んだ黒い御影石が建っている。刻み込まれた無数の名前。それを前に、半ば記憶を失った母は、かつての婚約者などの名を捜す。
そこでは見つからなかったものの、後に訪れた広大な共同墓地で、それは確認されたという。

タイトルの『スープとイデオロギー』は、しばしば出てくる全身の鶏肉の腹に、にんにくやナツメなど香辛性のものを詰め込んでじっくり煮込んだ蔘鶏湯に似た料理が対象で、いろいろな歴史的変遷、立場の変化などがあっても、その味は変わらないというところから付けられたらしい。

在日コリアンの一家族、その母の記憶、並びに記録だが、それは既に述べたように、朝鮮半島の戦後史を凝縮した形で色濃く保つものであった。 とはいえ、そのタイトルが示すように、話はその母と監督夫妻を中心としたホームドラマのような展開で、固っ苦しかったり、重苦しかったりといった感はない。
もうじゅうぶん長くなってしまった。もう一本の方はまた回を改めることにしよう。
*名古屋シネマテーク 2月17日まで
水田さんとは、特に師弟関係ということもなく、個人的に深い交わりがあったわけでもないが、私の20歳前後からいわば付かず離れずのお付き合いがあり、お元気な折の最晩年までお付き合いがあった。

水田さんと私とは、ちょうど20歳位の年齢差がある。
最初の出会いは、私が学生自治会の役員などをしていた1950年代の晩年、教職員勤務評定かあるいは警察官職務執行法改定かのどちらかへの反対闘争(それらはあの60年安保闘争の前哨戦とも位置づけられるものであった) を展開している折であった。私たち学生は教育、ないしは警察権の重要な変更の節目に当たって、 これらは先の敗戦の結果としてもたらされた戦後民主主義を後退させる脅威であるとして、反対の意思を固めていた。そしてその意思表示の形として、ストライキで もって闘うことも辞せずとしていた。
そうした私たちの動きに対して、それを説得すべく学校側が派遣したのが水田洋さんであった。当時水田さんは、新進気鋭の左翼経済学者として、私たち学生の間にも広くその名を知られていた。思うに学校側は、 学生にウケが良いその水田さんを派遣することにより、私たちの闘争をより穏便に収めることを図ったのであろう。
水田さんは語った。
「私もこの法案に反対である。 しかし、闘い方にはいろいろな方法がある。今諸君が選択しようとしているストライキは、いわば伝家の宝刀である。それを安易に抜くことは 許されない」と。
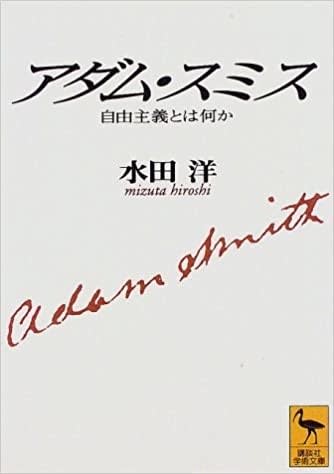
「ナンセンス!」の声が飛んだ。 私たちストライキ派は、その声に励まされるように水田さんに反論をした。「伝家の宝刀、宝刀といっても、いつまでもそれを抜かなければそれは錆つき、単なるなまくらに堕してしまう。 必要な時に抜いてこそ伝家の宝刀であり、そしてそれは今なのだ」と。
その折の、学生大会の結果がどうなったのかは覚えていない。当時の学生自治会運営は、後の学生たちからポッダム自治会 と揶揄されるほど民主的になされており、行動方針等は、一党一派の思惑を超えて多数決によって決定されていた。これが60年安保を経過して、多数の新左翼各派が それぞれの全学連=自治会を名乗ることにより、それが党派による複数の学生組織になってしまったのも周知の通りである。

学生組織の話はともかく、これが水田さんとの最初の出会いであった。その後は学部の違いなどもあって交流する事はなかったが、極めて私的な話では、 私の義理の弟が水田ゼミに入り、その彼のさまざまな事情につき、その適性をめぐって水田さんと話し合ったことがあった。
さらに 水田さんとの関係が深まったのは、いろいろあって私が名古屋は今池の地で居酒屋を開店した折であった。水田さんに最初会ったのは彼がまだ助教授(今の準教)の時代であったが、 それから何十年も経過したその頃には、名誉教授の称号を持ち、同時に各種市民運動の顔として広く名を知られていた。
まさにその時代、今度は居酒屋の亭主である私と、そのいわば常連客のような形での 水田洋さんとの付き合いが始まったのであった。 個人的にもよく話を交わしたのはその時代であった。
30年間にわたる居酒屋生活を終えて、岐阜の地に引っ込んだ私は、水田さんと会う機会もほとんどなくなったが、水田さんからは彼が主宰する同人誌「象」 が送られてきたし、私もまた自分が参加ししている同人誌を送ると言う関係が継続した。
そんなこともあって、かつての 水田ゼミのメンバーが中心になって行われる勉強会=読書会に招かれることとなり、そこで再び三度、水田さんとお目にかかることになった。 水田さんが100歳になった頃であった。

その会での水田さんはとても元気で、全体の討議に注意深く耳を傾け、しかるべき見解を述べるなど、今なお 現役を思わせるものがあった。その後の二次会にも、ご自分の足で数百メートルの距離を歩き、元気に飲み、そして歓談するのだった。
私が参加するようになって以降、そんな機会が2度ほど訪れたが、残念なのはコロナ禍によってその会が中断されてしまったことである。 そしてその間に、水田さんは体調を崩されたようで、それがこの訃報になってしまったわけである。
私は水田さんの業績をつまびらかに知るものではないし、また、その運動や思想の全てにわたって意見を共にしたわけでもないので、その業績を讃えたり、 顕彰したりする文章を書くことはできない。ただしほぼ60年間にわたり、付かず離れずのお付き合いの中で、これほど元気にその折々の課題に 取り組んできた人を知らないし、その意味では稀有な人であったと思う。
もう少し、その晩年から見た水田さん自身の回想のようなものを聞きたかった。それは私が招かれたあの勉強会の二次会で可能だったかもしれないと思っているのだが、それが、コロナ禍で中断されたのは、かえすがえすも残念だった。
なにはともあれ、水田さんの一世紀以上の生命を思い、その霊の安からんことを祈る次第だ。


















