別に暇な生活を送っているわけではない。朝起きて、さて何をしようかというようなことはいまのところない。やらなければならないことがけっこうあって、ちょっと怠けていると予め定めたことどもができなくて置いてゆかれることもある。
そんななかで、よく読めたなぁという比較的長い小説を読んだ。上・下二巻、合わせて700ページのものだ。一気に読んだわけではない。しなければならないことの合間合間に、ボチボチと読み続けてやっと読了したのだ。
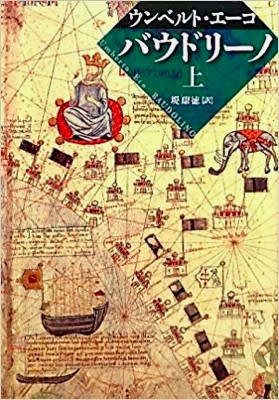
作品は、イタリアの記号論学者として高名なウンベルト・エーコの作品で『パウドリーノ』だ。
エーコの小説としては『薔薇の名前』が知られている。映画化もされたから、そちらの方で知っている人も多いだろう。私はこの小説も映画も両方に接したが、その乖離は甚だしかった。
小説の方では、若い僧が密かに思いを寄せる村の娘は、魔女として裁かれ処刑されてしまうのだが、映画の方では彼女は処刑されることなく、助かってしまうのだ。これによって、原作にあったヨーロッパ中世の不透明な厚みのようなものが一挙に吹っ飛び、映画の方はずいぶんと軽くなってしまった。
なぜこんなに著しい違いをもった映画化をエーコは承認したのかと疑問に思ったが、果たせるかな、新聞紙上でエーコがこの映画の解釈に激怒しているという記事が載るところとなった。
しかし、これはこれで、エーコ側が映画化を了承する際に、ろくすっぽ脚本もチェックしないままだったのかという疑問も湧く。それとも、途中で監督が勝手に原作を捻じ曲げてしまったのだろうか。

それはさておき、今回読んだ『パウドリーノ』は同じ中世に題材をとりながら、まったく違った趣を示している。『薔薇』の方が中世の聖性を司る闇の部分を描いた重厚なものであったのに対し、こちらの方は、その聖性すらも勝手にでっち上げて「商品」にしてしまおうというハチャメチャな冒険譚なのである。
パウドリーのは主人公の名前なのだが、貧しい農民の子として生まれながら識字と語学の才能に恵まれ、あわせて機転が利くホラ吹きでもある。
そんな才能を時の神聖ローマ帝国のローマ皇帝、フリードリッヒ・バルバロッサに見出され、高い評価を得て養子扱いをされるに至る。パウドリーノもまた、自分の養父ともいえるフリードリッヒに付き従い、遠征においてはそれに随行し、その過程で魑魅魍魎とも言える対象に出会い、あるいは敵対したり、あるいは同盟をしたり、恋をしたりの奇想天外な物語が展開される。
遠征先でのフリードリッヒの最期には密室殺人のサービスまでついている。
遊び心に満ち満ちた作品なのだが、私はそれらを、なんと想像力に満ちた作品なのだと感心しながら読み通した。
しかし、作家エーコの遊び心は、私のこんな感嘆を遥かに超えていたのだ。

そのひとつは、この小説がいかに荒唐無稽に見えようが、ここに登場する人物、例えばフリードリッヒは実在の人物であり、前半で描かれたイタリアの都市同盟との対立や、後半の十字軍遠征などは、すべて史実と一致しているのだ。
そればかりか、フリードリッヒの死が何に起因かはわかっていないようなのである。この小説がそうであるように。
もうひとつの例を見よう。
パウドリーノの冒険譚の聞き手であり、それを記録するのみか、最後には自身物語の中へと組み込まれるニケタス・コニアテスという人物が出てくる。
パウドリーノとニケタスの会話は、一つ一つのエピソードの間に通奏低音のように挿入される。それはまるで、ムソルグスキーのあの「展覧会の絵」に挿入されたプロムナードのようなものである。

で、このニケタス・コニアテスは、またビザンツ帝国に実在した政治家であり、歴史家でもあった。彼の主著は全21巻にも及ぶ『歴史』であるという。
その彼が、最終章では、パウドリーノから聞いた話をどうしようかと聖バフヌティウスに相談する。
そこで聖バフヌティウスはいう。
「あなたがこれをそのまま書けば、世に流通する聖遺物のかなりのものが捏造されたものであることを暴くことになる」
実際のところ、パウドリーノたちは多くの聖遺物を「作り出して」きたのだった。これはまさに、そう「名付けることによって事物は出現する」のだという記号論学者としてのエーコの面目躍如たる部分でもある。
聖バフヌティウスはさらに続けていう。
「たとえ事実に反しても、大きな歴史においては小さな真実を変更して大きな真実を浮かび上がらせることが可能なのです。あなたが書かねばならないのは、ローマ人の帝国の本当の歴史であって、遠く離れた沼地で起きた小さな出来事や野蛮な国々の野蛮な人びとのことではないはずです」
これにニケタスも屈することになる。
こうして、「大きな歴史」「ローマ帝国中心の歴史」のなかでは、その時代を実際に生きた人びとのことは、その存在をも含めて、とるに足りない些少なこととして抹消されることになる。
これがこの小説のラストシーンである。
「え、待てよ」と思う。ここにエーコの最大の遊びが、そのウィットがあるのではないか。
ようするに、700ページにわたって私が延々と読み続けてきたこの一大スペクタルは、実際には誰の手によっても「書かれなかった」物語なのだ。
私は、語り手不在の、書かれなかった物語を読んだということになるのだ。これはまるで、エッシャーのだまし絵のような話ではないか。もちろんこれは、エーコが仕掛けたトリッキーな設定である。

もうひとつ、エーコの遊び心を挙げておこう。
主人公のパウドリーノは、アレッサンドリアの貧しい農民の子なのだが、識字への能力が旺盛で、またどんな未知の言葉でも3日もそこで暮らすとその言葉を習得する程の記号に関する天才ぶりを発揮するのだが、エーコ自身がこのアレッサンドリアの出身であり、記号学者であるとしたら、彼は主人公のパウドリーノに自分をオーバラップさせてニンマリしているのではとも思える。
読んでいて、ヨーロッパ中世史への自分の未知を痛感させられた。それがわかっていたら、エーコがあちこちに仕掛けた「事実」と「物語」の共振をもっともっと楽しむことができたのにと思わざるを得なかった。
*私が読んだのは、図書館で借りたハードカバーのものだが、岩波で上・下とも文庫化されている。
そんななかで、よく読めたなぁという比較的長い小説を読んだ。上・下二巻、合わせて700ページのものだ。一気に読んだわけではない。しなければならないことの合間合間に、ボチボチと読み続けてやっと読了したのだ。
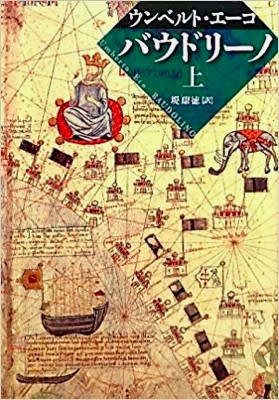
作品は、イタリアの記号論学者として高名なウンベルト・エーコの作品で『パウドリーノ』だ。
エーコの小説としては『薔薇の名前』が知られている。映画化もされたから、そちらの方で知っている人も多いだろう。私はこの小説も映画も両方に接したが、その乖離は甚だしかった。
小説の方では、若い僧が密かに思いを寄せる村の娘は、魔女として裁かれ処刑されてしまうのだが、映画の方では彼女は処刑されることなく、助かってしまうのだ。これによって、原作にあったヨーロッパ中世の不透明な厚みのようなものが一挙に吹っ飛び、映画の方はずいぶんと軽くなってしまった。
なぜこんなに著しい違いをもった映画化をエーコは承認したのかと疑問に思ったが、果たせるかな、新聞紙上でエーコがこの映画の解釈に激怒しているという記事が載るところとなった。
しかし、これはこれで、エーコ側が映画化を了承する際に、ろくすっぽ脚本もチェックしないままだったのかという疑問も湧く。それとも、途中で監督が勝手に原作を捻じ曲げてしまったのだろうか。

それはさておき、今回読んだ『パウドリーノ』は同じ中世に題材をとりながら、まったく違った趣を示している。『薔薇』の方が中世の聖性を司る闇の部分を描いた重厚なものであったのに対し、こちらの方は、その聖性すらも勝手にでっち上げて「商品」にしてしまおうというハチャメチャな冒険譚なのである。
パウドリーのは主人公の名前なのだが、貧しい農民の子として生まれながら識字と語学の才能に恵まれ、あわせて機転が利くホラ吹きでもある。
そんな才能を時の神聖ローマ帝国のローマ皇帝、フリードリッヒ・バルバロッサに見出され、高い評価を得て養子扱いをされるに至る。パウドリーノもまた、自分の養父ともいえるフリードリッヒに付き従い、遠征においてはそれに随行し、その過程で魑魅魍魎とも言える対象に出会い、あるいは敵対したり、あるいは同盟をしたり、恋をしたりの奇想天外な物語が展開される。
遠征先でのフリードリッヒの最期には密室殺人のサービスまでついている。
遊び心に満ち満ちた作品なのだが、私はそれらを、なんと想像力に満ちた作品なのだと感心しながら読み通した。
しかし、作家エーコの遊び心は、私のこんな感嘆を遥かに超えていたのだ。

そのひとつは、この小説がいかに荒唐無稽に見えようが、ここに登場する人物、例えばフリードリッヒは実在の人物であり、前半で描かれたイタリアの都市同盟との対立や、後半の十字軍遠征などは、すべて史実と一致しているのだ。
そればかりか、フリードリッヒの死が何に起因かはわかっていないようなのである。この小説がそうであるように。
もうひとつの例を見よう。
パウドリーノの冒険譚の聞き手であり、それを記録するのみか、最後には自身物語の中へと組み込まれるニケタス・コニアテスという人物が出てくる。
パウドリーノとニケタスの会話は、一つ一つのエピソードの間に通奏低音のように挿入される。それはまるで、ムソルグスキーのあの「展覧会の絵」に挿入されたプロムナードのようなものである。

で、このニケタス・コニアテスは、またビザンツ帝国に実在した政治家であり、歴史家でもあった。彼の主著は全21巻にも及ぶ『歴史』であるという。
その彼が、最終章では、パウドリーノから聞いた話をどうしようかと聖バフヌティウスに相談する。
そこで聖バフヌティウスはいう。
「あなたがこれをそのまま書けば、世に流通する聖遺物のかなりのものが捏造されたものであることを暴くことになる」
実際のところ、パウドリーノたちは多くの聖遺物を「作り出して」きたのだった。これはまさに、そう「名付けることによって事物は出現する」のだという記号論学者としてのエーコの面目躍如たる部分でもある。
聖バフヌティウスはさらに続けていう。
「たとえ事実に反しても、大きな歴史においては小さな真実を変更して大きな真実を浮かび上がらせることが可能なのです。あなたが書かねばならないのは、ローマ人の帝国の本当の歴史であって、遠く離れた沼地で起きた小さな出来事や野蛮な国々の野蛮な人びとのことではないはずです」
これにニケタスも屈することになる。
こうして、「大きな歴史」「ローマ帝国中心の歴史」のなかでは、その時代を実際に生きた人びとのことは、その存在をも含めて、とるに足りない些少なこととして抹消されることになる。
これがこの小説のラストシーンである。
「え、待てよ」と思う。ここにエーコの最大の遊びが、そのウィットがあるのではないか。
ようするに、700ページにわたって私が延々と読み続けてきたこの一大スペクタルは、実際には誰の手によっても「書かれなかった」物語なのだ。
私は、語り手不在の、書かれなかった物語を読んだということになるのだ。これはまるで、エッシャーのだまし絵のような話ではないか。もちろんこれは、エーコが仕掛けたトリッキーな設定である。

もうひとつ、エーコの遊び心を挙げておこう。
主人公のパウドリーノは、アレッサンドリアの貧しい農民の子なのだが、識字への能力が旺盛で、またどんな未知の言葉でも3日もそこで暮らすとその言葉を習得する程の記号に関する天才ぶりを発揮するのだが、エーコ自身がこのアレッサンドリアの出身であり、記号学者であるとしたら、彼は主人公のパウドリーノに自分をオーバラップさせてニンマリしているのではとも思える。
読んでいて、ヨーロッパ中世史への自分の未知を痛感させられた。それがわかっていたら、エーコがあちこちに仕掛けた「事実」と「物語」の共振をもっともっと楽しむことができたのにと思わざるを得なかった。
*私が読んだのは、図書館で借りたハードカバーのものだが、岩波で上・下とも文庫化されている。



















































