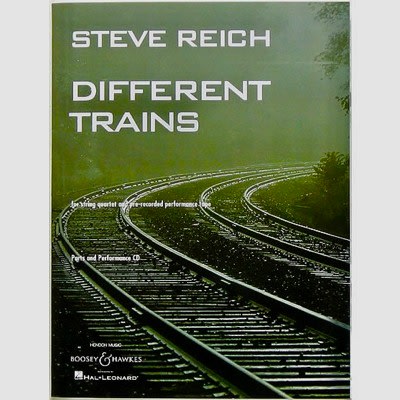私は歌舞伎については暗い方だ。まともな公演は、名古屋の御園座で2回ほど観たのみ。あとはTVなどで断片的に。
あ、そうそう、名古屋は大須の街を拠点に活躍していたスーパー一座の歌舞伎は何度か観たことがある。これはここで述べる「地歌舞伎」に近かったかもしれない。

岐阜は全国一といっていいほど地歌舞伎の盛んなところである。県内に30箇所の保存会があり、それぞれの伝統を継承し、それらを形として守るのみではなく、祭礼などのことあるごとに、その地で現実に生きたパフォーマンスとして公演が行われている。

地歌舞伎は、メジャーな大歌舞伎に対しては、大メーカーに対する地ビールや地酒のような位置づけだろう。演じる人たちも、みんな素人の地元の人たちである。
ただし、それはマイナーな歌舞伎が今もほそぼそと生き続けているということではなく、地域に溶け込んだ独自な伝統文化としてヴィヴィットに生きている。
だから、もはや大歌舞伎ではほとんど演じられなくなった演目を保持していたり、古くからの歌舞伎のための芝居小屋が残っていたり、社寺仏閣などの境内で奉納されたり、公演に協賛した人びとの名前がところ狭しと表示されたり、おひねりが飛び交ったりする。

その脚本も、おひねりが飛んだり、大向うから声がかかるための見栄きりの場面が多いという。その掛け声も、役を演じる人の本名や下の名前であったり、はたまたあだ名であったり、職業であったりいろいろだ。
ここには、むしろ、東京や大阪の大歌舞伎として集約されたものの、かつての原点のようなものが生きているといってよい。

そんな地歌舞伎の、中津川地域を中心としたものの公演が岐阜市で行われ、それに行ってきた。そのきっかけは、舞台を取り仕切る仕事をしている友人のY氏がFace Bookにそれを告知していたからである。
開演、30分前に会場に入ったが、演者の所作や表情がよく見える前方や中ほどは既に全て埋まっていて、後方からの鑑賞を余儀なくされた。
舞台の写真がボケているのは後方からガラケーで無理やり引っ張って撮したせいである。

さて、中身の方だが、地方に伝わる伝統的なものの資料と言った面を超えて、文句なしに楽しい。
今回は地元での公演と違って劇場での披露だが、それでもなお、大歌舞伎と違って客席との距離や交流が、とても近くて温かい。
ここぞというところで大向うから掛け声がかかり、前方ではおひねり がバラバラと舞台に投げ込まれる。
それにみんなうまいのだ。なかには端役が台詞につまり、プロンプターの声が聞こえてしまうというご愛嬌もあったが、主だったところはみな上手い。浄瑠璃や囃子方もなかなかのものだ。

舞台にバラバラと見えるのは飛んできたおひねり
出し物では、『一谷嫩軍記』(いちのたにふたばぐんき)「熊谷陣屋」が面白かった。この『平家物語』を下敷きとして展開される大河ドラマにも似た延々と続く物語は、そのパロディとも言える異説で成立しているのだが、それにさらに後世の江戸期の武家のモラルが加算されて、独特の物語構成となっている。
頼朝と義経の確執を前提とし、史実とはいささか異なる展開は、まるで陰謀論のように、なるほどそうだったのかと思わせる整合性も備えている。
この長い物語を、凝縮したようなのが三段目の中の「熊谷陣屋」といえる。その前後には膨大な物語が散りばめられているのだが、やはりその核心は「熊谷陣屋」だといえる。脚本もうまくできていて、この部分だけでも全体像を推し量ることができる完結したドラマになっている。

最後は町家の物語、いわゆる世話物で、『増補八百屋の献立 新靭八百屋』。これは中津川保存会の十八番らしく、NHKホールなどでの上演されたことがあるという。
母・くまを演じる役者さんは、かつての「ばってん荒川」のお米婆さんを彷彿とさせる演技で客席を沸かせていた。
こうした世話物になると、ダジャレや風刺、現代風物なども飛び出して楽しいのだが、このお芝居は最後は悲劇に終わる。
芝居も楽しかったが、それをめぐる全体も楽しかった。ロビーでは東濃地方の名産が販売され、五平餅やみたらし、焼きそばといった屋台が設えられ、幕間の人たちを惹きつけていた。
前に八百津の方に行った折、そこで求めたせんべいが美味しかったので、「昔懐かしいふる里せんべい」というのを三袋500円でゲット。そしたら、「ハイ、これもおまけ」と煎茶の入った袋を付けてくれた。

私がものごころついて始めてみた芝居は、疎開先の片田舎で70年ほど前の敗戦直後、村の祭礼での田舎芝居。復員してきた兵士たちも混じえて、手造りの装置や衣装、カツラによるものであった。出し物の詳細は忘れたが、戦争は終わった、もう戦地へ駆り出されることもなく、降り注ぐ爆弾のもと、死地を彷徨うこともないという解放感が溢れ、弾けた舞台であった。
これらが、戦時中は決してできなかったものだったことを考え合わせると、芝居を観せる・観るという関係も平和ならでこそのものだとしみじみ思う。
今度はおひねりを用意して、実際に地歌舞伎を上演している「現地」へ乗り込みたく思った。またひとつ地歌舞伎の「地」性が強く感じられることと思う。
あ、そうそう、名古屋は大須の街を拠点に活躍していたスーパー一座の歌舞伎は何度か観たことがある。これはここで述べる「地歌舞伎」に近かったかもしれない。

岐阜は全国一といっていいほど地歌舞伎の盛んなところである。県内に30箇所の保存会があり、それぞれの伝統を継承し、それらを形として守るのみではなく、祭礼などのことあるごとに、その地で現実に生きたパフォーマンスとして公演が行われている。

地歌舞伎は、メジャーな大歌舞伎に対しては、大メーカーに対する地ビールや地酒のような位置づけだろう。演じる人たちも、みんな素人の地元の人たちである。
ただし、それはマイナーな歌舞伎が今もほそぼそと生き続けているということではなく、地域に溶け込んだ独自な伝統文化としてヴィヴィットに生きている。
だから、もはや大歌舞伎ではほとんど演じられなくなった演目を保持していたり、古くからの歌舞伎のための芝居小屋が残っていたり、社寺仏閣などの境内で奉納されたり、公演に協賛した人びとの名前がところ狭しと表示されたり、おひねりが飛び交ったりする。

その脚本も、おひねりが飛んだり、大向うから声がかかるための見栄きりの場面が多いという。その掛け声も、役を演じる人の本名や下の名前であったり、はたまたあだ名であったり、職業であったりいろいろだ。
ここには、むしろ、東京や大阪の大歌舞伎として集約されたものの、かつての原点のようなものが生きているといってよい。

そんな地歌舞伎の、中津川地域を中心としたものの公演が岐阜市で行われ、それに行ってきた。そのきっかけは、舞台を取り仕切る仕事をしている友人のY氏がFace Bookにそれを告知していたからである。
開演、30分前に会場に入ったが、演者の所作や表情がよく見える前方や中ほどは既に全て埋まっていて、後方からの鑑賞を余儀なくされた。
舞台の写真がボケているのは後方からガラケーで無理やり引っ張って撮したせいである。

さて、中身の方だが、地方に伝わる伝統的なものの資料と言った面を超えて、文句なしに楽しい。
今回は地元での公演と違って劇場での披露だが、それでもなお、大歌舞伎と違って客席との距離や交流が、とても近くて温かい。
ここぞというところで大向うから掛け声がかかり、前方ではおひねり がバラバラと舞台に投げ込まれる。
それにみんなうまいのだ。なかには端役が台詞につまり、プロンプターの声が聞こえてしまうというご愛嬌もあったが、主だったところはみな上手い。浄瑠璃や囃子方もなかなかのものだ。

舞台にバラバラと見えるのは飛んできたおひねり
出し物では、『一谷嫩軍記』(いちのたにふたばぐんき)「熊谷陣屋」が面白かった。この『平家物語』を下敷きとして展開される大河ドラマにも似た延々と続く物語は、そのパロディとも言える異説で成立しているのだが、それにさらに後世の江戸期の武家のモラルが加算されて、独特の物語構成となっている。
頼朝と義経の確執を前提とし、史実とはいささか異なる展開は、まるで陰謀論のように、なるほどそうだったのかと思わせる整合性も備えている。
この長い物語を、凝縮したようなのが三段目の中の「熊谷陣屋」といえる。その前後には膨大な物語が散りばめられているのだが、やはりその核心は「熊谷陣屋」だといえる。脚本もうまくできていて、この部分だけでも全体像を推し量ることができる完結したドラマになっている。

最後は町家の物語、いわゆる世話物で、『増補八百屋の献立 新靭八百屋』。これは中津川保存会の十八番らしく、NHKホールなどでの上演されたことがあるという。
母・くまを演じる役者さんは、かつての「ばってん荒川」のお米婆さんを彷彿とさせる演技で客席を沸かせていた。
こうした世話物になると、ダジャレや風刺、現代風物なども飛び出して楽しいのだが、このお芝居は最後は悲劇に終わる。
芝居も楽しかったが、それをめぐる全体も楽しかった。ロビーでは東濃地方の名産が販売され、五平餅やみたらし、焼きそばといった屋台が設えられ、幕間の人たちを惹きつけていた。
前に八百津の方に行った折、そこで求めたせんべいが美味しかったので、「昔懐かしいふる里せんべい」というのを三袋500円でゲット。そしたら、「ハイ、これもおまけ」と煎茶の入った袋を付けてくれた。

私がものごころついて始めてみた芝居は、疎開先の片田舎で70年ほど前の敗戦直後、村の祭礼での田舎芝居。復員してきた兵士たちも混じえて、手造りの装置や衣装、カツラによるものであった。出し物の詳細は忘れたが、戦争は終わった、もう戦地へ駆り出されることもなく、降り注ぐ爆弾のもと、死地を彷徨うこともないという解放感が溢れ、弾けた舞台であった。
これらが、戦時中は決してできなかったものだったことを考え合わせると、芝居を観せる・観るという関係も平和ならでこそのものだとしみじみ思う。
今度はおひねりを用意して、実際に地歌舞伎を上演している「現地」へ乗り込みたく思った。またひとつ地歌舞伎の「地」性が強く感じられることと思う。