小説、『サダと二人の女』(山下智恵子 2018年8月10日刊 風媒社 330頁 1,700円+税)を読んだ。
書名から分かるように、これはいわゆる阿部定事件のヒロインであるサダと、二人の女性の物語である。年長のサダ、そして同様の事件を起こし、「戦後のサダ」などと騒がれたもうひとりの女性(チエミ)、さらには現代を生きる家庭の主婦(萌子)なのだが、後者二人の年齢差はさほど開いてはいない。また、前者の二人には実在の人物でありモデルがいる。
それをそれとして取り上げるには相当の覚悟を要する。いくら小説とはいえ、モデルがある以上その考証などが必要で、それから大きく逸脱すると現実感を損なう。
かといって、ルポルタージュやドキュメンタリーではないのだから事実を列記すれば済むわけでもない。
考証によって最低限の輪郭を得た人物やその立ち居振る舞いは、さらに作者の考察と想像力による肉付けで私たちの前に実在するかのような生きたリアリティをもって現れる。
それは(私のような)荒っぽい人間では思いつかないディティールに及ぶ。衣服、台詞、立ち居振る舞い、食い物、小道具類、当時の物価、舞台となった土地の景観などなど、そうしたものによる作者の肉付けによって、サダが、チエミが、萌子が私たちの受容のなかで具体的に生きて行動しはじめる。
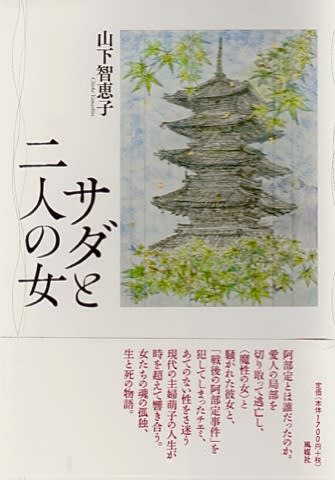
と同時に著者は、それら主人公たちが生きた時代の背景や事件、同時に進行した時代そのものの推移を挿入することを忘れない。それらは三人の登場人物それぞれに係るのだが、とりわけサダにおいては昭和の一桁から二桁へと、そしてあの戦争と戦後へと時代がドラスチックに動いたのであり、それらは随所にさらりと描写される。
とはいえ、それらの歴史背景と登場人物を短絡させて説明する愚は慎重に避けられている。
主人公たちはそうした時代に流されたり、抗ったりしながら自分の生を紡いでゆくのだがその時代の動向に還元されるわけではない。むしろそれからの逸脱、余剰のようなものこそが実際の生といえる。
ところで、この「阿部定事件」、かつては人口に膾炙されたものだが、妖婦列伝などの通俗本や実録もの以外で、彼女を対象として取り上げた文学作品はあっただろうか。
映画では大島渚の『愛のコリーダ』などが知られているが、文学作品ではほぼないといって良いのではないか。
戦後、坂口安吾がサダ本人と対談し、それをもとに短いエッセイなどを書いているが、どこか腰が引けている感がある。
「あなたは間違っていません」とさかんに繰り返すのだが、どう間違っていないのか、サダとその行為をなぜ評価するのかを積極的に言い切ってはいない。坂口をもってしても心身ともに合一という性愛の高揚、一見プリミティヴでありながら、その実、人間にのみ許されたひとつの愛の形をうまく対象化し得なかったのだろうか。
彼はサダとその相手、吉蔵の事件を、吉蔵のマゾヒズム嗜好にサダが合わせた結果だとしているが、そこへ還元していいものかどうかにも問題がある。
坂口の成果としては、吉蔵と出会う以前からサダの男出入りは多く、恋多き女と思われていたのに対し、彼女が本当に恋したのは三二歳の折、すなわち、吉蔵に出会った折の一度だけであることを聞き出したことである。
彼女は、本当に自分が心身ともに好きになった相手が、また自分のことを心身ともに好きになってくれたという充実感をもって本当の恋とする。そしてそれが吉蔵との出会いだったのだという。
(しかし、とはいえそれは移ろうものであり、その移ろいの予感があったがゆえにその絶頂でピリオドを打ったのではなどと注釈をつけたくなるが、それは知に走り過ぎというものだろう。)

さて、この山下さんの小説以前のこの事件に関する文学作品についてみてきたが、実は一九四七(昭二二)に、織田作之助が書いた『妖婦』というタイトルの短編があることはある。
しかもこれは、当のサダ自身が読んでいて、先に見た坂口との対談でもこれに触れ、他の通俗本には激しく抵抗し訴訟沙汰まで辞さなかった彼女が、暴露本でもなくエロ本でもなく「織田先生のような書き方なら」とこれを容認する発言をしている。
しかしこの織田の短編は、明らかにサダの子供の頃から思春期に至るエピソードを連ねてはいるが、主人公の名は「安子」であり、小説としての芯もはっきりしないまま、安子が兄に花柳界に売られるところまで(これは事実と相違する)の中途半端なプロローグに終わっているといってよい。
といったわけで、この山下作品のサダは、おそらくサダをその生涯にわたって(ということはその晩年も含めて)追い続けたほとんど唯一の文学作品ではなかろうか。
もちろんたんなる伝記ではない。先に見たように、作者の努力による考証に裏付けられ、さらにはその想像力によって肉付けされたサダが、その幾分危うい思考や行動のパターンを伴って私たちの前にいきいきと再現される。その意味で、サダの造形化はじゅうぶん成功しているといえよう。
サダは強烈なのだが、それに寄り添うように書かれた二人の女性もまた印象的である。
そのうちの一人、チエミは、貧困と暴力のうちに育ちながら、そこから離反しようとすればするほど、またもやそれに取り憑かれ、一度は死を決意したどん底から這い登るものの、やっと見出した場がもろくも崩壊し、またしても司直の手にかからざるを得ない女性である。作者は、やはりいくぶん危うい彼女の生涯を温かい眼差しで描き続ける。
すでにみたように、彼女にも実在するモデルがある。したがってここでも裁判記録など考証の努力は尽くされ、それに想像の肉付けをされた女性がさもありなんという風情で描かれている。
もうひとりの萌子は現代の普通の家庭を生きる主婦である。「普通」であるがゆえにある種の不定愁訴のような澱をもった主婦でもある。彼女もまたその前半では危うい場を経由しつつふとしたきっかけでその関心が変化する。
その変化は二つの面で見られる。ひとつは知り合った相手の子供の発育不全に対する関心から社会的なものへ、あるいは具体的実践的な場への関わりが始まるということである。
いまひとつは、一度、プラトニックなものへと引き戻された男性への関心であるが、これは、まだどう転ぶかわからないという余韻を残したまま終幕へと至る。
これら二人の女性は、一面ではサダと絡み合いながら、そしてまた一見、無縁のようでもある。しかし、当初は時空を超えて並行していたようなこの三人の像は、作者の構想のなかで三つ編みのようにあざなえる様相を呈してくる。
そして最終章、この三つ編みの先に結ばれたリボンのような印象を残して小説は終わる。ここでリボンというのは名古屋の鶴舞公園という限定された場での三人の交差を指すのであるが、その経緯は実に面白い。(実話では知られることがなかったサダの晩年も示唆されてもいる。)
題材は決して明るいとは言い難い。でも読み終わったあと、幾ばくかの清涼感を覚えるのは、ある時は危うく、切なく、苦しく、追い詰めれれたかのような女性たちではあるが、その三人が懸命に生き抜いた結果たどり着いたある種、見晴らしの効いた風景への到達、そんなことを思わせるからであろうか。
もって回ったこともいったが、小説そのものは一気に読ませる面白さをもっている。
====================================
この小説は、昨年秋の終刊まで、私も所属していた同人誌『遊民』の仲間だった山下智恵子さんが、同誌の第三号から第一六号まで一四回にわたって連載されていていたものです。
改めて通読してみると、ある種の感慨が湧いてきます。それは、ひとつには作者である山下さんがほぼ七年の間、いかに心血を注ぎ、かつ呻吟しながらこれを生み出したかを身近で知っているからです。
また、連載時に手にした感じと、一冊の冊子(三百三十ページ)となったのではまずそのボリューム感が違います。冊子を手にした質量感がこの間の彼女の努力の実体的な重みとして伝わってくるのです。
もう一つは、なんといってもその内容です。
細切れで読んだときにはよく見えなかったこの書の全体の構想、そしてその展開の流れが説得力をもって迫ってきて、こんな面白い小説だったのかと改めて思った次第です。
読書好きの方にお勧めできる一冊です。
書名から分かるように、これはいわゆる阿部定事件のヒロインであるサダと、二人の女性の物語である。年長のサダ、そして同様の事件を起こし、「戦後のサダ」などと騒がれたもうひとりの女性(チエミ)、さらには現代を生きる家庭の主婦(萌子)なのだが、後者二人の年齢差はさほど開いてはいない。また、前者の二人には実在の人物でありモデルがいる。
それをそれとして取り上げるには相当の覚悟を要する。いくら小説とはいえ、モデルがある以上その考証などが必要で、それから大きく逸脱すると現実感を損なう。
かといって、ルポルタージュやドキュメンタリーではないのだから事実を列記すれば済むわけでもない。
考証によって最低限の輪郭を得た人物やその立ち居振る舞いは、さらに作者の考察と想像力による肉付けで私たちの前に実在するかのような生きたリアリティをもって現れる。
それは(私のような)荒っぽい人間では思いつかないディティールに及ぶ。衣服、台詞、立ち居振る舞い、食い物、小道具類、当時の物価、舞台となった土地の景観などなど、そうしたものによる作者の肉付けによって、サダが、チエミが、萌子が私たちの受容のなかで具体的に生きて行動しはじめる。
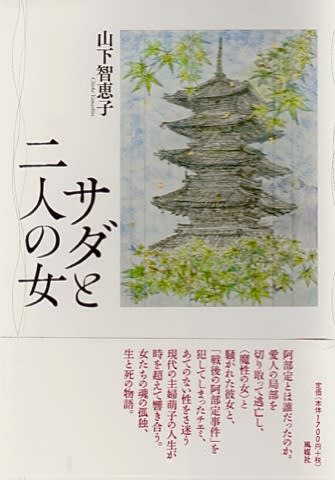
と同時に著者は、それら主人公たちが生きた時代の背景や事件、同時に進行した時代そのものの推移を挿入することを忘れない。それらは三人の登場人物それぞれに係るのだが、とりわけサダにおいては昭和の一桁から二桁へと、そしてあの戦争と戦後へと時代がドラスチックに動いたのであり、それらは随所にさらりと描写される。
とはいえ、それらの歴史背景と登場人物を短絡させて説明する愚は慎重に避けられている。
主人公たちはそうした時代に流されたり、抗ったりしながら自分の生を紡いでゆくのだがその時代の動向に還元されるわけではない。むしろそれからの逸脱、余剰のようなものこそが実際の生といえる。
ところで、この「阿部定事件」、かつては人口に膾炙されたものだが、妖婦列伝などの通俗本や実録もの以外で、彼女を対象として取り上げた文学作品はあっただろうか。
映画では大島渚の『愛のコリーダ』などが知られているが、文学作品ではほぼないといって良いのではないか。
戦後、坂口安吾がサダ本人と対談し、それをもとに短いエッセイなどを書いているが、どこか腰が引けている感がある。
「あなたは間違っていません」とさかんに繰り返すのだが、どう間違っていないのか、サダとその行為をなぜ評価するのかを積極的に言い切ってはいない。坂口をもってしても心身ともに合一という性愛の高揚、一見プリミティヴでありながら、その実、人間にのみ許されたひとつの愛の形をうまく対象化し得なかったのだろうか。
彼はサダとその相手、吉蔵の事件を、吉蔵のマゾヒズム嗜好にサダが合わせた結果だとしているが、そこへ還元していいものかどうかにも問題がある。
坂口の成果としては、吉蔵と出会う以前からサダの男出入りは多く、恋多き女と思われていたのに対し、彼女が本当に恋したのは三二歳の折、すなわち、吉蔵に出会った折の一度だけであることを聞き出したことである。
彼女は、本当に自分が心身ともに好きになった相手が、また自分のことを心身ともに好きになってくれたという充実感をもって本当の恋とする。そしてそれが吉蔵との出会いだったのだという。
(しかし、とはいえそれは移ろうものであり、その移ろいの予感があったがゆえにその絶頂でピリオドを打ったのではなどと注釈をつけたくなるが、それは知に走り過ぎというものだろう。)

さて、この山下さんの小説以前のこの事件に関する文学作品についてみてきたが、実は一九四七(昭二二)に、織田作之助が書いた『妖婦』というタイトルの短編があることはある。
しかもこれは、当のサダ自身が読んでいて、先に見た坂口との対談でもこれに触れ、他の通俗本には激しく抵抗し訴訟沙汰まで辞さなかった彼女が、暴露本でもなくエロ本でもなく「織田先生のような書き方なら」とこれを容認する発言をしている。
しかしこの織田の短編は、明らかにサダの子供の頃から思春期に至るエピソードを連ねてはいるが、主人公の名は「安子」であり、小説としての芯もはっきりしないまま、安子が兄に花柳界に売られるところまで(これは事実と相違する)の中途半端なプロローグに終わっているといってよい。
といったわけで、この山下作品のサダは、おそらくサダをその生涯にわたって(ということはその晩年も含めて)追い続けたほとんど唯一の文学作品ではなかろうか。
もちろんたんなる伝記ではない。先に見たように、作者の努力による考証に裏付けられ、さらにはその想像力によって肉付けされたサダが、その幾分危うい思考や行動のパターンを伴って私たちの前にいきいきと再現される。その意味で、サダの造形化はじゅうぶん成功しているといえよう。
サダは強烈なのだが、それに寄り添うように書かれた二人の女性もまた印象的である。
そのうちの一人、チエミは、貧困と暴力のうちに育ちながら、そこから離反しようとすればするほど、またもやそれに取り憑かれ、一度は死を決意したどん底から這い登るものの、やっと見出した場がもろくも崩壊し、またしても司直の手にかからざるを得ない女性である。作者は、やはりいくぶん危うい彼女の生涯を温かい眼差しで描き続ける。
すでにみたように、彼女にも実在するモデルがある。したがってここでも裁判記録など考証の努力は尽くされ、それに想像の肉付けをされた女性がさもありなんという風情で描かれている。
もうひとりの萌子は現代の普通の家庭を生きる主婦である。「普通」であるがゆえにある種の不定愁訴のような澱をもった主婦でもある。彼女もまたその前半では危うい場を経由しつつふとしたきっかけでその関心が変化する。
その変化は二つの面で見られる。ひとつは知り合った相手の子供の発育不全に対する関心から社会的なものへ、あるいは具体的実践的な場への関わりが始まるということである。
いまひとつは、一度、プラトニックなものへと引き戻された男性への関心であるが、これは、まだどう転ぶかわからないという余韻を残したまま終幕へと至る。
これら二人の女性は、一面ではサダと絡み合いながら、そしてまた一見、無縁のようでもある。しかし、当初は時空を超えて並行していたようなこの三人の像は、作者の構想のなかで三つ編みのようにあざなえる様相を呈してくる。
そして最終章、この三つ編みの先に結ばれたリボンのような印象を残して小説は終わる。ここでリボンというのは名古屋の鶴舞公園という限定された場での三人の交差を指すのであるが、その経緯は実に面白い。(実話では知られることがなかったサダの晩年も示唆されてもいる。)
題材は決して明るいとは言い難い。でも読み終わったあと、幾ばくかの清涼感を覚えるのは、ある時は危うく、切なく、苦しく、追い詰めれれたかのような女性たちではあるが、その三人が懸命に生き抜いた結果たどり着いたある種、見晴らしの効いた風景への到達、そんなことを思わせるからであろうか。
もって回ったこともいったが、小説そのものは一気に読ませる面白さをもっている。
====================================
この小説は、昨年秋の終刊まで、私も所属していた同人誌『遊民』の仲間だった山下智恵子さんが、同誌の第三号から第一六号まで一四回にわたって連載されていていたものです。
改めて通読してみると、ある種の感慨が湧いてきます。それは、ひとつには作者である山下さんがほぼ七年の間、いかに心血を注ぎ、かつ呻吟しながらこれを生み出したかを身近で知っているからです。
また、連載時に手にした感じと、一冊の冊子(三百三十ページ)となったのではまずそのボリューム感が違います。冊子を手にした質量感がこの間の彼女の努力の実体的な重みとして伝わってくるのです。
もう一つは、なんといってもその内容です。
細切れで読んだときにはよく見えなかったこの書の全体の構想、そしてその展開の流れが説得力をもって迫ってきて、こんな面白い小説だったのかと改めて思った次第です。
読書好きの方にお勧めできる一冊です。















 」
」



























































































































































































































