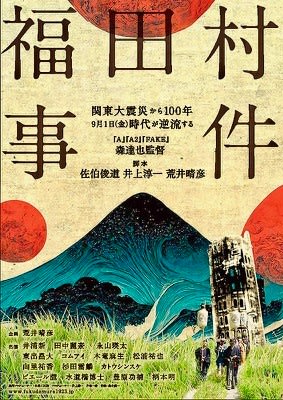年始の開演から少し遅れたが、やっと観る機会があった。
こんなの観せられるとやはり映画ってすごいなぁと思う。
回想シーンを主としたモノクロの映像とリアルな世界のカラー、外部世界として見せる都市シーンのガウディを漫画チックにしたような様相、それらはこの映画が描く時代を「はてな?」のなかに入れてしまう。解説によると19世紀末の英ヴィクトリア朝の出来事だとのことだが、そんな限定は吹っ飛んでいる。
色彩と画像の面白さに加えて、音響も効果的で面白い。

高度な脳外科手術が可能で、異種生物の接合手術すら可能なことを見せる映像からはSF的な近未来が頭に浮かぶが、登場する人物たちの衣服や振る舞いはなるほど19世紀末なのかもしれない。にも関わらずである、主人公が成長し到達する世界はまさに21世紀の現実ですらある。

いささかネタバレになるが、映画の状況設定としての主人公の特殊な情況を述べておこう。
彼女は、胎児を宿しながら自死した女性なのであるが(その自死の原因が夫のサディスティックなDVであることは後半で判明する)、脳死はしているものの生体反応はあるということで、宿していた胎児の脳が彼女に移植され、赤ん坊の脳を持った成人女性としての復活を遂げる。

彼女を規定しようとすると妙なことになる。彼女は自分の母であると同時に自分の娘でもある。そうした「胎児の脳をもった成人女性」の知能と精神の成長過程の映画である。
外界へと旅する彼女のロード・ムービー風の冒険は凄まじい。それも、この映画がR-18に指定されている面でのものが多い。しかし彼女は、それを身体的快楽としてのみではなく、「女」が生きてゆくうえでの体験として対象化し、それによってたくましく成長して行く。

脳の移植という特殊な条件はあるものの、ようするにこれは女性の成長物語である。
しかし、そうした女性の成長というのはこれまではそれを見守る「寛容な男」に支えられたものとして描かれてきた。ギリシャ神話のピグマリオンの物語、源氏物語の「若紫」の話を始め、映画では『マイ・フェア・レディ』もその類だろう。

しかし、この映画はそうした寛容な男の影は皆無ではないにしろ、むしろ彼女の成長は彼女自身の体験と学習によるものとする。この辺が新しいといえば新しいのかもしれない。
主演のエマ・ストーンの体当たり演技がすごい。脳がまだ幼少期の身体の動かし方から次第に成長する過程の表現、表情の変化。後半の何処かで、かつてやはり映画で観たメキシコの女性画家、フリーダ・カーロを思わせる表情にも出会った。

後半の彼女のレズ体験の場面で、席を立って帰った老夫婦(カップル)がいた。何を話ながら帰ったのだろう。
『哀れなるものたち』監督:ヨルゴス・ランティモス 主演:エマ・ストーン 23年