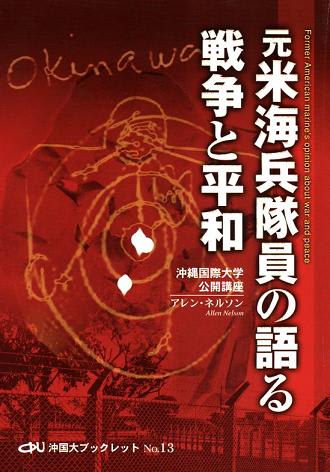山口県の岩国米軍基地に所属する米兵が、日本人の女性に性的暴行を加えたとされる事件があった。これの状況が実際にはどうだったのかについては、知らない以上、何とも言いようがない。私たちがしなければならないであろうことは、常に受苦の感情移入をしようと試みること、それから、この種の事件が「たまたま」ではないことを理解することだろう。
『イアブック核軍縮・平和2007』(ピースデポ、高文研)によると、米軍人による刑法犯検挙件数は、2005年に93件(うち凶悪犯5件)、2006年に76件(うち凶悪犯4件)である。また、米軍基地が存在する都県(青森、東京、神奈川、静岡、広島、山口、長崎、沖縄)の06~07年の合計は、168件(うち凶悪犯9件)にのぼる。
また、『被害者の会通信 第25号』(米軍犯罪被害者救援センター)でも、今年に入ってから沖縄など国内のみならず、韓国やイラクでも数多く米軍が関与した犯罪が報道されていることがわかる。
件数のみを追いかけることは、おそらくは、あまり意味がない。表面化しない犯罪が数多くあるだろうことが、容易に想像できるからだ。それは日本でも同じことだろう。
では、米軍が関与しないこの種の犯罪とを分つものは何か―――ひとつには「日米地位協定」の不平等さを前提にした行動、それから、他国(すなわち日本)の基地外の存在に人格を見出さないこと、ではないか。これが個人個人の問題ではなく、軍隊という組織が孕む構造的な問題だと指摘する本が、アラン・ネルソン『元米海兵隊員の語る戦争と平和』(沖国大ブックレット、2006年)である。先日、沖縄県東村の高江でも少し話題になった。
ネルソン氏は、米海軍の兵隊として、沖縄で「人殺し」のトレーニングを受け、そのあとにヴェトナム戦争に出征した体験を持つ。その実体験から、米軍の兵隊は、ほとんどが超貧困層の出身であり食べていくために入隊していること、ただただ「人殺し」の方法とマインドをすり込まれていること、を指摘している。これは、そのような境遇にある個人に対する差別ではもちろんない。そのような境遇になってしまうことの構造的問題だということができる。
「皆さんが基地の側を通るとき、常に覚えておいてください。その基地の中で行われていることは、毎日如何にして人を殺すかというトレーニングが行われているということです。」
「そして、私たちは街へ繰り出していくとき、三つの目的だけを達成するためにだけ街に出て行きました。酒を飲んで酔っぱらうこと。喧嘩をすること。三つ目は女性をさがすこと。」
「しかし、皆さんは理解しなければなりません。何を理解するかというと、私たちは海兵隊員であり、軍隊であり、私たちは人を殺すために訓練されているということです。そして、私たちがその暴力の訓練をうける時、基地のなかで、それを使うのではありません。私たちは街に繰り出していって、そこでその暴力を使うのです。」 「多くのアメリカ人にとって、原子爆弾を落としている相手は人間ではなくて、ネズミでありジャップであり、そして、多くのアメリカ人にとって、ジャップというのは人間ではありませんでした。」
「そしていまだに、米軍においては、イラクの人びとのことを人間というふうには見ていなく、人間としても扱ってもいません。彼らのことを、”砂漠の猿”としか呼んでいません。」
これをもって、個々の米兵をそのようなマインドを持つ人として色眼鏡をかけてみることは間違いだ。それは私たちが、相手を個別の人格として見ない側に立つことを意味する。
しかし、構造的な問題があることもまた確かだ。構造的な問題がある限り、この種の凶悪犯罪はなくならないのではないか。