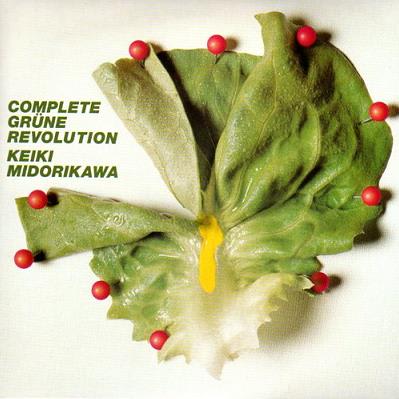鞄には2冊の本を入れておくことが多い。重いものと軽いものである。そうすれば、どっちの気分でも、とりあえずは電車や飛行機の中で読みすすめることができるからだ。
今回、フーコーとドゥルーズとの対話を読んでいて、ちょっと現実との乖離に辛くなったので、四方田犬彦『ソウルの風景―記憶と変貌―』(岩波新書、2001年)を取り出した。これがやめられなくなって、さきに読了してしまった。
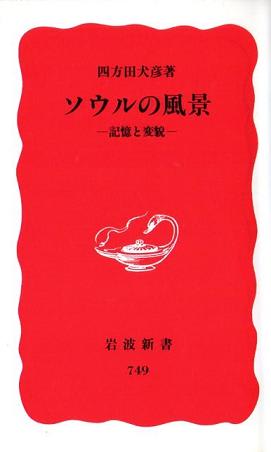
四方田犬彦は、1979年の朴正煕暗殺時に、ソウルに居合わせている。 本書には、さらに驚くべき体験が書かれている。KCIAが新規に採用するスタッフの面接にあたって、日本語能力を判断するという役割のために突然呼び出されたというのだ。この話は本書が書かれるまで誰にもされていない、というのは、密告と曲解がKCIAの脅威を支えていた時代にあっては、どんなことになるかわからないからだ。もちろん「アカ」と呼ばれることは、韓国では死を意味した。先日亡くなった金大中を1973年に東京で拉致して殺しかけたのもKCIAである。
ところが、もはやそのような雰囲気はどこかに消え去ってしまっている。
「人を見たら「北傀」のスパイだと疑えといったあの時代は、もう完全に終わってしまったのだ。今この場所で映画を勉強している学生たちは、すでにもの心ついた頃から民主主義を空気のように当然のこととして受け入れてきた世代なのであり、彼らにしてみればKCIAのことなど日帝時代同様、遠い過去の出来ごとにすぎないのだろうと、わたしは思った。」
そして、「太陽政策」を掲げる金大中が2000年に北を訪れ、金正日と握手を交わしてからは、主思派(チュサッパ)と呼ばれる学生運動の指導者集団は闘争目標を失い、きわめて孤立した状況にいる、とする説明は興味深い。
1980年、蜂起した民衆を軍部が虐殺した光州事件についても、軍事政権が終わり、金泳三が歴史的意義を認めるまで、口にはできないことだったという。そして今や、それどころか、国を挙げて光州事件のアピールがなされ、事件の直接の関係者の墓は「英霊」と呼ばれているという。この構造を、日本の靖国のそれと比較してみると、さまざまな違いが現れてくるようだ。
従軍慰安婦に関しても、世代間のギャップが著しいようだ。当事者、被害者たちはどんどん歳をとってゆき、方や、朝鮮史について基礎的な知識も持ち合わせていない日本人のOLが「ナヌムの家」を屈託なく訪れていることの違和感が、ここには提示されている。
「彼女たちはいったい何だろうかと、わたしは考えていた。おそらくナヌムの家を訪れることは、気楽に、そして友好的な気分のうちに遂行できる虚構の巡礼の一種なのだ。そこで彼女たちは、日本での生活ではどこまでも曖昧なままにされている自分の、女性としてのアイデンティティを、明確に確認することができる。少し過酷な表現になるかもしれないが、元宗主国の国民である彼女たちは、女性である自分を認識するために、旧植民地での従軍慰安婦との出会いという悲惨にして善意の物語を必要としているのではないだろうか?」
それはともかく、軍事政権下の閉鎖空間にあって、ヴェトナム戦争によって得た外資により発展し、変貌した韓国と、旧宗主国にして朝鮮戦争により発展し、歴史認識が子ども的な日本とは、違いがありすぎるのだという当たり前の事実がある。それをまじまじとは見ず、民族や文化の差異をブームにしていくあり方は、前向きのようでいて、極めて皮相的である。