インターネット新聞JanJanに、仙田満・上岡直見編『子どもが道草できるまちづくり』(学芸出版社、2009年)の書評を寄稿した。クルマの殺人機能を減じるためのまちづくり、という考え方にはかなり共感する。
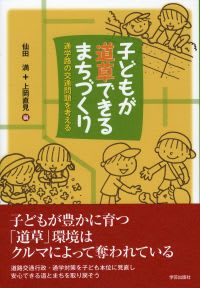
私はクルマが嫌いだ。保有したこともない。しかしその一方で、他人のクルマに乗せてもらったり、ときにはタクシーを使ったりもする。間接的にクルマがあるからこその便利な生活だということは、よくわかっている。もちろん、クルマがなければ成り立たない地域があることもわかる。何故か、運転免許も持っている。クルマの存在を全否定するわけではない。
結局、嫌いなのは、クルマという脅威をまったく意識しないメンタリティなのだ。自分は鉄の箱に入っているからといって、平気で横断歩道の歩行者にぐいぐいと迫ってきたり、狭い道をいい気になって猛烈なスピードで飛ばしたり、まったく信じ難い。ちょっと油断したりよろけたりすることは、人間だからありうることだ。だからといって、クルマに殺されるほどの罪であるはずはない。想像力の問題でもある。
実際に、そのようなクルマ社会にあって、子どもが生命を脅かされていることが、本書で示されている。日本における小児・若年者の死亡原因の第1位は事故(傷害)であり、交通事故死はその3分の1を占める。他の先進国と比較して、子どもの交通事故死は歩行中が多いのだという。そして、安心して子どもが外を歩けない社会を生み出してしまった。
本書では、オランダのボンエルフ(「生活の庭」の意味)という街路計画を紹介している。自動車がスピードを出せないよう、屈曲路、バンプ(路面の隆起)、障害物などを設け、歩行者優先の生活空間を生み出しているのである。子どもも街路で遊ぶことができる。私はこのあり方に全面的に共感する。弱者が気を遣う社会が良い社会のわけがない。
一方、歩車分離信号という方法がある。歩行者が道路を横断するとき、たとえば左折してくるクルマなどに殺されるリスクがない仕組みで、日本でも次第に導入箇所が増えてきている。本書ではその価値を高く評価しつつも、クルマと人間との分離という意味で、ボンエルフのような共存とは異なるものだと捉えている。私は、これもどんどん導入すべき信号だと考えている。
本書は子どもが安心して外で遊ぶことができる地域社会に向けて、示唆することの多い良書である。
さて、ここからは私の経験に基づいて考えたことである。
私の住む地域では、小学校への通学がとても危険な状況だったのだが、新たなマンションができる機会に、ディベロッパーと自治体とに働きかけて、最終的にはクルマの入り込めない通路を作ることができた。それでも、従来の道路の危険性がなくなるわけではないから、バンプの設置についても自治体に提案した。回答は、「バンプの効果は認めるが、クルマの走行音がうるさくなるため、道路沿いの住民の合意を取り付けなければならない」だった。住民合意というハードルにかまけて、子どものイノチを尊重していない政策なのだと、私は解釈した。
歩車分離信号については、近所の必要と考えられる2箇所について、警察に働きかけた(信号は警察の管轄)。青信号にも関わらず迫ってくるトラックが怖くて、子どもが渡れないのである。回答は、1箇所については「実地検分で検討」(導入の気配はない)、もう1箇所については「渋滞を引き起こすので不可」だった。やはり、子どものイノチを渋滞と天秤にかけ、後者を優先しているわけだ。
今後、これらの問題をどのように解決していけばいいのか。ひとつには「議員を使う」という方法がある。ただ、仮にその問題だけが解決しても、子どもが安心して成長できるまちに近づくための方法とは思えない。
やはり、「自治会など地域単位で運動にしていく」が模範解答か。自治体や警察の壁を最初から絶望視していては何も進まないだろう、とは思う。しかし、最大の問題は、クルマにイノチを脅かされる人がいる地域社会を、問題であると考えようとはしない人が必ずいることなのだ。これはやはり、大きな政策課題ではないのか。










