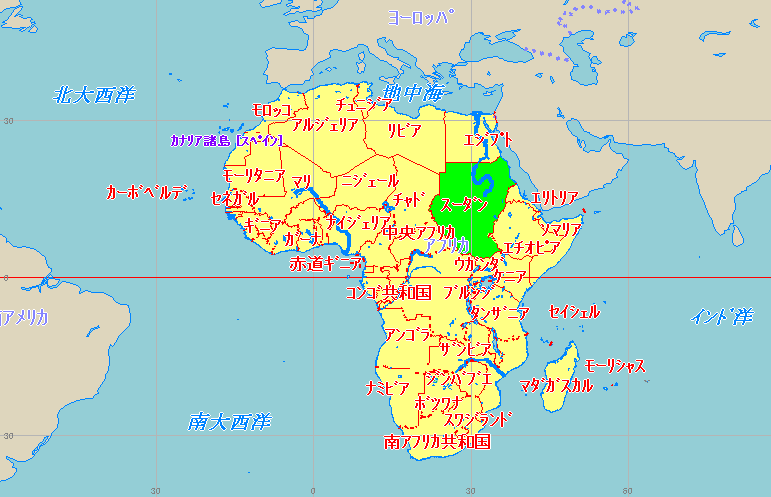今月に入って中国太湖の水質汚染のニュースを目にします。
太湖は上海も程近いエリアにある中国で3番目に大きい湖で、琵琶湖の3.5倍の広さがあります。
観光的にも有名なこの湖で有毒藻が大量発生して、沿岸の無錫(むしゃく)では水道の使用が停止されたとか。
無錫は昔の演歌“無錫旅情”で「上海蘇州と 汽車に乗り太湖のほとり 無錫の街へ・・・」とも歌われた町ですが、市区人口でも223万人という大都会です。
アパートの中庭に洗面器やたらいを並べて雨水を集める様子、ミネラルウォーターに殺到する住民の姿なども報道されています。
もっとも、被害の範囲・期間はよくわかりません。
本当に200万都市全市の水道が長期間ストップしたら国家的緊急事態になると思われますので・・・。
有毒藻の大量発生は数日間に突然起こったとの報道もありますが、太湖の水質汚染自体は以前から問題視されていたところで、水道の水が臭う、ごはんを炊くと色が着くなどの苦情はあったようです。
昨年9月にflickrに投降された太湖水質汚染の写真です。(By tingting8420)

汚染源は付近の工場排水と見られており、政府当局は太湖付近の地方自治体に対し、汚染源の工場をすべて閉鎖し、2008年6月末までに新しい排水基準を満たすよう命じているそうです。
また、温家宝首相は12日、太湖の有毒藻の発生は汚染に対する「警鐘」だと述べ、早急な対応を求めたとも伝えられています。
更に、関係地方政府幹部数人が責任を果たさなかったと懲戒免職されたとのこと。
政府当局は現在、揚子江から太湖へ水流を追加供給して藻の異常発生を引き起こした汚染要因を押し流しそうとしているそうです。
ただ、このような環境破壊の背景には基本的には国民一般を含めた意識の問題があるとも思われますので、今後も類似の問題が続出する事態が懸念されます。
私は無錫は行ったことはありませんが、お隣の水郷として有名な蘇州を16,7年前旅行したことがあります。
水路にかかる風情のある橋などはよく写真でも見るところですが、実際川面に近づくと生活排水で汚れ、いろんな物が浮かんでおりやや興ざめした記憶があります。
中国に限ったことではありませんが、シンガポール以外のアジアの国ではゴミをあたりに捨てるのはさほど珍しい光景ではありません。(シンガポールの潔癖性は、それはそれで息苦しい感じがしますが・・・)
中国の新疆方面を列車で旅行した際、席がなく車両と車両の連結部にうずくまって一晩過ごしたことがあります。
連結の隙間からゴミは捨てるは、子供のおしっこはさせるは、ゴミ溜めとトイレを一緒にしたよう状態で心底まいりました。
今となってはなつかしい思い出でもありますが。
そのような「ごみを捨てるのはあたり前」的な社会(近年改善はされてきているとは思いますが・・・)で急激な経済成長・工業化が進んでいるのが現状。
人間の意識・価値観という最も基本的な社会的基盤・枠組みが追いつかないところから、環境破壊・極端な利益第一主義・安全性の軽視、「儲かれば何をしてもいい」的な風潮が生まれて来ていると思われます。
そういう意識レベルの問題とは別に、技術面に限れば、今後中国が必要に迫られるのは環境保全・省エネの技術であり、まさに日本がアドバンテージを持つ分野です。
今後このカードを有効に活用することが日本の安全保障を含めた将来に非常に重要なポイントになるのではないかと思います。
その意味で、さらにこのカードを有効にするための環境保全・省エネに関する技術開発については、防衛システムなどより現実的な国家の命運をかけたプロジェクトとしてその進展を支援すべきだと思っているのですが・・・・。
冒頭写真は、風光明媚な太湖 “flickr”より(By Kos Live)