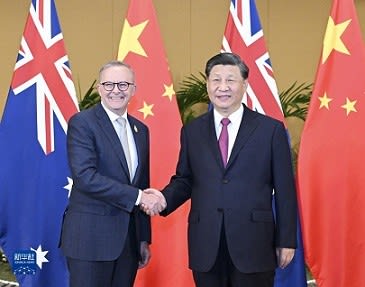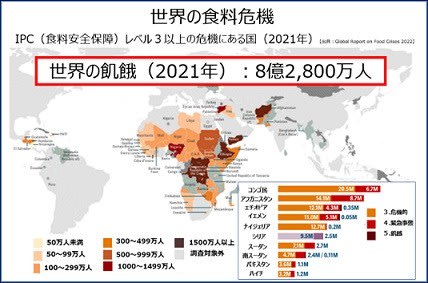(ネタニヤフ政権の「司法改革」に対する抗議デモ=イスラエル中部テルアビブで11日、ロイター【3月16日 毎日】)
【イスラエル大統領もバイデン米大統領も止めらないネタニヤフ「司法改革」 毎週の大規模抗議デモ】
昨年12月末に発足したイスラエルの「建国史上最も右寄り」とされるネタニヤフ政権が進めようとする「司法改革」が1月に明らかになって以来、民主主義の根幹たる三権分立を脅かすものとして、イスラエル国内では大規模抗議デモが続いています。
「改革」の背景には、収賄や背任の罪で起訴され、公判が進行中のネタニヤフ首相自身にとって有利な仕組みをつくりたいとの思惑があるのではないかと推測されています。
****イスラエルでデモ拡大 司法改革が国論二分 軍務拒否や通貨下落も****
イスラエルでネタニヤフ政権が司法制度改革を推進し、国論を二分する議論が起きている。
改革案は司法の権限を縮小して政府や国会の裁量を拡大する内容で、民主主義の根幹である三権分立を骨抜きにする狙いだとしてデモが頻発している。「建国史上最も右寄り」とされる政権の動きは海外でも懸念を招いている。(中略)
ネタニヤフ政権は1月前半に改革の草案を公表した。イスラエル有力紙ハーレツ(電子版)によると、司法が持つ違憲審査権の制限が盛り込まれており、国会で成立した法律について、最高裁がイスラエル基本法(憲法に相当)に違反すると判断しても、国会がそれを覆すことが可能になる。裁判官の任命をめぐっても、政権の影響力を強化する条項がある。
昨年12月末にネタニヤフ氏を首相として発足した連立政権は、同氏が党首を務める右派「リクード」や、ユダヤ教の戒律を厳格に守る超正統派、対パレスチナ強硬派の極右政党などで構成されている。ハーレツ紙によると、各党にはそれぞれ司法への影響力を強めたい事情がある。
ネタニヤフ氏は2019年に収賄や背任の罪で起訴され、公判が進行中だ。改革には自らに有利な判断を示す裁判官を任命する狙いがあると指摘される。
また、超正統派の政党は信徒の若者たちの徴兵免除を法制化して定着させる思惑がある。超正統派は宗教やユダヤ人の歴史を学ぶことを最優先しており、慣例として徴兵が免除されてきたが、世俗派のユダヤ人らが不平等だとして反発を強めている。
さらに、極右政党は、パレスチナ人が多く住むヨルダン川西岸でユダヤ人入植地を拡大する方針を公言してきた。司法の違憲判断を覆せるようになれば、入植推進に向けて大きな障害が消えることになる。イスラエル軍は年初以来、70人以上のパレスチナ人を殺害しており、双方の緊張は近年になく高まっている。
司法制度改革をめぐっては、最大の友好国である米国のナイズ駐イスラエル大使が「(国民の)総意を得るよう努力してほしい」と述べたほか、ベーアボック独外相が司法の独立は「常にイスラエルの大きな特徴」だったとし、それぞれ自制を促した。
9日にはイスラエルのヘルツォグ大統領がテレビ演説し、政権に改革案を撤回するよう求めた。ただ、与党各党には国民の支持を基に連立政権を発足させた自負があり、事態が収束に向かうかは不透明だ。【3月10日 産経】
**********************
ネタニヤフ首相は大統領の仲裁案も拒否して、「改革」を強行する構えです。
****イスラエル「司法改革」 大統領の仲裁案を与党が拒否 混乱深まる****
イスラエルで大規模デモを引き起こしている右派・ネタニヤフ政権の「司法改革」を巡り、ヘルツォグ大統領は15日、改革の仲裁案を発表した。ヘルツォグ氏は、与野党双方の意見を取り入れた代案と主張したが、ネタニヤフ首相は受け入れを拒否した。国内の混乱はさらに深まりそうだ。
ネタニヤフ政権は、国際法違反とされるヨルダン川西岸の入植地拡大などを目指し、最高裁による法律審査の権限を制限する「司法改革」を進める。改革は、国会が過半数の賛成で最高裁の判決を覆すことを可能にするなど、司法に対する政権の力を強めるものだ。
だが「三権分立が崩れ、独裁国家になる」との批判が野党支持者から噴出。各地で毎週末に抗議デモが開催され、今月11日には30万人以上が参加するなど、国内の対立が激しくなっている。
ヘルツォグ氏は「市民戦争を避けなければならない」として、仲裁案を発表した。最高裁の権限を一部制限する一方で、国会による判決の「無効化」は容認しないとの内容だが、与党側は「一方的だ」と強く批判。ネタニヤフ氏は15日夜、仲裁案について「(現行の司法制度を)継続するのと変わらず、受け入れられない」と述べた。
「司法改革」を巡っては、同盟国の米国も懸念を表明。専門家からは、政権が内政に集中し、対イランなどの外交をおろそかにしているとの指摘も出ている。【3月16日 毎日】
***********************
毎週末に行われている抗議デモは上記記事にあるように「30万人規模」とも、あるいは「50万人規模」とも報じられています。イスラエル人口は940万人ほどですが、全国民の3~5%がデモに参加していることにもなります。
同盟国アメリカ・バイデン大統領もネタニヤフ首相と電話会談を行い自重を促していますが、パレスチナの立場も一定に考慮し、人権問題にも敏感な米民主党政権とはもともと折り合いが悪いネタニヤフ首相ですから、聞く耳は持たないのでは・・・。
****米 バイデン大統領 イスラエルの司法制度改革めぐり電話会談****
イスラエルでは、司法制度の改革を巡り大規模な抗議デモが続いていて、アメリカのバイデン大統領はイスラエルのネタニヤフ首相と電話会談し、国民からの理解を得たうえで進めるよう示唆しました。(中略)
アメリカのバイデン大統領は19日、ネタニヤフ首相と電話会談し「民主主義的な価値観こそが、アメリカとイスラエルの関係の証だ」と強調しました。
そのうえで、司法制度改革が三権分立を脅かす可能性があると指摘されるなか「民主主義社会は真の均衡と抑制によって強化されるものであり、根本的な変革は人々からのできるかぎり広い支持のもとに進められなければならない」と述べ、国民からの理解を得るよう示唆しました。
これに対しネタニヤフ首相は「イスラエルはこれまでも、これからも強く活気のある民主主義国家だ」と述べたということで、バイデン大統領との会談のあと、どのような対応に出るかが焦点となっています。【3月20日 NHK】
そのうえで、司法制度改革が三権分立を脅かす可能性があると指摘されるなか「民主主義社会は真の均衡と抑制によって強化されるものであり、根本的な変革は人々からのできるかぎり広い支持のもとに進められなければならない」と述べ、国民からの理解を得るよう示唆しました。
これに対しネタニヤフ首相は「イスラエルはこれまでも、これからも強く活気のある民主主義国家だ」と述べたということで、バイデン大統領との会談のあと、どのような対応に出るかが焦点となっています。【3月20日 NHK】
*******************
「アメリカに民主主義の何たるかを教えてもらう必要などない」といった、会談の“冷え冷えとした”雰囲気が容易に想像できます。
あるいは、公表されないもっと“生々しい”やり取りがなされたのか・・・「強行するならアメリカはこれ以上イスラエルを支援できない」「そんなことができるのか?」っといった・・・
首脳会談に先だってイスラエルを訪問したオースティン米国防長官は9日、「米国とイスラエルの民主主義は独立した司法の上に築かれている」とのバイデン大統領の発言を引用し、ネタニヤフ政権が進める「司法改革」を暗に批判しましたが、変化はありません。
この問題でアメリカがイスラエルを制御できないということは、イスラエルがイランの核施設などを攻撃するようなことになっても、アメリカはイスラエルを制御できないという現状をも示してもいます。
【有事の際のネタニヤフ首相の指導力は認めるが、独裁も困る・・・というジレンマ】
「司法改革」については、一般国民だけでなく、警察や軍関係者にも困惑・抗議が拡大しているようです。
****司法制度改革反対デモ11週目も30万人:暴力エスカレート 2023.3.20***
司法制度改革反対デモ・毎週30万人規模:警察との暴力エスカレート
1月から始まった「オーバホール(乗り越え)法案」と呼ばれる司法制度改革案。イスラエルの民主主義が危ういとして、毎週、安息日明けの夜に、テルアビブを中心に全国で大規模なデモが行われている。この週末で11回目(2ヶ月半)となった。
このままでは、国が分裂するとして、野党側は、与党が、改革にむけた法案への動きを一時停止することを条件に交渉すると言ったが、与党側はこれを受けいれず、今も法案作りを急いでいる。今に至るまで、交渉は、まだ一回も行われていない。
こうした中、デモへの参加人数は、時間経過とともに増え続け、先週末とこの週末では、それぞれ30万人(メディアによっては50万人)を超えている。最もデモが盛んなのは、テルアビブでは、毎週、16-17万人が参加。町の中心を走るアヤロン・ハイウエイを一時的ではあるが、封鎖する事態になっている。
また、デモは、週末に加えて、国会で司法制度改革関連法案が議論される平日にも、エルサレムの国会周辺で大規模に行われるようになっている。今週も、木曜日に大規模なデモが予定されている。
平日のデモについては、反ネタニヤフ首相の動きになり、先週までに、イタリアやドイツに外交訪問したネタニヤフ首相の出国を妨害しようと、ベングリオン空港までの道中やその入り口を閉鎖する事態にまでなった。
こうした中でも、与党はあくまでも司法制度改革案を推し進めており、国会審議一回目を通過した法案はすでに2項目。今週、汚職で一度逮捕された経験を持つ政治家アリエ・デリ氏(ユダヤ教正当シャス党首)のような人物でも、閣僚になれるという法案についても、第一回目を通過させている。(法律になるには3回可決が必要)
連立政権と警察・軍との対立も深刻・複雑
警察は、できれば市民に危害は加えたくないと考えているが、連立政権(つまり司法改革推進派)で警察を管轄する極右正当のベン・グビル氏は、デモ隊は、“クーデター”だとして、暴動発生時の断固とした態度をとるようにとの指示を出している。
警察も態度を決めかねて、グビル氏とトップ警察長官らとの間でどろどろの対決になっている。
実際には、週を重ねるごとに、警察が放水銃や、威嚇用手榴弾を使ったり、デモ参加者と警察が掴み合いとなり、暴力の度合いがエスカレートしている。逮捕者も多数出ている。
特に、今週末には、安息日にベン・グビル氏が、滞在していたベイト・シェメシュに近いクファル・ウリヤのモシャブで、祈りに出かけたシナゴーグを、100人ほどのデモ隊が取り囲み、反対を訴える事態になった。
すると町の住民たちが、静かな安息日を邪魔したと、逆にデモ隊に向かって「死ね」と叫んだ者もいたとのこと。グビル氏は、「シナゴーグですることではない」とコメントしている。
また、さらに大きな問題は、軍隊への影響である。戦争の際には招集を受けて従軍する予備役兵たちが、この改革案に反対しており、招集に応じない動きにでていることはすでにお伝えした通りである。
しかしその後、軍情報部、特殊作戦部隊といったエリート部隊の予備役将校ら450人、サイバー部隊200人を含む将校たちを含む予備役兵たちが、招集に応じないとするボイコットを開始した。
警察と同様、政権とイスラエル軍トップの間でも、どろどろの対決になってはいる。
しかし、さすがに、今、パレスチナ人やイランとの対立がエスカレートしていることもあり、ギャラント防衛相、ハレヴィ参謀総からは、「国の防衛という最重要事項を背負っている予備役兵が招集をボイコットというのは、赤線を超える。」として、これに反対する意見を出している。
野党側で、この改革に反対しているガンツ元防衛相・参謀総長も、予備役兵は何があっても招集には応じるべきだとの考えを表明している。(中略)
ネタニヤフ首相をめぐるイスラエル人のジレンマ
世論調査によると、政権与党が進める司法制度改革については反対意見の方が多い。
しかしながら、防衛上の緊急事態において、憲法に払拭する可能性があるような指示が出た場合、警察や軍、シンベトといった治安部隊は、その時の政権側(今ならネタニヤフ首相)に従うべきか、憲法を重視して最高裁に従うべきか、となると意見が別れるようである。
この問題が浮上したのは、最近、イスラエル軍の中で、スモトリッチ西岸地区担当が、不用意にもフワラ(西岸地区でテロ事件があったパレスチナ人地区)は一掃すべきだ」との問題発言をして以来である。
軍はこれに従えば、この町に住むパレスチナ人を一掃する(殺すか追い出すか)ことになるが、当然ながらこれは違法行為である。
政府の指示に従えば、憲法の視点で違法になると判断される可能性がある。政府に従うべきか、最高裁の判断に従うべきなのか。今回は当然ながら、軍は、スモトリッチ氏の発言(後で失言と認めた)には従わないという道を選んだ。しかし、これは大きな論議を呼ぶこととなった。
この一件をもって、行政が司法の上になり、行政のいうことが全て通ってしまうことに危機感が広がり、司法制度改革に反対する予備役兵たちが増えたということである。
ところが、チャンネル12の調査では、治安部隊は常に最高裁に従うべきと答えた人は40%、政府側と答えた人は40%。わからないが20%と、政権側と答えた人と、最高裁側と答えた人はとんとんという結果であった。
さらに、現時点に限っていえば、本当に治安上の緊急事態になった場合、与党ネタニヤフ政権に従うべきと答えた人は43%で、野党ラピード氏側、つまりは最高裁の権限を維持する側に従うべきと答えた人は39%と、若干ながら、政権側に軍配があがるという結果だった。
現実をみれば、ネタニヤフ首相の指導者としての力量を認めるしかないという思いと、ネタニヤフ首相に、全権を委ねて独裁のようになっても困る・・という複雑な人々の思いとと現状が今、イスラエルにはあるということである。
イスラエルという国は、世界に先んじて、いろいろな問題を突きつけられる国だが、今も、かなり本質的な問題をつきつけられているようである。【3月20日石堂ゆみ氏 オリーブ山通信】
**********************
【政権に参加する極右勢力の「信念」に基づく暴言】
上記記事にあるスモトリッチ西岸地区担当(財務相でもあります)の「問題発言」は以下のようなもの。
****イスラエル財務相がパレスチナの村「せん滅」発言、国連非難****
国連難民高等弁務官事務所のボルカ―・ターク高等弁務官は4日、イスラエルのベザレル・スモトリッチ財務相がパレスチナ自治区ヨルダン川西岸の村フワラの「せん滅」を求めたことを「理解し難い」と非難し、イスラエル人とパレスチナ人の衝突の終結を呼び掛けた。
イスラエル人入植者2人がフワラで撃たれて死亡したことへの報復として数十人が同村を襲撃したのを受け、スモトリッチ氏は1日、「フワラ村をせん滅する必要がある」「イスラエルが国家としてやるべきだと思う」と述べた。
スモトリッチ氏はその後、ツイッターで「フワラ村を消し去るという意味ではなく、テロリストを一掃すべきという意味だった」と釈明した。 【3月4日 AFP】
******************
発言後に釈明したようですが、スモトリッチ氏の発言は、失言でも何でもなく、彼のゆるぎない「信念」です。
***イスラエル極右党が狙う西岸支配、新たな火種に****
イスラエルのベザレル・スモトリッチ新財務相は、ヨルダン川西岸のユダヤ人入植地にインフラ整備など巨額投資を行う方針を打ち出した。同氏は極右政党「宗教シオニズム」党首で、西岸地区の少なくとも一部併合を唱えている人物だ。
入植地の出身者が大半を占める宗教シオニズムのメンバーは、ベンヤミン・ネタニヤフ元首相が樹立した新政権の連立相手として不可欠な存在で、現在は入植地の権限を握る重要ポストを占めている。
同党の狙いはさらにユダヤ人100万人の入植に道を開き、国際的に認められたイスラエル領土内と入植地における生活水準の格差を段階的に解消することにある。将来的には西岸地区におけるパレスチナ国家の可能性を消し去ることが究極の目標だ。(後略)【1月5日 WSJ】
********************
従って、以下のような発言を繰り返すことにもなります。
****イスラエル閣僚、暴言連発 「パレスチナ人存在せず」****
イスラエルの極右閣僚、スモトリッチ財務相がパリで開かれたユダヤ系フランス人らの会合で「パレスチナ人など存在しない」「歴史も文化もない」と暴言を連発したことが分かった。イスラエルやフランスのメディアが20日、伝えた。演壇では「大イスラエル」と称された地図が示され、ヨルダンも含まれていた。
暴力の連鎖が続くイスラエル、パレスチナの当局者は19日にエジプトで事態沈静化に向け協議し、情勢を悪化させる言動の自制で一致したばかりだった。閣僚の暴言でネタニヤフ政権の在り方が問われそうだ。
ヨルダン外務省は20日、イスラエル大使を呼び出し抗議した。【3月21日 共同】
**********************
イスラエル、パレスチナの当局者の事態沈静化に向けた合意は以下のようにも。
****暴力抑制の仕組み構築=イスラエルとパレスチナが合意****
イスラエルとパレスチナ自治政府の当局者は19日、エジプト東部シャルムエルシェイクで、エジプト、米国、ヨルダンの当局者を交え、暴力の応酬が止まらないパレスチナ情勢を巡り協議した。
共同声明によると、イスラエルとパレスチナは「暴力や扇動的な言動を抑制し、それらに対抗する仕組み」の構築で合意した。
イスラム教のラマダン(断食月)が今週始まり、期間中にユダヤ教の祝祭「過ぎ越しの祭り」が重なることから、対立感情激化への懸念が高まっている。5者は、エルサレム旧市街にある両教の聖地を巡り、イスラエルとパレスチナ双方が「神聖さを乱す行為」を防ぐ必要性を強調した。【3月20日 時事】
******************
ただ、上記のような極右勢力が入閣し重要閣僚を務めるネタニヤフ政権と、ハマスや武装勢力への「グリップが全く効かない」パレスチナ自治政府が何を合意しても、どれだけの実効があるのか・・・疑問と言わざるを得ません。