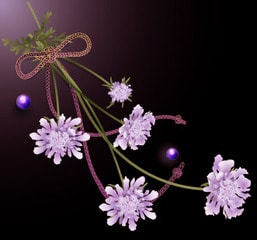久しぶりに、こんな面白い本を読んだ!!と少し興奮気味。
ナチ政権下のドイツ・ハンブルグ。大儲けしている軍需工場の経営者のドラ息子が、敵性音楽のジャズが大好きで、同好のドラ息子ドラ娘たちとジャズパーティを開き、ゲシュタポに捕まって殴られたり、鑑別所送りになる。
懲りずに自分たちでジャズレコードをコピーして、地下で売りさばき大儲け。いくらアーリア人種はワーグナーを聴け!と言っても、アメリカ文化や音楽が好きな人は、相当数いるのだ。
戦局はどんどん悪化し、ハンブルグも何度も空襲にあう。ノルマンディーに連合軍が上陸し、パリが解放され、ついには川向うに連合軍が現れ…。
こういった大金持ちや上流階級の人たちは、外国の事をよく知っている。ナチの党員バッチを持っていても、それは生きて行く上での便宜的なもので、ヒトラーの信奉者という訳じゃない。ヒトラーが破竹の勢いで勝ち進んでいる時は、それに乗っかろうと思ってるだけで、心の中では「このチョビ髭の伍長あがりが」とバカにしている人が多いだろう。
でも庶民は違う。心の底から信奉している。明日食べるパンにも事欠く貧農の小せがれが「あなたはアーリア人種だ。世界の支配層となる人種なのだ。」と吹き込まれれば、そう思い込んでしまう。なんて甘美な言葉。
だから、こういったドラ息子たちの「高貴な放蕩」には、胸がざらつく。例えば、主人公のエディは、ゲシュタポに捕まり、収容所で強制労働させられたが、軍隊には行っていない。経済界の大立者の父親が守ってくれたのだ。汚ったねーーー!
どうしてこうも胸がざわつくかと言うと、たぶん、この本を読む少し前に、『ちいさな独裁者』という映画を観たからだと思う。
これは実話を基にしているというから驚く。
ドイツ敗戦まで1カ月。(ヒトラーは1945年4月30日に自殺した) ドイツでは脱走兵が相次いでいた。その一人ヘロルドは、道に打ち捨てられていた車の中で軍服を発見。それを着て大尉になりすまし、ヒトラー総統の命令と称する架空の任務をでっちあげ、途中で出会ったはぐれ兵たちを部下にし、軍規違反した兵士たちの収容所を訪れる。
そりゃ、入隊した軍が食べ物をくれなきゃ、近郊の農家を襲って略奪するだろうね。当たり前だ。生きて行かなきゃならないんだもの。
爆弾で自分の隣の兵士が肉片になったら、恐怖で逃げ出すだろう、誰だって。
そういった軍規違反した兵士たちを、大尉の軍服を着た脱走兵ヘラルドは「イギリス軍に寝返るかもしれないから処刑する」と宣言。実行させる。
あと1か月しないうちに戦争は終わるというのに、縄に繋がれ集団で銃殺される脱走兵たち。死ぬ前に、自分たちで堀った穴に投げこまれ、消毒用の白い粉を撒かれる。
反ナチと叫べるのは、高貴な放蕩なんだよ。貧乏人からすれば。
ナチ政権下のドイツ・ハンブルグ。大儲けしている軍需工場の経営者のドラ息子が、敵性音楽のジャズが大好きで、同好のドラ息子ドラ娘たちとジャズパーティを開き、ゲシュタポに捕まって殴られたり、鑑別所送りになる。
懲りずに自分たちでジャズレコードをコピーして、地下で売りさばき大儲け。いくらアーリア人種はワーグナーを聴け!と言っても、アメリカ文化や音楽が好きな人は、相当数いるのだ。
戦局はどんどん悪化し、ハンブルグも何度も空襲にあう。ノルマンディーに連合軍が上陸し、パリが解放され、ついには川向うに連合軍が現れ…。
こういった大金持ちや上流階級の人たちは、外国の事をよく知っている。ナチの党員バッチを持っていても、それは生きて行く上での便宜的なもので、ヒトラーの信奉者という訳じゃない。ヒトラーが破竹の勢いで勝ち進んでいる時は、それに乗っかろうと思ってるだけで、心の中では「このチョビ髭の伍長あがりが」とバカにしている人が多いだろう。
でも庶民は違う。心の底から信奉している。明日食べるパンにも事欠く貧農の小せがれが「あなたはアーリア人種だ。世界の支配層となる人種なのだ。」と吹き込まれれば、そう思い込んでしまう。なんて甘美な言葉。
だから、こういったドラ息子たちの「高貴な放蕩」には、胸がざらつく。例えば、主人公のエディは、ゲシュタポに捕まり、収容所で強制労働させられたが、軍隊には行っていない。経済界の大立者の父親が守ってくれたのだ。汚ったねーーー!
どうしてこうも胸がざわつくかと言うと、たぶん、この本を読む少し前に、『ちいさな独裁者』という映画を観たからだと思う。
これは実話を基にしているというから驚く。
ドイツ敗戦まで1カ月。(ヒトラーは1945年4月30日に自殺した) ドイツでは脱走兵が相次いでいた。その一人ヘロルドは、道に打ち捨てられていた車の中で軍服を発見。それを着て大尉になりすまし、ヒトラー総統の命令と称する架空の任務をでっちあげ、途中で出会ったはぐれ兵たちを部下にし、軍規違反した兵士たちの収容所を訪れる。
そりゃ、入隊した軍が食べ物をくれなきゃ、近郊の農家を襲って略奪するだろうね。当たり前だ。生きて行かなきゃならないんだもの。
爆弾で自分の隣の兵士が肉片になったら、恐怖で逃げ出すだろう、誰だって。
そういった軍規違反した兵士たちを、大尉の軍服を着た脱走兵ヘラルドは「イギリス軍に寝返るかもしれないから処刑する」と宣言。実行させる。
あと1か月しないうちに戦争は終わるというのに、縄に繋がれ集団で銃殺される脱走兵たち。死ぬ前に、自分たちで堀った穴に投げこまれ、消毒用の白い粉を撒かれる。
反ナチと叫べるのは、高貴な放蕩なんだよ。貧乏人からすれば。