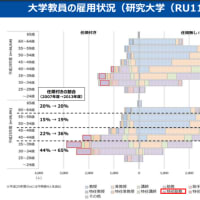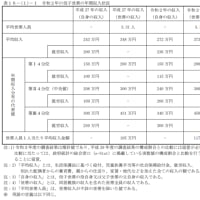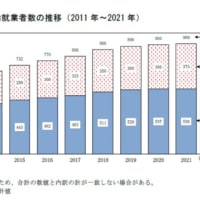今朝、ネットニュースをチェックしていたら、イギリスのロックスター・スティングの記事があった。
amass:スティング、ウクライナの人々を支援するために冷戦を批判した80年代の楽曲「Russianrs」を新たに演奏
1985年に、オマー・ハキムやブランフォード・マルサリスなど、若いジャズミュージシャンを起用して制作されたアルバム「ブルータートルの夢」に収録されている楽曲である、ということは洋楽ファンであればご存じだと思う。
収録楽曲の中でも、日本では「イングリッシュマン・イン・ニューヨーク」がCMに起用されたこともあり、アルバム1枚を通して聞いたことは無くても、いくつかの楽曲は聞いたことがある方は多いのでは?と、思っている。
スティングが、この「ブルータートルの夢」の制作に取り掛かっていた頃と今とでは、社会情勢は全く違う。
アルバムが制作された当時のアメリカ大統領は、レーガン大統領で当時のソ連邦に対して、相当強権的な態度であった。
それは、ソ連邦のフルシチョフも同じで、「世界終末時計」が終末まであと3分という時間を指すほどだった。
そのような世界情勢の中でこの「Russians」という楽曲は作られたのだった。
その後「ベルリンの壁崩壊」があり、ソ連邦の解体、ペレストロイカ政策と、ロシアが民主政策へと舵を切ったことで、「世界終末時計」の時間も後退していくことになる。
スティングが、この楽曲を書いた時の世界情勢がわかれば、その歌詞の意味もまた理解しやすくなると思う。
ただ、スティングらしい比喩的な表現をしている点でも、考えさせられるところがある。
それは「Oppenheimr’s deadly toy?」という部分が顕著かもしれない。
Oppenheimというのは、「原爆の父」とも言われたオッペンハイマー博士の事だ。
「Oppenheimr's deadly toy」とは「核兵器」の事を指している。
それを何故、スティングは「おもちゃ」という表現をしているのか?といえば、おそらく「核兵器」を外交カードの一つとして、平和の均衡を保っているという状況があったからだろう。
しかし、その外交カードの一つである「核兵器」と同様の被害(在るいはそれ以上の被害かもしれない)をもたらす、「原子力施設」を攻撃するという暴挙に、ロシアは出てしまったのだ。
このような暴挙を繰り返すロシアというよりもプーチン氏に対して、世界が非難をするのは当然だろう。
その非難はあくまでも、プーチン氏をはじめとするロシア政府に対してであって、ロシア市民に対してではない。
それは「Russianrs」の中でも、「ロシアの人たちもまた、自分の子どもたちを愛していると願っている」という、最後の言葉に表れている。
私たちが非難すべきは、この暴挙に出ているプーチン氏であり、ロシアの人たちではない、と理解する必要があると思う。