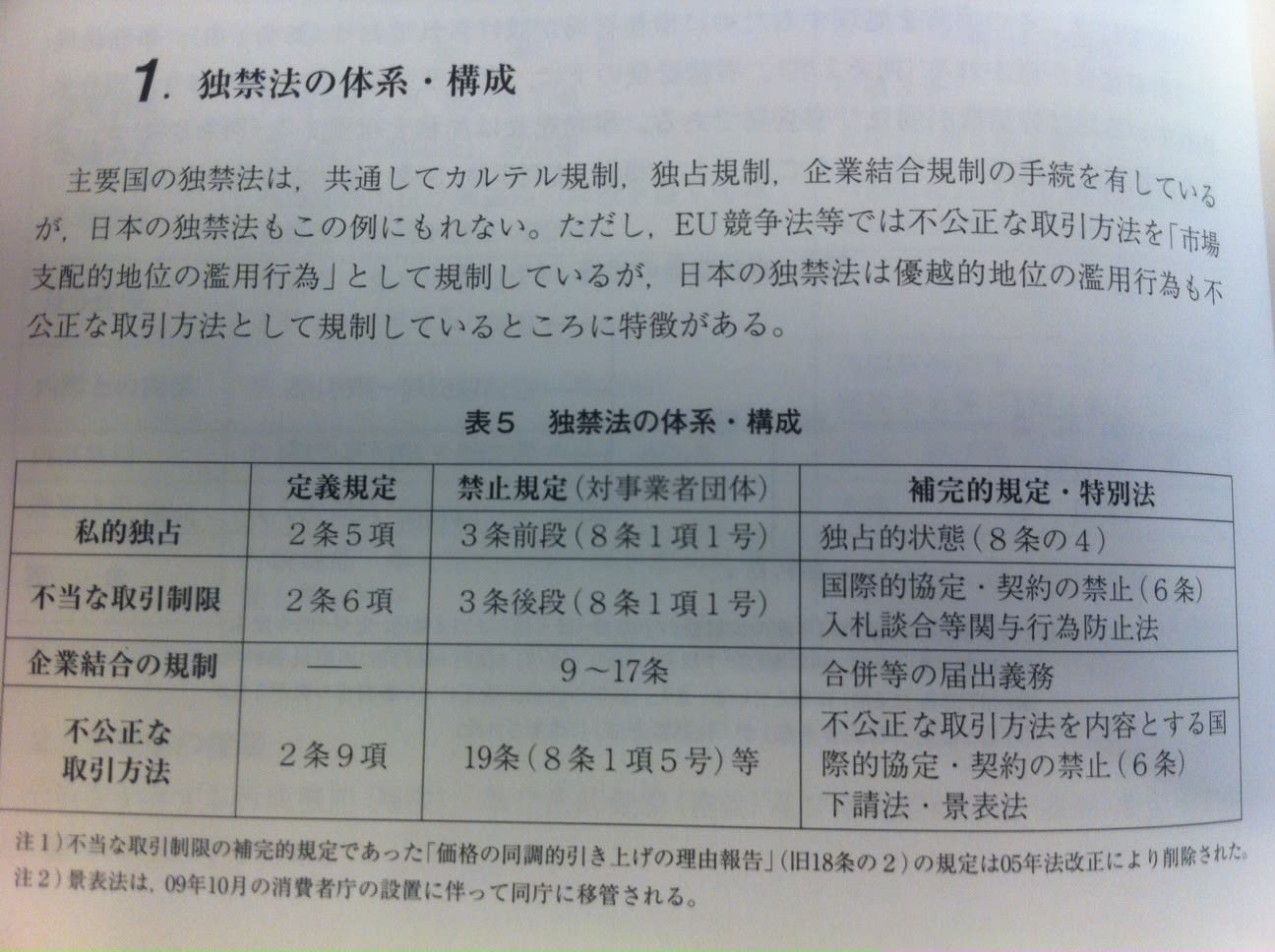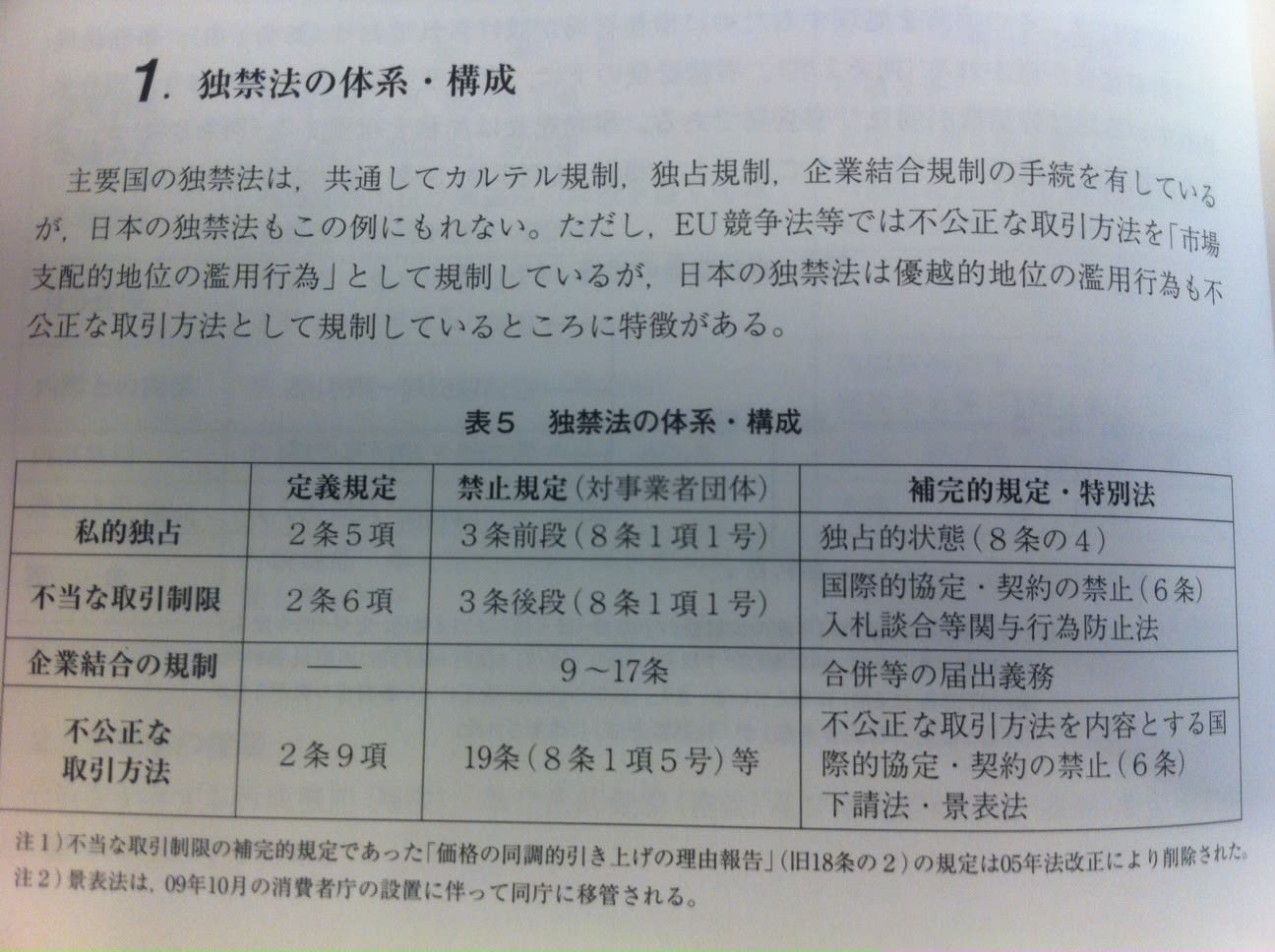手続保障を裁判所は、かなり守ろうとしていると思います。
自分が知らない間に、誰かが自分の名を名乗って裁判がなされてしまうことは、ありえないと安心できます。
たとえ、自分の家族が、訴状を受け取っていたとしても、民事訴訟法106条1項の趣旨(訴状送達は補充送達として有効)に反してでもです。。
再審事由(338条1項3号)の存否は、訴状送達の有効・無効にかかわらず、当事者に対する手続保障の有無の観点から判断される。
最高裁の理由の主要な部分。
「受送達者あての訴訟関係書類の交付を受けた同居者等と受送達者との
間に,その訴訟に関して事実上の利害関係の対立があるため,同居者等から受送達
者に対して訴訟関係書類が速やかに交付されることを期待することができない場合
において,実際にもその交付がされなかったときは,受送達者は,その訴訟手続に
関与する機会を与えられたことにならないというべきである。そうすると,上記の
場合において,当該同居者等から受送達者に対して訴訟関係書類が実際に交付され
ず,そのため,受送達者が訴訟が提起されていることを知らないまま判決がされた
ときには,当事者の代理人として訴訟行為をした者が代理権を欠いた場合と別異に
扱う理由はないから,民訴法338条1項3号の再審事由があると解するのが相当
である。」
**********最高裁ホームページ*********************
最高裁決定 平成19年3月20日
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070323154018.pdf
主文
原決定を破棄する。
本件を東京高等裁判所に差し戻す。
理由
抗告代理人伊藤諭,同田中栄樹の抗告理由について
1 本件は,抗告人が,相手方の抗告人に対する請求を認容した確定判決につ き,民訴法338条1項3号の再審事由があるとして申し立てた再審事件である。
2 記録によれば,本件の経過は次のとおりである。
(1) 相手方は,平成15年12月5日,横浜地方裁判所川崎支部に,抗告人及 びAを被告とする貸金請求訴訟(以下「前訴」という。)を提起した。
相手方は,前訴において,1B1及びB2は,平成9年10月31日及び同年11 月7日,Aに対し,いずれも抗告人を連帯保証人として,各500万円を貸し付け た,2相手方は,Bらから,BらがAに対して有する上記貸金債権の譲渡を受けた などと主張して,抗告人及びAに対し,上記貸金合計1000万円及びこれに対す る約定遅延損害金の連帯支払を求めた。
(2) Aは,抗告人の義父であり,抗告人と同居していたところ,平成15年1 2月26日,自らを受送達者とする前訴の訴状及び第1回口頭弁論期日(平成16 年1月28日午後1時10分)の呼出状等の交付を受けるとともに,抗告人を受送 達者とする前訴の訴状及び第1回口頭弁論期日の呼出状等(以下「本件訴状等」と いう。)についても,抗告人の同居者として,その交付を受けた。
(3) 抗告人及びAは,前訴の第1回口頭弁論期日に欠席し,答弁書その他の準 備書面も提出しなかったため,口頭弁論は終結され,第2回口頭弁論期日(平成1
-1-
6年2月4日午後1時10分)において,抗告人及びAが相手方の主張する請求原 因事実を自白したものとみなして相手方の請求を認容する旨の判決(以下「前訴判 決」という。)が言い渡された。
(4) 抗告人及びAに対する前訴判決の判決書に代わる調書の送達事務を担当し た横浜地方裁判所川崎支部の裁判所書記官は,抗告人及びAの住所における送達が 受送達者不在によりできなかったため,平成16年2月26日,抗告人及びAの住 所あてに書留郵便に付する送達を実施した。上記送達書類は,いずれも,受送達者 不在のため配達できず,郵便局に保管され,留置期間の経過により同支部に返還さ れた。
(5) 抗告人及びAのいずれも前訴判決に対して控訴をせず,前訴判決は平成1 6年3月12日に確定した。
(6) 抗告人は,平成18年3月10日,本件再審の訴えを提起した。 3 抗告人は,前訴判決の再審事由について,次のとおり主張している。 前訴の請求原因は,抗告人がAの債務を連帯保証したというものであるが,抗告
人は,自らの意思で連帯保証人になったことはなく,Aが抗告人に無断で抗告人の 印章を持ち出して金銭消費貸借契約書の連帯保証人欄に抗告人の印章を押印したも のである。Aは,平成18年2月28日に至るまで,かかる事情を抗告人に一切話 していなかったのであって,前訴に関し,抗告人とAは利害が対立していたという べきである。したがって,Aが抗告人あての本件訴状等の交付を受けたとしても, これが遅滞なく抗告人に交付されることを期待できる状況にはなく,現に,Aは交 付を受けた本件訴状等を抗告人に交付しなかった。以上によれば,前訴において, 抗告人に対する本件訴状等の送達は補充送達(民訴法106条1項)としての効力
-2-
を生じていないというべきであり,本件訴状等の有効な送達がないため,抗告人に 訴訟に関与する機会が与えられないまま前訴判決がされたのであるから,前訴判決 には民訴法338条1項3号の再審事由がある(最高裁平成3年(オ)第589号 同4年9月10日第一小法廷判決・民集46巻6号553頁参照)。
4 原審は,前訴において,抗告人の同居者であるAが抗告人あての本件訴状等 の交付を受けたのであるから,抗告人に対する本件訴状等の送達は補充送達として 有効であり,前訴判決に民訴法338条1項3号の再審事由がある旨の抗告人の主 張は理由がないとして,抗告人の再審請求を棄却すべきものとした。
5 原審の判断のうち,抗告人に対する本件訴状等の送達は補充送達として有効 であるとした点は是認することができるが,前訴判決に民訴法338条1項3号の 再審事由がある旨の抗告人の主張は理由がないとした点は是認することができな い。その理由は,次のとおりである。
(1) 民訴法106条1項は,就業場所以外の送達をすべき場所において受送達 者に出会わないときは,「使用人その他の従業者又は同居者であって,書類の受領 について相当のわきまえのあるもの」(以下「同居者等」という。)に書類を交付 すれば,受送達者に対する送達の効力が生ずるものとしており,その後,書類が同 居者等から受送達者に交付されたか否か,同居者等が上記交付の事実を受送達者に 告知したか否かは,送達の効力に影響を及ぼすものではない(最高裁昭和42年 (オ)第1017号同45年5月22日第二小法廷判決・裁判集民事99号201 頁参照)。
したがって,受送達者あての訴訟関係書類の交付を受けた同居者等が,その訴訟
において受送達者の相手方当事者又はこれと同視し得る者に当たる場合は別として
-3-
(民法108条参照),その訴訟に関して受送達者との間に事実上の利害関係の対
立があるにすぎない場合には,当該同居者等に対して上記書類を交付することによ
って,受送達者に対する送達の効力が生ずるというべきである。
そうすると,仮に,抗告人の主張するような事実関係があったとしても,本件訴 状等は抗告人に対して有効に送達されたものということができる。
以上と同旨の原審の判断は是認することができる。
(2) しかし,本件訴状等の送達が補充送達として有効であるからといって,直 ちに民訴法338条1項3号の再審事由の存在が否定されることにはならない。同 事由の存否は,当事者に保障されるべき手続関与の機会が与えられていたか否かの 観点から改めて判断されなければならない。
すなわち,受送達者あての訴訟関係書類の交付を受けた同居者等と受送達者との
間に,その訴訟に関して事実上の利害関係の対立があるため,同居者等から受送達
者に対して訴訟関係書類が速やかに交付されることを期待することができない場合
において,実際にもその交付がされなかったときは,受送達者は,その訴訟手続に
関与する機会を与えられたことにならないというべきである。そうすると,上記の
場合において,当該同居者等から受送達者に対して訴訟関係書類が実際に交付され
ず,そのため,受送達者が訴訟が提起されていることを知らないまま判決がされた
ときには,当事者の代理人として訴訟行為をした者が代理権を欠いた場合と別異に
扱う理由はないから,民訴法338条1項3号の再審事由があると解するのが相当
である。
抗告人の主張によれば,前訴において抗告人に対して連帯保証債務の履行が請求 されることになったのは,抗告人の同居者として抗告人あての本件訴状等の交付を
-4-
受けたAが,Aを主債務者とする債務について,抗告人の氏名及び印章を冒用して Bらとの間で連帯保証契約を締結したためであったというのであるから,抗告人の 主張するとおりの事実関係が認められるのであれば,前訴に関し,抗告人とその同 居者であるAとの間には事実上の利害関係の対立があり,Aが抗告人あての訴訟関 係書類を抗告人に交付することを期待することができない場合であったというべき である。したがって,実際に本件訴状等がAから抗告人に交付されず,そのために 抗告人が前訴が提起されていることを知らないまま前訴判決がされたのであれば, 前訴判決には民訴法338条1項3号の再審事由が認められるというべきである。
抗告人の前記3の主張は,抗告人に前訴の手続に関与する機会が与えられないま ま前訴判決がされたことに民訴法338条1項3号の再審事由があるというもので あるから,抗告人に対する本件訴状等の補充送達が有効であることのみを理由に, 抗告人の主張するその余の事実関係について審理することなく,抗告人の主張には 理由がないとして本件再審請求を排斥した原審の判断には,裁判に影響を及ぼすこ とが明らかな法令の違反がある。論旨は,以上の趣旨をいうものとして理由があ り,原決定は破棄を免れない。そして,上記事由の有無等について更に審理を尽く させるため,本件を原審に差し戻すこととする。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官 堀籠幸男 裁判官 上田豊三 裁判官 藤田宙靖 裁判官
那須弘平 裁判官 田原睦夫)
-5-