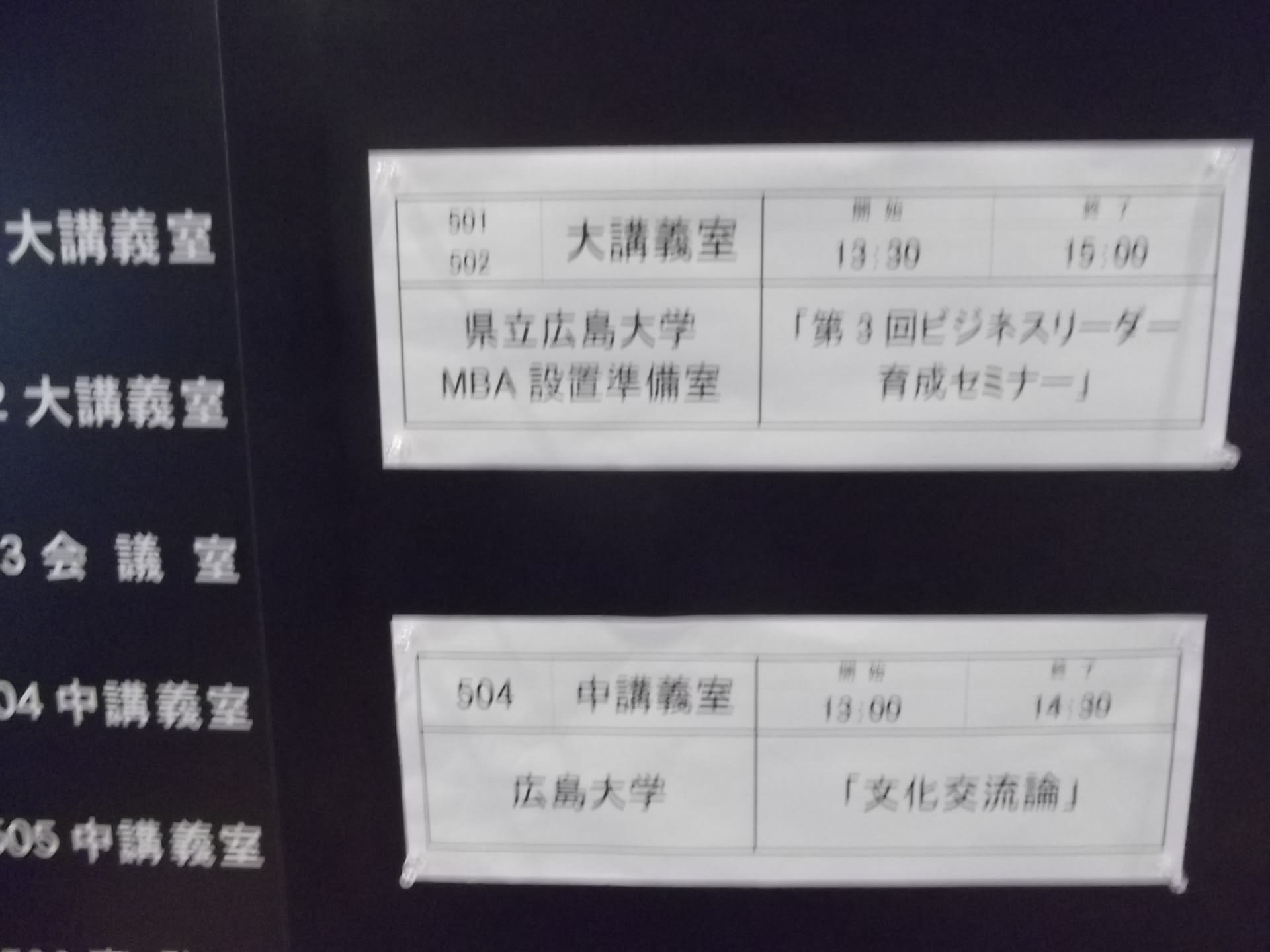| べっぴんぢごく (新潮文庫) |
| クリエーター情報なし | |
| 新潮社 |
岡山を舞台にした淫靡でホラーな話を書かせたら、この人の右に出る者はいないだろうという、岩井志麻子の「べっぴんぢごく」(新潮社)。私など、岡山というと、「晴れの国」という明るいイメージがあるのだが、確かに北部は中国山脈が深く、明治、大正のころだったら、こう言ったどろどろとした話の舞台に相応しい雰囲気だったのかもしれない。
この作品は、女6代の100年以上にもわたる、忌まわしくも淫靡な運命を描いた作品である。幕開けは明治30年代の岡山の寒村。作品全体を通しての主人公であるシヲは、乞食の娘として放浪の生活を送っていた。ところが、この地で母を殺され、村一番の分限者の家に下女として引きとられる。だが、心に病を持っていたその家の娘が死んだため、養女として過ごすことになった。
シヲは禍々しいまでの美貌を備えていたが、その娘のふみ枝は、牛蛙と渾名されるほどの醜女だった。しかし、ふみ枝の産んだ小夜子は、シヲゆずりの美貌を受け継いでいた。以下、冬子、未央子、亜矢と続くが、なぜか、シヲの子孫は、美女と醜女が交互に出現する。
シヲの誕生自体も業にまみれたものだった。そのためか、シヲにはこの世の住人ではない者たちがつきまとう。シヲ自身は、自分の業をよく認識しており、子孫たちに比べれば、平穏な人生を過ごす。しかし、子孫たちは、奔放だったり、嫉妬深かったりと、それぞれの女の業にまみれた人生だった。
物語のそこかしこに死霊たちも登場するが、それ自体は別に恐ろしいものとして描かれてはいない。描かれているのは、因果の糸で操られるような女系6代の女たちの哀しさだ。グロテスクとも言える女たちの性と業を描きながら、それを独特の筆致で、単なる官能小説ではなく、見事な文学作品として仕上げている。まさに岩井志麻子の真骨頂発揮といったところだろう。
美しいが、どこか耽美な香りのする少女を描いた表紙イラストも素晴らしく、この作品の雰囲気を盛り上げてくれる。
☆☆☆☆
※本記事は、2012年02月11日付で、拙ブログ「風竜胆の書評」に掲載したものです。