(過去記事です)
わが子が幼い頃や小学生時代、いっしょに交わす会話が面白くてよく記録に取ったものでした。
それが子どもが成長するにつれ、学校、通学、趣味、友だちとのつきあい、バイト……と親より慌ただしい生活をするようになって、
顔を合わせて話をする時間が激減していました。
それが、受験生になった息子が学校が休みの日も 遊びに行かずに家で勉強するようになって、勉強に疲れると気分転換に家族としゃべる機会が増えて……。
そうするうちに、自分の中にむくむくと「子どもとの会話を記録しておきたい」という思いが復活してきました。
「なぜ?」と問われたら困るのですが、カメラ好きの方が わが子の姿を写真に残しておこうとするのと近いものだと思います。
そのため虹色教室の日誌代わりに続けてきたこのブログは、
以前より私的なものに変化しつつあります。自分にために書いているやたら長ったらしい記事も増えましたが、面倒な方はどうか飛ばし読みしてくださいね~。
今後も教室でのレッスン風景や教え方の記事も、
書いていきます♪ どうぞよろしくお願いします。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
先日、進路について悩む息子から相談を受けました。
進路といっても、大学や学部選びはもう自分の中で決まっているようで、
迷っているのは将来の仕事に向けて
これから何を学んでいくべきか、
就職する会社はどのような職種から選んでいけばいいのか
といったことでした。
途中で現われたダンナが、
「先のこと考えて御託並べてないで、まずしっかり勉強しろ!」
と雷を落とし、
息子が「受験勉強はしてるさ。でも闇雲に勉強するだけでは、大学卒業時にそこから4,5年かかる勉強をスタートすることになって、出遅れるよ。ビル・ゲイツが成功したような まだネット社会が未完成だった時代じゃないんだからさ」と言い返すシーンもありました。
夕食後に3時間近く話しあって、
最後には、「話をしてみてよかったよ。おかげで行きたい方向がはっきり見えてきた」と言われて胸が熱くなりました。
息子の進路について相談に乗っているつもりが、
私自身の進路というか……これから自分が歩んでいく方向性のようなものを考えるきっかけにもなった会話でした。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
息子 「最近、ただIT関連の仕事がしたいと漠然と考えて、
大学で情報工学を学ぶだけじゃ、
本当にやりたい仕事からずれていくような気がしてさ。
ITといったって、今はひとつひとつの分野が専門的に進化しているから、
それぞれの先端じゃ互換性はないはずだよ。
だからといって念のためにと あれこれつまみ食いするように学ぶんじゃ
1しっかり学べるところを、2分の1、3分の1ずつしか学べなくなってしまう。
今、一番迷っているのは、ソフトを作る力を蓄えるか、ハード面で強くなっておくかということなんだ。
もしこれまでのネットのあり方を根源から変えるようなものを作りたいとすれば、大学を卒業しても、そこから研究生活に入ってく形になる。
それがぼくが本当にやりたいことなのか、自分にあっていることなのか迷っているんだ」
私 「今後、ネットの世界は飽和状態に向かうと考えているんでしょ。
ただプログラミングを学ぶだけでは、いずれ、どんなに質の良いものを作り出しても、競争の中で消えていくだけかもしれないわ。
だったら、時間や手間がかかってもハードそのものを扱う勉強をした方がいいんじゃないの?」
息子 「勉強や研究が嫌なわけじゃないんだ。」
私 「早く働きたいの?」
息子 「それもあるけど、それより自分が本当に創りだしたいものは何なのか、そう考えていくと、今 立ち止まってじっくり考えておかないと、
何となくそっちの方が良さそうだという気分に流されるうちに、自分自身を見失いそうな気がしているんだ。
それで、ぼくの、ぼくだけの特技ってなんだろう?
将来の仕事の決め手になるような他のみんなより誇れるところって何だろうって煮詰めていくとね、
『みんながみんな左に向かっているときにも、右に向かうことができる』
ってところだって思い当たってさ。
じゃあ、そんな自分が活かせる仕事、いきいきと働き続けることができる仕事は何だろう
……それとぼくが創りたいものの本質は何だろうって考えていたんだ」
「『みんながみんな左に向かっているときにも、右に向かうことができる』能力って、単にひねくれ者ってわけじゃなくて、
多くの人がいっせいに左に向かっているときって、
その時点で もう本来の左に進むべき目的が見失われているときがあって、
みんな薄々、それには気づいてるんだけど、
動きが取れなくなっていることがあるよね。
そんなときにぼくは
潜在的にそこにある大切そうなものを汲み取って、
ひとりだけでも右に方向転換することができるってことだよ。
そういう能力が将来、活かせるかもしれないって気づいたのは、
プログラミングを自分で学んでいたときなんだ。
学べば学ぶほど、より優れた技術、より精巧な動きっていうのを、
無意識に求める気持ちに呑まれていくんだけど、
一方で、より面白く、よりすごいものを作ってくって
技術面だけにこだわってていいのか? って考えたんだ。
もちろん、技術の向上が大切なのはわかっている。
でもね、もし技術ばかりがひとり歩きして、こんなものが欲しいという人の欲望みたいなものから離れてしまったら、
それは死んだ作品じゃないだろうかって。
ほら、3Dテレビって今どんどん進化しているじゃん。
100年前の時代だったら、
3Dテレビを作り出すために一生かけてもいい、
3Dテレビをどんな苦労してもひと目見たいって、願った人もいると思う。
で、今、3Dテレビがそれほど求められているのかっていうと、
100年前と比べると、それに対して人々が抱いているロマンのようなものが変質したと思うんだよ。
それでも技術革新は必要なんだろうけど、
同時にどうしたら生きた作品を生み出せるのかって考えるときが
来たんじゃないかな?
それで、ぼくは技術を身につけて、自分で制作に入りたくはあるけど、
その一方で、『プランナー』といった面を持っている仕事も
自分にあってるんじゃないかと思いだしたんだ」
私 「生きている作品ってどんな感じのものなの?」
息子 「感情を揺さぶるライブ的要素も持った作品かな?
今の世の中がこんなにも『うつ』っぽくなっちゃった理由は、
何でもかんでも、そうしてはならないものまで、
品物化していった結果だと思うんだ。
ほら、エンデの『モモ』って童話があるじゃん。
あれを子どもの頃に読んだとき、
みんな何日で読んだ~何ページも読んだ~
他の本と比べてどのレベルで面白かったかってことばかり話題にして、
どうして、自分自身の今の生活が、
時間泥棒に奪われているモモの世界の出来事と
同じことが起こっている事実について考えてみないんだろうって
不思議だったんだ。
みんなはどうして人間としての自分の感情を通して、
物と付き合わないんだろうっさ。
いろんなものを品物として見るって、
高級料理にしたって、勉強の授業のようなものにしたって、品物化されて、
数値化されてるよね。
友だちのようなものまで、
ネット内でボタンひとつで友だちかどうか選別したり、
グループ内で友だちを格付けしたり、友だちを数でコレクションしたりする
ようになってくる。
でも、本当は、そんな品物化した『友だち』を、誰も求めちゃいないはずだよ。
友だちを欲するのは、友だちという人を求めているというより、いっしょになって団結して何かしてみたり、
冒険したり、共感しあったり、
そこで動く感情を欲しているはずなんだから。
みんな感情を求めていて、それに気づいていないんだよ。
何でも品物化したあげく、これは品物にしようがないっていう感情でしか処理しようにない『死』を、偏愛する人も増えている。
もし、IT産業で何かを作っていくにしても、
そんな風に物を求める根底になる感情の流れを揺さぶる生きた作品を作ることを目指していきたいんだ」
息子 「ぼくはずっとゲームクリエイターになる夢を抱いてきたけど、
ゲーム好きの人たちと自分の間には、
かなり感性の違いがあるのはずっと感じてきて……
最近になって、本当にぼくはゲームが好きなんだろうか?
って思うことが増えてきたんだ。
ぼくがゲームに対して感じている面白さって何なんだろう
って突き詰めてみると、
さっきお母さんが京都の巨大鉄道ジオラマの話をしていたから
閃いたんだけど、
『仕事の遊び化』って部分に
惹かれているんじゃないかと思うよ。
ぼくがゲームを面白いって感じている基盤の部分に、
この『仕事の遊び化』を生み出したい気持ちがあると思ったんだ。
ジオラマ作りに参加した職人やアーティストは、
退屈で苦しいはずの作業の中に、わくわくする楽しい気持ちやフローの感覚を抱いていたはずだよ。
この『仕事の遊び化』って、昔から人が苦しいものを喜びに変えたり、
辛い作業から楽しみを抽出する知恵として
存在しているものだと思うんだ。
たとえば、プラモデルなんかも、設計の仕事から、
楽しい部分だけを抜き出したようなおもちゃだよね。
ぼくがゲーム作りをしたかった一番の理由は、
ゲームという媒体を使って、
人間の営みをいろんな視点から眺めたり、そのユニークな一面に光を当てる
のが楽しいからなんだって気づいたんだよ」
私 「『仕事の遊び化』……そうね。日本が豊かになって、
物ではうんざりするほど満たされた後に、
きっと人はそうしたものを求めだしているように感じるわ。
遊び化といっても、遊び半分という意味でなくて、プロフェッショナルとして、天職として仕事に関わるとき
そうしたものを感じることができるのよね。
人の営みの面白い面を再体験したいって思いから
ゲームは生まれたのかもしれないわね」
そう言いながら、私は息子が小学生のとき
モノポリーが好きでたまらなかったことを思い出しました。
何度やっても、いつも息子の一人勝ち。
どんなに他のメンバーの情勢が良いように見えるときも、
なぜか最後には息子の戦略にまんまとはめられて、
お金をほとんど奪い取られてしまうのでした。
手作りモノポリーもたくさん作っていました。
モノポリーは投資のゲームですから、それもおそらく『仕事の遊び化』という一面で惹かれていたのでしょう。
息子 「現実に体を動かしてやった方が面白いものを、
ゲームにするのは好きじゃないんだ。
どんなにリアルさを追求しても、実体験には負けてしまうから。
でも、そこのゲームの世界も、より美しい画像で、より高い技術でってことを追いかけていくうちに、人間的な部分が置いてけぼりになっている気がしてさ。
人が何を面白く感じ、何に心が動かされるのか……って所を見失ったまま進化が進んでいるようだよ。
それで、そうした世界でぼくは本当にゲームが作りたいんだろうか?
面白いものが作れるんだろうか? って思いだしたんだ。
先々、ゲームを作るにしろ、作らないにしろ、
まずゲーム会社とは全く職種の違う世界で働いて、
そこでの仕事に熱中しながら、自分の作りたいものを捉えなおした方が
いいような気がしているんだ」
私 「どんな職種を考えているの?」
息子 「アプリケーションの制作会社とか、
それか、シンセサイザーなんかといっしょに新しい音響機材を作る会社なんかも考えている。
ゲームを作りたいから、
新しいエンターテイメントを生み出したいから、
ゲーム会社に入るというのは、ぼくにはあっていない気がするんだ。
そんなことを思いだしたのは、マンガを読んでいたときなんだけど。
今さ、たくさんマンガの勉強をしたんだろうな
という技術レベルの高いマンガ家がたくさんいるんだけど、
そりゃぁたくさんの人がマンガを描いているんだ……
でも、どれを読んでも面白くないんだよ。
生きている作品がないって感じ。
一方で、ある時期までマンガとは全く関係ない異分野の仕事をしていて、
途中でマンガ家になった人たちが描く職業マンガが、
けっこう面白くって、このごろ気に入ってるんだ。
単純に考えると、少しでも早い時期からマンガを描き始めて、
それだけに打ち込んだ方が、良いものができるに決まってるって思うじゃん。
でも、マンガの世界もある程度
成熟し終えた面があるから、
無意識のうちに すでにできあがった価値観の影響を受けながら、
その世界でよりすばらしくって技術を向上させるだけじゃ、
人の心が動くような作品は生まれにくいんだよ。
その点、異業種から遅れて参入してきた人の作品は、
多少いびつなところがあっても、
思いもかけない斜めからの視点があって
新鮮で読みたい気を起させるんだ。」
私 「そうね、ものづくりの現場でも
そうした異業種同士の連携が、
不況を超えるカギになっているようだものね。」
息子 「ぼくも、自分が抱いている面白さを追求する道を、
既存のイメージができあがっている世界ではなくて、
ストレートにそのまんまじゃない……
別の職種の枠の中で探求していく方がいい気がしてきててさ。
そう考えだしたのには、受験勉強の影響もあるんだ。
受験って、ランキングで格付けされて、合格の道筋がマニュアル化されて、
いかにも品物化が進んでいる分野でもあるけど、
でも勉強していると 意外なんだけど、どの勉強も人間的な性格的なものが
その底にあるんだなって気づかされることがよくあったんだ。
かしこさって、いかにもIQや頭の回転のよさだけで測られるように思うじゃん。
でも、国語を学ぶって、結局は、そこにあるのは人間の営みや生きていることへの理解を深めることに過ぎないんだって学ぶほどにわかってくる。
文章のすばらしさをただ公式を当てはめて、答えをはじきだす作業じゃなくて、
読む文章から生きていることの何かを受け取ることが国語なんだなって。
数学のように、人間的なものからかけ離れているように見えるものでも、
生きていることのすばらしさを放っておいて、存在しないんだよ。
数学がすばらしいのは、そこに
人間的な評価が潜んでいるからでもあるんだから。
それで勉強するうちに、自分が表現したいものは、この人間的なことや
生きる営み、人の感情を揺さぶることを抜きにして考えられないなって。
そうした本質的なものを含んだ作品は、小さな枠の中で近視眼的に
他人と技術を競うだけでは生まれてこないと思ったんだよ」











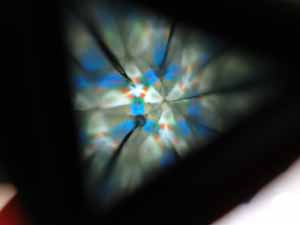

 (この本、ダンナからの苦情のもとでもありますが……)
(この本、ダンナからの苦情のもとでもありますが……)