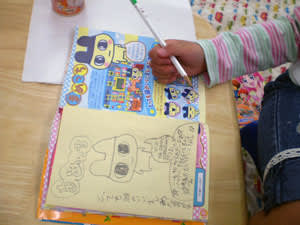国語の学習につまずく子の多くは
語彙量が少なくて
「言葉」をあまりしりません。
子どもとしゃべっていると、
「短い」鉛筆も、「浅い」池も、「ゆるやかな」坂も
「少ない」量も、「小さい」とか「あれ、あれ」という言葉で済ませるなど、
意味は通じるけれど、それはちょっと……という言葉の使い方をしていることがよくあります。
しょっちゅう訂正していたのでは
しゃべること自体を嫌がるようになるかもしれませんから、
楽しくおしゃべりのキャッチボールを続けながら
少しずつ間違いが修正されて、語彙量が増えるようにしてあげることが
大事だと思っています。
たとえば、子どもが作った新聞紙でできた剣を見ながらする会話でしたら、こんな感じです。
<形容詞の理解が乏しい子との会話>
わたし 「この剣、かっこいいね。えいって振ったら、高い高いたか~い木も
スパッスパッて切れるよね」
子 「うん」
わたし 「木をね、剣で切ったら、どうなると思う?」
子 「ドテッてなる」
わたし 「そうよね。ドテッとね、倒れる。木が倒れるよね。雷が落ちた時みたいに」
子 「かみなりはね、こわいよ~ガラッガラバリンだよ」
わたし 「木はどうなるの?」
子 「ガシャガシャってね、壊れるよ」
わたし 「ああ~幹のところが、真っ二つに割れて、枝が1本1本、ポキンポキンと折れて落ちるよね。
火が燃えて、煙がもくもく舞い上がるかもしれないね。
かみなりは、どこから落ちてくるの?」
子 「上」
わたし 「上って、天井のところ?」
子 「ちがうよ。空のくものところだよ」
わたし 「空から地面まで落ちてくるのよね。すごくすごく遠いよね。空と地面は遠いからね」
子 「遠くても、落ちるんだから、落ちる時はすぐなんだよ」
わたし 「滑り台を滑る時といっしょのことね。滑る時は人間も速いもんね。新幹線みたいに。
かみなりも落ちてくるから、速いのね」
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
先の会話を読んでいただくとわかるように
語彙量の少ない子は、おしゃべりが楽しくなってきて言葉数が多い時にも、
「ドテッ」とか「バラバラ~」など擬音語だけでしゃべりながら、
手を振り回したり、身体ごと前のめりにこける真似をしたりして
言いたいことを伝えがちです。
そんな時、言いなおさせるのではなくて、
「そうよね。ドテッとね」と子どもの言葉をそのまま受け取ってから、
「倒れる。木が倒れるね」など、正しい言い方で言いなおすようにしています。
できるだけ短い言葉で言い直し、
後から主語をつけた形でも言い直すようにしています。
「倒れるのと、ぐらぐら揺れるだけなのと、どっちが怖い?」といった質問をして、
今、学んだ言葉を使う場面を設けるのもいいですね。
語彙の少ない子は
相手の話を聞くこと自体に無関心なことがよくあって
話している最中にも
プイッとよそ見をして、自分の遊びに没頭しはじめることがあります。
無理のない形で、「おしゃべりをしている間は、相手の顔を見て、
最後まで聞くのよ」といったルールを繰り返し教えることも必要かもしれません。
また子どもがもっとしゃべりたい、面白い、楽しい、と感じるような
話題で会話をすることも大切だと思っています。
次回に続きます。
























 まず絵の名前を言って取る
まず絵の名前を言って取る
 「らーめんてんし」
「らーめんてんし」