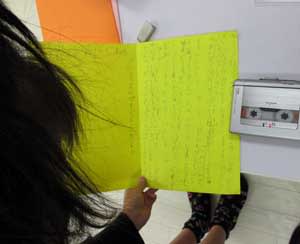小2のAちゃんがおひな様を作ってきてくれました。教室に通い出した未就園児の頃から
エネルギッシュに物作りを続けているので、どんな大掛かりなものも全て自分の力で作ってしまう
実力派です。
ひとりひとりのおひな様の表情が味がすてきです。ぼんぼりがすごくきれいだったのに
写真に撮るのをうっかりして残念です。

↑ これはお姉ちゃんにならって、何でもひとりで作ってしまう妹のBちゃんの
おひな様。これもいい顔していますね。

Aちゃんが年長の時に作ってきてくれたおひな様の画像があったので
ついでに載せておくことにします。
なつかしいおひなまつりのごちそう作り 「何通りある?」の問題
の記事にありました。
こんな風にひとりの子が異なる年代で作った作品を並べると、時を経ても
変わっていないその子の個性が垣間見えて面白いです。

今回のレッスン中、Aちゃんがこんな小さなティーポットを作っていました。
そういえば、2年前のAちゃんはティーポットを作っていました。

全て紙で作られたティーポット。



今回、Aちゃんが教室で作っていた家具。
Aちゃんが使う素材は、紙が主で、
どんな形も折ったり貼り合わせたりすることで作ってしまいます。
あまり試行錯誤することなく的確な形を作りだすので、
紙を切る段階で、どのような立体ができあがるのか仕上がりをイメージできている
ようです。
こうした扱う素材や物の作り方は子どもによって
ずいぶん異なります。
同じ親に育てられている姉妹でも、Aちゃんの妹のBちゃんの場合、
主に使いたがるのは、プラスチックや布などで、
動きのあるからくりについてのイメージは仕上げのイメージを
しっかり持って作っているけれど、形は布を巻きつけるといった
大胆で実験的な作り方をします。お姉ちゃんの作品を模倣することも
多いのに、いざ、自分の作品を作るとなると、
Bちゃん独特の世界が表現されるところが面白いです。


これは、Aちゃんと同じグループの小2のCちゃんが作ったテーブル。
ヨーロッパ風のドールハウスの写真に載っていたテーブルが作りたくて
細部にまでこだわって作った作品です。
Cちゃんの物作りは、まるで職人さんのようです。
「こんなものが作りたい」という思いがすごく強くて、
どんなに時間がかかっても、何回作り直すことになっても、
イメージ通りのものを作ろうと奮闘します。


Cちゃんが数ヶ月前に凝っていた靴作りとからくりハウス作りの様子は、
うまくいかない時も、投げ出さずに何度も何度も再挑戦する力
の記事で紹介しています。
(この記事のBちゃんとは、今回の記事のAちゃんのことです)

写真は同じグループのDちゃんのビー玉迷路。
Dちゃんは語彙が豊富な国語が得意な子です。以前は他の子らが工作を
する時に別の活動をしたがることが多かったのですが、最近、物作りに目覚めて
もりもり作っています。うまくいかない時、思わぬ素材を使って解決するところが
すごいです。
やわらかく変形できるアルミ箔を使ったり、ビー玉を滑らせる通路を細いストローをいかだ状に貼り合わせて
作ったりしていました。
この頃、算数の力も伸びています。

いつも、「こんなものが作りたい」という壮大なイメージを抱いているEちゃん。
工作の好きさと熱心にやり遂げる根気と意欲、考える能力の高さでは、
教室の中でも一、二を争う小2の女の子です。
「ボタンを押すと音が出るようにしたい」と奮闘していました。

Eちゃんの「こうしたい」を実現するのに、今回はいらなくなった音の出るグッズから
一部を取りだして利用することになりましたが、ボタンを押そうとすると、
貼っていたテープがはがれていくので土台を作って補強したり、
穴を開ける位置を調べるのに、わざと落ちやすいインクを穴と合致させたい部分につけて
箱に押しつけて調べたり、接続させるパーツを手作りしたりと、かなり苦労しました。

写真は、算数学習の一コマ。
『旅人算』を学習中です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ちえ子さんは 1びょう間に 2m、ひろ子さんは 1びょう間に
3m 歩きます。
①2人は 10m はなれた ところに 立っています。
これから 2人は 同時に はんたいの むきに すすみます。
8びょう後に 2人は 何m はなれていますか。
②ひろこさんは ちえ子さんより 10m 前に 立っています。
2人は 同時に 同じ むきに 歩きます。
6びょう後に 2人は 何m はなれていますか。
(最レベ2年生 130ページ)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


4人とも物作りになれているので、算数で線分図を描いて
考えるのも得意です。全員、きちんと解いていました。
AちゃんとEちゃんが、2mずつ、3mずつの矢印を一部だjけ書いて、
規則を見つけ出して、途中からは計算式で解いていました。
自分たちで、工夫する方法を考えたそうです。
そこで、みんなに、「今はすべてていねいに書いていくのもいいけれど、
AちゃんとEちゃんみたいに、こういうルールで増えているな減っているな、と気づいたら、
全部全部書かずに、そこからは計算して解くのは大事よ」と褒めて、
ふたりに、どうやって工夫したのかみんなに説明してもらいました。
それから、「でもね、よく見て考えてルールに気づいてから、全部書かずに省略するのは
いいけれど、前にこんなこと習ったなと思って、よく考えないで省略するのはダメよ。
前に、そうやって省略して大失敗をしてしまった子がいるのよ」と
注意をうながすと、全員、「どんな失敗?どんなの?」と興味しんしんでした。

そこで、こんな勝手省略、大失敗の例を見せました。
「あっ!ゼロが並んでる。知ってる、知ってる、こういう時は、9、10って
書くんだった……と左のような計算をしてしまったの。」
「えー!!どうして?」「なんで、こんな途中のところに10を書いちゃったの?」と
子どもたちはびっくり。
「それはね、1000-260みたいに
1の位がゼロのの数を引く計算を教わった時に、隣の大きな位から10を借りてきて、もう一方の隣の小さい位に1を貸すから
9になるんだなって、ちゃんと意味をわかった上で9や10を書き込むんじゃなくて、
ゼロがたくさんある数から引き算する時は、9書いて、10書いたらいいんだななんて
丸暗記をしてしまったんじゃないかしら?」
そう説明すると、「わかったわかった。1の位がゼロじゃない時も
1の位がゼロの時と同じやり方で考えないでしちゃったのね」とAちゃんが
うなずきながら言いました。
他の子らも口ぐちに、「省略する時は、ちゃんと意味がわかってる時じゃないと
ダメなんだね」と言いあっていました。