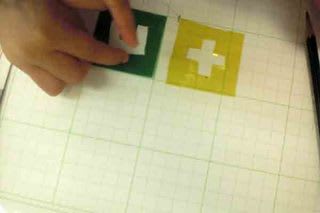レッスンに親御さんも同席していただいて、
親御さんに「子どもへの教え方のコツ」を学んでいただいた後で、
それまでどうしてうまく伝わっていなかったのか、
どういう点がわかりにくいのか見えてくることがあります。
そこで、親御さんが混乱しやすい
子どもへの教え方のコツについて、いくつか紹介していこうと思います。
昨日、午後の科学クラブは
親御さんに参観していただくことにしました。
すると、子どもだけのときは、かなり集中してさまざまな取り組みができる子たちなのですが、
日ごろ、お母さんと一緒に遊びに行ったときのモードになったようで、
自由にはじけて遊ぶ姿がありました。
それはそれで、友だち同士の協力の仕方や、問題の解決法、
長所や性質を親御さんに具体的に子どもが地を出している姿から
学んでいただけるのでよいかと思い、
子どもたちはゆるめのレッスンにして、親御さんたちにいろいろ学習していただきました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
段ボールで作った自動販売機で、100円、150円のコインを持たせて
買い物をさせるというシーンで、
★100円と50円を合わせたら、150円がわかっているか?
それがわかっている場合、100円と20円なら?
100円が2枚と50円なら?
という課題がありますよね。
★50円2枚と100円が交換できるか?
それから、
★200円を投入し、50円のおつりが返ってくる体験。
★100円2枚と50円1枚持っていて、
130円のものを買うとき、どの2枚を出すとおつりが少なくてすむか。
そのように、段ボールに穴をあけただけの自動販売機ごっこで、
どんどんお金や大きな数への理解度をあげていくことができます。
親がそうしたゆるやかな段階にどんなものがあるかを把握していることで、
算数の文章題でも、国語の読解でも
簡単に解けるように、勉強時間をあえてとらなくても
子どもを導いていくことができます。
よくブログでは「教えすぎない」と書いているのですが、
正確には、
「まだ子どもがその概念を理解していない場合、無理矢理わからせようと
がんばらない」という意味で、
何ひとつ教えてはダメという意味ではないのです。
はじめて知識に触れるとき、子どもの中で、その情報に関する
「おわん」ができます。
それにいろんな体験で、ポタン、ポタン、しずくのような情報がたまっていって、
あるときそれがあふれるとき、理解するのです。
「教えすぎない」とは、
おわんを作って、集中豪雨を浴びせて、無茶して
水をあふれさせたらいけない……という意味なのです。
まだ書くことがおぼつかない子に、
文字をていねいになぞることを徹底すれば、
なぞるべきでない、アバウトに捉えて描く場面でも、なぞることしかできなく
なってしまいますよね。
知的にも、身体の技術としても、自然に自分で欲して理解にいたる時期でないと、思い込みや勘違いをたくさん生んでしまうのです。
プリント学習の教室に通っている子が、
どう見ても引き算の文章題を足し算で解くので、
どのように考えたのかたずねると、
「1つ前の問題が、引き算の時はいつも引き算だから」という答え。
(その子の教室のプリントは、1問目が引き算の場合、すべて、
引き算の問題で構成されているそうなのです)
わかっていないときに、正解するために編み出す方法は、
場面が変わると通用しなくなる例ですね。
先ほどのお金でしたら、両替がわからない子には、
その場で教え込むのでなく、
買い物やお手伝いなど、さまざまな場面で、両替をする体験を増やして
あげることだけでしいのです。
1回ですべてわからせようとすることから、
うろ覚えの理解が生じます。
子どもの自然な知力の発達を見守りながら、
新しい「おわん」を作っては、どこでも、ポタンポタン水がたまり続けている
状態にすることが
親のちょうど良い教え方だと考えています。
他のポイントは、またの機会に書きますね。

web拍手を送る)
親御さんに「子どもへの教え方のコツ」を学んでいただいた後で、
それまでどうしてうまく伝わっていなかったのか、
どういう点がわかりにくいのか見えてくることがあります。
そこで、親御さんが混乱しやすい
子どもへの教え方のコツについて、いくつか紹介していこうと思います。
昨日、午後の科学クラブは
親御さんに参観していただくことにしました。
すると、子どもだけのときは、かなり集中してさまざまな取り組みができる子たちなのですが、
日ごろ、お母さんと一緒に遊びに行ったときのモードになったようで、
自由にはじけて遊ぶ姿がありました。
それはそれで、友だち同士の協力の仕方や、問題の解決法、
長所や性質を親御さんに具体的に子どもが地を出している姿から
学んでいただけるのでよいかと思い、
子どもたちはゆるめのレッスンにして、親御さんたちにいろいろ学習していただきました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
段ボールで作った自動販売機で、100円、150円のコインを持たせて
買い物をさせるというシーンで、
★100円と50円を合わせたら、150円がわかっているか?
それがわかっている場合、100円と20円なら?
100円が2枚と50円なら?
という課題がありますよね。
★50円2枚と100円が交換できるか?
それから、
★200円を投入し、50円のおつりが返ってくる体験。
★100円2枚と50円1枚持っていて、
130円のものを買うとき、どの2枚を出すとおつりが少なくてすむか。
そのように、段ボールに穴をあけただけの自動販売機ごっこで、
どんどんお金や大きな数への理解度をあげていくことができます。
親がそうしたゆるやかな段階にどんなものがあるかを把握していることで、
算数の文章題でも、国語の読解でも
簡単に解けるように、勉強時間をあえてとらなくても
子どもを導いていくことができます。
よくブログでは「教えすぎない」と書いているのですが、
正確には、
「まだ子どもがその概念を理解していない場合、無理矢理わからせようと
がんばらない」という意味で、
何ひとつ教えてはダメという意味ではないのです。
はじめて知識に触れるとき、子どもの中で、その情報に関する
「おわん」ができます。
それにいろんな体験で、ポタン、ポタン、しずくのような情報がたまっていって、
あるときそれがあふれるとき、理解するのです。
「教えすぎない」とは、
おわんを作って、集中豪雨を浴びせて、無茶して
水をあふれさせたらいけない……という意味なのです。
まだ書くことがおぼつかない子に、
文字をていねいになぞることを徹底すれば、
なぞるべきでない、アバウトに捉えて描く場面でも、なぞることしかできなく
なってしまいますよね。
知的にも、身体の技術としても、自然に自分で欲して理解にいたる時期でないと、思い込みや勘違いをたくさん生んでしまうのです。
プリント学習の教室に通っている子が、
どう見ても引き算の文章題を足し算で解くので、
どのように考えたのかたずねると、
「1つ前の問題が、引き算の時はいつも引き算だから」という答え。
(その子の教室のプリントは、1問目が引き算の場合、すべて、
引き算の問題で構成されているそうなのです)
わかっていないときに、正解するために編み出す方法は、
場面が変わると通用しなくなる例ですね。
先ほどのお金でしたら、両替がわからない子には、
その場で教え込むのでなく、
買い物やお手伝いなど、さまざまな場面で、両替をする体験を増やして
あげることだけでしいのです。
1回ですべてわからせようとすることから、
うろ覚えの理解が生じます。
子どもの自然な知力の発達を見守りながら、
新しい「おわん」を作っては、どこでも、ポタンポタン水がたまり続けている
状態にすることが
親のちょうど良い教え方だと考えています。
他のポイントは、またの機会に書きますね。
web拍手を送る)