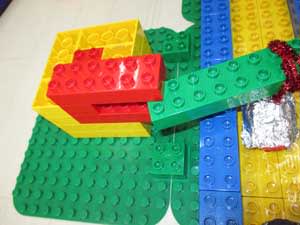『ひとがひとをわかるということ 間主観性と相互主体性』という本の中に
こんなエピソードが紹介されています。
著者の鮫岡峻先生が「主体として受け止める」とはどういうことなのか、
奥さんと議論するうち、奥さんがこう言ったそうです。
「むずかって泣いている赤ちゃんを一個の主体として受け止めるときに母親(養育者)に
できることは、『おお、よしよし』なのよ。泣きやませようとすることではないのよ」。
この奥さんの一言に、鮫岡先生は、はっと気づかされたそうです。
養育者も一個の欲望の主体。自分のペースで事を進めたい気持ちがあるはずです。
むずかりを鎮めたいという養育者の主体としての思いが先行すれば、
「泣きやませよう」と強く働きかけてしまいます。
しかし、その思いがありながら、なおむずかっている我が子を主体として受け止めようと
するとき、必死にこらえながら「おお、よしよし」ではなく、
ゆったり落ち着いて、自分も主体としておりながらの「おお、よしよし」であり、
「赤ちゃんにも泣きたい気持ちがあるのだ」と鷹揚に受け止める態度なのだとか。
このエピソードを読みながら、
子どもが意欲、意思、意図などを持った一個の主体として 目覚めていくには、
親の側に、子どもの姿を「ひとりの人」として受け止めていく態度が必要なんだな、
と再認しました。
それと同時に、
子どもが個性を持った親とは別の主体であるにもかかわらず、
早期教育のシナリオには、
前もって親が子どもから何を受け取るのか書きこまれていることに
早期教育の危険性があるのかも、とも感じました。
早期教育の情報をもとに子育てすると(早期教育情報で頭をパンパンにして子どもと
対面すると)、知らず知らず、自分が受け取りたいものを受け取って、
受け取りたくないものや関心がないものはスルーしがちになるでしょうから。
もちろん、親になった人がみんな
鮫岡先生の奥さんのような鷹揚に構えた「おお、よしよし」ができるとは限りません。
でも、「なあに?」「どうしたの?」と戸惑いながら、
子どもの発しているものを読みとろうしていたら、だんだん思いが通じあっていくという
自然なプロセスを踏んでいくことでしょう。
問題なのは、子どもの気持ちや思いなんて少しも受け止めていないのに、
子どもが一個の主体として成長していく様にきちんと付き合えていないのに、
早期教育から得られる「成果」や「結果」や親同士の情報交換のせいで
親だけが欲望の主体として暴走していても、
自分で自分にブレーキをかけられなくなることかもしれません。
鮫岡峻先生によると、
人は、どこまでも自分を貫きたいという「自己充足性」と、
常に誰かと繋がれて安心を得たいという「繋合希求性」という相矛盾する欲望を抱えた
存在なのだそうです。
ですから、お互いが主体として生きようとすれば、対立や摩擦は避けられないし、
葛藤状態があるからこそ喜怒哀楽が生まれてくるのだとか。
子どもが主体として育つためには(子どもと養育者は対等な関係にないので)、
一個の主体として成長を遂げた養育者が、子どもを懐深く一個の主体として受け止め、
主体として育つのを支え、待つことが不可欠なのだそうです。
(『ひとがひとをわかるということ 間主観性と相互主体性』 鮫岡峻著/ミネルヴァ書房)
親自身が「子ども」から「大人」に成長できていないと、数値で子どもを管理したがるのでは?
この記事を書き終えたとき、こんなコメントをいただきました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
はじめまして。素晴らしい内容の数々に本当にいろいろなことを教えられ、
考えさせらております。
3歳男児を二人育てております。最近特に、言うことを聞かなくなってきて、
いらいらすることが多くなったのですが、先生の書いていらっしゃることを読むにつれ、ふと、
〝言うことを聞かせる″ことに躍起になっている自分、のおかしなメンタリティーに
気が付かされました。指摘したことを直すのが目的ではなく、私の主張を通す、ことが
目的になっていたのです。
早期教育に関してもしかり(大したことはしていないのですが・・・)。
育児とは不安の塊で、特に第一子はわからないことだらけ。″遅れをとるまい”と
右往左往しているうちに、やっぱり、子供という一人の人間、が置き去りになり、
手軽に測れるインプットーアウトプットに夢中になり、”子供のため”という大義名分が、
結局私の、″ほら見て、うちの子こんなこともできちゃってすごいでしょう!”という
自己満足が目的にすり替わっていってしまっていたのですね。だからプリントが予想通りに
できないといらいらする。目的はそこではないのに。
独り言のコメントでごめんなさい。いろんなことがすっきりしました。
襟を正し、再び子供をしっかり見て理解する、ことからはじめたいと思います。
ありがとうございました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
伝えたいことがうまく表現できなくて心配していたけれど、言葉の背後にあるものを
きちんと受け止めてくださっていることに、ほっとすると同時にうれしくなりました。