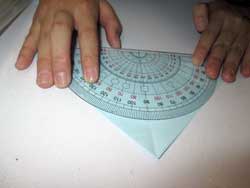『だんだんややこしくなっていく子、どんどん成長していく子』というタイトルで
書いた過去記事です。
今回の記事と関連がある(リンク先の正解を急ぐ子育ての部分から)ので、
紹介させていただきます。
このところずっと、
「保育士おとーちゃんの子育て日記」というブログを読ませていただいています。
現在の家庭の育児の危うさ、保育の危機、虐待について、子どもの人格形成のこと、
早期教育の問題点、日本の子育て文化の落とし穴について……。
どれも日々実感していることばかりで深く共感しながら読ませていただきました。
特に次の一連の記事は、虹色教室でも常々、頭を悩ませている点で(それを解消する
ために親子同室のベビーレッスン、2・3歳児用のグループレッスンを始めた経緯が
あるほどです)。ぜひ、多くの方に読んでいただきたいと思いました。
現代の子育ての落とし穴 「いい子・できる子」
現代の子育ての落とし穴 「いい子・できる子」 2 「抑圧ポイント」
現代の子育ての落とし穴 「いい子・できる子」 3 「抑圧された子」
現代の子育ての落とし穴 「いい子・できる子」 4
現代の子育ての落とし穴 「いい子・できる子」 5 「認可園と認証保育所」
今回、わたしが書こうとしている記事は、この「いい子・できる子」という話題とは
ちょっと異なるのですが、重なる部分も大いにあります。
前にも一度記事にしたことがあるのですが、虹色教室にもごくごくたまに
「だんだんややこしくなっていく子」というのがいます。
大多数は「どんどん成長していく子」ですが、
少数ながら、その中間の「ややこしくはならないけれど、あまり成長が見られない子」
というのもいます。
子どもとたくさん接しているうちについた勘なのか、
親御さんの子どもとの関わり方を見ていると、
その先、どれに行きつくのか、特に「これはだんだんややこしくなっていきそう」
というケースは即座にピンとくるようなところがあります。
子どもの障害のあるなし、その重い低い、
問題行動の多い少ない、知力の高低に関わらないのが不思議です。
子どもがある時点でさまざまな発達上の遅れを抱えていても、
それが非常に深刻なものだったとしても、親御さんの関わり方を見ていると、
「ああ、この子は大丈夫」と感じることは多々あって、
実際、半年なり1年するとみちがえるように成長していくのを実感しています。
でも、「あんまりダメ出しばかりしていると、混乱したり、子育てを続けていく
エネルギーが枯れてきたりしそうだから、言うに言えないけれど、
このままいったらややこしい子に育っていきそう」とヒヤヒヤしながら
見守っている方の場合、子ども自身はハンディーキャップもないし、
知力もしっかりしているという子であっても、
十中八九、すごく扱いにくい子になったり、学習面で伸び悩んだり、社会性の面で
幼さが目立つようになったりしていくのです。
それなら、その「ややこしい子になりそう」という勘は
何を根拠にどんな基準のもとで
「大丈夫」「危なっかしい」と判別しているのかというと、
それが世間一般の常識的な子育ての良し悪しの判断とはかなりずれている
わたし独自の感じ方であって、上手く言葉にできるか自信がありません。
それでも、保育士おとーちゃんさんの言葉を借りなどしながら、
何とか説明していこうと思います。
幼稚園や保育所、小学校などには
「虐待寸前」「子どもをどなったり、叩いたりしてしまう」
「子どもがかわいく思えない」「早期教育に走って子どもを競争に追い立てている」
といった、誰の目から見ても子どもの育て方に危なっかしさを感じさせる親御さん
というのも、一定数存在していることと思います。
でも虹色教室にいらっしゃる方というのは、
そんな無茶な子育てをしている方というのはまずいらっしゃらなくて、
問題があると言ったって、せいぜいちょっと甘やかしすぎるか、
ちょっと干渉しすぎるか、ちょっと心配しすぎるか、ちょっと放任しすぎるか、
ちょっと期待をかけすぎちゃうか、といった程度のものです。
それもたいていは、月に一度とか2ヶ月に一度でも教室に通っていただくうちに
良い具合に接し方の加減をマスターして、
「親子共々成長していってるな~、ついでにわたしもそれに便乗して成長させて
いただいたな」と思っているうちに、
子どもの目を見張るような成長ぶりや個性のすばらしさの発露に、
親御さんもわたしも感激し、
子どもは自信に満ちてくるという流れを何度も繰り返し体験してきました。
そうした親御さんと、
「だんだんややこしくなっていく子」や
「ややこしくはならないけれど、あまり成長が見られない子」の親御さんに
大差はありません。
非常に言語化しにくい事柄で誤解を承知で書くならば、
子どもの成長の足を引っ張りぎみな親御さんというのは、
「子育てには興味があるけれど、その子自身にはあまり関心がないようだなぁ」
と見えるのです。
子育てブログや幼児教育ブログの文面から、それを感じ取ることもよくあります。
「見たところ、子どもに過剰なほど関心があるようでいて、その子が大好きなもの、
その子を笑顔にして夢中にさせるものは必ず軽く扱うなぁ、
幼稚っぽいもの、くだらないものという判断をくだすなぁ」と感じるのです。
それこそ、しょっちゅうギューっと抱きしめたり、
子どもの喜ぶ場所にあちこち連れて行ったり、
外遊びをさせたり、子どもをのびのびと育む園を選んだり、より良いおもちゃや服を
買いそろえたりしている方なのに、
「この方は子育てには興味はあるし、すばらしい子育てをしようとしているけれど、
その子自身には、その子の内面には少しも興味がないんだな」と感じることが
あるのです。
案外、「わたしは良い親になれない。叱りすぎてしまう」など悩みつつ子育てしている
方にはそれほど問題はなくて、
「良い親」と周囲から認められるバリエーションをすべてこなして
自他共に良い親をしているとがんばっている方が、わたしの目からすると、
その方の子どもにまったく関心がないように感じられることって大いにあるのです。
子育てが上手くいかないと悩んでいる方の、上手くいかないと感じておられる原因は
だいたい次の3つのどれかに当てはまるのではないかと思っています。
①親の子育て態度が、子どもに対して強圧的で支配的に振舞っているか、
子どもの言いなりになって振り回され気味になっているか、
そのどちらかに大きくぶれている。
保育士おとーちゃんの子育て日記 では
相談 「弱い大人」と「強い大人」
という記事で説明されています。
②子どもに発達障害や感覚統合の問題などがあるのに気付いていないか、
それから目を逸らしている。
障害については理解し受け止めているけれど、障害名に踊らされて、
わが子自身が見えにくくなっている。
③子育てや子どもの教育に強い関心がある一方で、わが子そのものに関心が薄い。
世間的により良いとされるものや、自分好みの子育てがしたくて、
わが子の喜びや好みに注意がいかない。自分の子を笑顔にするものに興味がない。
自分が喜んでもらいたい、わが子に好きになってもらいたいと期待するものにだけ、
わが子の喜びや興味を感知して、それ以外は無意識にスルーしている。
それでも、ほかの人がいる場では、子どもの喜びが自分の喜びであるような
感情表現をしているため、自分自身でさえ自分の子に関心がないことに気づいていない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
以前、一度だけブロック講座に参加させていただいたandoです
今回書いてある、子供が喜ぶかより習い事に行かせ、
たくさんの知育玩具を与えることが教育のすべてであり、賢くすることだけが
子供にとってよいことだと奈緒美先生の教室を知るまで信じていました。
最近、ブログを読みながら日々勉強をしているのですが、しかし、読んで納得は
するのですが子供との接し方、自分の子供が何に喜び何が嫌なのかわからないのです。
(恥ずかしながら、主人に対してもと思ったり)
最近、子供が嫌なことがあると大声を出したり、手を出したりするようになり、
私の接し方に問題があるのかなと思うんですが、あまり怒ったことがないので、
周りからは甘やかしすぎと言われたり、子供に対してどのように接すればいいのか
わかりません。
ブロック講座で、椅子を投げられたお子様がおられ、
講座終了後、そのお母様とお話をされるというので、その間いい子だったら
粘土遊びをしてもいいというやり取りをされていて、
それを聞いた息子が「僕もいい子だったよね、だから粘土遊びしてもいい?」と
言ってきました。私は息子の言葉を無視するかのように教室を出たのですが(どう
対応すればいいかわからず)、最近「僕はいい子」という言葉が度々でてきます。
直接言ったことはないのに、いい子であるということを基準に叱ったり褒めたり
していることがこの子にこういう発言をさせているのでしょうか?
一度だけしか教室に行ってないのですが、
覚えていらしたら気づいたことなどがあれば教えていただきたいです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
まず、この日の未就園児のブロック講座であった出来事について説明させてください。
この日、一人の3歳の男の子が荒れ気味で、「それやりたい」「それほしい」と
自分の我を通すのに大声をあげたり、相手から無理やり奪い取ろうとしたりして
いました。
終いには、プラスチック製の軽い幼児椅子を本人なりに加減して
誰にもあたらない方向にですが、投げることまでしました。
好き放題に乱暴をするというより、物に当たり散らしたという程度なのですが、
この日のかんしゃくの出し方はその子のお母さんにとってもわたしにとっても
いささか呆気にとられるような度合いでした。
この子は数ヶ月前から月に1度の通常レッスンにも通っている子で、
それまでも我慢が苦手だったり、思い通りにいかないことがあると、次第に声を荒げて
いきながらお母さんに反抗する姿はありましたが、
目立って激しいものではなかったのです。
この子のお母さんは気持ちが優しい常識的できちんとした方で、
誰の目から見ても安心できるようなていねいな子育てをしておられる方です。
この子にしても、少し衝動的で落ち着きがないところがあるものの
利発で素直な性質の子でした。
ただこの子とお母さんの関係には気になるところもありました。
お母さんはその子とはかなり年が離れた上のお子さんの子育てで、
「厳しくしつけようとしすぎたために失敗してしまったな」という挫折感を
抱いておられました。
本当は失敗などではないのかもしれません。思春期の子というのは
どの子もややこしいものですから。
そのため、この子がかんしゃくを起こし始めると、
自分のやり方が間違っていたという思いがブレーキとなって、
腫れものに触るような接し方になりがちでした。
周囲にとても気を使う方で非常に細かなことまで気付いて
喉元まで声が出かかっているのに、親としての自分の出方に自信がなくなって、
毅然とした態度が取れずにいたのです。
自分が我を張るたびにお母さんが下手に出ていると、子どもの方は、
どこまでなら許されるのか限界に挑戦するようになります。
また自分で自分の感情をセーブしていく力が育たなかったり、
叱られてはいないけれど、自分が悪いことをしているという不安な精神状態を高ぶらせて
いったりします。
その子の態度も、徐々にですがエスカレートしつつありました。
ブロック講座があった頃は、ほかの心労もいろいろと重なって
その方の親としての自信が一番揺らいでいた時期だったようです。
ブロック講座の日、聞き分けのなさがピークに達し、わたしに対しても
わがままの限りを尽くして自分の言いなりになるように挑戦してくるその子の姿を見て、
これは、きちんと対処しておかなくてはならない分岐点だとは思いました。
そこで、そのレッスンのあとで、今後の対応などについてゆっくりお話しました。
するとこのお母さんはもともと判断力のあるしっかりしている方ですから、
それ以来、生活や子どもとの関わり方の見直して、改善に努めておられました。
するとその後は、その子の短所のかんしゃくの激しさはおさまってきていて、
長所である頭の良さや創造力や想像力の豊かさなどが伸びてきています。
お母さんの子育てのあり方が、弱いや強いに偏っているとき、
子どもの側から、いったんその関係を壊して立て直すことを求めるかのような
挑戦的な態度が出てくることがあるんですね。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
前置きが長くなってしまったのですが、
ブロック講座の日にお会いした
andoさんのお子さんについて、記憶している限りでお返事させていただきますね。
この子はおりこうさんではあるけれど、
まだ自分というものがしっかり育っていない印象をお受けしました。
自分の意志や自分の考えといったものがはっきりしていなくて、
自分が何が好きかとか、何をやったら楽しいかとか、自分はこういう子だとか、
自分は何がやってみたいかといったことが漠然としていてわからない……といった
感じです。
いただいたコメントに「 子供が喜ぶかより習い事に行かせ、
たくさんの知育玩具を与えることが教育のすべてであり賢くすることだけが
子供にとってよいことだと奈緒美先生の教室を知るまで信じていました」と書いて
おられましたよね。
もしかしたら、お子さんはそうしたお母さんの与えてくれるものや
期待するものを受動的に受け取ることを続けるうちに
自発的に能動的に外の世界に関わって行こうとする自分のエネルギーの源のようなもの
との接点を、失ってしまったのではないかと思います。
また、「ぼくも粘土したいなぁ」や「いいなぁ。ぼくもやっていい?」という自分を
主語にした話し方ではなく、
「僕もいい子だったよねだから粘土遊びしてもいい?」というお母さんの気持ちを
優先するような願望の表現の仕方は、
保育士おとーちゃんの子育て日記の
現代の子育ての落とし穴 「いい子・できる子」 2 「抑圧ポイント」
に書かれているような、いつも大人の理詰めの正しさの前で
自分の心の中に浮かんできたり渦巻いたりしている感情や思いを
ないもののように扱われてきたために、大人の判断や気持ちに媚びるような
問い方になっているのかな、とも思われました。
andoさんのお子さんは穏やかな気質のおっとりした感じの男の子ですから、
もしそうした子が大声を出したり、叩いたりするようになっているとすれば、
自分を自然に出していい場面で抑圧を受けることが続いて、
それが一気に噴き出しているのかもしれません。
また、2歳くらいからはじまる反抗期が
それまでのお母さんとの関係のあり方のせいで、ちょっとゆがんだ
複雑な表われ方をしているのかもしれません。
わたしには、その日、
andoさんがよりよい子育てをしよう、子育てで成果をあげよう、として行動や
環境の一つひとつを言語でチェックしているため、
お子さんのありのままの姿を感受したり、気持ちの流れに気づいたりする力が
弱まっているように見えました。
といってもいきなり自分の子育てを全否定したり、180度いいものに変えようとしても
うまくいかないはずです。それに、これまでかわいがって育ててきたからこそ
穏やかな性質のいい子に育ってきているはずですよね。
子育てに100%の成功なんてないように、100%の失敗だってないはずです。
子どもが大きな声を上げたり、叩いたりするときには、
それ自体に対する「それはいけないこと!」と毅然とした親の態度で示す必要がある
でしょうが、それと同時にもう少し積極的な対応が必要なのかもしれません。
それについては、過去記事の
わがまますぎる要求にどう対応すればいいでしょう?
で説明しています。よかったら読んでくださいね。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
続きを読んでくださる方は、次のリンク先に飛んでくださいね。
だんだんややこしくなっていく子、どんどん成長していく子 3
だんだんややこしくなっていく子、どんどん成長していく子 4
だんだんややこしくなっていく子、どんどん成長していく子 5
だんだんややこしくなっていく子、どんどん成長していく子 6
タイトルは異なるけれど、
だんだんややこしくなっていく子、どんどん成長していく子の続きです。
結果を急ぐ子育て 最初から正解を用意している子育て 1
結果を急ぐ子育て 最初から正解を用意している子育て 2
結果を急ぐ子育て 最初から正解を用意している子育て 3
結果を急ぐ子育て 最初から正解を用意している子育て 4
上の記事で登場しているやんちゃくんたち……記事を読んだお母さん方が、
子どもとの関わり方をていねいに調整していかれて、
現在は、とても賢くてしっかりした協調性のある社会性の高い子に成長しています。