
展開図への興味につながる簡単な工作アイデアを紹介します。

最近のお菓子の箱は形が、かばんのように見えるかわいらしいものが
けっこうあります。

お菓子の箱の底の糊をはがしてぺったんこにして、作りたいサイズに切ります。

側面を切って箱を開きます。

底の幅だけ切り込みを入れます。

切り込みを折って組み立てます。

ビーズや紙で留め具を作ります。

輪ゴムを貼る時に、上からホッチキスでとめるとはずれにくくなります。
危ないので上からテープでカバーします。

取っ手をつけたらこんな感じ。

展開図への興味につながる簡単な工作アイデアを紹介します。

最近のお菓子の箱は形が、かばんのように見えるかわいらしいものが
けっこうあります。

お菓子の箱の底の糊をはがしてぺったんこにして、作りたいサイズに切ります。

側面を切って箱を開きます。

底の幅だけ切り込みを入れます。

切り込みを折って組み立てます。

ビーズや紙で留め具を作ります。

輪ゴムを貼る時に、上からホッチキスでとめるとはずれにくくなります。
危ないので上からテープでカバーします。

取っ手をつけたらこんな感じ。

3歳1ヶ月の★くんともうすぐ2歳になる●くんのレッスンで。
★くんはブロック大好きの子鉄くん。
そんな★くんに憧れている●くんは、★くんのすることは何でも
吸いこまれるように見つめています。
「こうやって、こうやってしたら、新しい大阪駅とそっくりになるね~」と
★くんのお母さんがブロックで駅の2階部分を作って見せると、
●くんは真剣な顔つきで説明に耳を傾けていました。

その間、★くんはお家の2階部分から階段を作りたかった模様。
自分でがんばって工夫していました。
★くんは、ブロックで動きを作りだすことに興味を持ち始めていて、
「作った駅に前後に動く部分を取り付けたい」と一生懸命説明していました。
★くんとてもアイデアマンで自分で考えるのが得意な子です。
お家じゃ年長さんのお姉ちゃんも★くんの発想に乗っかって遊んでいるそうです。

マジックボールで遊んでいます。
マジックボールを飛ばすマシーンを手作りすることにしました。


はさみで切ってテープをつけたら、2分でできあがり。よく飛びます。

カード遊び。●くんは、物の名前と特徴でカードを取ります。
★くんは、「文房具」とか「遊具」といった大きなグループでカード探しをして
遊んでいます。

●くんは、物の扱い方についての勘がいいようです。★くんと上手に遊んでいます。

トーマスゲームを出してみて……。まだルール通りきちんと遊ぶ根気はないけれど、
コマを選んで数字を読んでごきげんです。

●くんが大好きな阪急電車の車掌さんの帽子を作りました。
算数遊びでは、意欲満々の★くんの取り組み方を見て、
●くんも1や2の指を作ろうとして一生懸命でした。

初めて虹色教室に来てくれた3歳6ヶ月の★くん。
頭の回転がいいしっかりした印象の男の子です。
いろんなものに興味をしめして、「やりたい!」と意欲的です。
けれど、いざゲームや工作やブロック製作をやりはじめると、
すぐさま飽きて別のものを触りに行こうとします。
まだ3歳ですし、これまで教室での体験を積んでいるわけでもありませんから、
すぐに目移りして集中できないのはしかたがありません。
しかし、★くんが意欲的に取り組み出したとたん、★くんがだんだんやる気がそれて、
投げやりな態度になるような、あれこれ口を出してしまう★くんのお母さんには
何度もダメ出しをすることになってしまいました。
(申し訳ありません~ )
)
★くんのお母さんは余裕を持って子育てをされている落ち着いた方です。
過干渉というわけではないのですが、
★くんが何かに取り組み出すと、優しい口調でスローステップで先を示して
誘導することが習慣になっているようでした。
たとえば、★くんが「(紙コップの)エレベーター作る~」と言ったとすると、
「さ、先生の方見て」「コップを持って、それから~するのよ」
「あっそれはちがうよ。よく見てごらん」
「ほら、次はどこに貼るんだったかなぁ?」と言う感じに、
★くんの次の行動をわかりやすい言葉で提示していくのです。
また、★くんに「今度は何するのかな?」「どれがしたいの?」「それはなあに?」
「次はどうするんだった?」とたえず質問を投げかけてもいました。
わたしは失礼とは思いつつも、「そんなに質問ばかりされては会話するのが楽しくないし、
次に何をするかは本人が自由にやってみるまでわからないので、
先にこういうことをさせようと大人が決めたり、こういうことがしたいんだなと
勝手に解釈して指示を出してしまっては、どの取り組みもつまらなくなって
飽きてしまいます」とお伝えしました。
その後も★くんのお母さんはついつい先回りして誘導するような指示を
出していたんですが、
そのたびに、★くんの集中力が途切れて、別のことを始めたり、
「もうおしまい?もうするのはやめるの?」とたずねても、
グズグズとそれに答えようとしないで別の遊びをする様子を見て、
自分の言葉と★くんの困った態度のつながりにはっと気づいたようでした。
とても勘がよくて、物分かりがいい親御さんなのです。
そうしてしばらくお母さんには言葉を控えていただいて、
わたしが直に★くんと対応することにしました。

お母さんがいつも次の指示を出してくれていたので、
★くんはお手本を見るのがとても苦手です。
わたしが作った紙コップのブランコを見て、「ぼくも作る~」と
紙コップを切って、ひもも手にいれたものの、
「ブランコにならない、できない~できない~」とぐずぐず言いだしました。
ひもをセロテープでつけることはわかっているのでしょうが、いつもならお母さんが、
「次は何をするんだったかな?ほら、あそこにテープがあるよね。
それを、取って~それから、どこにペタンとするのかな~?」と言ってくれる
はずなのに、何も言ってくれないものですから、
「できない~できない~」と言い続けて誰かに何かしてもらうのを
待っているようでした。

しばらく黙って見ていると、
ケロッとして「あ~セロテープでつければいいや」と言うと、自分でテープをとって
ちゃっちゃと作ってみせました。
わたしの見本とはちがうけれど自信ありげです。
「うまくできたね。これがツーッてケーブルカーみたいに
動くようにしてあげようか?」とたずねると、大喜びしていました。
★くんが「やりたい」と言いだした時に、危険がない限り失敗しそうでも本人の
思うようにさせて、上手にできたところや、次の活動の指針になりそうな部分を、
「テープ切る時に危なくないように引っぱっれているね」
「最後までがんばって切れたね」「ひもがいるのによく気がついたね」などと
言葉で振り返らせます。
★くんは自分で失敗しながらやったことは
長い間しっかり関わることができるようになっていました。

★くん作の移動できる乗り物。モノも運べます。

左横でぶらさがっている紙コップは1歳の弟くんのブランコです。
そのまんまの紙コップにテープでひもを貼ると、立派なブランコになりました。


エレベーターです。

野球ゲームを作りたがったので、アイスの棒に楊枝を貼って
玉を打つバッドの部分を作りました。輪ゴムを引っ掛けているので、
アイスの棒を手前に少し引いて手を放すと玉を打つことができます。

Aくんはやんちゃで衝動性が強くひとつのことに集中できない一面と
秩序のある美しいものが好きで完璧主義で好きなことに深く集中する一面という
正反対の性質を併せ持った男の子です。
同年代の子といっしょの時はわくわくするあまり気持ちが高まって
自己コントロールがききにくくなるため、個人レッスンに切り替えて、
Aくんがやりたいことをとことんやりつくすことができるような
環境を用意するようにしています。
そうして、Aくんという子とじっくり関わってみると、
この子は面白い子だなぁ、賢い子だなぁ、やんちゃさの背後にこんなに繊細で
優しい性質が隠れていたんだな、ちょっとした刺激に影響されやすくて、
おふざけ全開モードになっている時は遊びの成り立ちにくさが気になっていたけど、
環境次第で上手くいかないことが続いても何度もチャレンジしなおすほど
エネルギッシュにひとつのことに集中できる子なんだな、
とAくん独自の魅力が浮き彫りになってきます。
この日、Aくんが興味を持ったのは、他のグループの子が作って帰った
警察署の車を上らせていくための坂の部分でした。
その上にビー玉を落とす仕かけを取りつけて、
大きいサイズのビー玉を落として遊びだしました。
Aくんは実験が大好きです。
他の子らとブロックでミニ四駆のレース場を作った際、ゴールのトンネルに
ティッシュペーパーを挟んでおいたら、
車がそれを突き破って走っていった話に強い関心をしめしました。
ビー玉を滑らせる坂の途中にトンネルを作り、
ティッシュペーパーを挟んでみることにしました。


突き破って滑っていくのかと思いきや……この通り。
とても感心したのは、
もっと高いところからビー玉が落ちるようにしたらいいんじゃないか」
「もっとビー玉をたくさん転がしたらいいんじゃないか」
と試行錯誤するAくんの根気とていねいさ。
何度やっても上手くいかなくても、驚くほどへこたれないし、
それは熱心に、条件をひとつずつ慎重に変えていきました。
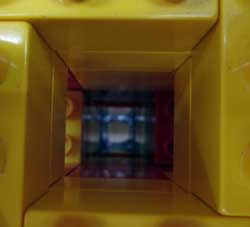

どの条件でティッシュペーパーが破れるのかわかった後で、
ビー玉の落下装置にアルミ箔をはさんでみることにしました。
はじめ、簡単に破れてしまったのですが、
Aくんの「アルミ箔をボコッとさせて、ビー玉が入るようにしたら?」という意見を
取り入れて、アルミ箔をピンッと張らずにブロックに挟んだところ、
ビー玉を落としても穴が空きませんでした。
面白かったのは、
意外なほど予測がはずれてしまうことです。
見た感じこだろうと踏んでいても、
実際にやってみると思ってもみなかったような結果を得るのです。



先月のブロック講座まではAくの作品は平面が主でしたが、
ほんのひと月ほどで物を立体的に組み立てるのが得意になっていました。
あってという間にビー玉を落とす道具やサッカーゲームなどを
ブロックで作っていました。
Aくんの個性にゆったりと関わったことが功を奏したのか、
算数の学習でもすばらしい集中力と実力を発揮してくれました。
年長と小学1年生の子たちのグループレッスンで。
レッスンのはじめに、『プログラミン』という子ども向けの
プログラミング体験用アプリケーションで少し遊びました。
(文部科学省が提供している無料のアプリケーションです。)
選んだキャラクターを動かす際、いたずらっ子のAちゃんが、
1秒間に進む値に、「1000」とか「10000」なんて
大きな数を入れるので、目にもとまらぬ速さでキャラクターが動いていました。
いっしょにパソコン画面を覗きこんでいた子どもたちは、大笑い。
普段、大きい数といえば、たくさん物がある様子をイメージするのですが、
大きい数が、スピードとして目に見えるものになったことは
子どもたちにとって新鮮だったようです。


リニアモーターカーの科学工作キットを組み立てる際、
銅箔のシートを20×210㎜にはさみで切る作業がありました。
「ものさしの目盛を見ると、2と21なのに、説明書に20×210とある理由は?」
と、目盛を見ながら考えました。
ミリメートルの目盛は、まるでまつ毛が並んでいるように見えますね。
ものさしを扱うついでに、折り紙の一辺を測ってみたら15センチでした。
Bちゃんが家からお気に入りの犬のぬいぐるみを持参していたので、
折り紙に乗せてみると、犬の鼻先だけ折り紙から出ています。
「犬は何センチくらいだと思う?」とたずねると、
Aちゃんが、「折り紙が15センチなんだから、17センチくらいでしょ」と言い、
BちゃんとCちゃんは、「16センチ」と言いました。

そこで、Aちゃんに協力してもらって犬の身長測定をすることにしました。

ものさしとブロックで身長計風に。
15センチ4ミリメートルでした。
つまり154ミリメートル。
こんなふうに、遊びや工作で出会う数や形が子どもたちの心に響いた時、
それをちょっと深めるような取り組みをしています。
今回のレッスンでした紙コップ人形やびっくり箱作りの途中でも、
数や形の世界の不思議さや魅力に触れる場面がありました。

工作タイム。
1年生の女の子たちは、新しい技術の習得にとても熱心でした。
じゃばらの折り方、箱の留め具の作り方、りぼんの作り方など。
ソファを作るのに、平行な辺の長さをそろえること、四角い箱の蓋の周りを
モールで囲うと、ひとつの辺の長さの4倍のモールが必要なことを学びました。











ずいぶん間が空きましたが、
の続きです。
出先で、『0歳から6歳までの困った子が変わる育て方』という本を買ってきました。
育児や教育、子どもの心理を研究する専門家として
1万2000人以上の子どもを見てきたとおっしゃる、
日本キッズコーチング協会理事長の竹内エリカさんの著書。
「子どもの性格は育った環境の影響を受けるといわれるけれど、
生まれながらに、ある程度の個性を持っていることも事実」
「気質に合った育て方をすれば、成長して社会性が身につくとともに自然と
問題行動もなくなりますので、あまり心配する必はありません」と主張しておられる
竹内エリカさんは、子どもの気質を
①アクティブタイプ
②ネガティブタイプ
③デリケートタイプ
④テキストタイプ
⑤エンジェルタイプ
の大きく5つのタイプに分けておられます。
(子どもは、先の五つの気質のどれかに属しているというより、いくつかの気質が
混ざりあっています。)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「1歳と3歳のときに要注意のアクティブタイプ(落ち着きがなく乱暴だといわれる子)
は、9歳からやさしくなる。将来は社長や発明家向き」
「ネガティブタイプ(意地悪で可愛くない子)は、芸術家やアスリートに多い気質。
2歳、4歳、10歳を乗りきれば、うんと育てやすくなる」
「デリケートタイプ(引っ込み思案で、繊細すぎる子)は、入園入学では
お母さんを困らせるけど感性豊かな芸術家タイプ。いろいろな色や音で
感性を刺激すると、想像力豊かで才能あふれる子に育つ」
「テキストタイプ(生意気で理屈っぽい子)は、
6歳までに失敗してもいいことをしっかり教える。
子どもの「やりたい!」はできるだけ尊重する」
「エンジェルタイプ(のんびり屋で人の真似ばかりする子)は、
人生を謳歌する気質。2歳で集中力をはぐくみ、達成感を体験させておけば、
問題行動は自然になくなる。
生きるための知恵をつけるのには、「どうしたらいい?」と聞いて考えさせる」
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
といったアドバイスは、教室で子どもたちが成長していく姿と重なる
強く共感できるものでした。
わたし自身は、子どもの生来の気質を理解して
大らかに子育てする考えを指示する一方で、
発達障害の特性や感覚統合のつまづきが感じられる場合、
「気質だから……」という捉え方だけでなく、ていねいに困り感と関わる必要も
感じています。
感覚統合のつまづきへの対処を学ぶのに、
『育てにくい子にはわけがある(木村順 大月書店)』が、とても役立ちます。
育ちに何の問題もないように見える子の中にも、
赤ちゃんのようにおもちゃや指などを口に入れたり、
水面をたたいたり紙をちぎったりするような「感覚あそび」や「感覚へのこだわり」が
続く子や、手を使うとき手元を見なかったり、筆圧や弱かったり、身体がグニャッと
しやすい子は大勢います。
自分からはベタベタくっついてくるのに、触られるのは嫌がるという子も。
教室で見ていると、感覚統合の問題を抱えている子は、
他の子らの反抗期が落ち着いてくる時期に
善悪がわからないかのような態度に出たり、
暴力を伴う激しいかんしゃくを起こしたりしがちです。
子どもには生まれ持っての気質がありますから、
「育て方が間違っているの?」と不安になる必要はないけれど、
感覚統合についての知識に触れて、子どもに困り感があれば
それを軽減してあげることも大切だと思っています。

レッスンが終わった後で、3歳のAちゃんに呼ばれて外に出ると、ミミズがいました。
「触ると、ピョンって動くよ。丸くなるよ」とAちゃん。
ずっと怖かったのに、最近、虫に触るのが平気になったのだとか。
教室に戻って、ミミズがどのように世界を眺めているのか
『動物の見ている世界』という仕掛絵本図鑑で確かめることにしました。

↑ は、カメレオンの見え方。左右の目が全く別のものを眺められるのだとか。

かたつむりとミミズの見え方にびっくり。
かたつむりは一応目が見えるには見えるけれど、輪郭がはっきりしないあいまいな
影しか見えていないそうです。
ミミズは……というと、目はないのだけど、光を受け取る細胞が体中にちらばっていて、
光を感じることができるそうです。
でも光は、大嫌いで光を避けています。悪魔か吸血鬼のよう……。
ミミズを見つけるという現実の体験は、子どもの図鑑や知識の絵本の眺め方を
それまでとは全く違うものに変えてしまいます。
Aちゃんも繰り返し熱心にこの絵本図鑑を見ていました。
昨日、レッスン後に子どもたちと新大阪駅に行ってきました。
『新幹線のたび』という教室で人気の絵本を持って。

絵本に描いてある新大阪駅のホーム。
本物のホームにも防犯カメラや緊急時のブザーや売店などを見つけました。

絵本には、新大阪駅で見ることができるのは、300系、500系、700系、
700系レールスター、N700系と書いてありました。
駅のホームに700系の新幹線が到着しました。
子どもたちといっしょに「のぞみかな?さくらかな?新幹線の顔を見に行こう」
と言いながら、ホームを移動するものの、新幹線は思ったよりずっと長くて
とにかく歩きに歩きました。
ようやくホームの端に着いて、左右に並んでとまっている新幹線の顔を見ると、
どちらもよく似ています。
子どもたちは、「どっちもさくらだ」と言います。
理由は、絵本と同じように新幹線の窓の上の部分に、大仏さんのほくろのような
ポチっとしたでっぱりがあるから。
そんな話をしていると、駅にいた車掌さんが、「さくらものぞみも同じ車体で、
色だけが少しちがうんだよ」と説明してくださいました。
絵本ののぞみでは省略されていたのですが、のぞみにも大仏さんのほくろのような
ポチッとしたでっぱりあることがわかりました。
車掌さんは、福岡の方面に行く奥側の線路の新幹線は、さくらが多いよ」ということも
教えてくれました。
それまで気づかなかったのですが、のぞみには青い筋が、さくらには細い灰色の筋が
入っていることに気づきました。
新幹線ってよく似ているだけに、どこが違うのか見分けるのが楽しいです。
さんざん歩いて見に行った新幹線のさくらとのぞみの顔。
さくらは鹿児島中央行きでした。
目の前にあるさくらがこれから鹿児島中央駅に行くのだと知ると、
それまで何気なく眺めていた絵本の鹿児島中央駅に急に親しみが湧きました。
そして、日本地図上の新幹線の路線図にも。

小1のAくんとBくんの算数の学習の様子です。
『きらめき算数脳』2~3年生 の問題を解きました。
紙に情報を整理しながら解く練習をしています。

AくんもBくんも、
「確実だと思われるものから答えを決めていく」
「条件をていねいに洗いだして、しらみつぶしに調べていく」
といった作業が上手にできるようになってきました。


「あわせて10になるペア」や「あわせて20になるペア」をすばやく見つける
遊びをしています。

ふたりが熱中していた、4つの数を足したり引いたりして10にするゲーム。
「自由に数を4つ選んで、足したり引いたりすると、結果が10になるようにする」
というルールです。

ふたりにとって思いの外、難しかったようで、何度も試行錯誤を続けていました。
が、上手くいかない事態そのものを楽しみ、満足いく式ができるまで
取り組み続ける姿がありました。


こんばんは。
本日はすごい雨の大阪でした…
梅雨を実感致しました。変な天気ぃ
さて、各種ご連絡というか報告です。
まず、夏のユースホステルレッスンについて。
ご参加者さまでまだ連絡が来ていない方がおられましたら、再度、こちらのコメント欄または事務Kへメールを下さいますようご協力お願い致します。
続いて、夏の日帰りレッスンについて。
今回のご応募にて、ご本名にてご応募頂いた方がおられました。
その方々は此方でアルファベットに変換して発表しております。
ですので、一度『私かしら…?』と思った方はご連絡下さいませ。
なお、訂正が御座いましたので以前の記事を修正致しました。
再度ご確認くださいますよう宜しくお願い致します。
本日より7月のレッスンの方よりお送り致します。
それでは、もう少し頑張りますよー
そういえば…今夜?あたり満月のようですね。
久しぶりに夜空が楽しめそう…だといいな(=_=)
近々、教室の子らと新幹線の駅の見学に行く約束をしています。
新幹線好きの子に
『カンセンジャー』というJRのアニメ動画(駅内や新幹線の中の実写もあり)
がおすすめです。
興味のある方は、「カンセンジャー スペシャルムービー」で検索してみてください。
指令番号013 新幹線の車掌の仕事を調査せよ
指令番号O11 新幹線を支える仕事を調査せよ
指令番号005 新幹線の線路を調査せよ
といった動画は、ごっこ遊びや工作の参考にもなりますよ。

「子どもがやりたがらない遊びに誘うべきかどうか?」という質問 1
「子どもがやりたがらない遊びに誘うべきかどうか?」という質問 2
「子どもがやりたがらない遊びに誘うべきかどうか?」という質問 3
の続きです。
前回までにうまく伝えられなかったのですが、
このタイトルで記事を書きはじめた理由は、
ネット上で、この質問に対する自分の意見を述べることと、
実際に質問の相手や質問の対象(子ども)を前にして、質問に答えることの
間にあるずれや違いやギャップを伝えたかったからです。
ネット上での意見の交換には、その子ども個人の正確な情報が抜けています。
子どもについて説明して質問していたとしても、それは「質問主さんからすると
そのように見える」のにすぎません。
「誘っても乗ってこない子をその遊びに誘うべきかどうか」という疑問の背後に
子どもの側に他者の行動を模倣する力の弱さや
ひとつのことに注意を向けていることの困難さや親のすることや声かけへの無関心、
感覚の過敏さや鈍感さによって行動が限られていることや
遊びの成り立ちにくさ、目と手の協応作業の苦手さ、極端な不器用、
イメージすることの難しさや愛着の希薄さなどの気になる面が隠れていた場合、
答えはひとりひとり異なるとてもデリケートなものになります。
また親と子の関わり方に自然なやり取りや遊びの生じにくさや
奇妙な緊張感がある場合も、
親の側のあり方に自己肯定感の低さや結果を求めて子どもと関わる習慣や
親自身の困り感などがある場合もそうです。
何で遊ぶかはさておき、子どもには他者とのやり取りを持続していく力が
育まれていくような環境が必要ですし、
何らかの困り感のある子へは、具体的でまとまりのある行動にゆったりと向き合う力が
つくようなていねいな関わりが必要です。
話が少し逸れるのですが、
親しくさせていただいている『遊びのアトリエ』のジェリーさんが
赤ちゃん学会学術集会に参加した感想を書いておられました。
その中に教育哲学を専門とする久保先生の
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
教育・学習とは、身体を土台とした意味をめぐる活動であり、
動機、欲求や技術も持たないで知識を持つのを「教育」とするのをやめたい
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
という言葉が紹介されていました。
この言葉、わたしが工作や遊びを子どもといっしょにする時の
基盤となっている考えにとても近いのですが、
わたし自身はまだうまくそれを言葉にできずにいます。
教室で工作やブロックや科学実験をしているというより、
そうした媒体を利用して、子どもの中に今ある……また生じようとしている
……動機や欲求を
見ようとしているのですし、
それを通じて、子どもがまとまりのある行動に親しんでいくのを補助しているのです。
ピタゴラ装置DVDブックの中で佐藤雅彦さんが、
『言語化されていない面白さを素直に感じる能力』と
呼んだものを子どもといっしょに味わうための創作や実験ですし、
子ども自身が日々の体験を消化するのを助けるものでもあります。
もし「子どもが工作やブロック遊びをしたがらない場合、誘うべきかどうか?」
という質問の工作やブロック遊びが、
わたしが子どもとしようとしているものとかけ離れていたら、答えるのが難しいな……と
感じています。
言葉で説明することに限界を感じるので、
10月か11月にでも、工作の親子講座を開こうかと思っています。
募集は、8月末か9月の頭に予定しています。