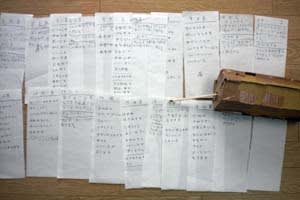4年生の子をお持ちの知人が、
近い学年の子を育てている数人の幼馴染と雑談していた時のこと。
勉強の話になると、みな一様に、
「この頃、ややこしいことばっかり言って、先に進まないのよね。
あーだこーだ言ってないで、早く勉強やっちゃいなさいっていうの!」と
9歳を超えて、もうじき高学年を足を突っ込もうかという年代の子たちの
減らず口っぷりへの不満であふれかえっていたそうです。
3年生までは、黙々と計算ドリルをこなしていた子たちが、
「割り算の筆算って、どうしてこんな変な形なの?」とか、
「何で、1㎝は10㎜なのに、1mは100㎝なの?1時間が60分ってのも
おかしいし!」などと、どうでもいいような質問をくり返しては
勉強を脱線するものだから、10分ドリルに30分も1時間もかかるらしい。
「大きくなるにつれて反抗的になって困っちゃう」
「どうして何も言わずにさっさとできないのかしら?」
「悪知恵ばっかりついて……」と笑いながら愚痴るお母さんたちの言葉を耳にしながら、
教育関連の仕事をしている知人は、その年代の子のややこしさを別の視点から
捉えていたようでした。
「この年代の子たちって、それまで意味について考えずに取り組めていたものにも、
どうして?という疑問を抱くようになるんですよね。
時間の無駄のようにも感じても、そこで、そうした疑問に『面白いね、ほんと、
どうしてだろう?』って親もいっしょになって考えをめぐらせるのと、
つまらないことばっかり言って怠けていないで早くやっちゃいなさいと一喝するのとで、
その後、その子が算数や数学が好きで得意になっていくかの分かれ目になっていくと
思うんですよ。
9歳の壁って、そういう面でのできるかできないかの分かれ道でもあるのかも」
といったことをおっしゃいました。
「そういえば、そうだな~」と共感しました。
抽象的な思考の入り口に立とうとする子らの言葉は、どうでもいい御託を並べて、
物事を混ぜ返して中断しているようにしか見えないものです。
でもそうした思考の種を拾い上げて、
ていねいに良い土壌に埋めて、水や肥料を与えるか、ただの種だからとゴミ扱いするか、
それは子どもの勉強との関わり方を大きく左右するものだと思われました。
子どもの思考の種を大切に扱うためには、
近視眼的な成果を見過ぎないことが大事なのかな、とも感じ、
先週のレッスンでのこんな出来事を思い出しました。
という年長さんと1年生の子らのレッスンでの出来事です。

「サーカスの舞台を作りたい」という子らのために
ネットで検索したサーカスの画像のひとつに
下の写真のような二等辺三角形の旗が吊下がっている写真がありました。
これは、子どもたちの心を引きつけて、「作ってみたい」という子が数人いました。

そこで、折り紙を用意して、「どうしたらこんな旗がたくさんできるのか」という
話し合いをしました。

年長さんと1年生の子とはいえ、工作に慣れているので、二等辺三角形を作ることには
長けています。
いくつか折り紙を重ねて、半分に折れば、たくさん二等辺三角形ができることを
承知していました。

切った後で、上の写真のような二等辺三角形と直角三角形に分かれた時に、
「できるだけ折り紙を無駄遣いしたくない」
「二等辺三角形を切った残りの直角三角形から
二等辺三角形は作れないだろうか?」と考えた時に、
「答えがわからないから徒労に終わるかもしれないけれど、
うまく二等辺三角形が作れたら折り紙を有効利用できるし、面白いなぁ」という課題が
生じました。

「サーカスを作る」という目的のもとでは、
その一部である旗の切り方に試行錯誤するなんて時間の無駄でしかありません。
いろいろやったあげく、ひとつもいい考えが浮かばない可能性だってあります。
それでも、それぞれの子が、
「こうしたらどうかな?」「わかった!できるよきっと!」と
そこに関心を集中させて、いろいろなアイデアを出していると、
折り紙としてはあたり前の、「折ると、三角形ができました」というような
上の写真のようなアイデアでも、子どもの理解の度合いによっては、
二等辺三角形とは何なのか、補助線を引く時にどこに注目すればいいのか……
といったことが見えてくるような体験となるのです。

そうやって小さい二等辺三角形を切りとると、そのあまりは二等辺三角形になります。
図形の性質に気づく瞬間ですね。