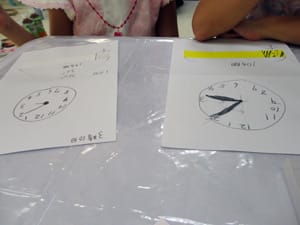遊びでも勉強でもお手伝いでも、子どもの気持ちを尊重しようという思いから、
「これ、やりたい?」「やりたくない?」と子どもにその時の気持ちを
訪ねすぎる親御さんがいます。
まだ、1、2歳の子を相手にするときにも、親が提案する何かを見せて、
「やりたい?」「やりたくない?」とたずねたり、
そうたずねないまでも、飛びついてやりはじめたら「あっ、食いついた!」と喜び、
気乗りしないようだと、大人がおろおろし、
「ちょっとしてみたら?なら、こっちをしてみる?」と
やたらスタート時の子どもの気持ちに過敏になっているのです。
親がそのように子どもの気持ちに過敏に一喜一憂すれば、子どもは当然、
自意識過剰になって自分のその瞬間の気持ちや気分に集中するようになります。
子どもが、自分が「それをしたいかどうか」や
「やったら楽しいか」「得するか」にばかり敏感になるのです。
もしかしてうまくできないかも、やったらつまらないかも……と思うだけで、
簡単な遊びも工作もするのが億劫……、それこそ携帯ゲームすら
(ルールを覚えなくてはならないので)めんどくさい(上手な子に頼んでポイントだけ
いれてもらう)なんて子もいて気になっています。
ですので、それこそ勉強や他の課題で「ちょっと苦手」「ちょっとめんどくさそう」
というものにぶつかれば、やりもしないうちから、「やりたくない」と自分の弱さを
守ることに一生懸命になります。
もちろん、子どもの気持ちを無視して、「あれをしろ」「これをしろ」と動かして
いいわけでもないのです。それはそれで、さらに深刻な心の問題を生むかもしれません。
でも、「やりたいか」「やりたくないか」という自分の気分が、
いちいち親を喜ばせたり、がっかりさせたりするといった結果につながったり、
気分というのが、面倒なことを避けられる免罪符となったりすることを繰り返せば、
メンタル面での危うさを身につけていくのは避けられないのではないでしょうか。
前々回の記事で、
「そうして至れり尽くせりしてしまってお客さん状態を過ごした子らというのは、
必ずといっていいほど、ちょっとぞんざいな他人の姿が目に入っていないような行動を
取ります。遊ぶ時に拾った木の実を投げ合ってみたり、大人の指示を無視して
駆けまわったり……」ということ書きました。
これは他人からそのように接遇されることだけでなく、親がわが子をお客さんのように
扱って、子どもにおうかがいを立てては、「喜んでくれた」「がっかりさせてしまった」
「お得な体験をさせてあげられた」「レベルアップできるアイテムを身につけさせて
あげることができた」「子どもを喜ばしてあげるものを見つけることができない」
「キラキラおめめが見れた!」と一喜一憂することが子どもへの愛情だと捉えてしまうと、
子どもは自分がその体験を通して
「成長していく主体」「変化し、進歩していく存在」という実感が持てません。
そして、無料サンプルのモニターでもしている気分で自分の人生に参加して、
苦手なものや学んで克服しなくてはならないものに対して、
「これはおいしいね」「これはまずいね」とコメントする立場になってしまいます。
「国語の漢字はおいしいけど、読解問題はまずいから食べない」
「計算は好きだけど、図形問題はきらいだから食べたくない」というように。
テレビを見ながら、「面白い」「面白くない」と判断して、チャンネルを変えるスタンスで
学習に参加するようになります。

「やりたい?」「やりたくない?」と気持ちをたずねるとき、
子どもが何かする際の最初の気持ちや判断に圧力がかかりすぎるきらいがあります。
実際、人が成長するときや、学ぶときというのは、
気になるけど、「きらいー」って言いたい複雑な気分から、
しているうちにだんだん身体がなじんでいって、
「もしかして面白いかも」と思えて、やり終えたらスカッと気持ちよくて
自分が変化しているとか、最初はただその空間でいっしょに過ぎているだけで
無関心だったのに、無関心のまま終わることが何度かあった後で、何かの拍子で関わりが
始まって、それまでの苦手意識や拒絶心が溶けだして、しまいに、「これ楽しいかも?」
「私はこれが上手にできるかも?」と思うようになる過程だったりします。

そこで、まるでカタログショッピングでもするように、
「これを買おう(してみよう)かな?あっちにしようかな?」と
選ぶ時点にやたら力を投入して、
何かをするときは、自分の変化を待たずに、それが「いい」か「悪い」か
評価をしてしまうと、そこには、成長も学びも起こりようがないのです。
「やりたくない」と避けていたことも、次に年上のお兄ちゃんお姉ちゃんと
いっしょにするのなら魅力的な作業になるかもしれないのです。
いちいち、自分の気持ちを過大評価していると、一度感じた思いが
理由もなく強く刷り込まれて、単なるその日の疲れや気分が、
そのまま「苦手意識」にまでなってしまうこともあります。
そのように親御さんが、そのときそのときの子どもの反応にいちいち敏感だと、
子どもは長い目で物事に取り組んでいく姿勢を失うことも多々あるのです。
視野を広げ続けて、さまざまな価値観を取り入れていこうとする態度も
弱まるようです。
「そのときは面白くなかったけど、もう一度やってみたら、
どうかわからない」という子どもならではの
以前の失敗はすぐさま忘れて、何度も再チャレンジしていこうとする気楽さが
なくなります。
そうした特殊な成長できない心や学べない心を作るのは、
幼児期からの通信教材や習い事を通じて
親が「悪い心の見本」を子どもにたくさん見せてしまうこともあるような気がします。
「悪い心の見本」というのは、「選ぶ」ことと「評価」することが、
自分の仕事であるかのように錯覚させてしまうことです。
お金が関わることや、一度始めたら簡単に抜けるわけにはいかないという体験は、
最初に「やりたい」と感じるか、「やりたくない」と感じるか、どっちを選ぶかが、
その後の自分の幸不幸を決めるような印象を子どもに与えます。
何度もこうした体験をして挫折している子は、選ぶ際には、
チャレンジが必要なことを避けて、遊園地やショッピングに行くような
その場で楽しみが完結するものを選びがちです。
(何事もやめずに続けて成功しているように見える子も内心は無理しすぎていて、
思春期を過ぎてからの目標のハードルを下げ気味になるように感じます)
また、「公園デビュー」なんて言葉があるように、
自然な生きる営みに対して、いちいちメンタル面に強い負荷がかかることのように
解釈してしまうのも「悪い心の見本」の一例だと思います。
いつでもどこでも「正しさ」と「平等さ」で、子どもの世界から苦しいことや
悲しいことや理不尽なことを一掃してしまうことも、
子どもが何に対しても本気になれず、生きることにしらけてしまう原因を
作るのではないでしょうか。

子どもの世界でも、友だちは、「デビュー」なんていう最初の一瞬で、
できるできないが決まるものではなくて、
勝手に自分側からだけの目線で友だちに○×つけられるものでもなく、
「自然に素直に関わり合っていれば、いずれ、かけがえのない親しさが生まれて
くるかもしれない」という長い時間の経過のなかで自分も相手もともに変容しながら
できてくるもののはずです。
そうした良い変化が起こるには、
「自分」や「自分の生きている場所」や「人」に対するゆったりした信頼感が必要です。
最初に自分の気持ちに過度に集中してしまうと、何をするにも気持ちがすくんだり、
妙に冷めた商品でも見定めるような視線で人や出来事を眺めるようになってしまうでしょう。
子どもを観察するとき、近視眼的になったり、感情移入したりして、
変化の流れにある子どもの一瞬、一瞬を、大人の心で乱してはいけないと感じています。
子どもが「やりたくない」と言って、親御さんのもとに来たとき、
その気持ちをしっかり受け止めてあげることは大事です。
でも、そこで、「やりたくないなら、こうしよう、ああしよう」と
すぐさま大人が解決してしまったり、
「どうしてうちの子だけ」と他の子と比べて悩む行為は、
「大人の心で子どもの成長に向かう流れを乱している」ことになると思います。
子どもはそうやってそれまでの自分の殻を破らなくてはなない事態に出会って、
何度も安全な親御さんのもとに来てエネルギーを充電して、
黙ってゆっくり待っていてもらったら、自立心にスイッチが入って、
「同年代の仲間入りをしてうまくやっていきたい」
「親しくなりたい」「あの子のように上手に~できるようになりたい」「認められたい」
というそれまでなかった新しい課題を胸に育んでいきます。
上手くいかないこととの出会いは、そのまま成長しようとする意志の誕生へと
つながっているのです。