ケン・ローチの映画にもって回った表現はない。そのテーマにズバリ、内角をえぐるストレートで迫る。余分なメタファーを排除した映像もまた明快そのものである。
だからといって決して凡庸でつまらないわけではない。それどころかその普遍性をもったリアリズムが私たちをグイグイ惹きつけてやまない。そして何よりも、そこには社会の片隅で懸命に生きる人たちへの温かい連帯の眼差しがある。

私が子どもの頃、イギリスは福祉の先進国で「揺りかごから墓場まで」といわれたりした。しかし、それは今や面影もない。恐らくサッチャーリズムにみられる新自由主義の導入のなかで、そんなものはすっ飛んでしまったのだ。
病気、それは自己責任。貧困、それは自業自得。これが当たり前の世の中になってしまったのだ。
もちろん、これはイギリスのみのことではない。私たちの国においても、片山さつきの反生活保護キャンペーンなどによって、本来機能すべきセーフティネットは針のむしろに転じ、それを受容するためには引き換えに人間としての尊厳を手放せと強要されるに至っている。
もちろん、そうした格差が何によって生じ、それを払拭するために何が必要なのかは不問に付されたままである。
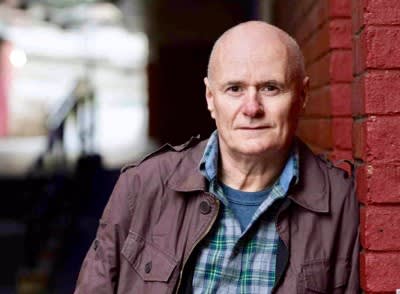
いきなり硬いことを書いたが、ケン・ローチの映画はそうした理不尽な仕組み、排除を旨とするような窓口の対応に自己の尊厳をかけて立ち向かうベテランの大工職人を描いてある種爽快である。
彼の腕前は、時折描写される彼のちょっとした細工物によく表れている。

彼の被る理不尽は例えば次のようなものである。
彼は心臓発作のため医師から就労を止められている。したがって未就労の手当を求めて申請するのだが、そのためには、就労をしようとしてもできないことを証明するために、履歴書を作り就労活動をすることが求められる。彼はあたう限りそれに従うのだが、時折は切れる。
切れればこんどはシステムに従順ではないとして懲罰的に排除される。
それに不服申立てをしようとすると、それはネットを通じてしかできないといわれる。IT がアナログ人間を排除するアイテムとして機能する。

彼と同様にセーフティネットから排除される2児をかかえたシングルマザーが登場する。この一家も悲惨である。ベテラン大工は、自分自身の困窮も忘れて一家の面倒を見る。
ケン・ローチの目線はいつもながら弱者たちとともにある。そして、彼の映画においては、弱者に寄り添うのもまた弱者なのである。
隣室のヤンキーのような青年たち(BL?)も、当初は得体が知れないが、正規労働の枠からはみ出たがゆえにネットを使って怪しげな商売をしているようなのだ。しかし、アナログ人間の主人公にもっとも親切にパソコンを教授するのは彼らなのである。そして、「困っているならなんでもいえよ」という泣かせるセリフまでいってのける。

これ以上はネタバレになるから書かないが、私たちは、排除を旨とするシステムに登場人物とともに憤りながら、どこかでホッとした温かみを感じるのは、こうした弱者相互に情感として伝わる連帯意識のようなものがあるからである。
そんななかで、彼が「英雄」になるシーンがあるが、それは書かないでおこう。
この映画のシチュエーション、どこか既視感があったが、それはクリント・イーストウッドの『グラン・トリノ』であった。
しかし、似ているだけで中身はまったくちがう。ケン・ローチは冒頭に書いたようにはるかに地味で堅実であるが、それだけにリアリティがある。たぶんそれは、ケン・ローチがあくまでも庶民の目線を手放さないからだと思う。

*まったく私的なことだが、この映画を観ようと入った映画館、なんと至近距離の座席に旧知の女性二人がいて、しかもこの二人も相互に知り合いとあって、映画が終わってもただで済むはずはない。三人揃って居酒屋へ直行。
一人は20年以上前、市民派として参院選に立候補したMさん。もう一人は、かつて一緒に雑誌づくりをしてきたTさんで、ラジオの台本作家のほか、映画好きが高じてついに昨年、監督として映画を作ってしまった人。
この女傑に囲まれて、年老いていることのみを唯一の武器として両手に花の桃源郷に遊んだひと時。
だからといって決して凡庸でつまらないわけではない。それどころかその普遍性をもったリアリズムが私たちをグイグイ惹きつけてやまない。そして何よりも、そこには社会の片隅で懸命に生きる人たちへの温かい連帯の眼差しがある。

私が子どもの頃、イギリスは福祉の先進国で「揺りかごから墓場まで」といわれたりした。しかし、それは今や面影もない。恐らくサッチャーリズムにみられる新自由主義の導入のなかで、そんなものはすっ飛んでしまったのだ。
病気、それは自己責任。貧困、それは自業自得。これが当たり前の世の中になってしまったのだ。
もちろん、これはイギリスのみのことではない。私たちの国においても、片山さつきの反生活保護キャンペーンなどによって、本来機能すべきセーフティネットは針のむしろに転じ、それを受容するためには引き換えに人間としての尊厳を手放せと強要されるに至っている。
もちろん、そうした格差が何によって生じ、それを払拭するために何が必要なのかは不問に付されたままである。
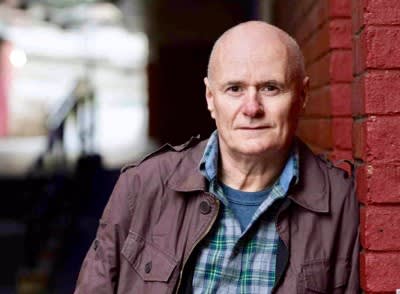
いきなり硬いことを書いたが、ケン・ローチの映画はそうした理不尽な仕組み、排除を旨とするような窓口の対応に自己の尊厳をかけて立ち向かうベテランの大工職人を描いてある種爽快である。
彼の腕前は、時折描写される彼のちょっとした細工物によく表れている。

彼の被る理不尽は例えば次のようなものである。
彼は心臓発作のため医師から就労を止められている。したがって未就労の手当を求めて申請するのだが、そのためには、就労をしようとしてもできないことを証明するために、履歴書を作り就労活動をすることが求められる。彼はあたう限りそれに従うのだが、時折は切れる。
切れればこんどはシステムに従順ではないとして懲罰的に排除される。
それに不服申立てをしようとすると、それはネットを通じてしかできないといわれる。IT がアナログ人間を排除するアイテムとして機能する。

彼と同様にセーフティネットから排除される2児をかかえたシングルマザーが登場する。この一家も悲惨である。ベテラン大工は、自分自身の困窮も忘れて一家の面倒を見る。
ケン・ローチの目線はいつもながら弱者たちとともにある。そして、彼の映画においては、弱者に寄り添うのもまた弱者なのである。
隣室のヤンキーのような青年たち(BL?)も、当初は得体が知れないが、正規労働の枠からはみ出たがゆえにネットを使って怪しげな商売をしているようなのだ。しかし、アナログ人間の主人公にもっとも親切にパソコンを教授するのは彼らなのである。そして、「困っているならなんでもいえよ」という泣かせるセリフまでいってのける。

これ以上はネタバレになるから書かないが、私たちは、排除を旨とするシステムに登場人物とともに憤りながら、どこかでホッとした温かみを感じるのは、こうした弱者相互に情感として伝わる連帯意識のようなものがあるからである。
そんななかで、彼が「英雄」になるシーンがあるが、それは書かないでおこう。
この映画のシチュエーション、どこか既視感があったが、それはクリント・イーストウッドの『グラン・トリノ』であった。
しかし、似ているだけで中身はまったくちがう。ケン・ローチは冒頭に書いたようにはるかに地味で堅実であるが、それだけにリアリティがある。たぶんそれは、ケン・ローチがあくまでも庶民の目線を手放さないからだと思う。

*まったく私的なことだが、この映画を観ようと入った映画館、なんと至近距離の座席に旧知の女性二人がいて、しかもこの二人も相互に知り合いとあって、映画が終わってもただで済むはずはない。三人揃って居酒屋へ直行。
一人は20年以上前、市民派として参院選に立候補したMさん。もう一人は、かつて一緒に雑誌づくりをしてきたTさんで、ラジオの台本作家のほか、映画好きが高じてついに昨年、監督として映画を作ってしまった人。
この女傑に囲まれて、年老いていることのみを唯一の武器として両手に花の桃源郷に遊んだひと時。


















