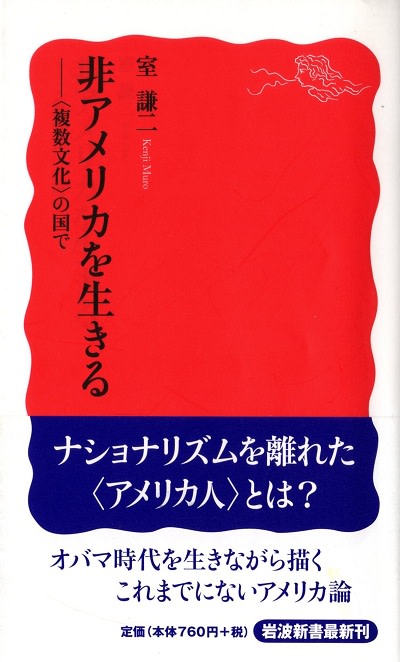マーティン・スコセッシ『レイジング・ブル』(1980年)。中古DVDを500円で入手した。

元ボクシング世界ミドル級チャンピオン、ジェイク・ラモッタの映画化である。時代は主に1940年代から50年代。ラモッタは「怒れる牡牛(レイジング・ブル)」の渾名の通り、ワイルドなスタイルで闘った。伝説的なシュガー・レイ・ロビンソンとのファイトも再現されている。
映画はドキュメンタリー風のつくりであり、ラモッタの人間的な側面や弱さを押しだしたものだった。NYの顔役たちとの付き合い、嫉妬、DV、離婚、ショービジネス。
さすがのスコセッシ、完成度が高く充分に面白いのではあるが、どうも巧みすぎる似非ドキュメンタリーが気にいらない。破綻のない予定調和のドキュメンタリー「風」なんて何の意味があったのか。
当時のカメラはやはりスピードグラフィックなどの大判がほとんどだ。ウォーレンサックのラプター127mmF4.5というレンズがアップになる場面がある。中途半端な焦点距離なのではなく、単に5インチというだけである。調べてみると、同スペックで、戦後レンズが足りなかったライカにLマウントレンズを供給したり、引き延ばし用レンズとして売ったりもしていたらしい。このような米国レンズもちょっと使ってみたいが、どんな感じだろう。
●参照
○マーティン・スコセッシ『ザ・ローリング・ストーンズ シャイン・ア・ライト』、ニコラス・ローグ+ドナルド・キャメル『パフォーマンス』
○鈴木清順『百万弗を叩き出せ』、阪本順治『どついたるねん』(ボクシング映画)
○勅使河原宏『ホゼー・トレス』、『ホゼー・トレス Part II』(ボクシング映画)