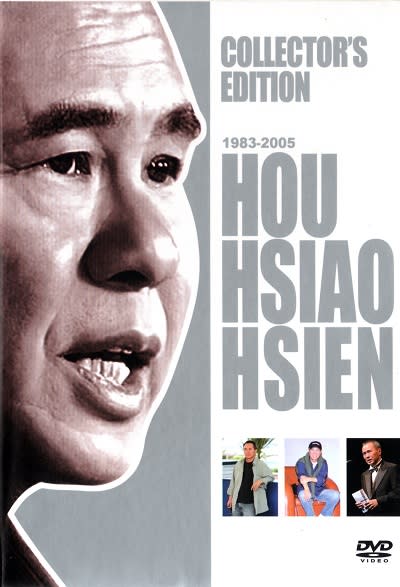ハリー・コニック・ジュニア+ブランフォード・マルサリス『Occasion』(Marsalis Music、2005年)を聴く。ブックオフの500円棚にあった。
何しろハリー・コニック・ジュニアがヴォーカル抜きで活動しているということなどまったく知らなかった。というよりまったく興味を持たなかった。洋楽好きの姉が1990年代初めころに何やらうっとりして聴いていたのを目撃して以来、自分の中ではミーハー向けというレッテルを貼っていた有様である。
そういえば、故・古澤良治郎さんは、スクールの待合室でいつも仙人のように存在していたが、その古澤さんが、「あの人、何だっけ、ハリー・ニコック・ジュニア!」とか叫んでいた記憶がある。(どうでもいいか・・・。)

Harry Connick, Jr. (p)
Branford Marsalis (ts, ss)
ブランフォード・マルサリスとピアニストとのデュオというと、父エリス・マルサリスと吹き込んだ『Loved Ones』を思い出してしまうが(「Maria」の演奏などは印象的だった)、ハリーは実はエリスに師事していたのだという。そうか、ジャズの伝統を既得権益のように抱え込むネオコン一味か、と一言で片付けず、聴く。
ハリーのピアノは、当然というべきか、エリスのピアノよりもモダンな要素を取り入れている印象がある。そしてブランフォードのサックスは、相変わらず、巧すぎるくらい巧い。もうヤンチャ臭はない。実はそれがつまらない。かつて『The Dark Keys』というピアノレスグループの作品に熱狂した自分だが、それ以降は、綺麗なだけに感じられて、聴く気がしなくなっていた。改めて聴くと、これはこれで悪くない。
「Steve Lacy」という曲が収録されている。文字通り、ソプラノサックスの巨匠、故・スティーヴ・レイシーに捧げられた演奏であり、解説を読むと、『Sands』にインスパイアされたものであるらしい。しかし、やはり当然というべきか、似ても似つかないどころか、雰囲気もない。ケニーGかなにかを聴いているようだ。
ニューオリンズ風あり、シャンソン風ありと、悪くないのだけど。

『Sands』(TZADIK、1998年) 昔、レイシーにサインをいただいた

『Sands』(TZADIK、1998年)の内部の写真
●参照
○『Point of Departure』のスティーヴ・レイシー特集(『Sands』)