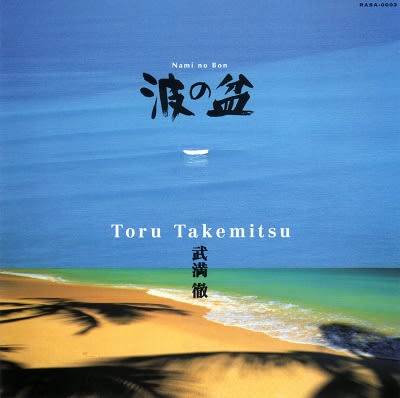何しろ『Ascension』である。とはいっても、最近また特定方面で盛り上がっているらしい「アセンション」ではない(知らないが)。ジョン・コルトレーンの永遠の問題作のことである。
ロヴァ・サクソフォン・カルテットが、「Rova's 1995」名義で、『John Coltrane's Ascension』(Black Saint、1995年)という作品を出している。
盤の存在を知ったのはつい最近、中古CD店の棚で発見してからのことだ。これを演るのか!

Jon Raskin, Steve Adams (as)
Larry Ochs, Bruce Ackley, Glenn Spearman (ts)
Dave Douglas, Raphe Malik (tp)
George Cremaschi, Lisle Ellis (b)
Chris Brown (p)
Donald Robinson (ds)
即興集団にはひとつのテーマが与えられたのみで、それをユニゾンでもなく吹いては、ソロイストに演奏を渡していく。その繰り返しである。
管のソロの順番は、スペアマン(as)→マリク(tp)→アダムス(as)→アックリー(ts)→オクス(ts)→ダグラス(tp)→ラスキン(as)。
聴くとやはり興奮してしまうのだが、なかでもラリー・オクスの潰れたような音色のテナーサックスが良いと思った。
ところで、デイヴ・ダグラスのトランペットは抑制が効きすぎていて、さほど好みではない。以前に随分と持て囃されて、それなりに聴いてもいたのだが、何度かジョン・ゾーンのクレズマー音楽のグループ・MASADAでの演奏を目の当たりにして、少し失望した。それ以来、ダグラスの作品をほとんど聴いていない。この思い込みを変えてくれるような演奏に接したいと思ってはいるのだが。
オリジナルは、言うまでもなく、ジョン・コルトレーン『Ascension』(Impulse!、1965年)である。

昔、エルヴィン・ジョーンズにサインをいただいた
John Coltrane, Pharoah Sanders, Archie Shepp (ts)
Marion Brown, John Tchicai (as)
Freddie Hubbard, Dewey Johnson (tp)
McCoy Tyner (p)
Art Davis, Jimmy Garrison (b)
Elvin Jones (ds)
管のソロは、ジョン・コルトレーン(ts)→デューイ・ジョンソン(tp)→ファラオ・サンダース(ts)→フレディ・ハバード(tp)→アーチー・シェップ(ts)→ジョン・チカイ(as)→マリオン・ブラウン(as)、となっている。実際のところ、世に出たヴァージョンによって違いがあるらしい。
さすがというのか、それぞれ個性大爆発である。ファラオ・サンダースの地響きがするようなテナーも、一際モダンなフレディ・ハバードも、見た通りの精悍なアルトを吹くマリオン・ブラウンも良い。マッコイ・タイナーは、何だか終わりで自棄になったようなピアノソロを弾くが、実際にミスマッチで面白い。そして全体を締めるエルヴィン・ジョーンズのドラムス。
コルトレーンのサックスの音色が苦手な自分だが、これは数少ない好きな盤である。
しかしふと思ったのだが、この曲、もっと多くの演奏があってもいいのではないか。野球のように、集団即興と個人の見せ場が順番に来るのだから、参加者にとっては腕の見せ所に違いない。
ところで、藤岡靖洋『コルトレーン ジャズの殉教者』によれば、このセッションに、怪人ジュゼッピ・ローガンが参加した可能性もあったということで、そうなればさらに妖しさ爆発になったはずだ。(いや、まだ遅くない。ESPディスクなんかがそのつもりになってくれれば。)
●参照
○藤岡靖洋『コルトレーン』、ジョン・コルトレーン『Ascension』
○ラシッド・アリとテナーサックスとのデュオ(コルトレーンとの『Interstellar Space』)