
何の気なしに手に取った『スペイン市民戦争とアジア』(石川捷治・中村尚樹、九州大学出版会、2006年)だが、思いもよらず、この70年間をくねくねと結び付けられてしまった。言い換えれば、いまという、権力至上主義と暴力が揺り戻っている社会にあって、判断できる「個」の復権を、熱く、熱く、熱く、呼びかけている本である。
スペイン内戦(この本では、あえて、大義や理想に共鳴した市民の参加を強調するため、「スペイン市民戦争」と称している)は、1936年から39年に起こった。共和国政府に対し、フランコ将軍が率いる軍部が仕掛けたクーデターである。フランコにはドイツ、イタリアという当時のファシスト政権が支援している。一方の共和国政府には、ソ連(これは結局、民主主義と自由への支援ではなかった)が支援し、それ以上に、主に欧米の多くの市民が義勇兵として参加している。
内戦は、フランコ側の勝利に終わり、1975年のフランコの死まで権力政治が敷かれることとなる。
米国から参加したアーネスト・ヘミングウェイは、これを『誰がために鐘は鳴る』に小説化した。いまの私たちが知っている知識といえば、この小説や映画、フランコ将軍、それからパブロ・ピカソの『ゲルニカ』、といったところだろう。 ピカソは『ゲルニカ』を描くにあたって、いくつもの習作や準備的作品を描いている。そこでは、最終作において(芸術的に)洗練されシンボリックなものとなった馬や牛や母親が、より現実的な形となっている。『フランコの夢と嘘』というタイトルにもあるように、フランコ政権とそれを支援するファシスト政権への怒りが、生々しく噴出しているのだ。その意味で、『ゲルニカ』は芸術的には完成されたかもしれないが、今の私たちには、漠然と、抽象的な「悲惨な戦争の画」としか受け取られていないかもしれない。
もっとも、ピカソ自身は『ゲルニカ』をやや異色なものと認めたうえで、「私はいつも現実の精髄の中にいた。だれかが戦争を表現したいと望めば、弓と矢を描けばもっと優美で文学的だろうね。それが一層美的だからだ。しかし私としては、戦争を表現したいときは機関銃を使うだろう。」と述べてはいる(『ピカソ 愛と苦悩―「ゲルニカ」への道』、東武美術館、1995年)。ただこれは結果論であり、『ゲルニカ』の持つ力が美学的にのみ受け取られがちなことは、ピカソ自身の意図とは関係なく、いまの時代性と70年という時間によるものが大きいのだろう。

パブロ・ピカソ『フランコの夢と嘘 II』(1937年)
さて、この本の題には「アジア」と入っている。スペイン市民戦争に参加した義勇兵は、欧米人ばかりではなかった。中国、朝鮮、フィリピン、インド、ヴェトナムでは、主にスペインで義勇兵として参加した人々が、それぞれ帰国し、市民参加の社会を作るという理想に向かって活動している。状況として、必然的に、抗日運動や反帝国主義運動となっている。「市民」が、民主主義や自由といった大義を胸に秘め、国の戦争としてではなく、自発的に駆けつけた。そのスペイン市民戦争が、その後のアジア社会構築やヴェトナム戦争につながっているというわけだ。
ジャズ・ベーシスト、チャーリー・ヘイデンは、ピアニストでありビッグバンドを率いるカーラ・ブレイに編曲を依頼し、1969年に『リベレーション・ミュージック・オーケストラ』(Impulse)という傑作をものしている。スペイン市民戦争、それから革命家チェ・ゲバラ、さらにはヴェトナムへの米国の介入に対し、音楽という手段で意志を表現したものだ。
ヘイデンのベースもさることながら、自由人ドン・チェリーのコルネット、ガトー・バルビエリの過剰な泣きのサックス、デューイ・レッドマンのもこもこしたサックスなどが素晴らしい。この場合、音楽をプロテストの手段として捉えるのが不純で低レベルだということには、決してならない。(むしろ、一般論としても、音楽にせよ映画にせよ絵画にせよ、それが産み出された背景をおしはかることなく「芸術」として鑑賞することは、浅はかに過ぎるのではないか、と思えることが多い。)
ヘイデンの「リベレーション・ミュージック・オーケストラ」はまだ活動している。最近作『NOT IN OUR NAME』(Universal、2005年)では、いまの世界における不正や暴力に対し、闘いを宣言している―――相手は、悪しき米国であり、帝国主義であり、力による圧制だろう。「私たちの望むものではない、勝手に国として行動するな」といったところだ。ヘイデンとカーラ・ブレイ以外のメンバーは異なるが、相変わらず、センチメンタルで力強い。このような本人たちの意志を知っても知らなくても、という前提はナンセンスである。ここでは、意志とメッセージと音楽はセットなのだから。

36年間の時間を隔てた第1作と最近作 チャーリー・ヘイデンとカーラ・ブレイは両端にいるが左右を交代している(笑)
ヘイデンがライフワークで世界に問うているように、この本でも、全世界の市民が自分の意志で駆けつけたスペイン市民戦争の意義は、いまでも(いまでこそ)重いものだと締めている。
「視点を現代に転ずると、東西冷戦の終結後も世界各地で紛争、テロ、そして戦争が絶えない。「人道的介入」や「積極的介入」をすべきか、すべきではないか、あるいは「超大国の単独行動主義」は許されるのか、といった問題点がその度に指摘される。
確かにスペイン市民戦争の時代は、市民が自らの力を信じることができた時代だった。だからこそ、自分で武器をとり、不正な権力と闘った。そしてそのこと自体の重要性は、いまも変わらない。いや、自分の力を信じるという面でいえば、その重要性はさらに強まっている。しかし逆の言い方をすれば、信じるものは自分の力しかなくなっている。」
「社会主義を掲げたソ連は崩壊し、アラブの”理想”を掲げるグループは、卑劣なテロを繰り返す。日本の政治は実現すべき目標を見失い、政権与党の外交政策は国際協調の名の下で対米追従、内政の最大の課題は借金の返済と経費の節減である。
しかし、そんな時代だからこそ、いまいちど”理想”を、そして”希望”を考えてみる必要があるのではないだろうか。」
「私たち一人ひとりが”判断力”を身につけて行動するとき、そこには国境や人種の違いを超えた新しい理想、そして新しい希望が生まれてくるのではないだろうか。現代の大企業は多国籍企業と呼ばれるように、国境がほとんど存在しないかのような市場が形成されている。その結果としておこるのは、なし崩し的な民主主義の破壊である。それに対抗できる現代の統一戦線が求められている。様々な暴力によって苦しめられている人々の、グローバルな連携である。その原点として、スペイン市民戦争に集った人々の足跡はいまもなお、輝きを失ってはいないはずである。」
『スペイン市民戦争とアジア』(石川捷治・中村尚樹、九州大学出版会、2006年)
パブロ・カザルス(カタルーニャ語ではパウ・カザルス、パウは平和の意味)は、フランコ独裁政権に反発し、祖国に自由が戻るまでは公開演奏をやめると宣言した。国家と対峙しうると考える、強烈な自負心である。
しかし、いまは、私たちのそれぞれが、カザルスやヘイデン、さらには自分の意志と正義を支えにする義勇兵になりかわることが、必要とされると言うべきだろうと思う。言うまでもないが、戦争をしない義勇兵である。

パブロ・カザルス『J.S.バッハ 無伴奏チェロ組曲 第1番~第3番』
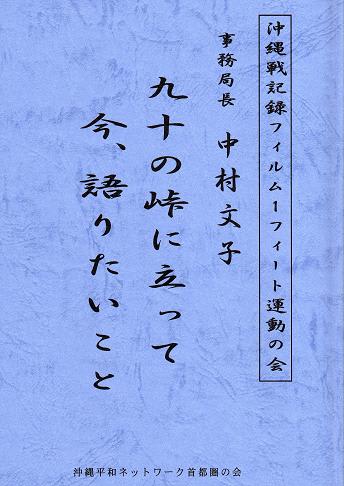


















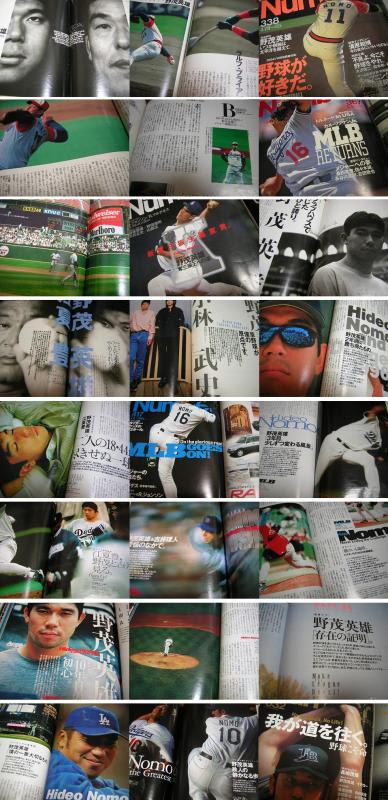

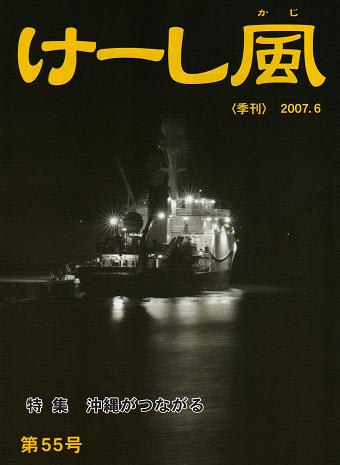









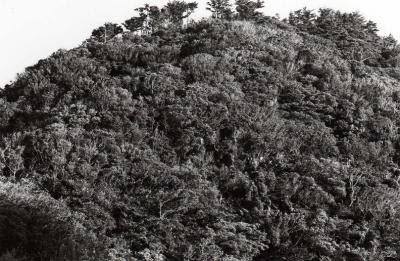



 =====
=====

