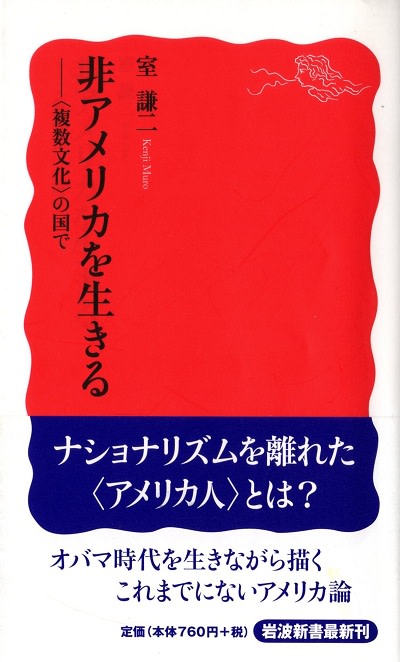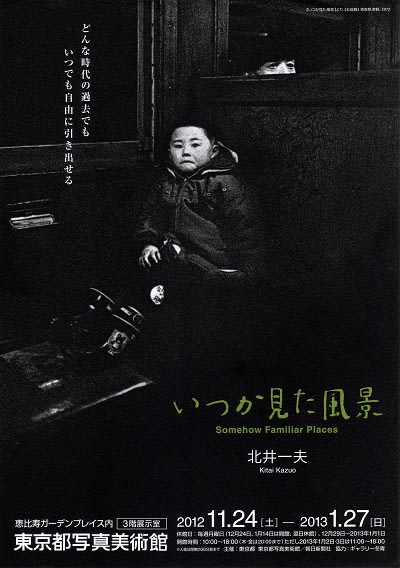悔し紛れに昼から夜のツイッター再録。https://twitter.com/Sightsongs

田村理 『国家は僕らをまもらない』(朝日新書、2007年)は、日本国憲法の位置づけを、「ほっておくとろくなことをしない」国家権力に対して制約を加えるものだと明言している。このストッパーを外そうとしているのが改憲勢力。
http://pub.ne.jp/Sightsong/?entry_id=681332

菅首相が福島第一原発の冷却水を止めたという話は安部氏による虚偽情報だった。民主党の偽メール事件の際には全メディアが議員を非難したにも関わらず(のちに議員は自殺)、これについて責任追及の声はメディアからは出てこない。
http://pub.ne.jp/Sightsong/?entry_id=4150004

北朝鮮を遂に戦争のターゲットとする愚かさ。彼らは時が来れば戦犯とみなされるだろう。「日本側代表団は、拉致問題に対するマスメディアの反応に強い影響を受けた。「相手に向かって机を叩いて怒鳴ってりゃいいだけでした」と交渉担当者は語っている。」
http://pub.ne.jp/Sightsong/?entry_id=2063655

日本国憲法は、国家が規定した法ではなく、国家権力に規範を与えるために存在する。(柄谷行人『政治と思想 1960-2011』)
http://pub.ne.jp/Sightsong/?entry_id=4387030

前回安部政権時に、対北朝鮮強硬姿勢をさらに過激化しようとしていたところ、水面下で北朝鮮と交渉していた米国に梯子をはずされ、直後に安部首相は辞任(豊下楢彦『「尖閣問題」とは何か』)。あんな戯画的なタカ派の主張は国を滅ぼすのみ。
http://pub.ne.jp/Sightsong/?entry_id=4661611

「リアリズムのない 「現実主義」という滑稽な姿は勿論維新の精神とは無縁である。」藤田省三
http://pub.ne.jp/Sightsong/?entry_id=4120423

勿論、自民党にリアリズムなど無い。大きなヴィジョンを掲げて実行できなかった民主党は力不足だったが、だからといって自民党が真っ当だということには決してならない。

結局、多くの有権者は雰囲気とか見てくれとか、白痴的な投票しかしないんだな。政策のことを考えるのはタブーであるかのように。どれだけ我が身に危険が迫っているか微塵も想像できずに。しかし、必ず再び決定的な揺り戻しがあるだろう。反撃はむしろこれからだ。

民主もなにも、民が無いんじゃ民主主義などあり得ない。というとニヒリズムか。

いずれ、憲法改正とか国防軍とか中国・北朝鮮との戦争とか言論統制とか基本的人権の軽視とか、そんなわかりきった矛盾が顕在化してきて、多くの人が「気がつく」。反撃はそのときだ。

菅原琢『世論の曲解』より:「(自民党は)…結局、民主党政権の失政を待つしかないだろう。もちろん、ただ待つだけでなく、そのときに受け皿となるべく、党を刷新し、人を入れ替え、有権者が投票したくなる政党として存在している必要がある。」後半をどう読むか。
http://pub.ne.jp/Sightsong/?entry_id=2637495