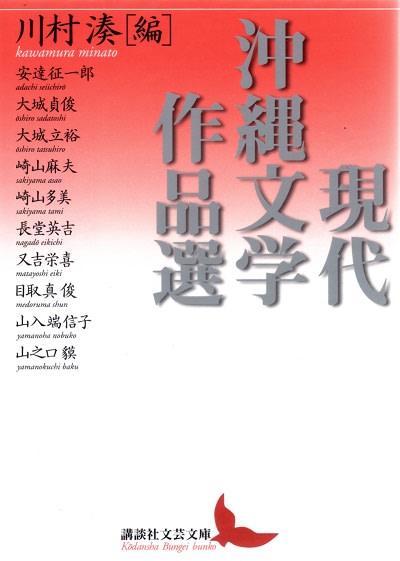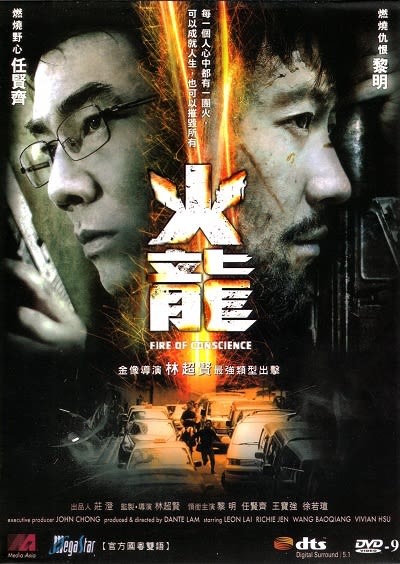先日、DJの井上和洋さんがustreamでロル・コクスヒルの珍しい音源をたくさん披露してくれていて、改めてコクスヒルというソプラノサックス奏者が好きになってしまった。
これまで魅力だと感じていた脱力感だけでなく、奇妙なバランス感のもとにメロディアスなプレイも行っていたことが新鮮だった。淡々とわけのわからないユーモアを提示する「静かなる過激」なのだった。中でも、突然段ボールとの共演盤は愉快だった(欲しい)。
コクスヒルは1998年に来日し、確か、突然段ボールともそのとき共演している。わたしが観た演奏は、歌舞伎町ナルシスでのサックスソロであり、ほとんど予備知識なしに聴いたものだから、激しいわけでも奇をてらうわけでもないプレイに、ピンとこなかった。魅力は聴いているうちにじわじわと身体に侵入してくるものだ。そんなわけで、2010年にロンドンのCafe Otoに「ロンドン・インプロヴァイザーズ・オーケストラ」を聴きに行ったとき、その中にコクスヒルが座っていて、またしてもユルいサックスを吹いているのを見つけたのは、とても嬉しいことだった。
アレックス・ワードとのデュオ『Old Sights, New Sounds』(Incus、2010年)は、同年の録音。コクスヒルが亡くなったのは2012年であるから、最晩年の時期の録音でもある。

Lol Coxhill (ss)
Alex Ward (cl)
これはメロディアスな愉快犯モノではない。淡々と、クラリネットとくんずほぐれつ吹き続けており、決して「吹きまくる」だとか「ブロウ」だとか「バトル」だとかの言葉は当てはまらない。サックスのベンドと脱力は相変わらずである。勿論、つまらないわけではない。聴けば聴くほど、「よくわからない人たち」感が強くなっていく不思議さがある。

コクスヒルを探せ(2010年) Leica M3、Summicron 50mmF2.0、Tri-X(+3)、フジブロ4号

コクスヒル(2010年) Leica M3、Summicron 50mmF2.0、Tri-X(+3)、フジブロ4号
●参照
○ロル・コクスヒルが亡くなった
○G.F.フィッツ-ジェラルド+ロル・コクスヒル『The Poppy-Seed Affair』
○ロル・コクスヒル、2010年2月、ロンドン
○ジミー・スミスとコクスヒル/ミントン/アクショテのクリスマス集