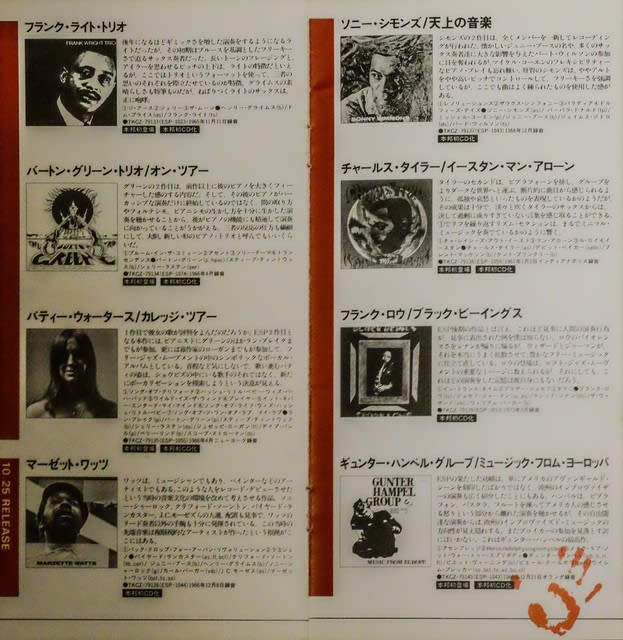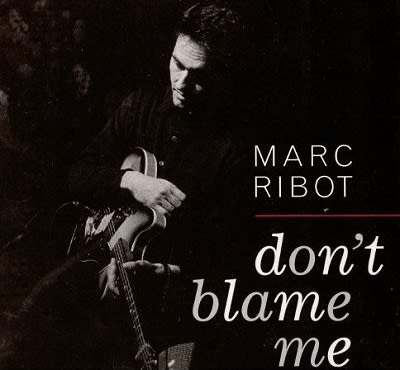鎌田慧『死に絶えた風景―ルポルタージュ・新日鉄』(現代教養文庫、原著1971/82/85年)を読む。

1950年に財閥解体とともに発足した八幡製鉄は、1970年に富士製鉄と合併して新日鉄(現・新日鉄住金)となる。本書は主にそれ以降の八幡製鉄所の姿を描いたルポである。著者はそのために労働下宿に入ってもいる。
読んでいて露わになっていくのは、既に斜陽であった石炭産業と同じ労働構造であることだ。あるいは現在の原子力産業との類似点を見出せるのかもしれない。何重もの下請けがあり、労働者はその何重もの搾取をもろに受ける。労働現場や下宿や地域からは逃げ出せない工夫が仕掛けられている。死者が高い割合で出ざるを得ない3K労働。
労働下宿は「飯場」そのものだった。明治30年代の官製製鉄所建設当時に「千人小屋」として登場し、形を変えて存続してきた。被差別出身者が多く、また炭鉱労働者が流れてきていた。かれらは自分にどんな労働が与えられるか知らずに、労働力供給機能を持つ労働下宿に生きた。
驚くべきは、明治以降の国策産業に、かれらが安く使い潰せる労働力として投入されたということだけではない。かれらは同じ鉄鋼産業の中でも使いまわされた。君津や光や堺に新しい製鉄所ができると、万単位の3K労働者が、「兵站所」の八幡から民族移動させられた。労働者はスクラップ・アンド・ビルドの手段に過ぎなかった。そして、北九州は公害の町から住宅地と化して、地域全体が労働下宿と化したのだった。
●鎌田慧
唖蝉坊と沖縄@韓国YMCA(2017年)
鎌田慧『怒りのいまを刻む』(2013年)
6.15沖縄意見広告運動報告集会(2012年)
金城実+鎌田慧+辛淑玉+石川文洋「差別の構造―沖縄という現場」(2010年)
鎌田慧『沖縄 抵抗と希望の島』(2010年)
『核分裂過程』、六ヶ所村関連の講演(菊川慶子、鎌田慧、鎌仲ひとみ)(2009年)
鎌田慧『抵抗する自由』 成田・三里塚のいま(2007年)
沖縄「集団自決」問題(8) 鎌田慧のレポート、『世界』、東京での大会(2007年)
鎌田慧『ルポ 戦後日本 50年の現場』(1995年)
鎌田慧『六ヶ所村の記録』(1991年)
ええじゃないかドブロク