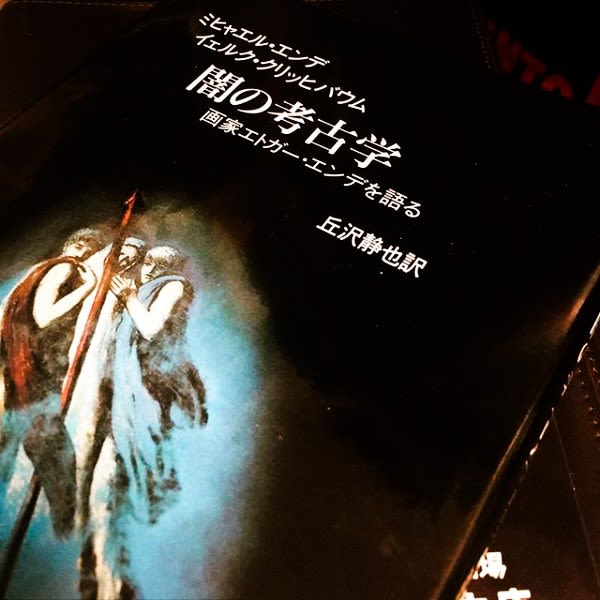デイヴィッド・マレイの1980年のソロ演奏が『Solo Live Vol.1』と『Solo Vol.II』の2枚に収録されている。(CD版は1枚)


David Murray (ts, bcl)
2枚とも1980年5月30日、スイスでのライヴ演奏である。このときマレイは25歳。『The London Concert』の翌々年であり、またこの直後からヘンリー・スレッギルらを擁したオクテットの吹き込みを始めている。つまり勢いがあって怖いものなどないであろう時期。
これを聴くと、マレイの傑出した才能がよくわかる。オリジナル曲でも、モンクの「We See」やスタンダード「Body and Soul」でも、大きなヴィブラートをもって、大きな音の振幅で、鼻歌でも歌うかのような余裕で狂暴でもあるソロを吹いている。ブルースやソウルの味わいもマレイの身体を通過して出てきている。
それと同時に、後年のマレイを思い出すと、内部からどうしようもなく出てくるコアの部分は衰えるにまかせて、味の部分だけを拡大して提示してきたことも実感される。しかし、この5月にベルギーで聴いたトリオは素晴らしかったのだ。かつての天才が、ポール・ニルセン・ラヴ、インゲブリグト・ホーケル・フラーテンという若い実力者に突き上げられて安穏としているわけにはいかない。また蘇ってほしい。
●デイヴィッド・マレイ
デイヴィッド・マレイ+ポール・ニルセン・ラヴ+インゲブリグト・ホーケル・フラーテン@オーステンデKAAP(2019年)
デイヴィッド・マレイ feat. ソール・ウィリアムズ『Blues for Memo』(2015年)
デイヴィッド・マレイ+ジェリ・アレン+テリ・リン・キャリントン『Perfection』(2015年)
デイヴィッド・マレイ・ビッグ・バンド featuring メイシー・グレイ@ブルーノート東京(2013年)
デイヴィッド・マレイ『Be My Monster Love』、『Rendezvous Suite』(2012、2009年)
ブッチ・モリス『Possible Universe / Conduction 192』(2010年)
ワールド・サキソフォン・カルテット『Yes We Can』(2009年)
デイヴィッド・マレイの映像『Saxophone Man』(2008、2010年)
デイヴィッド・マレイ『Live at the Edinburgh Jazz Festival』(2008年)
デイヴィッド・マレイの映像『Live in Berlin』(2007年)
マル・ウォルドロン最後の録音 デイヴィッド・マレイとのデュオ『Silence』(2001年)
デイヴィッド・マレイのグレイトフル・デッド集(1996年)
デイヴィッド・マレイの映像『Live at the Village Vanguard』(1996年)
ジョルジュ・アルヴァニタス+デイヴィッド・マレイ『Tea for Two』(1990年)
デイヴィッド・マレイ『Special Quartet』(1990年)
デイヴィッド・マレイ『The London Concert』(1978年)
デイヴィッド・マレイ『Live at the Lower Manhattan Ocean Club』(1977年)