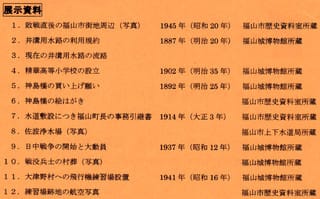御野村第五部のエンボス表示が見られる倉庫状の建物前の石碑には「金五百圓 ガソリン喞筒購入資金寄附 在布哇カフルイ 小林元市」の刻銘があった。布哇はハワイと読む。

ハワイ州マウイ島北部の都市カルフイ在住の日本人が消防用ガソリンポンプの購入資金として地元へ多額の寄附をしたという意味だろうか。石碑の南側が石仏を祀った祠である。


神辺と近世山陽道の一里塚
江戸時代の古地図を見ると,よく街道に一里塚の記号が書き入れてある。その起源についてはまちまちであるが,近世山陽道(旧山陽道)では制度的には寛永十年(1633)とも言われている。
当時の旅人にとって,一里塚は的確に目的地に近づく里程標であった。一里は三十六町と定められるのが普通であり,一里毎に道路の両側に土石を積んで堠とし,松或いは榎を植えた。その木陰は旅の疲れを休めるのに恰好な場所であり,多くの場合には喉をうるおすための井戸がその傍らにあった。
平野一里塚敷地内に,道路に面して遺在する小井戸。近隣の古老の話では非常に古く,江戸期の旅人に役立った井戸かもしれない。
『風土記№1 / 菅波堅次(1982)』の記述通り、平野の一里塚(南)敷地付近に井戸が残っていた。我々は木の有無についてばかり語りがちだが、井戸の果たした役割についても思いを馳せるべきであろう。福山市中心部(城下町)から神辺町平野まで(念仏街道…木綿橋→通り町→土橋・惣門→千田大峠→唐丸峠・湯坂峠→神辺宿)自転車で旅をするといろんな発見があって非常に面白い。



ハワイ州マウイ島北部の都市カルフイ在住の日本人が消防用ガソリンポンプの購入資金として地元へ多額の寄附をしたという意味だろうか。石碑の南側が石仏を祀った祠である。


神辺と近世山陽道の一里塚
江戸時代の古地図を見ると,よく街道に一里塚の記号が書き入れてある。その起源についてはまちまちであるが,近世山陽道(旧山陽道)では制度的には寛永十年(1633)とも言われている。
当時の旅人にとって,一里塚は的確に目的地に近づく里程標であった。一里は三十六町と定められるのが普通であり,一里毎に道路の両側に土石を積んで堠とし,松或いは榎を植えた。その木陰は旅の疲れを休めるのに恰好な場所であり,多くの場合には喉をうるおすための井戸がその傍らにあった。
平野一里塚敷地内に,道路に面して遺在する小井戸。近隣の古老の話では非常に古く,江戸期の旅人に役立った井戸かもしれない。
『風土記№1 / 菅波堅次(1982)』の記述通り、平野の一里塚(南)敷地付近に井戸が残っていた。我々は木の有無についてばかり語りがちだが、井戸の果たした役割についても思いを馳せるべきであろう。福山市中心部(城下町)から神辺町平野まで(念仏街道…木綿橋→通り町→土橋・惣門→千田大峠→唐丸峠・湯坂峠→神辺宿)自転車で旅をするといろんな発見があって非常に面白い。