昔、会津地方にオオルリシジミというチョウが生息していた。しかし半世紀以上も前にすでに絶滅してしまった。
今、このチョウが幼虫のときの食草クララが花をつけている。
【オオルリシジミ ネットより】

いつも里山の自然に触れながら、いま細々と生息している希少なチョウやトンボを心配している。
たとえば最近、十数年来虫たちを観察していたフィールドで、大規模な堰の改修工事があった。
木漏れ日にイトトンボが舞い、クワガタやチョウが集まった林の多くの樹木が伐採され、コンクリートの護岸に変わった。
林間に道路ができて、にぎやかだった虫たちの楽園は消滅してしまった。環境アセスメントは十分だったろうか。
生物多様性という言葉がある。
数十億年の生物の進化の歴史が多くの生物をはぐくんできたが、毎日多くの生き物が絶滅している。
すべてが人間の行為によるものだ。
小さな虫たちの命を見つめ、絶滅を防ぐためのあらゆる保全対策が急務だと思っている。
【今年も会いたいマダラナニワトンボ 2009.10撮】












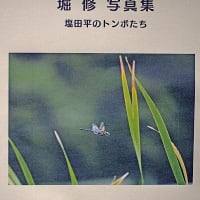








人間の叡智の限界に溜息をついたヒメオオです。