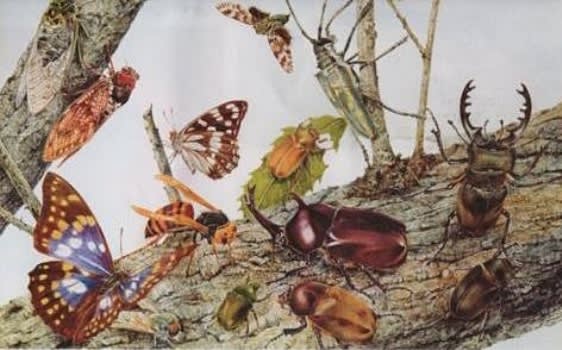【巨大な蕗の薹(トウブキ)】
雪のあるうちは近づけけなかったが、しばらくぶりに庭の木々と話した。
まだ吹く風も冷たい庭に、愛おしい一木一草を見つめた。
ジンチョウゲの花芽はいよいよ咲きだしそうだ。
ユキヤナギの芽が少し色付いてきたか、薔薇の紅い芽があざやかだ。
イロハモミジの紅い芽がかわいい。ライラックも赤く、大分膨らんでいた。
 【沈丁花の花芽】
【沈丁花の花芽】
 【イロハモミジの芽】
【イロハモミジの芽】
 【ライラックの芽】
【ライラックの芽】
クマシデの幹には縦の筋がはいっている。イタヤカエデの木の幹の皺は風格を感じさせるものだった。
木の肌も、ウメ、イチョウ、トウカエデ、ヒマラヤスギ・・・それぞれに興味深いものだ。
裏庭に回ると、何と雪の消えたムクゲの根元に大きなフキノトウが黄緑色に輝いていた。
いているではないか。大きいのは直径4~5cm、こんなに見事なフキノトウを見るのは初めてだった。
ついこの前、雪の消え始めた山里に探したフキノトウが、目と鼻の先にあろうとは。
まさに「灯台もと暗し」とはこのことか。
そういえば、数年前に信州の妻の実家からもらったトウブキを植えておいたことを思い出した。
冬を耐えた木々もそろそろ目覚め始めようとしていた。
≪樹皮≫
 【イチョウの樹皮】
【イチョウの樹皮】
 【ヒマラヤスギの樹皮】
【ヒマラヤスギの樹皮】
 【イタヤカエデの樹皮】
【イタヤカエデの樹皮】
 【トウカエデの樹皮】
【トウカエデの樹皮】
 【クマシデの樹皮】
【クマシデの樹皮】

雪のあるうちは近づけけなかったが、しばらくぶりに庭の木々と話した。
まだ吹く風も冷たい庭に、愛おしい一木一草を見つめた。
ジンチョウゲの花芽はいよいよ咲きだしそうだ。
ユキヤナギの芽が少し色付いてきたか、薔薇の紅い芽があざやかだ。
イロハモミジの紅い芽がかわいい。ライラックも赤く、大分膨らんでいた。
 【沈丁花の花芽】
【沈丁花の花芽】 【イロハモミジの芽】
【イロハモミジの芽】 【ライラックの芽】
【ライラックの芽】クマシデの幹には縦の筋がはいっている。イタヤカエデの木の幹の皺は風格を感じさせるものだった。
木の肌も、ウメ、イチョウ、トウカエデ、ヒマラヤスギ・・・それぞれに興味深いものだ。
裏庭に回ると、何と雪の消えたムクゲの根元に大きなフキノトウが黄緑色に輝いていた。
いているではないか。大きいのは直径4~5cm、こんなに見事なフキノトウを見るのは初めてだった。
ついこの前、雪の消え始めた山里に探したフキノトウが、目と鼻の先にあろうとは。
まさに「灯台もと暗し」とはこのことか。
そういえば、数年前に信州の妻の実家からもらったトウブキを植えておいたことを思い出した。
冬を耐えた木々もそろそろ目覚め始めようとしていた。
≪樹皮≫
 【イチョウの樹皮】
【イチョウの樹皮】 【ヒマラヤスギの樹皮】
【ヒマラヤスギの樹皮】 【イタヤカエデの樹皮】
【イタヤカエデの樹皮】 【トウカエデの樹皮】
【トウカエデの樹皮】 【クマシデの樹皮】
【クマシデの樹皮】



















 【朝河博士の肖像画】
【朝河博士の肖像画】 【2階の講堂】
【2階の講堂】 【旧開智学校】
【旧開智学校】