都月満夫の絵手紙ひろば💖一語一絵💖
都月満夫の短編小説集
「出雲の神様の縁結び」
「ケンちゃんが惚れた女」
「惚れた女が死んだ夜」
「羆撃ち(くまうち)・私の爺さんの話」
「郭公の家」
「クラスメイト」
「白い女」
「逢縁機縁」
「人殺し」
「春の大雪」
「人魚を食った女」
「叫夢 -SCREAM-」
「ヤメ検弁護士」
「十八年目の恋」
「特別失踪者殺人事件」(退屈刑事2)
「ママは外国人」
「タクシーで…」(ドーナツ屋3)
「寿司屋で…」(ドーナツ屋2)
「退屈刑事(たいくつでか)」
「愛が牙を剥く」
「恋愛詐欺師」
「ドーナツ屋で…」
「桜の木」
「潤子のパンツ」
「出産請負会社」
「闇の中」
「桜・咲爛(さくら・さくらん)」
「しあわせと云う名の猫」
「蜃気楼の時計」
「鰯雲が流れる午後」
「イヴが微笑んだ日」
「桜の花が咲いた夜」
「紅葉のように燃えた夜」
「草原の対決」【児童】
「おとうさんのただいま」【児童】
「七夕・隣の客」(第一部)
「七夕・隣の客」(第二部)
「桜の花が散った夜」
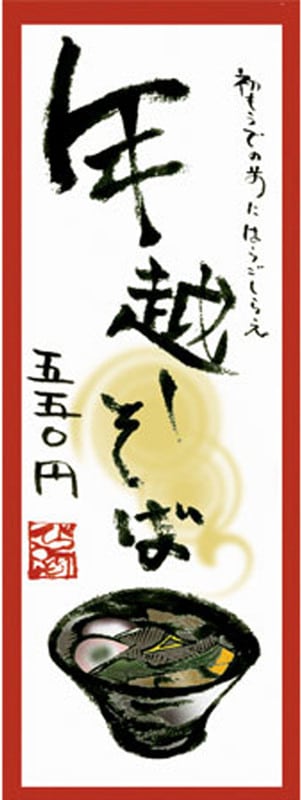 年越し蕎麦(としこしそば)とは、大晦日(12月31日)に縁起をかついで食べられる蕎麦のことだそうです。
年越し蕎麦(としこしそば)とは、大晦日(12月31日)に縁起をかついで食べられる蕎麦のことだそうです。
元々、江戸時代中期には月末に蕎麦を食べる「三十日(みそか)そば」という習慣があり、 大晦日のみにその習慣が残ったものと考えられているようです。
大晦日のみにその習慣が残ったものと考えられているようです。
年越し蕎麦の由来とされる説は「細く長く達者に暮らせることを願う」というものがもっとも一般的です。他に「蕎麦が切れやすいことから、一年間の苦労を切り捨て翌年に持ち越さないよう願った」という説もありますが、後付けの説とも言われています。
1年の最後の日を「大晦日(おおみそか)」または「大晦(おおつごもり)」とも呼びます。「晦日(みそか)」とは毎月の末日のことです。一方「晦〔つごもり〕」とは、"月が隠れる日"すなわち「月隠〔つきごもり〕」が訛ったもので、どちらも毎月の末日を指します。"1年の最後の特別な末日"を表すため、末日を表す2つの言葉のそれぞれ「大」を付けて「大晦日」「大晦」と言います。
家族揃って新年を迎える
12月31日「大晦日」には1年の間に受けた罪や穢れ(けがれ)を祓うために、大祓い(おおはらい)が宮中や全国の神社で執り行われます。仏教色が強い夏のお盆に対して、正月の行事の1つである大晦日は新しい年の穀物に実りをもたらし、私たちに命(年)を与えてくださる歳神様を祀る意味を強く感じます。
昔、1日は夜から始まり朝に続くと考えられていたため、大晦日は既に新しい年の始まりでした。そのため、この日に縁起物であるお頭(かしら)付の魚を用いた正式な食事やお雑煮などを家族揃って食べるなどするのです。
これを「年越し」「年取り」といいます。年越しの夜は除夜(じょや)ともいいます。かつて、除夜は歳神様を迎えるため一晩中起きている習わしがあり、この夜に早く寝ると白髪になる、シワが寄るなどの俗信があったそうです。
古くから行われていた年越しの行事
 大晦日の行事は古く、平安時代頃から行われていたようです。本来大晦日は歳神様を祀るための準備が行われる日でしたが、仏教の浸透とともに、除夜の鐘をつく習慣も生まれました。
大晦日の行事は古く、平安時代頃から行われていたようです。本来大晦日は歳神様を祀るための準備が行われる日でしたが、仏教の浸透とともに、除夜の鐘をつく習慣も生まれました。
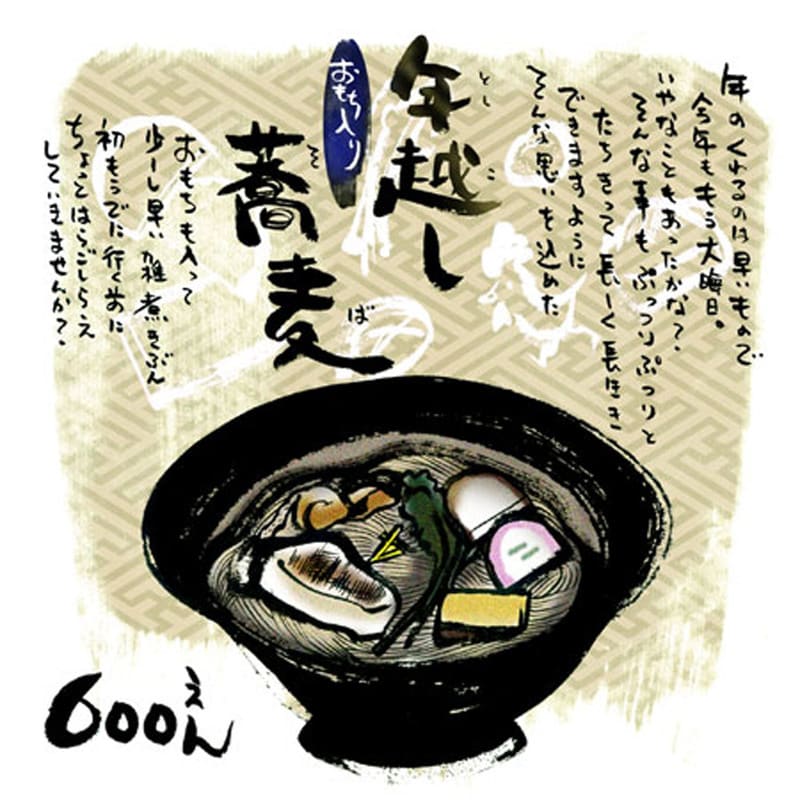
 大晦日の風物詩である年越し蕎麦(としこしそば)は江戸時代頃から食べられるようになりました。金箔職人が飛び散った金箔を集めるのに蕎麦粉を使ったことから、年越し蕎麦を残すと翌年金運に恵まれないと言われています。
大晦日の風物詩である年越し蕎麦(としこしそば)は江戸時代頃から食べられるようになりました。金箔職人が飛び散った金箔を集めるのに蕎麦粉を使ったことから、年越し蕎麦を残すと翌年金運に恵まれないと言われています。
また、江戸時代の町人は大晦日になると借金の返済に追われていました。これは、年内に借金を返済し、新しい気持ちで新年を迎えたいという人が多かったからです。
 私が就職したころは、大晦日は大変でした。合言葉は「紅白歌合戦を見よう。」でした。大晦日に売り掛けを支払う人が多く集金に追われていました。集めては銀行に持ち込み、また集金です。銀行も商店も遅くまで開いていました。
私が就職したころは、大晦日は大変でした。合言葉は「紅白歌合戦を見よう。」でした。大晦日に売り掛けを支払う人が多く集金に追われていました。集めては銀行に持ち込み、また集金です。銀行も商店も遅くまで開いていました。
結局「「紅白歌合戦」までには帰れないのです。お盆と年末にしか支払をしない人もいたくらいです。
その代わりといってはなんですが、元旦は何処の店も休みでした。
したっけ。




























