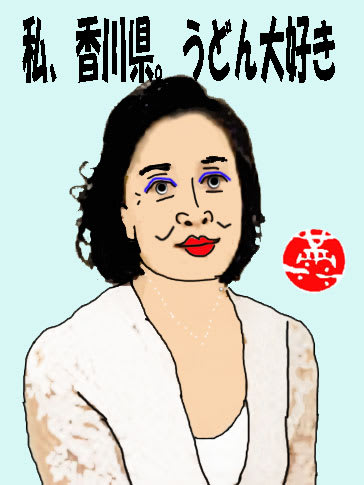都月満夫の絵手紙ひろば💖一語一絵💖
都月満夫の短編小説集
「出雲の神様の縁結び」
「ケンちゃんが惚れた女」
「惚れた女が死んだ夜」
「羆撃ち(くまうち)・私の爺さんの話」
「郭公の家」
「クラスメイト」
「白い女」
「逢縁機縁」
「人殺し」
「春の大雪」
「人魚を食った女」
「叫夢 -SCREAM-」
「ヤメ検弁護士」
「十八年目の恋」
「特別失踪者殺人事件」(退屈刑事2)
「ママは外国人」
「タクシーで…」(ドーナツ屋3)
「寿司屋で…」(ドーナツ屋2)
「退屈刑事(たいくつでか)」
「愛が牙を剥く」
「恋愛詐欺師」
「ドーナツ屋で…」
「桜の木」
「潤子のパンツ」
「出産請負会社」
「闇の中」
「桜・咲爛(さくら・さくらん)」
「しあわせと云う名の猫」
「蜃気楼の時計」
「鰯雲が流れる午後」
「イヴが微笑んだ日」
「桜の花が咲いた夜」
「紅葉のように燃えた夜」
「草原の対決」【児童】
「おとうさんのただいま」【児童】
「七夕・隣の客」(第一部)
「七夕・隣の客」(第二部)
「桜の花が散った夜」

仏教の発祥の地といわれ、最初の普及地であるインドだが、現在では仏教徒は人口の1パーセント程度しかいないそうです。
ヒンドゥー教80%イスラム教13%だそうです。
インドに仏教が何故残らなかったのかは、平等を説く仏教がカースト制度のインド社会に受け入れられなかったからだといわれています。
ちなみに、仏教徒が多い国は
1.中国
2.日本
3.タイ
だそうですが、日本は本当の仏教徒が多いといえるのでしょうか。お葬式は仏式が多いですが、お正月には神道になります。クリスマスまで行う国です。
真の仏教徒というのはどのような人をいうのでしょうか・・・。
したっけ。
エンジュ (槐) マメ科 エンジュ属 落葉高木
学名:Sophora japonica
花期:7~8月
花色:白~淡黄色 小花径:1~1.5cm 花弁形:蝶形 両性花
樹高:10~25m
分布:北海道~九州の日本、朝鮮半島、中国
成実期:10月 果実径:4~8cm 種子色:褐色 果実形:鞘状
中国原産で、夏、枝先から円錐花序を伸ばし多数の白い蝶形の小花を集合させて咲かせる広葉樹です。
花は蜜源となっており多数の蜂や蝶、小鳥が飛んできます。葉形はニセアカシアと同様、奇数羽状複葉で、小葉が互生して付きます。相当高くまで生長する木で、マンションでは6~7階まで達してしまいます。
中国では神聖木とされ出世への縁起を担いで植えられます。公害性に強いので街路樹や庭木とされます。花の蕾は槐花と言いルチンを多量に含むので、毛細血管を回復し止血や高血圧用の薬の原料とされます。
果実は槐実または槐角と呼ばれ痔の薬となりますが、形は数珠状にくびれた豆花で粘液を含み乾きにくく裂開しません。尚、「エンジュ(延寿)」という名で、仏壇、鍋敷き等の彫刻、細工・加工物の材としているものは、イヌエンジュという別の木です。
したっけ。
カスタネットの語源は、スペイン語で「栗」を表す「カスターニャ(castaña)」という単語だそうです。ギリシャでは、栗の木で作っていたからとも、形が栗の実に似ているからともいわれています。手のひらに納まるくらいの丸い貝型の木片を2枚合わせ、これを打ち合わせることによって音を出す楽器ですね。
ところが、教育用楽器として、また幼児のおもちゃとしてよく見られる赤色と青色の板(一方の板には突起がついている)をゴムひもでくくったものは、「ミハルス」というものらしい。日本の舞踊家「千葉みはる氏」が、カスタネットをもとに考案したものだそうです。(正確には「カスタネット」に似た楽器)
学校のカスタネットが赤と青の二色なのは、カスタネットが学校教育に取り入れられる時(昭和22年:1947年)、男の子用の青と女の子用の赤に色分けしていたそうです。
しかし毎年変わる児童数や男女比を考えると結局男女別に塗り分けるのは不経済なので、赤青二色で男女区別なく使えるようにしたそうです。
したっけ。
日本には、もともと丑の日に「うどん」、「うり」、「ウド」などの「う」の付くものを食べると体に良く、暑さに負けないとの言い伝えがあったそうです。
では何故、ウナギを食べるようになったのでしょう。夏バテ防止のためにウナギを、という食習慣は江戸時代後期になってからとのこと。
当時の鰻屋さんは夏場に売上が落ちるということで悩んでいたのです。
そこで、相談をしたのが「平賀源内」さん。発明家なのですが、今でいうコンサルタントのようなこともしていたようですね。
で、この源内さんが「夏バテを防ぐ為に土用の丑の日にウナギを食べる」と言う理由と「本日土用丑の日」というキャッチコピーを考え出して鰻屋さんがそれを大きく書いた幟(のぼり)を店頭に出したのです。
源内さんは、日本最初のコピーライターということになります。
すると・・・
それが評判となって売り上げは倍増。それどころか鰻屋さんは夏場の方が忙しくなったそうです。
それにしても平賀源内は栄養学も無い時代に、どうして夏バテに鰻をという組み合わせを思いついたのでしょう。
その答えは奈良時代にありました。
『万葉集』を編纂した一人として知られる歌人「大伴家持」が夏痩せしてしまった知人に、こんな歌を贈っています。
「夏痩せに よしといふものぞ むなぎ(鰻)とり召せ」。
つまり、夏痩せには鰻を食べるといいらしいですよってことですね。
源内さんのキャッチコピーは大伴家持さんのパクリだったというオチでございます。
今日は「うどん」に続き2回目の更新です。「うどんの起源」も読んでいってください。
したっけ。
小麦粉を使った「麺」の代表的なものに、「うどん」・「そうめん」・「ひやむぎ」があります。
「うどん」の原形は、もともと中国のもので、広い意味の麺類として、奈良時代(8世紀)に日本に入ってきました。
それらは、小麦粉を練って形を整え、煮たり焼いたりしたもので「唐菓子」と呼ばれていました。その中のあるものがヒントになって、日本の麺類が生まれたと考えられています。
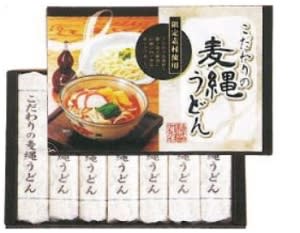 今日の干しうどんに近いものは、奈良時代に遣唐使によって中国から渡来した菓餅14種の中にある「索餅(さくべい)」で、和名で「麦索(むぎなわ)」と呼ばれ、太く伸ばし索(なわ)のようによったもので、奈良時代の終わり頃には、流通する食品になっていたと考えられています。
今日の干しうどんに近いものは、奈良時代に遣唐使によって中国から渡来した菓餅14種の中にある「索餅(さくべい)」で、和名で「麦索(むぎなわ)」と呼ばれ、太く伸ばし索(なわ)のようによったもので、奈良時代の終わり頃には、流通する食品になっていたと考えられています。
 平安時代中期の法典『延喜式』に記載されている「索餅」の作り方をみると、小麦粉と米粉を混合して臼に入れ、塩湯で練り合わせたものです。
平安時代中期の法典『延喜式』に記載されている「索餅」の作り方をみると、小麦粉と米粉を混合して臼に入れ、塩湯で練り合わせたものです。
えんぎしき【延喜式】
弘仁式・貞観式以降の律令の施行細則を取捨・集大成したもの。50巻。三代式の一。延喜5年(905)醍醐天皇の勅により藤原時平・忠平らが編集。延長5年(927)成立。康保4年(967)施行。
大辞泉
鎌倉時代になると新しい麺の製法が禅僧によってもたらされます。
挽き臼で挽かれた粒子の細かい小麦粉だけで作る麺です。
しかも小麦粉に食塩と水を混ぜてよく練り、植物油を塗って延ばす全く新しい製麺法で、「素麺」と呼ばれました。この「素麺」の製法が主流になると米粉が混入された「索餅」は、貴族階級の祝膳の菓子のような形でかろうじて残っていきます。
同じ時期に小麦粉だけの、麺棒と案、包丁で作る「切り麦」が登場します。
「切り麦」を熱くして食べるものを「熱麦(あつむぎ)」、冷やして食べるものを「冷麦(ひやむぎ)」呼ぶようになりました。いまは「冷麦」だけが言葉として残っていますが、「うどん」と「冷麦」は同じものだったのです。
ですから、「冷麦」を買ってきて熱いまま食べたら「細いうどん」ということになります。
上記のように、「うどん」の起源は、中国の切麺を鎌倉時代に取り入れた「切り麦」です。室町時代には現在とほぼ同じ製法で作られています。それがやがて「うどん」と呼ばれるようになりました。
うどん店は安土桃山時代から見られ、江戸時代初期には街道筋に普及していきます。江戸中期の元禄時代には江戸ではそば屋を圧倒してうどん屋が優位になります。しかしこれは都市での話で、農村では事情が違ったようです。
 うどんは祝い事ある時のハレの食べもので、江戸時代には日常農村でうどんを打って食べることをお上から禁じられていました。贅沢と見られていて、田舎でうどんを打つのは検視の訪問の時か祝い事の時にのみ許されていました。寛永19年(1642年)には飢饉対策として幕府から代官に御触書が出されていて、農民に対しうどん・きり麦・そうめん等の売買を禁じています。禁じられていても普及していたからだと思います。
うどんは祝い事ある時のハレの食べもので、江戸時代には日常農村でうどんを打って食べることをお上から禁じられていました。贅沢と見られていて、田舎でうどんを打つのは検視の訪問の時か祝い事の時にのみ許されていました。寛永19年(1642年)には飢饉対策として幕府から代官に御触書が出されていて、農民に対しうどん・きり麦・そうめん等の売買を禁じています。禁じられていても普及していたからだと思います。
「うどん」を語源的にみると、奈良時代の「唐菓子」の「混沌(こんとん)」があげられます。「混沌」は餡を入れた小麦粉の団子を煮たもので、熱い汁の中でどろどろしている食べ物だそうです。
「うどん」といえば、「讃岐うどん」ですが、四国には餡餅を入れたお雑煮があると、香川県出身の人に聞いたことがあります。もしかしたら、「混沌」の名残かもしれません。
いまの「うどん」とは違うようですが、江戸時代後期の『嬉遊笑覧(きゆうしょうらん)』という本には次のように書かれているそうです。
「混沌は温麺にて、あつむぎといふものなりといへり」。
きゆうしょうらん【嬉遊笑覧】
江戸後期の随筆。12巻。付録1巻。喜多村信節(きたむらのぶよ)著。文政13年(1830)成立。諸書から江戸の風俗習慣や歌舞音曲などを中心に社会万般の記事を集め、28項目に類別して叙述したもの。
大辞泉
唐菓子の「混沌(こんとん)」が食物なので食偏を与えられて「餛飩(こんとん)」となり、それが熱いからというので「温飩(おんとん)」になりました。そして温をもう一度食偏に変え「饂飩(うんとん)」となり、これが転化して「うどん」になったということです。
現代でも「うどん」の漢字表記は「饂飩」と書きます。
したっけ。」
 名古屋名物といえば、「金のシャチホコ」と「きしめん」と相場は決まっています。
名古屋名物といえば、「金のシャチホコ」と「きしめん」と相場は決まっています。
この「きしめん」、漢字では「棊子麺」と書きます。「棊」とは「碁」に同じで「棊子」とは「碁石」のことだそうです。「きしめん」と「碁石」、何のつながりもないように思えますが、これがおおありなのです。
「きしめん」は、はいまでは長い平打ちの麺ですが、もともとは丸い「碁石」のような形をしていたのです。
江戸時代末に発行された『貞丈雑記』に書かれているところでは「小麦粉を練って薄くのばし、竹の筒を使って碁石の様な丸い形に切り取り、それを茹で上げた物に、きな粉を振りかけたり、汁で煮たりして食べた」とされているそうです。この丸い形を、白い碁石に見立てた名前だったのです。
ていじょうざっき〔テイヂヤウザツキ〕【貞丈雑記】
江戸時代の有職故実書。16巻。伊勢貞丈(いせさだたけ)著。子孫のために書き記した宝暦13年(1763)以降の雑録を、死後弟子が校訂して天保14年(1843)に刊行。武家の有職に関する事項を36部門に分けて記したもの。
大辞泉
碁子麺(きしめん)は鎌倉時代に中国から伝えられた点心の1種で、小麦粉で作った碁石形の小さい丸い麺それが、いまのように変わったのは江戸時代のことだそうです。
 『守貞謾稿』(1853年)には「今江戸にてひもかはという平打うどんを、尾の名古屋にてはきしめんというなり。」とありますから、「きしめん」の名は江戸後期に名古屋から伝わったようです。
『守貞謾稿』(1853年)には「今江戸にてひもかはという平打うどんを、尾の名古屋にてはきしめんというなり。」とありますから、「きしめん」の名は江戸後期に名古屋から伝わったようです。
形は変わっても、「棊子麺」の名前だけは残ったということです。
そのほかの説も、紹介しておきましょう。
「雉麺(きじめん)説」 。その昔、雉の肉を入れた「雉麺」という麺類があり、後にその名がきしめんに変化した説。
「雉麺」は元来、尾張徳川家だけに食することが許された特別な食べ物で、ある時、藩主が「雉の肉の代わりに油揚げを入れれば、庶民に食べさせてもかまわない」と言ったことから、油揚げを入れて庶民も食するようになったと言われています。
そんな特別な食べ物なら、名古屋だけで食べていればいいんでないかい。
「紀州麺説」。 紀州藩の殿様が尾張藩の殿様におみやげで持ってきた麺類を「紀州麺」とよんでおり、それが変化して「きしめん」になったという説などがあります。
 名古屋土産の定番お菓子「ういろう」も、鎌倉時代に生まれで長い歴史をもつ、もっちりとした歯ごたえと上品な甘さがうれしいお菓子です、とあります。
名古屋土産の定番お菓子「ういろう」も、鎌倉時代に生まれで長い歴史をもつ、もっちりとした歯ごたえと上品な甘さがうれしいお菓子です、とあります。
もっちりとした歯ごたえと上品な甘さが、中途半端であまりピンとこないのは私だけでしょうか・・・。
「きしめん」、「ういろう」、「赤味噌」と名古屋の食文化はなにかと個性的です。
名古屋在住のみなさん、これはあくまで個人的な見解です。名古屋には何の恨みもありませんよ。
したっけ。
世の女性たちは、宝石には目がないという方も多いのではないでしょうか。男性諸氏はそんな女性に、宝石の名前を漢字で書いて贈ったら彼女の心をつかむことができるかもしれませんよ。
漢字で宝石の名前を書きますから、読んでみてください。「アカダマイシ」なんて読んだら、ガッカリされますよ。
② 翡翠
③ 青玉石
④ 紅玉石
⑤ 珊瑚
⑥ 柘榴石
⑦ 琥珀
⑧ 土耳古石
⑨ 紫水晶
⑩ 緑玉石
⑪ 黄玉石
⑫ 蛋白石
⑬ 瑠璃
⑭ 月長石
⑮ 真珠
⑯ 瑪瑙
どうです読めましたか?
① 金剛石 ダイヤモンド(こんごうせき):宝石の中ではもっとも魅力ある光沢がある。四月の誕生石。
② 翡翠 ひすい:緑色でガラス光沢がある。カワセミの別名。雄が翡、雌が翠。美しさをカワセミ(翡翠)の背にたとえた名前。
③ 青玉石 サファイア(せいぎょくせき):透明な清澄色の宝石。九月の誕生石。
④ 紅玉石 ルビー(こうぎょくせき):濃紅色で透明なものが優良とされる。七月の誕生石。
⑤ 珊瑚 さんご:花虫類サンゴ科に属する腔腸動物の総称。固体が死んだ骨軸を加工してネックレスなどをつくる。三月の誕生石。
⑥ 柘榴石 ざくろいし:色は黄・赤・黒・褐色などで、主に研磨材に利用し、美しいものは宝石とする。ガーネットのこと。一月の誕生石。
⑦ 琥珀 こはく:地質時代の樹脂の化石。黄色で半透明、樹脂光沢があり、しばしば昆虫などの入ったものも見つかる。アクセサリーなどに利用
⑧ 土耳古石 とるこいし:ペルシャからトルコを経て、西欧に入ったので、この名がつきました。空色または、青緑色。十二月の誕生石。
⑨ 紫水晶 アメジスト(むらさきずいしょう):水晶の中でももっとも高く評価され、日本人には特に愛好される宝石。二月の誕生石。
⑩ 緑玉石 エメラルド(りょくぎょくせき):緑柱石の中で濃緑色のものをいう。宝石の女王といわれる。翠玉(すいぎょく)ともいう。五月の誕生石。
⑪ 黄玉石 トパーズ:黄色のトパーズは宝石としての価値が高いが、無色透明であることが多い。十一月の誕生石。
⑫ 蛋白石 オパール(たんぱくせき):半透明または不透明の乳白色で、不純物により種々の色が現れる。美しい真珠光沢のあるものは宝石となる。十月の誕生石。
⑬ 瑠璃 るり:古代インド・中国などで珍重した宝石。七宝の一。青色の美しい宝石。赤・緑・紺・紫色などもあるという。ラピスラズリのこと。
⑭ 月長石 ムーンストーン(げっちょうせき):乳白色、半透明で、カットされた曲面から青色の閃光を放つもの。
⑮ 真珠 しんじゅ:アコヤガイ・シロチョウガイなどの体内にできる球状の物質。体内に入り込んだ異物に分泌液が層状に沈着して作られる。天然に産するが、養殖も盛ん。銀白色の光沢があり宝石として珍重される。パール。六月の誕生石。
⑯ 瑪瑙 めのう:石英の結晶の集合体(玉髄(ぎょくずい))で、色や透明度の違いにより層状の縞模様をもつもの。色は乳白・灰・赤褐色など変化に富む。赤縞瑪瑙はサードにクスと呼ばれる。八月の誕生石。
ほう‐せき【宝石】
産出量が少なく、硬度が高くて、美しい光彩をもち、装飾用としての価値が高い非金属鉱物。ダイヤモンド・エメラルド・サファイア・ルビーなど。
大辞泉
「ボクにとっては、君の瞳がどんな宝石よりも美しい。」なんて、気障な台詞は時代遅れかもしれませんよ。
したっけ。
<サッカー女子W杯>日本、初優勝 PK戦の末
【フランクフルト(ドイツ)江連能弘】サッカーの女子ワールドカップ(W杯)ドイツ大会は17日(日本時間18日)、当地で決勝を行い、日本(なでしこジャパン)がPK戦の末、世界ランキング1位の米国を降し、初優勝した。年齢制限がないフル代表の国際大会で日本が優勝するのは男女を通じて初めて。澤(INAC)が通算5得点で大会得点王に輝いた。(毎日新聞)
大和撫子とは、「クシナダヒメ」の別称。
クシナダヒメは、日本神話に登場する女神。『古事記』では櫛名田比売、『日本書紀』では奇稲田姫と表記する。
ヤマタノオロチ退治の説話で登場する。アシナヅチ・テナヅチの8人の娘の中で最後に残った娘。ヤマタノオロチの生贄にされそうになっていたところを、スサノオにより姿を変えられて櫛になる。スサノオはこの櫛を頭に挿してヤマタノオロチと戦い退治する。その後、救われたクシナダヒメはスサノオの妻となった。
やまと‐なでしこ【大和撫子】
1 ナデシコの別名。2 日本女性の清楚な美しさをほめていう語。
大辞泉
撫子(なでしこ) 科名:撫子科
別名:大和撫子,河原撫子
試合後のインタビューで、監督が、「小さい娘たちがよく頑張った。」と、笑顔で語っていたのがとても印象的でした。それとフェアープレー賞というのも、さすが「なでしこ」という感じで、いいですね。
早朝に起きた甲斐がありました。
澤選手、頑張りましたね。私も頑張りましたので、寝ます。
したっけ。
安全だといわれた日本の原子力発電所が今大変なことになっています。いろいろ先行きを「杞憂(きゆう)」されておられる方も多いかと思います。
さて、この「杞憂」にはどんな謂われ(いわれ)があるのでしょう。
周(しゅう)代の頃(紀元前1046年頃 - 紀元前256年は、中国古代の王朝)、今の河南省あたりに「杞という国」があったそうです。
そこに住む一人の男は、あることを考えると心配で、食事ものどを通らず、夜も眠れずにいたそうです。
「もし天と地が崩れてしまったら、身のよせるところがなくなってしまいどうすればいいんだろう。」
一方、そんな友人を見ていて心配をした男がおりました。彼は出かけていって、男に言い聞かせました。
「天なんてものは空気が積もってできているのさ。空気のないところなんてありゃしないよ。体を曲げたり伸ばしたりしている今だって、天の中でやっているのさ。どうして天がなくなるなんて心配するなよ。」
「天が空気の積もったものならお日様や月や星が何で落ちてこないかなぁ。」
「お日様や月や星などは空気が積もった中で輝いている部分なのさ。万が一、落ちてきたって当たって空気だ。怪我なんかしないよ。」
「それなら、どうして大地は壊れないのだろう?」
「大地は土が積もっただけで、それが四方に満ち満ちているので、土のないところなんかありゃしない。飛んだって跳ねたって、いつも大地の上にいるじゃないか。だから、大地が壊れるなんて心配いらないよ。」
それを聞いて、心配していた男はようやく不安が治まり、たいそう喜んだそうです。言い聞かせた男も気分が晴れて安心したそうです。
これが、「杞憂」(いらぬ取り越し苦労をする)(いわれなき心配をする)の語源となったエピソードです。
き‐ゆう【杞憂】
《中国古代の杞の人が天が崩れ落ちてきはしないかと心配したという、「列子」天瑞の故事から》心配する必要のないことをあれこれ心配すること。取り越し苦労。「―に終わる」
大辞泉
「杞憂」は列子(中国、※戦国時代の思想家)の「天瑞篇」に出展されています。列氏はその解釈として、こう付け加えています。
「天地が壊れるという者も、壊れないという者も間違えている。壊れるとか壊れないとかは我々の知ることのできないものだ。さりとて、壊れるという者にもひとつの道理があり、壊れないというものにもひとつの道理がある。生は死を知らないし、死は生を知らない。将来は過去を知らないし、過去は将来を知らない。天地が壊れるとか、壊れないとかをどうして我々が心に入れて考慮できようか?」
つまり、天地が壊れるというものにも、壊れないというものにもそれぞれの言い分があり、誰にもそんなことはわからないのだというのです。
※戦国時代:紀元前403年に晋が韓・ 魏・趙の3つの国に分かれてから、紀元前221年に秦による統一がなされるまでをいう。
唐の時代になり、李白(701-762:中国、盛唐の詩人)は「杞の国人は無事なれや、天の傾ぐを憂うなり」とうたっています。李白は取り越し苦労など味気ないという風潮に対して、古代の人たちの実直で虚心のない人柄を温かく肯定しているのです。
今、大地が割れるような地震のために、天地には放射能がばら撒かれました。原子力発電所が壊れるなんて「杞憂」だといい続けてきたことが、今や「杞憂」ではなくなったのです。私たちは、謙虚にこのことを受け止め、将来に「杞憂」のないようにしなければなりません。
天が落ちてくる。大地が割れるといった男を笑うことはできません。
四字熟語では「杞人天憂(きじんてんゆう)」と言います。
したっけ。