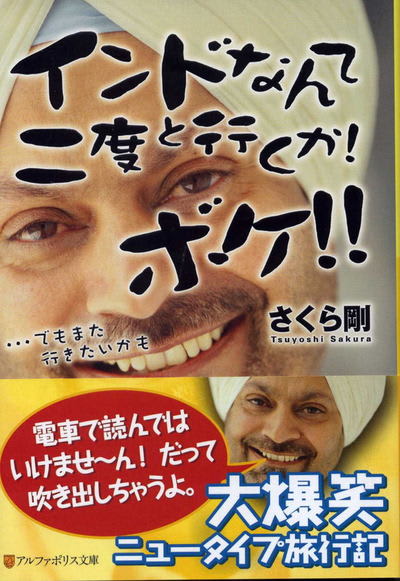本書は面白い。
古代史シリーズ5巻を読んでからでは、なおさらだ。
古代史シリーズは、いろいろな観点からの話だったが、本書は、陵墓(天皇陵と思われている古墳)の観点からの一気通貫だから、読みやすい。
この観点からだと、どうしても宮内庁への批判にもなってしまう。宮内庁の、陵墓への立ち入り禁止のおふれは、一見、それもありかなと思うけど、陵墓自体が間違っていて、本当の陵墓は、誰でも入れたり、勝手に公園化され、ただの丘が、陵墓化され、立ち入り禁止になっていたりする。
これは、いかがなものか?宮内庁の不作為の罪ではないか?
被葬者が正しい天皇陵は、5/40という。確率12.5%!これは、急進的な研究者の偏った意見ではなく、過去の文献を調べていくと、そうなるし、学者は皆そう思っている。たぶん宮内庁もわかってる!
天皇陵は、残念ながら、ずっと大事にされてきていたわけではない。再評価されたのは、江戸時代だが、そのころすでに史実はよくわからなくなっていた。当時不明とされた御陵は、たくさんあった。それらを、明治維新の時期に、ばたばた比定したのだ。
学術的に一番重要なのは、江戸時代の古図や絵画で、そのほかには、宮内庁の実測図がかろうじてあるぐらいという。それで、研究しろというのは、はっきり言って無理だ。盗掘の記録などが、貴重な資料になっている始末だ。
それにしても、著者の古墳への思いは凄い。私も知らなかった珠城山1号墳からみた景行天皇陵の写真などは、思い入れいっぱい。
古墳の研究は、特に江戸時代盛んだったようで、その中の蒲生君平の研究は、貴重な情報源になっている。奇人の一人になっているらしい。
それにしても、古墳の扱われ方は、厳しいものがある。周濠は、灌漑に利用されており、研究しようにも、厳しい状況がある。私も、釣り堀になっていたり、果樹園になっているのを見た。
でもそれにしても、えぇ!?という陵墓も多い。崇峻天皇陵などは、噴飯ものだ。2つの古墳を一つにしたりということが、平気で行われている。極めて、大事な天皇なのにだ。
去年行った百舌鳥古墳群の巨大な3古墳についても、議論は、終わっていない。石棺が、円墳部分にあるのか、方墳部分にあるのか、両方にあるのか、まったくわからない五里霧中状態なのだ。
継体天皇陵についての議論も終わっていない。継体天皇は、今の天皇の本当の祖先である可能性が高い天皇であるにもかかわらずだ。古墳については、古事記、日本書紀は、もちろんだが、延喜式の記述が一番参考になるそうで、総合的に判断すると今城塚古墳しかないのではと、著者は言う。
話題の多い斉明天皇については、牽牛塚古墳の発掘で、決着が着いたようだが、この古墳の八角形ピラミッドは、凄いものだったという。そして、私も訪れた謎の多い益田岩船だが、この牽牛塚古墳の発掘により、同時代に、同様の石室を作ろうとして、諦めた残骸であると考えられるようになったという。説得力があるし、たぶんそうだと思う。
火の路を書かれた松本清張さんに、ご意見をお伺いしたい。これと似た石が、兵庫県にもあるが、これも斉明天皇期のものと本書は言う。
発掘により、新たな真実が浮かび上がるし、それにより、本当の歴代天皇の御霊に祈りを奉げることができるのだ。
宮内庁の罪の最たるものが、近代の天皇陵という。近代の天皇陵は、古墳が作られた最後の天皇である天智天皇陵をモデルにしている。天智天皇陵は上円下方墳と思われていたが、近時の研究により、上八角下方墳であることがわかってしまったのだ。
宮内庁は、その事実を認めながら、結論は変えない。これで、皆いいかと言いたくなる。役所仕事、ここに至れりという感じだ。
掘ればいいというものではないが、10年に1つづつぐらいのペースで、日本の成り立ちについての洞察を深める機会があってもいいのではないかという感を強く持ったし、宮内庁の方々も、少しは理解すべきではと、本書を読んで強く思った。
素人にもわかりやすく書かれているので、古代史に興味のある人に、是非お勧めしたい。