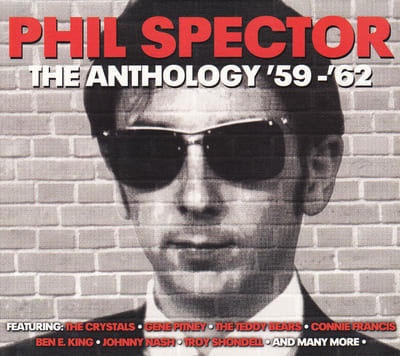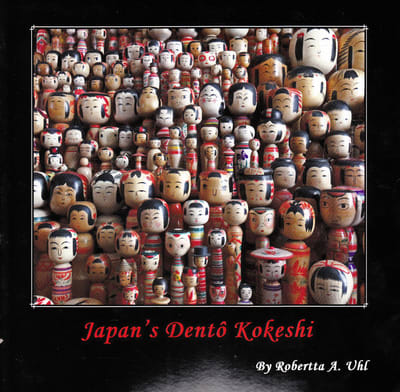
Japan's Dento Kokeshi という本が出た。
コケーシカさんのブログで、見つけて、週末に、鎌倉に行った時に、GETした。
こけしには、大きく分けて、古くからある伝統こけしと、新しいデザインの創作こけしがある。
どちらがいい、悪いという話ではないが、本書は、伝統こけしの方の英語版入門書である。
作者は、ロベルタ(良場田)さんという方で、1983年の少女時代に、沖縄に初来日されたという。
米軍人の娘さんだったのだろうか。
そして、日本の郷土玩具、特にこけしに魅せられ、永年収集を続けてきたという。
そして、今般、本書を出版。
豪華すぎず、簡素過ぎず、ちょうどいい塩梅に仕上がっている。
収集を始められてから、30年ぐらいということだから、比較的新しいこけしが中心だが、骨董屋で、古いものも、時々入手されているようだ。
各系統毎の説明が、バランスよく、ビジュアルに、説明されていて、ひじょうにわかりやすい。
特に、日本人では、訳しにくい言葉を、平易な英語で訳してくれているのが嬉しい。
例えば、
Futae-maburta = Western double eyelids,
Hitoe-mabuta = Asian single eyelids(そうか!一重まぶたは、亜細亜人の特徴なのか!),
Maru-bana = Round nose,
Neko-bana = Cat nose,
Tare-Bana = Dropping nose,
Namida-bana = Teardrop nose,
Ware-bana = Split nose,
Ni-fude-nose = Nose painted with two brush strokes,
Bachi-bana = Shamisen pick nose
Shishi-bana = Lion nose etc.
たぶん、ご自分で考えられたのだろう。
全般的に使われている英語も平易。
こけし工人さんの店にも、熱心に通われていたようで、写真や、色紙なども、紹介されている。
各系統の特徴や、技法などにも、説明が加えられ、これ一冊読めば、伝統こけしの基礎はOK!
ということで、誰に勧めたらいいかわからないが、ロベルタさんの熱意に拍手である。